
interview Michelle Willis:『Just One Voice』からクワイア、カナダ由来の影響まで
スナーキー・パピーのマイケル・リーグが主催するレーベル GroundUP Musicの中で最も飛躍したひとりが、シンガー・ソング・ライターのミシェル・ウィリスだろう。
ソロアルバムのリリースから、スナーキー・パピーとのコラボを経て、デヴィッド・クロスビーがSky TrailsやLighthouseなど、あらゆるプロジェクトで起用していて、今やクロスビーの活動のキーマンになっている。その鍵盤と声を駆使した刺激的なハーモニーは輝きを増している近年のクロスビーの音楽に欠かせない要素だ。
そんな彼女の音楽はGroundUpからのデビュー作『See us Through』の時点で個性的なだけでなく、すでに成熟を感じさせるほどに完成されていた。その影響源は公式サイトのバイオグラフィーに自身の手で記している。
90年代のラジオから流れてきたショーン・コルヴィン、ローリン・ヒル、アマンダ・マーシャル、ジャン・アーデン、ホイットニー・ヒューストン、アラニス・モリセット、ジャネット・ジャクソン、サラ・マクラクランに夢中になり、教会のクワイアではブラームス、モーツァルト、バッハを歌い、その後、ジョニ・ミッチェル、スティーヴィー・ワンダー、キャロル・キング、ダニー・ハサウェイ、CSN&Y、レイ・チャールズ、ポール・サイモン、ジミー・ウェッブ、そしてビートルズを聴き込んだとのこと。ミシェル・ウィリスの音楽を聴けば、その影響は様々な形で聴きとれるだろう(サラ・マクラクランやアラニス・モリセット、ショーン・コルヴィン、アマンダ・マーシャルといった女性シンガー・ソング・ライターたちの影響がミシェルのようなアーティストの中に息づいているのはとても興味深い)。それと同時にそれらをインスピレーションにしたうえで、彼女はオリジナルな音楽を作り続けていることもわかる。
とはいえ、彼女についてはまだまだわからないことも多い。
2022年、デヴィッド・クロスビーやマイケル・マクドナルドも参加した『Just One Voice』がGroundUp Musicからリリースされた。このアルバムの話を中心に、彼女にいろいろな話を聞いてみた。
取材・編集:柳樂光隆 通訳:染谷和美 協力:COREPORT
◉『See us Through』のこと
――まず2016年の『See us Through』について聞かせてください。
とにかく仕上げることを考えていた(笑) 曲自体は以前からあったもので、ライブでもやっていたものばかりだったから、あらかじめテーマを設けてから作るというよりは、普通に暮らしていく中で、それを曲にしていくってことをずっとやってきたってことだと思う。でも、せっかく“アルバム”というフォーマットにするわけだから、収録された曲をコネクトするためのテーマを設けられたらいいなとは考えてた。曲ができた後から、それらの共通項を探したら、それはセラピーだと気付いたんです。きっと“自分が安心できる場所”や“自分の人生について語ることを安心してできる場所”、つまり曲は自分にとってセラピーのような場所だとアルバムを作る過程で気付くことができました。
ちなみに2016年5月に私はNYに引っ越していて、あのアルバムはその前にすべてトロントで作ったもの。マスタリングまですべて仕上げてからマイケル・リーグに送ったらマイケルが興味を示してくれて、GroundUPからリリースすることになり、私はGroundUPのファミリーになったって経緯。ちなみに2011年に『Coasting Notes』ってアルバムを出しているので、それが私のファースト・アルバムで『See us Through』はセカンド・アルバム。
◉GroundUp Musicとスナーキー・パピー『Family Dinner vol.2』
――GroundUPに参加するきっかけってどんなことだったんですか?
当時の私にはレーベルをやっている知り合いがマイケルしかいなかったから、出してくれるレーベルはGroundUp Musicしかなかった(笑) そのころ、すでに私もあの界隈のミュージシャンたちのファミリーになっていた感じもあったし。2015年はスナーキー・パピー『Family Dinner vol.2』のレコーディングに参加した年で、あのアルバムに収録された「Sing to the Moon feat. Laura Mvula & Michelle Willis」に参加した後にGroundUPから私のアルバムを出すって流れがそこで出来ていた。GroundUP自体もどんどん成長していった時期だったから、私もそこから出すのが最もいいかなと思っていた。
――GroundUPのファミリーになるきっかけはどんな感じだったんですか?
初めてスナーキー・パピーがトロントで演奏した場所はThe Rex Hotel Jazz & Blues Clubというバーで、私はそこのバーテンダーだった。私はそこで彼らを初めて見て、すごく気に入ってレコードも買った。その時はメンバーと話したりもしていない。お客さんは5人くらいしかいなかったんじゃないかな。これはスナーキー・パピーの定番の話なんだけど、だいたいどこに行っても最初はガラガラでほぼ空っぽ。でも、2回目に来た時は満員ってことを繰り返してきた人たち。つまり、REXに関しても二度目に来た時は満員だったってこと。2回目の時は弟から「この前、レコード買ってた人たちがまたトロントに来るから行かなきゃ」って教えてもらって、見にいって、そこで初めてメンバーと話をして、すごく打ち解けたのを覚えている。その時に私がThree Metre Dayってバンドで活動しているって話をしたのもあって、その次にトロントに来る時には自分たちをオープニング・アクトに使ってくれたりした。
――そこからGroundUP Musicと契約して、スナーキー・パピー『Family Dinner vol.2』に参加することになると。『Family Dinner vol.2』のレコーディングはどんな感じでしたか?
ミュージック・キャンプみたいな感じ。とにかくみんなスキルが高くて、人生=音楽キャリアみたいな人たちばっかり。なのに、ものすごく親切で、情熱があって、一緒に音楽を作るってことに対して一生懸命だった。それにあの場ではお互い“知り合おう”って気持ちもすごくあって、一緒に食事をしたり、いろんな話ができた。あそこで知り合った人たちとは今もすごく仲が良い。ご存知の通り、あの時に知り合ったおかげで、私はベッカ・スティーヴンスのバックで歌うようになったり、デヴィッド・クロスビーと一緒にやることにもなった。あれから6年くらいの間で、私が最も一緒に音楽を作っているのはあの時に知り合った人たちばかり。一回一緒にやったことで“じゃ、次もお願い!”って声がかかった。私の人生はあのレコーディングで変わったと思う。
◉『Just One Voice』のこと
――素晴らしい経験ですね。ところで、僕は2019年にあなたにインタビューしてるんですが、その時に“新作を来年(2020年)に出すから”って言ってたんですよね。今回、『Just One Voice』がリリースされて聴いてみたら、2019年に僕がマイアミでのGroundUP Music Fesivalであなたのライブで聴いた曲や、デヴィッド・クロスビーのアルバムに収録されていた曲も入っているので、長期間書き溜めた曲をレコーディングしたのかなと想像します。
あなたがマイアミで聴いたのはたぶん「Janet」って曲。実は『See Us Through』よりも前に書いていた曲も入っている。それが「How Come」「Just One Voice」。『See Us Through』はアメリカーナでシンガー・ソング・ライターのフィーリングのアルバムだったから、それと違うタイプの曲は次のアルバムで使えればと思って、取っておいたから。
――なるほど。
でも、『See Us Through』の後、徐々に忙しくなってしまって、メンタル・スペース的にも自分のことをやる余裕がなくなってしまっていた。家に2週間いられることがほとんどない生活だったから。そんな中で2018年にFabrice Dupontと会ってプロダクション・ミーティングを始めて、どんなものを作りたいかを話し合った。とは言いつつも、その後もなかなか時間が取れなくて“絶対に作りたいのに”って葛藤の中で過ごしていた。
そんな時にライブ録音していた「How Come」「Just One Voice」をデヴィッド・クロスビーとのツアー中にデヴィッドに聴かせたことがあった。それは『See Us Through』のツアーの時にたまたま録った音源だったんだけど、すごくよく録れていて、私たちのバンドの良さが溢れていて、自分にとってはカタルシスになるような音源だった。それを聴いたデヴィッドが“これは正にミシェルの音だし、ミシェルにしか出せない音だからリリースすべきだ”って言ってくれて、私はそれにすごく勇気づけられた。その2曲ではライターとしての自分のほんの一部しか見せていないと思うけど、それでもクロスビーがあれだけ興奮してくれたっていうことが私にとってはものすごく励みになって、より真剣に取り組もうと思い始めた。
それであのライブ録音のどこがそんなにデヴィッドを惹きつけたのかは考えた。それに私はその頃、業界全体の流れにけっこう失望していた時期だった。デジタルばっかりになっていて、部屋でスマホでリリースを確認して“クール!”とか言われるだけで終わりの感じが好きじゃなかった。『See Us Through』を出して、ライブをやっている中で、自分たちの持ち味を考えた時に、ライブを録ってもいいかなとも思ったんだけど、一方で私はそんなにライブ・レコーディングが好きじゃない。そこで悩んでいた。でも、ライブ・レコーディングで録った「How Come」「Just One Voice」があそこまでいいものになったのなら、よりレベルの高いプロダクションで色んな事を試していったら、スタジオでもすごくいいものが作れるんじゃないかと思うようになった。スタジオでうまくいけば、もう少しポップ寄りにもなり得る可能性をこの曲たちは持っているんじゃないかと思ったのもある。そうやって考え抜いた結果、とりあえず2つのバージョンを作ることにした。ひとつは“とにかくプロダクションにこだわったスタジオならではのバージョン”、そして、もうひとつはお客さんも入れて、映像も撮ったライブ・バージョン“。最終的に2つとも実現したことには自分でもびっくりしてる。
ライブ・レコーディングをやってみて思ったのはやっぱりお客さんの存在の大きさだった。いいバンドのいいパフォーマンスはお客さんのそこでの反応が返ってくるからこそ生まれることを実感できた。2019年の10月5日に、以前は仏教の寺院だった場所を使っているイベントセンターでレコーディングしたんだけど、そこにデヴィッド・クロスビーが2曲で参加している。でも、スタジオ・バージョンに関しては2020年になっても私はまだ家でヴォーカルを録ったりしていて、最終的にミックスが終わったのは21年の4月だった。
だから、ダブル・アルバムにしようと思えばできたんだけど、最終的にはスタジオで作ったものをアルバム『Just One Voice』として出すことにしたって流れだった。
――プロデュースのファブリス・デュポンはデヴィッド・クロスビーの作品を手掛けている人ですよね。
『Lighthouse』で仕事をしたときに「僕でよければ一緒にやりたい」って、彼の方から申し出てくれて、一緒になることになった。とにかく過去の仕事でも彼は私のことを信じてくれているし、リスペクトがあるし、私の作る曲が好きだって言ってるし、彼は私のことをずっと応援してくれている。人として、仕事中に彼の娘さんが出てきたら一緒に遊んだり、ワインを飲む時間があったり、彼は生活者って感じがある。音楽以外の生活を楽しんでいるし、一緒にいて、楽しめる。レコーディング・オンリーにならない感じも良かったと思ってる。
――『See Us Through』はかなりアコースティックな質感でしたけど、『Just One Voice』はエフェクトもかなり使ったエレクトリックな質感が増えたアルバムです。例えば、ファブリス・デュポンはEchoplexとしてもクレジットされています。Echoplexはテープエコーなので楽器じゃなくて、エフェクターですよね?
ライブ演奏するときに彼がEchoplexで参加してくれていた。「10th」では私がローズを弾いて、クリスチャンがNORDを弾いてるんだけど、私のローズをEchoplexに通している。最初、ライブの時、NORDにDeluxe Memory Man(アナログ・ディレイ)でディレイをかけていて、フィードバックをがんがんやったらいい感じで、スタジオ・レコーディングではもっと歪めたいって思っていた。フィードバックがんがんかけて最後にドーンってなるイメージ。それをファブリスに手伝ってもらった。ライブでは私の隣に彼がいて、「もっと上げて」「ほんとに大丈夫?」「大丈夫!どんどん行って」みたいな感じでやってる。だから、彼はエフェクターを演奏してくれていたと思う。
――ここでは様々な種類の鍵盤が使われています。Fender Rhodes、Nord Stage 3、Wurlitzer、Korg MS20、Mellotron、 Pump Organ、Arp Omni、Akai AX60、Moog Model D、Piano,、Prophet V、Arp Ensemble IV。このほとんどをあなたがひとりで弾いて重ねています。
最初のインスピレーションはスナーキー・パピーのジャスティン・スタントン。ジャスティンのバンドにChristian Almironがいて、そこでクリスチャンには知り合った。そのバンドがやっていたモーグ、フェンダーローズ、プロフェット、そして、リズムセクションとシンガーって組み合わせで作ったサウンドがすごく美して、それが最初のヒント。
――そして、Christian AlmironはNYの人気セッションのホストでもあったレッスンGKのキーボード奏者。彼の貢献も大きいですよね。
クリスチャンはここではほぼノードを弾いてる。ノードをあんな風に弾けるのはクリスチャンしかいないと思う。どんどん機材を操作して音を変化させていく。「Liberty」「Green Grey」「Black Night」の最後の方で聴けるローズっぽい歪んだ音も実はクリスチャンがノードで鳴らした音。私はあのサウンドを“Christian Darkness”って呼んでるんだけど、そのくらいくらいオリジナルなサウンド。
――なるほど。
クリスチャンみたいなミュージシャンと共に様々な音を生み出して、それらを織り成していくようなやり方がすごく楽しかったので、最終的に多くの鍵盤を使ってしまったんだと思う。もうひとつのインスピレーションはスティービー・ワンダー『Innervisions』。ファブリスもスティービー的なアナログシンセが好きで、AKAIやKORG、ウーリッツァーを集めているから、彼のスタジオにはそんな楽器がずらっと並んでいる。彼のスタジオでヴィンテージなシンセをとっかえひっかえ弾いて、その音を重ねて作ってる。
――「Just One Voice」ではArp Ensemble IVを使ってます。これはかなり変わったシンセですよね。
アープに関してはデヴィッド・クロスビーのアルバム『Here If You Listen』の何曲かでも弾いていたんだけど、特に「Vagrants of Venice」で弾いてみたら気に入ってしまって、自分の作品でも使おうと思っていた。このシンセはストリングスをエミュレートしているんだけど、決して生の弦の音そのものにはなっていない。でも、その本物ではなくて、真似ている感じの音色がクールで好き。だから、使える場所があったらいろんなところで使いたいなって思ってる。
――声を重ねるのはあなたのトレードマークだと思います。例えば、「10th」は正に声をたくさん重ねてますけど、前作よりもたくさん重ねてて、厚みがあります。
『See Us Through』以降、沢山のレコーディングに参加できたし、自分の声を重ねるってこともさんざんやってきた。だから、自分の声をダブルやトリプルで重ねることに関しては技術的にも、経験的にも長けてきたっていうのはあると思う。あと、最初のレコードの時との違いはマイクを変えたことも大きいかも。それに今回はどうせダブルで重ねるんだったら、トリプルにしちゃおうって感じでどんどんやったのもあると思う(笑)。厚みが出ているのはたぶんそこが理由かな。
◉英国国教会のクワイアからの影響
――そのようなハーモニーに対する感覚はどうやって得たんですか?
私は9歳から19歳まで主に教会のクワイアで歌ってきた。歌っていた中で一番大規模のクワイアーは、約20人編成のアングリカン・チャーチ(英国国教会)のクワイアー。13歳頃からはセクション・リードを担当していたから、意識していたかどうかはわからないけど、そこでものすごく多くのことを学ぶことができた。コーラスの世界は私の大好きな場所。そうやってハーモニーを担うことで耳も鍛えられたし、後に知り合ったミュージシャン勢から彼らにそういった経験がないことを聞いた時、ハーモニーのトレーニングを積むことができた自分がいかにラッキーだったかを実感ししたりもした。
もともと私が地元トロントの英国国教会へ通うようになったのは、うちの母がクワイアで歌いたくて、一緒に行くようになったのがきっかけ。英国国教会では賛美歌を沢山歌うから。あの『ブルー・ヒム・ブック』(Blue Hymn Book)のハーモニーは、私のソングライティングに多大な影響を与えている。今でもヴォーカルのコードに取り組んでいる時間が一番好きだと思う。
――その『ブルー・ヒム・ブック』についてもう少し詳しく教えてください。
『ブルー・ヒム・ブック』は讃美歌集の本。私が行っていたアングリカン・チャーチのクワイアは『ブルー・ヒム・ブック』に載っている曲を歌っていた。だからこの本はハーモニー的な面で私の血として流れている気さえしている。そこに載っていた讃美歌のハーモニーの動きも私の中に刻み込まれていて、今では自分にとってはそれが最も気持ちいいハーモニーになっている。エディションがいくつかあって、その他には『レッド・ヒム・ブック』(Red Hymn Book)もある。でも、私は一生ブルー派だって決めてるからレッドには手を出さない。例えば、『ブルー・ヒム・ブック』にはバッハのコラールみたいな美しいメロディがいっぱい入っている。
ちなみにローラ・マヴーラを初めて聴いたときに、この人は『ブルー・ヒム・ブック』の人だって思った。彼女はきっと『ブルー・ヒム・ブック』の人だし、この人の音楽は同じ言葉を話しているって思った。そのくらい特徴的なマイナー6thとマイナー7thのフィーリング、ベースの動き、独特なハーモニーの作り方がある。私にとってローラ・マヴーラはその要素が聴こえてくる音楽としか言いようがないって感じ。
◉影響源と大学での経験
――教会の音楽以外で、過去に研究したミュージシャンがいたら教えてください。
ナット・キング・コールはいろいろ聴いた。それからオスカー・ピーターソン、レイ・チャールズ、ジョニ・ミッチェル。それにアヴィシャイ・コーエンも大好き。アヴィシャイからは作曲面で影響を受けたし、こういった音楽スタイルでのピアノとベースラインが織りなす音の感触の面からも刺激を受けた。
あと、ブラジル人ピアニストのジョヴィーノ・サントス(Jovino Santos Neto)だったと思うんだけど、大学で開催された彼のクリニックからは衝撃を受けた。ブラジル音楽にブルースを融合させたようなピアノ演奏で、リズムの外し方に物凄くグルーヴ感がある。リズム面でいろんな方向に展開していくんだけど、次の展開が全く読めないから、例えば次に変拍子が来るかどうかも全く分からない。もう最高にかっこいいと思った。彼からは多大なる影響を受け、その後、私もタイミングをずらした拍子でグルーヴのある曲を書くようになったくらい。ジャズ・スクールには変拍子の曲を書いて、自慢気に自分の手腕を披露する人もいるでしょ?でも、ジョヴィーノ・サントスの音楽は興味深いリズム的な動きがある一方で、聴いていてとても気持ちが良く、ソウルフルだったから。
――大学の話が出たので、the Humber College Jazz Programに通っていたころの話も聞かせてもらってもいいですか?
音楽とは一生涯かけて学んでいくものだと教えてくれたと思う。私が師事した先生達も生涯を音楽やジャズに捧げていて、その「終わりのない研究」が素晴らしいと思った。それから、自分がミュージシャン達が集まるコミュニティにいることも学んだ。ミュージシャンとのコミュニケーションは、音大で学んだ基本的なプラス面かな。それから、ピアノ・トリオものが大好きになったのも大きかった。例えばピアノとダブル・ベースの組み合わせとかね。
それから、ある時自分の先生から「君、卒業後はどうしたいの?」と聞かれたことがあって、私は「一生涯、練習室で練習するような自分の姿は想像できない」って答えた(笑)。「私は物凄い練習量にコミットするのも無理だと思うし、即興するような音楽家にもならないと思う」とも伝えた。その時に先生から直球で「何でもなれるのに、君は努力していないだけ」とバッサリ言われた(苦笑)。そのひとことは私の目を覚ましてくれた。実際にその一言を実感し、理解できるようになったのは、それから少し後だったけど。私は音楽理論も理解していたし、音大のクラスでは上位にいる生徒なのに、私が十分に努力していなかったことを先生は認識していたからそう言ったんだと思う。その先生の言葉は、永遠に私の頭の中で流れるようになった。どんな形でも音楽に関わりたいなら、研究も努力も自分の成長や自信を得るために重要だから。非常に重要な教訓だったし、今となっては先生に心から感謝している。
――その先生のお名前を聞いてもいいですか?
カーク・マクドナルド(Kirk MacDonald)というサックス奏者。それから、他にはデヴィッド・レスティーヴォ(David Restivo)とブライアン・ディッキンソン(Brian Dickinson)からピアノを、シャノン・ガン(Shannon Gunn)から音楽理論と聴音、それから私が大好きだった先生のリサ・マーティネリ(Lisa Martinelli)からはジャズ・ヴォーカルを習った。
◉カナダの音楽について
――あなたの先生にはカナダの名ジャズ・プレイヤーが多いんですね。ところで、僕は『See Us Through』を聴いたときに「どこかカナダっぽいな」って思ったんです。変な質問ですけど、自分の音楽の中にカナダっぽさってあると思いますか?
うーん、それは他の人から見て、指摘してもらうほうがわかりやすいかも。ただ、友達とギグに向かう際に、6時間くらい車で移動しなきゃいけなくて、私が助手席だったから私のプレイリストを流していた時に、自分では気が付いていなかったんだけど、好きで聴いているバンドはカナダが多かった。ドライブが終わって、友達から「カナダ人ばっかりだったね」って言われて気付いた。友人が言うには私が好きな音楽はカナダっぽいものばっかりだったみたい。
世界中のどこの国にも聞きたくない音楽があるように、カナダにだって聞きたくない音楽はあるんだけど(笑)。でも、その中で私が好きだなと思ったり、私がインスピレーションを受けたカナダの音楽を考えると、何か“確信の欠如(Lack of Certainty)”みたいなものはあるのかもしれないと思ってる。それは“確定しきらないオープンな姿勢”だと私は考えている。問いかけが多くて、“こうなんだよ!”って感じのステイトメントじゃなくて、疑問を投げかけるようなものが多い。好奇心があって、自分のことを曝け出していくような書き方の音楽が好きで、そういうミュージシャンはカナダに多いのかなって感じるかも。
例えば、Martin TielliがソングライティングをしているNick Buzzは好奇心旺盛で、変わってて、奇妙な音楽なんだけど、『A Quiet Evening at Home』ってアルバムの最後に収録されている「The Birds of Lanak Country」って曲は素晴らしい。
Henrysってグループの『Is This Tomorrow』は私のフェイバリット。そして、私が言ったような音楽の完璧な一例だと思う。このアルバムにはベッカ・スティーヴンスも参加している。
Henrys のメンバーでもあるMary Margaret O'Haraも私が考えるカナダっぽさを持っていて、私は彼女からすごく影響を受けている。彼女みたいな存在は他にいないと思う。
私の友人でもあるSSWのCharlotte Cornfieldもそう。彼女はローリングストーン誌が"Charlotte Cornfield Is Canada's Best-Kept Secret"って書いたこともある素晴らしいシンガー・ソング・ライター。戸惑いみたいなものも含めて、すごく人間らしい曲を書く人だと思う。
トロントはエラスティックで、モダンで、フレッシュな独特なシーンがあるから。すごく魅力的な街だと私は思ってる。
※記事が面白かったら投げ銭もしくはサポートをお願いします。
あなたのドネーションが次の記事を作る予算になります。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
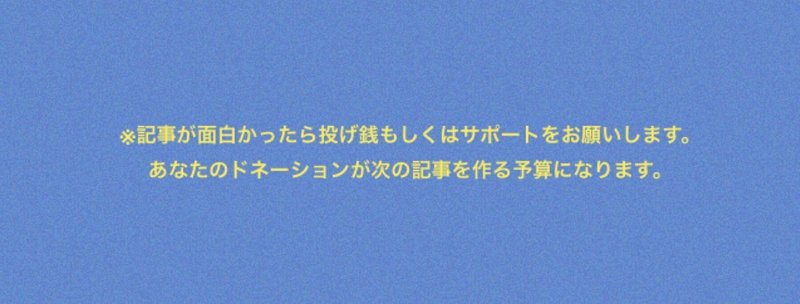
◉GroundUp Music関連記事
ここから先は
¥ 150
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
