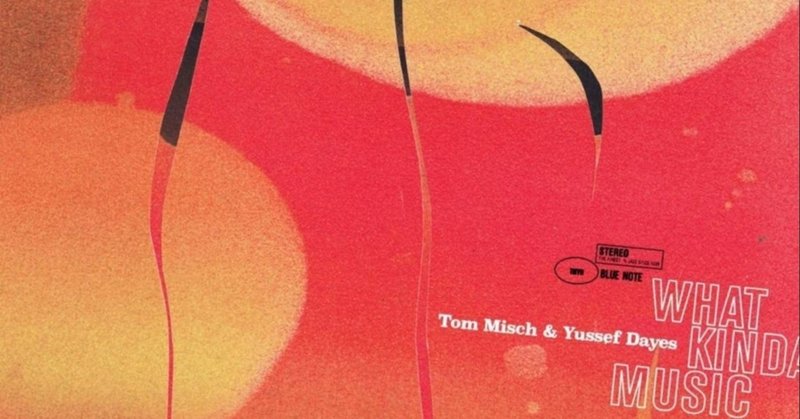
interview Yussef Dayes - ユセフ・デイズ:『What Kinda Music』お互いが奏でる音楽に耳を傾けて、それを補ったり、より発展させようと思った
トム・ミッシュの2020年の新作『What Kinda Music』は2018年の『Geography』とは全く別のトム・ミッシュが聴ける作品だ。以下のインタビューでトム・ミッシュはその変化について、
「これまではトム・ミッシュのサウンドを築くことに専念してきたんだ。だから今回のアルバムは違うことを試す絶好の機会だった。自分の中にあって、追求したいけど、これまで自分の名義ではできなかった色々なサウンドを試すことができた。」
と語っている。この『What Kinda Music』はトム・ミッシュにとって実験であり、チャレンジだったのだろう。
そのチャレンジに欠かせなかったのが、コラボレーターとなったドラマーのユセフ・デイズ(Yussef Dayes)。
ユセフ・デイズはユセフ・カマール(Yussef Kamaal)名義で発表した『Black Focus』で昨今のUKジャズ・ムーブメントに火を着けたシーンのキーマンだ。
もともとビートメイカーとして出てきて『Beat Tapes』シリーズをリリースしているトム・ミッシュがなぜ、ドラマーと組んだのか。その理由はトム・ミッシュ本人にすでに聞いた。ただ、この『What Kinda Music』を知るにはユセフ・デイズという人物がどんなドラマーなのか、どんな音楽家なのかを知る必要があると僕は思った。
ここではアルバムのリリースに際して、柳樂光隆がユセフ・デイズに行ったオフィシャル・インタビューを掲載します。
ユセフ・デイズの発言からはユセフ自身のスタイルだけでなく、イギリスのミュージシャンの特徴が見えてきます。UKジャズ・シーンの、もしくはイギリスのミュージシャンを理解するためのヒントに溢れている記事になりました。
※この記事と併せて、トム&ユセフが公開した『What Kinda Music - Documentary』というショートムーヴィーを見ると、このアルバムのことがより理解できるかもしれないのでおススメです。
質問作成・構成:柳樂光隆 | 電話取材・通訳:伴野由里子
――トム・ミッシュとどのようにして知り合ったのでしょうか?
「共通の友達がいるんだ。Alfa MistとかJordan Rakeiを通して知り合った。2018年にジャム・セッションをやるようになった。最初は1曲一緒にやろうくらいのノリだったんだけど、一度セッションに入ったらいきなり10曲くらいのアイディアが出てきた。だったら、ジョイント・テープじゃなくて、ジョイント・アルバムを作ろうかってことになった。具体的には2018年の夏にEastbourneのスタジオに行って、その時に他にもいろいろアイディアあるからアルバムができそうだねって話をしたって感じだね」
――『What Kinda Music』では、多くの曲でクレジットがWritten by Tom Misch、Music by Yussef Dayes、Produced by Tom Mischとなっています。この役割分担について教えてください。
「トムが曲の構成や歌詞を書いて、曲の方向性をまとめる。僕の役割は主にリズムだけど、僕のドラムが曲を作るきっかけになることも多かったね。僕が最初にあるグルーヴを叩く、あるいはシンセのアイディアを弾いて、そこから構築していくような形だね。トムはPCでの作業が多かったけど、曲のアイディアはどっちからも出てきていた。プロデュースはトム主導でやるけど、僕もその場で色々意見を出していたから、共同プロデュースに近い部分もあると思うよ。」
――あなたはドラマーであり、あなたはジャズが叩けるドラマーであり、プログラミングされたビートのようにドラムを叩くこともできるドラマーです。そのあなたがビートメイカーでもあるトム・ミッシュとのコラボレーションで、どのようにリズムを作っていったのでしょうか。
「基本的には全てオープンにしていたね。何が正しいとか、何はダメというのは一切なかった。お互いが奏でる音楽に耳を傾けて、それを補ったり、より発展させようと思ってやっていた。単純に僕が刻んだビートに彼がギターを乗せるという時もあれば、より実験的なことをやってみることもある。これはヒップホップ・ビートかどうかって考えるより、何かぶっとんだことをやってみようって感じでね。あるいは僕のドラムを録って、それをトムが持ち帰って全く違うものに仕上げてきたこともあった。一つの決まった形があるというより、いろんなことをやったんだ」
――より実験的なものってどういう曲ですか?。
「“Festival”。僕からすると西アフリカ音楽の影響があって、ダブル・キックとダブル・スネアを多用している。普段トムが使うビートとは違うと思うよ。」
――では、トム持ち帰ったのだと?
「“The Real”だね。色々な曲を録った日があったんだけど、そこで僕がドラムのループを作ったんだ。それを彼が持ち帰って、次に持ってきた時にはプロデュースされていて、ドラムの音も全然変わっていた。驚いたよ。」
――あなたはいつもベースのロッコ・パラディーノ(Rocco Palladino)と一緒に演奏しています。きっとあなたにとってロッコは特別なプレイヤーだと思います。ロッコについて教えてもらえますか?
「僕らはCarlton BarrettとAston Barrett(※ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズのリズムセクション)、あるいはSly DunbarとRobbie Shakespeare(※レゲエ史上最高のリズムセクションのひとつ。通称スライ&ロビー) のようなリズム隊を目指している。いいリズム隊は音楽の要になるんだ。僕とロッコは数年一緒にプレイしていて、ライヴもたくさんやっているし、僕が携わった作品はどれもロッコがベースを弾いている。彼は最高のベーシストなんだ。だから当然、『What Kinda Music』にも参加してもらったし、featuring している曲以外にも数曲に参加している。過去の名作と言われるレコーディングには必ずいいドラムとベースが存在する。リズムセクションが曲を作っていると言ってもいいものも少なくない。Bob Marley & the Wailersにしても音楽の土台はドラムとベースなんだ。僕とロッコはそんなリズムセクションを再び呼び戻そうとしているんだ。」
――あなたから見たロッコってどんなベーシストですか?
「彼は独特なグルーヴの感性を持っていて、言葉で説明するのは難しいんだけど、「タメ」を作るんだ。で、こっちも「おっ」ってなる。ノリ遅れているんじゃないかって思うくらいだ。でも、それは彼独自のグルーヴの感じ方だから、そうなってるだけ。彼はきちんと拍子をわかった上でやってるから、こっちも安心して叩ける。最近はまた幅を広げてソロもやるようになって、また進化しているよ。僕がドラムでやっているように、彼もベーシストだけど、一人のアーティストでもある。ただの楽器奏者ってだけじゃなくて、音楽の発信者なんだ」
――あなたはジャズ、ファンク、ヒップホップだけでなく、ダブステップやグライムなどのUK独自の音楽を生演奏のドラムで叩けるドラマーです。『What Kinda Music』でUK独自のビートが聴ける曲があったら教えてください。
「曲によって特定できるものじゃないと思う。「新境地」こそがこのアルバムが意図しているもので、例えばロッコとトムとやった”Lift Off”だったり、”Kyiv”あたりの曲が自分たちが目指していた方向なんじゃないかな」
――逆にもっとも「ジャズ」なドラムを叩いたと思う曲があったら教えてください。
「ジャンルを気にせずに何でもやってみるというのが今作の意図だったんだよ。その中でも”Storm Before the Calm”のイントロにそういう要素があるかな。フリースタイルで叩いて、ジャズ寄りと言えると思う。ここではトムも何もフィルターをかけていない。「好きに叩いてみよう」と思って、ただドラムを演奏したんだ。NYのフリー・ジャズをイメージしてる。今回トムとのアルバムで、そういう、自由にやってるのが1曲あってもいいかなと思ったんだ。アルバムの最後の曲だよ」
――技術的にハードルが高かった曲はありますか?
「挙げるとするなら”Tidal Wave”だね。技術的に難しかったというのではないんだけど、本来自分はテンポの速いドラムンベースのようなのを叩くのが好きなんだ。でも、あの曲はテンポがゆったりとしている。あのテンポで心地いいノリを出すのにこだわったんだ。シンプルに聴こえるかもしれないけど、あれくらいのテンポで気持ちいいグルーヴ感を出すのは難しい。技術的に難しかったわけではないかもしれないけど、スローな曲でいいグルーヴ感を出すのが課題だったね。僕はスロー・テンポで心地良いグルーヴが出せることがトップ・ドラマーの証だと思っている。例えば、マーヴィン・ゲイの作品を聴いていると、テンポが速くなくても気持ちいい。それはいいグルーヴがあるからなんだ。
それにあの曲ではいろんなことを試しているんだ。実はいろんなシンバルを試していて、その中でもトルコから取り寄せたシンバルがあって、あの曲で初めて使ってみたんだ。だから、新しい試みをたくさんしている曲だね。」
――『What Kinda Music』にインスパイアを与えたドラマーやビートメイカー、プロデューサー、DJがいたら教えてください。
「とにかくたくさんの音楽を聴いているから絞るのは難しいけど、今作で言うと、UKサウンドを追求した部分はある。UKロックだね。例えばTalk Talk。彼らの作品を数年前に聴いて凄くインスパイアされたんだ。Talk Talkの音楽は一聴した感じの印象はメロウなんだけど、時間をかけてじっくりと聴き込むうちに、内省的な別世界に連れてってくれるんだ。僕のライヴを見に来るとわかると思うけど、ライブだと思い切り激しくドラムを叩いている。でもスタジオでは普段ライヴでは見せない面を追求することができる。だから、このアルバムではマーヴィン・ゲイっぽいノリだったり、さっき言ったUKロックっぽい要素を取り入れたり、実験的なシンセを使ったり、音色をいろいろ加工したりしたんだ。当然インスパイアされた人は他にもたくさんいるよ。でも、そういう人たちにリスペクトを表すのも大事だけど、ここでは下手にそれを意識するよりも、自然に自分たちから出てきたものを大切にしたかったんだ。」
――『What Kinda Music』でのドラムの音の音色や音質や低音の処理などを聴くと、録音にも編集にもこだわっているようにも感じます。ドラムの録音やミックスで何か特別なことをやっていたら教えてください。
「今作におけるメイン・エンジニアはAdam Jaffreyだった。彼のUnbound Studiosでアルバムの大半の録音を行った。この2年間、アルバムを制作する過程で、彼が色々なマイクの設置やドラムのセッティングを行ってくれたんだ。彼の細かい部分へのこだわりは凄かったよ。巻尺とかを持ち出してきて、ミリ単位でマイクの位置にこだわるんだ。公開している制作中の動画で僕がしてるマイクに位置云々って話はまさにAdamのこだわりのことだよ。彼のお陰でドラムのサウンドが定まったし、彼はエンジニアとしてもレコーディングにたくさんの力を貸してくれた。録った後に当然Tomが持ち帰って編集したり、音を加工したりするわけだけど、元になったドラムの音はアダムの貢献が大きいね。
あと2度ほどEastbourneにあるスタジオ(※おそらくユセフ・デイズが2020年にリリースしたシングル『Duality』をレコーディングしているEcho Zoo Studios)で、親しくしているエンジニアのMiles Jamesとも作業した。Eastbourneにあるアナログ・スタジオで、テープ機がたくさん置いてあって、直接テープに録音することができる。素晴らしいコンソールも置いてあるんだ。”Nightrider”と”Festival”はそこで録った。より暖かい、70年代っぽいアナログ・サウンドだ。でも、決して70年代を再現したいわけじゃない。僕らは新しい音にしたいわけだから、そういうレコーディング方法を取り入れながら、叩いているビートは新しいものを心がけたんだ。
今回はその2箇所でドラムを録ったわけだけど、僕がドラムの音作りをお願いするのは限られたエンジニアだけなんだ。こっちがどういう音を求めているかわかって貰うまでにはどうしても時間がかかってしまうから。でもそこは当然のように要の部分でもあるから、いきなり適当なスタジオに行って直ぐに録るわけにはいかないんだ。レコーディングする以上、自分のサウンドがきちんと出せる確信が持てなきゃダメだからね。だから、ここ数年は決まった人たちとしかレコーディングしていないんだ。でも、それはエンジニアだけじゃない。ロッコにしてもトムにしても、いい化学反応が生まれるまでには時間が必要。僕はドラムで食べてるわけだから、いきなり変なものを出したら「おいおい、大丈夫か?」って思われてしまうよね。ミュージシャンとして活動していく上で、自分の音を守るのはレコーディングする上で重要なんだよ。
ーーなるほど。
でも、長い間、レコーディングに携わってきたけど、自分のドラムをどう録ってもらいたいとか、どこにマイクを置くとどういう音になるとかこだわるようになったのは実はここ5年くらいのこと。色々試しながらレコーディングを学んでいったんだ。そういうレコーディングを学ぶプロセスって科学の実験みたいだよね。このアルバムでは今までやったことのなかった新しいことにも挑戦した。トムとのセッションの多くはそういうノリだったよ。だって、1回目のセッションでいきなり3、4曲のアイディアが出てきたっていうのも、まだ自分たちがアルバムを作るなんて思ってなかった段階で、ただ1日スタジオを借りて、ドラムを設置して、そのまま色々試して録ったってだけだったけど、それがこうしてアルバムに発展したわけだから。」
――最後にあなたが最も影響を受けた「ジャズ・ドラマー」「ファンク・ドラマー」「ヒップホップ・ドラマー」をそれぞれ教えてもらえますか?
「一人に絞ることは不可能だから、「数ある中から今日選んだ一人」って但し書きを必ず書いて欲しい。
ということでジャズ・ドラマーは今日はMax Roachで行こう。素晴らしいドラマーで、非常にテクニカルで数学的とも言えるほど。常に彼の動画を見たり、彼のドラムを研究している。自分のテクニックや基礎を磨きたい時、彼は基礎がしっかりしていて、知識も広い。だからジャズ・ドラマーはMax Roachだ。
ファンク・ドラマーはClyde Stubblefield。ジェイムス・ブラウンのドラマーだ。彼は凄いよ。彼の作品を物凄く聞き込んだし、自分のプレイに大きな影響を与えている。
ヒップホップ・ドラマーはChris Daddy Daveかな。Robert Glasperの作品にも参加している。彼はロッコのことも知ってて、自分たちをいつも応援してくれる。会うと必ず褒めてくれる。尊敬している人から同様の敬意を示してもらえるのは本当にありがたい。Chris Daveは本当に凄い。自分たちの世代の多くのドラマーにとってドラムに対する意識を変えた人でもある。だから彼を選んだ。
でも、あくまで今日のセレクションだってことを忘れないでね。」
以下のトム・ミッシュのインタビューも併せて読んでください。
※Rolling Stone Japanに以下のような解説記事を作りました。
※記事が面白かったら投げ銭もしくはサポートをお願いします。
あなたのドネーションがこのnoteの次の記事を作る予算になります。
■おまけ
あのUKのドラマー特有の硬さと動かなさ含めて、演奏からセッティング、マイキング、出音などのレゲエから発展したドラマサウンドの作り方と、そのリズムを軸にした作曲・編曲法を考えたら、今のUKジャズ周りが見えてくるものあるかもね。スラロビから始まるUKジャズ論https://t.co/wHaZ3PDody
— 柳樂光隆 《Jazz The New Chapter》 (@Elis_ragiNa) June 2, 2019
これまでUKジャズをいろいろリサーチしてきて、UKの音楽を理解するにはたとえジャズ寄りのドラマーでも、レゲエ・ドラマーからの影響を考慮しないとわからないことが多いのかもしれないと僕はなんとなく推測していた。
2020年2月にエズラ・コレクティブのドラマーのフェミ・コレオソに会ったとき、フェミがレゲエ・ドラマーの話をしていて、やっぱりそうかと思っていたところで、ここでのユセフ・デイズのインタビューでもスライ・ダンバーとカールトン・バレットとレゲエ・ドラマーの名前が出てきたことでほぼ確信に近いものになった気がします。ここでの話を聞いていても、叩き方や奏法だけでなく、スタジオでのドラム・サウンドの作り方、録音のやり方に関してもレゲエ~ダブからの影響が大きい予感も。今後もこのあたりのUKジャズに関しては引き続き、Jazz The New Chapterなどでリサーチしていきます。UKジャズとレゲエの関係に関しては『Jazz The New Chapter 6』のコートニー・パインのインタビュー記事を参照していただけると嬉しいです。

続きをみるには
¥ 250
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
