
interview BIGYUKI『2099』:今、こんな終末っぽい雰囲気の中でネガティブなものを出す意味はないと思った
2020年のアメリカは激動の1年だった。新型コロナウィルスによるパンデミックが起きた中で、大統領選があり、Black Lives Matterが大きくなった。トランプ政権の醜悪な新型コロナウィルス対策により世界でも類を見ない甚大な被害が発生した上に、国内情勢は常に不安定。選挙ではバイデンが勝ったが、陰謀論が蔓延し、差別も加速した。アメリカはまるで内戦のようだった。
そんな状況下でリリースされたのが『2099』だった。ATCQ『We Got It from Here... Thank You 4 Your Service』に起用され、カマシ・ワシントンのワールド・ツアーのメンバーでもあった彼がそんなアメリカの状況を現地でどんな思いで見つめていたのかは僕には想像さえできない。
ただ、そんな中で彼が完成させたこのEPには、どんな思いでここ数年のアメリカを見ていたのかが少なからず封じ込められているはずだ。そんなことを考えながら、僕はBIGYUKIに話を聞いた。
取材・構成・編集:柳樂光隆
――『2099』に収録されている曲はいつごろから作ってたんですか?
元々はフルアルバムを作る予定で、一年以上前から始めてた曲がいくつかある。「Trust Us」「MRO (Water Tale)」は一年以上前ですね。
――では、まず「Joy」から話を聞かせてください。
元々イメージとしては昂揚感がある曲を作りたいと思っていて、80年代のゴスペル・クワイアをサンプルするアイデアから始めました。カニエ・ウエストがゴスペルのプロジェクトをはじめるくらいの時期だったと思います。昔、毎週チャーチで演奏していたゴスペル・サウンドを活かした曲作りをするために、クワイアのサンプルを探して、そこから曲を組み立てるコンセプトで始めたんですけど、この曲がかなり紆余曲折してて、初めにあった曲のアイデアが全部なくなって、最終的に別物になりました。その結果が「Joy」ですね。
――この曲はポール・ウィルソンとの共作になっていますね。
ポール・ウィルソンはブルックリンのプロデューサーでマルチインストロメンタリスト。彼はカッサ・オーヴァーオールともやっています(※『I think i'm good』)。元TDE、ケンドリック・ラマーのところのお抱えのビートメイカーとしてもやっていた経歴もあります。でも、本人はアンダーグラウンドな志向なので、TDEは辞めちゃいましたけど。俺は彼のオーヴァーグラウンドにも刺さるキャッチ―さを持っているところが好きですね。
――では、ここではポール・ウィルソンにビートを提供してもらったってことですか?
2人でジャムりながら一緒に作っています。サンプルをリップするところから始めて、ビートを組んで、そこに俺の演奏を重ねて、一度、完成が見えかけたところでビートを少し残して、また大幅に変えたりして、最終的にこうなった感じですね。ポール・ウィルソンは俺のアルバムのサウンドの肝であり隠し玉。前作『Reaching For Chiron』でも一緒に作ってるし、次のアルバムを作るときにも彼のサウンドはかなり重要な位置を占めると思います。
――ここにクレジットされてるBae Broって誰ですか?
それはポールの別名義です。
――なるほど。あと、これまでのBIGYUKI作品で見ないのはドラムのThomas Pridgen。
彼はロナルド・ブルーナーJrやマイク・ミッチェルと並ぶドラム・スターの一人です。俺と同じ時期にバークリーに行ってて、クリスチャン・スコットのバンドの超初期のドラム叩いてたり、マーズ・ヴォルタのドラムやってたり、彼はずっと面白いことやってるミュージシャンですね。演奏は野生的で、テクニックは当然すごいんですけど、それを超える精神的な圧を感じさせます。彼は西海岸在住だから、彼との曲はコロナの前にLAでレコーディングしたものですね。
――ところで、このアルバムではエンジニアのクレジットがたくさんクレジットされてますね。
Yaniv FarberはLAでトーマスのレコーディングのために急ぎでドラムが録れるところを紹介してもらったときのエンジニアです。あとは『Reaching For Chiron』と同じで、ジェシ・フィッシャーのエレクトリック・インディゴ・スタジオとか、アーロン・パークスも使ってるストレンジ・ウェザー・スタジオとかでレコーディングをしてます。
ストレンジ・ウェザーのエンジニアのダニエル・シュレットは前のアルバム『Reaching for Chiron』でミックスを担当してくれています。彼は柔らかめの音が得意なので、今回は「Trust Us」「MRO (Water Tale)」の2曲をお願いしてます。アナログっぽくて、あったかい感じの音像が彼の仕事ですね。
一方で、バキバキの激しめの音はブレア・ウェルス。前のアルバムでは「ECLIPSE feat Chris Turner」の1曲だけミックスしてもらったんですけど、今回は初めからお願いしています。彼はQティップのお抱えのエンジニアで、ATCQのミックスなどの大きな仕事をしている人でもありますね。
――では、曲の解説に戻って「Trust US」はどんな曲か教えてください。
俺とマーカス・ギルモアでスタジオに入って「曲やろうよ」って感じで演奏したものがベースになっています。これもかなり前の録音ですね。ドラムとセッションしたものの上に、俺が更にシンセを入れたりして、どんどん曲の構成を変えていきました。最初、そこにタリブ・クウェリにラップを入れてもらって、更にケンドラ・フォスターにも頼んだら彼女のメロディがハマりましたね。
――ダニエル・シュレットのクレジットにある”サウンドデザイン”って何をやってるんですか?
彼はプロデューサーとしても優秀で、テデスキ・トラックス・バンドとかいろいろやっている人です。彼は曲にひと捻りをするのがうまいタイプ。この曲だったら、ドラムにグリッチかけているのが彼のサウンドデザインですね。
ジェシ・フィッシャーのスタジオでマーカス・ギルモアがドラム叩いて、俺が(シンセで)ベースを弾いて、ウワモノもちょっと弾いて、それをダニエルのストレンジ・ウェザー・スタジオに持って行って音を加工しています。例えば、ピアノにリヴァーブかけて、それを逆回転させたり、そのままだったらつまらない曲を面白くしてくれるエンジニアがダニエルですね。
あと、彼のスタジオには本物のメロトロンがあったから、ここでは俺はベース以外ではほとんどメロトロンしか弾いてないんですよね。ウワモノとして乗せたものはメロトロンで、そのメロトロンの音にインスパイアされるがままにどんどん乗せていったら最終的にこうなりました。ちなみに「Joy」の曲の構成にも彼のインプットが入っているから、それもかなり大きいと思しますよ。
――では次は「Faded」。
前のアルバムでも参加してるルーベン・ケナーが参加してくれました。彼はイギリス出身で、UKのスタイルの影響を受けてます。
この曲はもともとは倍速くらいのファンキーでアップテンポなインストの曲だったんですけど、聴いてるうちに”これはキャッチーでいいんだけど、俺の音楽じゃない”と思うようになってしまって。そんな時に、前からずっとスクリューをやりたいと思ってたことを思いだして、MP3をエイブルトンに入れて、1/2位のテンポにして、ピッチも落としたら、遅いテンポになったことでエロさが出て、俺らしくなったんですよね。
ちなみに最初に遅くしたのはルーベンのドラム・シークエンス。ルーベンのUKエレクトロニカ的な感じだと、俺の音楽のアメリカのブラック・ミュージックらしいエロさが薄くなりがちだったんです。俺の音っていろんなもののコラージュなんですけど、その中でも根底にある一番大事な部分はブラックミュージックのフィール。でも、それが無くなってる気がしたから、ポール・ウィルソンに相談したら「これはシンプルに90年代R&Bオマージュっぽいアプローチでいいんじゃない?」ってアドバイスをくれて、このアレンジになりました。俺のアルバムって、それぞれの曲のキャラクターが違うんだけど、どこかで繋がっていて、同じ匂いを感じたり、統一されたテーマがあるように聴こえる人もいると思うんです。それはグルーヴ感だったり、色気や臭みが理由かなと思ってるから、そこにはこだわりがあるんですよね。
あと、ヴォーカルは最初、クリス・ターナーを考えたんだけど、ちょうど歌入れしようとしたタイミングがコロナが始まったころで彼のスケジュールが合わなくて。その時にSmithsoneonはライブでは歌ってくれてるけど、シンガーとしてレコーディングしてないことに気付いたから、この曲では彼をフィーチャリングしようと決めました。
そして、歌詞は「ECLIPSE」を書いてくれたJ. Ivyに事前に頼みました。J. Ivyはカニエ・ウエストのアルバムにも参加してるスポークンワードの人。「Faded」を作ってるプロセスをJ. Ivyに送ったらすごく喜んでくれて、この曲の俺のシンセソロのセクションに彼がスポークンワードのヴァースを入れてくれました。でも、そのままだと、シンセと声がかぶってしまうので、ミキシングの時に、ブレア・ウェルズと一緒にシンセのソロにリヴァーブかけてからかなり後ろの方に置いて、前の方にJ. Ivyのヴァースを持ってきたら、シンセと声が共存できるようになったと思います。
――「Soundcheque」にはヴィブラフォン奏者のジョエル・ロスが参加していますね。
この曲はピアノに座ってたらコードが出てきたところから始まりました。ギターのランディとドラムのSmithsoneonの3人でスタジオに行ってジャムって作った曲で、ジョエル・ロスは別録りです。
俺はジョエルの音楽が好きなんですよ。ブルーノート・クルーズにカマシ・ワシントンのバンドで乗ったときに、ジョエルのバンドもいたから、毎日、彼の演奏を見てたくらい。あと、2年前くらいに深夜のNuBluでマーカス・ギルモアと俺とジョエル・ロスの3人で全部フリー・インプロヴィゼーションでライブやったことがあって、ジョエルは半分のサイズのヴァイブと、プロフェット6持ってきたんですけど、その時の彼も最高だった。彼のオリジナルは難解で、作曲はスルーコンポジションで長い組曲っぽい感じになるし、彼のバンドのドラマーは常にリズムを変えてる。でも、ジョエルは今っぽいループ主体の音楽も実は頭の中にある人なんですよね。
――ジョエル・ロスはインタビューでそういうバックビートはできるけど、自分の作品で自分の音楽としてはやらないって言ってましたね。
俺はループ主体の音楽に対する彼のアプローチが好きなんですよね。彼の同世代はそういうのをやってるし、自分が敢えてやることは無いと思っているかもしれないですけど。
――ジョエルには何かリクエストはしたんですか?
「ここからここまでソロを弾いて、ここにピークを持ってきてほしい」くらいです。送ってくれたテイクは全て素晴らしかったんですけど、自分なりの好みの部分を選んで編集して合体させました。もう一度、彼と制作ができるなら、彼のインプロヴィゼーションも含めたアレンジでの曲を作りたいですね。彼が自分のアルバムではやらないフレイヴァ―を俺の曲でやりたいと思うから。ジョエルは俺が一番好きなミュージシャンの一人。彼は俺の心をぐっと掴むんですよ。
――では次は「MRO (Water Tale)」。
これはマウンテン・リヴァー・オーシャンの略。俺は曲を作り始めるときにはまず最初にイメージが浮かぶことが多くて、この曲は山の上の雪解け水がだんだん溶けて、川に合流して、最後に海に混ざっていくイメージ。もともとは俺が酔っぱらってるときにやってた「マウンテン・リヴァー・オーシャン!」ってダンスがベースになってるんですけど(笑)俺とランディは酔っぱらうと、自然をモチーフに踊りを考えるんですよ。そのダンスのイメージをアナ・ワイズに伝えたら、この曲ができました。後半に出てくるリフレインの「マウンテン・リヴァー・トゥ・ジ・オーシャン」がそれですね。
曲はエレクトリック・インディゴ・スタジオでJUNOでコードを弾いて、そこを出発点に組み立てました。ドラムに関しては俺の中にあったイメージをもとに簡単なビートを打ち込んで作って、曲の最後の方でマーカス・ギルモアにシンバルを、小川慶太にパーカッションを叩いてもらいました。慶太のパーカッションのサウンドが最後のセクションにメリハリを与えてくれていると思います。
あと、この曲はアナ・ワイズの世界観がハマりましたね。彼女がキュートでセクシーかつ壮大な曲にしてくれました。
――なるほど。
『2099』をEPではなくて、アルバムとして出すんだったらもう少しえぐい曲も入れたと思います。例えば、ビートがバキバキ出てるポール・ウィルソンの打ち込み主体の曲も入ったかもしれない。俺の音楽的な理想ってハドソン・モホークの生演奏バージョン。彼の音楽のミックスの生々しさや質感、顔の前に音がガーっと出てくる感じや、シンプルなアイデアのリフレインでも一回聴くと掴まれてしまう感じを演奏で生演奏で作りたいんですよね。
俺が曲を作るときに一番大事なのは、リスクを常に負っていること。これやったらハマるからとか、流行りっぽいからをやってしまうと、感覚も音も死んでしまうと思います。だから、演奏や作曲や編曲だけではなくて、ミックスでもリスクを負ってほしいと思ってます。「ここの音は少し出過ぎじゃない?」くらいの方がスリリングだし、そういうミックスがハマったときのインパクトは、曲をさらに引き上げて輝かせてくれると思うので。同じことはマスタリングのエンジニアにも言ってます。みんな一流なので「こうすれば大丈夫」ってセオリーをそれぞれが持ってるんですけど、その上で、もっと攻めてほしいっていつも伝えています。
――そういう意味ではエンジニアに関してもWARPとかで仕事をしているUKの人の方が合うこともあるかもしれませんね。
ホセ・ジェイムスに紹介してもらったエンジニアで、フルームとかジェイムス・ブレイクのマスタリングをやってる人がいて、彼にも頼みたかったんですけど、彼は忙しすぎて無理でした。でも、いつかUKの人にも頼みたいと思ってる。俺の音楽はもうヒップホップでもビートミュージックでもないと思うから。
ーーたしかに。
ちなみに理想はハドソン・モホークでああいう攻めた音楽を作りたいってさっき言いましたけど、今年はコロナのパンデミック。正直、自分でもそんなに音楽は聴いてなかったんですよ。コロナ禍みたいな状況だと、みんな音楽の聴き方が変わるって記事も読みましたけど、新しいものを掘るよりは慣れ親しんだものを聴いてる人も少なくないと思う。新しいものの昂揚感よりも、想像できる範疇のものを聴いて、ほっとするみたいな感覚かもしれない。例えば、昔流行ったカーク・フランクリンのゴスペルの曲を聴いて「やっぱりいいな」みたいな感じだったりすると思うんですよね。だから、これだけ世の中が狂ってるときに、俺がとんがった音楽作っても今の空気じゃない気がしたんです。
今回の5曲に関して、「Joy」は少しは攻めた曲だから、今、俺がやってることとこれからやることを象徴してる曲だとは思いますけど、残りの4曲はほぼ歌ものや、ストレートなグルーヴ系の曲になってます。それらは今、聴いてもストレスにならないような曲にしています。自分自身もガツガツしたぶっといものが揃ったアルバムを今は聴きたくないので。だから、このEPには今の不安な気持ちがいろんな形で反映されてるとも思います。
――なるほど。
『2099』っていうタイトルも、もともとのイメージはプリンスの『1999』。『1999』がリリースされたころ(1982年)って終末思想が流行っていて、世界情勢も不安定(※東西冷戦、イラン・イラク戦争、フォークランド紛争など)でした。だから、プリンスは「どうせ世界が終わるならパーティしよう」って言ったと思うんですよ。不安だらけの世界の中で希望を持てる音楽ってことですね。そう考えると、2020年は自分たちが子供のころに感じていた1999年くらいの世界観なのかもしれないと気付いて、プリンスの題名に100を足した2099にしてみたら、しっくり来たんです。
後から2099年でググってみたら、スピリチュアルな話が出てきたんです。スピリチュアルな界隈ではエンジェル・ナンバーって呼ばれてる数字があって、その中でも2099って数字には意味があると言われています。そっちの人たちの中では世の中のために何かをする人のことを”ライトワーカー”って言うんですけど、俺たちの中には潜在的なライトワーカーがいて、2099っていうのはその潜在的なライトワーカーを目覚めさせて、世の中のために何かをさせるためのシグナルだって書いてありました。そのライトワーカーっていうのは世の中をよくするために何かを与えたり、持ってくる人間みたいな存在で、ヨガの先生や、教職、そして、ミュージシャンもそれに該当する。面白い話ですよね。
EPを作ろうと思ったときに、今、こんな終末っぽい雰囲気の中でネガティブなものを出す意味はないと思いましたし、もし俺が何かを出すなら、ポジティブな意味合いを持たせたいと思ったのはあります。後付けですけど、更に欲を言うと、俺が音楽を出したことで、その音楽を何かしらのシグナルとして受け取って、世の中のために何かをしようって、何かを高めようとか思ってくれる人が出てきたらいいなとも考えました。そういう気持でもなければ、こういう時期に何か出す意味はないですよね。
以下、ウェブで読めるBIGYUKIの過去のインタビューです。
併せてどうぞ。
※記事が面白かったら投げ銭もしくはサポートをお願いします。
あなたのドネーションが次の記事を作る予算になります。
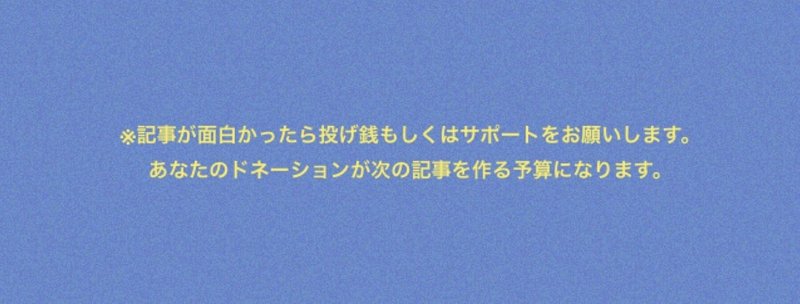
ここから先は
¥ 200
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
