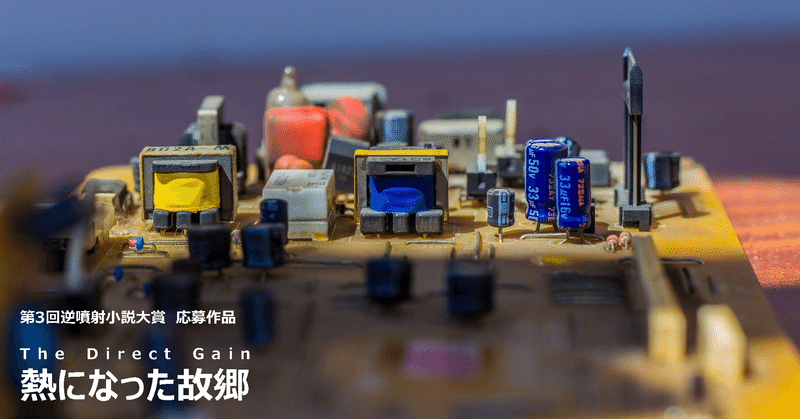
熱になった故郷
顔に被せられた白い布を振り落とし、彼は起き上がった。磁器のように固く冷たかった瞼が今は開かれ、自身の体を見降ろしている。
クラスの通夜。奇病の噂。さして仲が良くなかったくせに泣き崩れる級友たち。白い顔で固まった彼。それらが頭の中で渦巻き、逆巻いて、全身の力を吸い上げた。
ぐらりと視界が揺れ、すごい勢いで傾いていく。
排水溝に吸い込まれていくような世界。彼はそこからまっすぐ飛び出してきて、私を抱きとめた。
「大丈夫?」
前後が分からない。吐き気がする。起き上がった死体、その声でさらにかき乱されていく。
人はいつか必ず死ぬ。そして戻ってこれない。
それは自然の摂理ではなかったのか。15年間で学んだそれは、こんな何でもない顔と声で覆るものなのか?
「ごめん。驚かせて」
「尾久、くん……?」
「それもごめん。違う」
尾久春彬はそう言って、生前けっして見せなかった笑顔を私に向けた。
「自分は尾久春彬じゃない。でも」
言葉は引き戸の滑る音で遮られた。目の前で輝く彼の裸眼に白い服の看護師が映る。歪んだその姿は、こちらに何か突きつけたように見えた。
胸元でぶちりと音がした。彼の右腕が霞む。時を置かず、重いものが落ちたような衝撃音が背中の後ろで響いた。
ふらつく頭を押さえてそちらを向くと看護師が仰向けで倒れている。その額には細かいヒビが入っていた。尾久くんがそっと私から手を放し、素早くそれへ駆け寄る。その背中から目を離せないまま胸元をまさぐると、ブラウスのボタンがひとつ無くなっていた。
「こちらエス」
彼は看護師の手から黒っぽいものを引きはがした。どう見ても拳銃だ。映画やアニメでしかみないような。尾久くんはその凶器を、俳優なんかよりずっと無駄のない動きで確かめ、ポケットに押し込む。
さらに看護師の割れた額に両親指をかけ、卵の殻を向くようにはがし取る。金属の光沢をもつ何かが覗いていた。
「え、え?」
「見えてるか?見た目は日本製だ」
(続く)
サポートなど頂いた日には画面の前で五体投地いたします。
