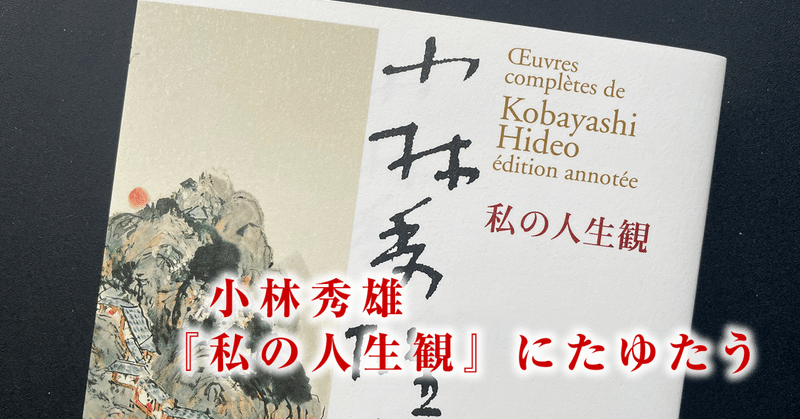
Cultureの本当の意味とは
自分では真っすぐに話しているつもりでも、周りからは話が逸れている、脱線していると思われてしまうこともある。
花を詠んだ西行の歌で胸がざわめく。それは仏教によって養われた我々の「美を観る眼」が心に浸透しているからだ。それが伝統であり、人間は伝統から離れて生きることは決して出来ない。伝統のないところの文化は存在しない。
そんな審美眼の話から一転して、小林秀雄は文化について話し出す。
一体文化などという言葉からしてでたらめである。
もともと民を武力を用いずに教化するという意味だった「文化」という言葉をcultureの訳語にしてしまったことに原因がある。果樹を栽培し、いい実を結ばせるのがcultureの意味であり、そのものの素質や個性を育て、発揮させることのはずなのに、個性を無視した加工であるtechniqueと混同している。これはおかしいと指摘する。
それこそ唐突で、小林秀雄の胸にわだかまっていた考えなのだろうが、いまひとつ分からない。しかし『私の人生観』の講演が行われた3ヶ月後の1949(昭和24)年1月に、別の講演をした内容が『文化について』と題して同年5月に発表されている。実はそのほうが真意をつかみやすい。
小林秀雄はcultureは栽培することだと定義したうえで、ドイツの哲学者ジンメルの文化論を紹介する。リンゴの木にはもともと立派な実を結ぶ素質と可能性があり、それを人間の知識と努力によって実現させた場合、リンゴの木を栽培したといえる。すなわちcultureだ。しかし、リンゴの木を材料として別なものを造った場合、リンゴの木にはもともとそんな素質は備わっていない。それはcultureではなく、『私の人生観』でいうtechniqueでしかない。
日本では、カルチャーという言葉は教養とも訳されているが、人がどんなに多くの教養を外部から取り入れても、その人の素質を育てないならば、その人は教養人、文化人とはいえない。その人のなかに人格を完成させる可能性があると仮定のもとに教養が役立つのだ。その人の素質や個性がその人自身を向上するという信念がなければ、文化を論じても無意味だと小林秀雄は指摘する。
さらには、文化とは単なる観念ではなく、むしろ人間の努力の精神を印した「物」なので、ある現実のはっきりした対象を材料として、人間の精神が何か新しい価値のある形を創り出した場合でなければ、文化という言葉は意味をなさないのだと断ずる。
小林秀雄は『私の人生観』でも『文化について』においても、語感のない言葉がでたらめに使われている、言葉に語感がないことは恐ろしいと語っている。本当の意味も知らず、また知ろうともせずに使ってしまう。見た目の良さや、周りが使っていることに流されて、その言葉を使っている自分に酔ってしまう。自らを文士と称し、言葉で生きてきた小林秀雄だからこそ、肚に落ちないところがあったのだろう。
最近では「哲学」という言葉が本当に軽く使われている。小林秀雄は名著「考えるヒント」における『哲学』で、なぜ西周がphilosophyをそのように訳したのか、じっくり考えている。それに触れたいところだが、まさに話が逸れる、脱線するので、いまはやめておこう。
(つづく)
まずはご遠慮なくコメントをお寄せください。「手紙」も、手書きでなくても大丈夫。あなたの声を聞かせてください。
