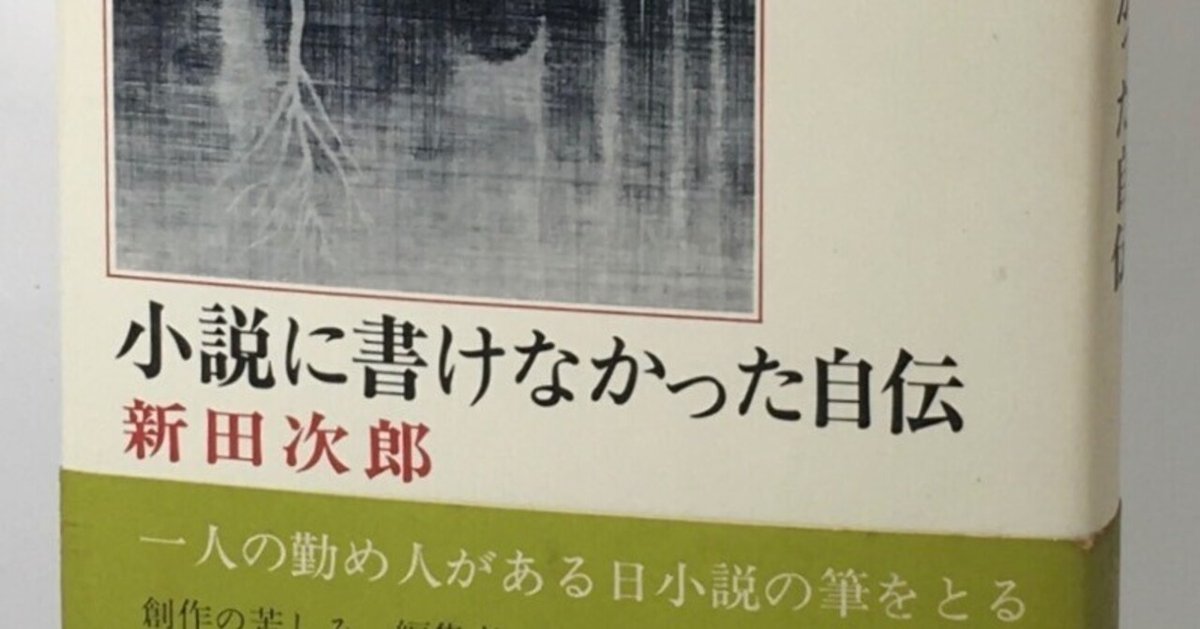
子供のころ、祖母に新しい本を買って貰うと枕元に置いて寝たものである。

『小説に書けなかった自伝』、タイトルに自伝とある本は手に取ってみる。ちょっと拾い読みすると、面白そうだったので買って帰った。これが当たりだった。新田次郎はこういう作家である。
新田 次郎(にった じろう、本名:藤原 寛人(ふじわら ひろと)、1912年6月6日 - 1980年2月15日)は、日本の小説家、気象学者。無線電信講習所(現在の電気通信大学)卒業。
中央気象台に勤めるかたわら執筆。山を舞台に自然対人間をテーマとする、山岳小説の分野を開拓した。『強力伝』(1955年)で直木賞受賞。作品に『孤高の人』(1969年)、『八甲田山死の彷徨』(1971年)などがある。
山岳小説にはまったく触手が動かないためこれといって新田作品を読んだ覚えはない。むろん山岳小説以外にも数多く作品を執筆しているが、それらにも縁がない。強いて言えば『八甲田山死の彷徨』や『アラスカ物語』の映画を見たくらい。文壇デビューしてからも長らく役人(気象庁職員)として二足の草鞋を履いていた。その理由というか、筆一本に踏み切れなかった心の動きは本書を読むとよく分かる。非常に率直に書かれている。
他には編集者とのやりとりがほぼ実名で記されており、文学史においては閑却されがちな黒子なのだが、編集者こそが作家を作り、そして動かして行くのだから、いや、個人的に編集者や出版人に興味があるから、その点も非常に面白かった。なかで最もエキサイティングなのが新潮社の斎藤十一である。
昭和34年の3月半ばころ、新田次郎は「週刊新潮」の新田敞からロアルド・ダール『あなたに似た人』(早川書房)を渡され《この本に書いてあるような傾向を持った小説を、書いていただきたい。》(p79)という依頼を受けた。一度は断ったが、押し切られて引き受けた。『冷える』というタイトルで12回連載(三ヶ月分)。まず3篇を書いて渡した。担当の南政範が受け取って面白いと思いますと言ったのだったが、3つともダメだった。
これにはショックを受けた。五時の過ぎるのを待って役所を出て、神田の喫茶店で南さんにくわしく話を聞いてみると、この小説を「週刊新潮」に載せるかどうかは編集担当重役の斎藤十一さんが決定することになっているので、われわれとしてはどうにもならないということだった。
新田はさらに5つほど筋書きを考えて南と相談のうえ2つを小説にした。
〈やっと通りました〉
という電話を二日後に受けたとき、二つとも通ったと思いきや、一つだった。つまり私は二十枚の短篇小説五篇を書いて、そのうち一篇が、やっとお取り上げ[5文字傍点]になったのである。(原稿料は掲載分だけいただいた)たいへんなことになったと思った。
2回目は3篇のうち1篇が取り上げられた。
七篇のうち二篇が取り上げられた経過から判断して、斎藤さんの好みがどうやら分るようになった。彼は、作者の頭の中ででっち上げたものではなく、社会一般に実在する(むしろ実在した)テーマを用いて創れ[2文字傍点]、と云っているのである。この時点に至って新田さんが私に要求していたものと、斎藤さんが要求しているものとの間にかなりへだたりがあることが分った。斎藤さんは恐怖をそれほど求めていなかった。
こういうスレ違いは頼まれ仕事ではよくあるだろう。この後も容易に斎藤のOKは出ず、新田は苦しみ抜く。なんとか12回を終えたが、創作の喜びなどというものは全くなかった。
『冷える』に関する限り、文学などというものとはほど遠いもので、それまで私が抱いていた、小説についての私なりの定義とかけ離れたものだった。これはテクニックだけの問題として処理されるべきものだった。私は商品としての小説の在り方を身を以て教えられたのである。文学意識のようなものはいっさい捨てざるを得ない、現代におけるもの書きの姿勢を教えられたとも云える仕事だった。
斎藤十一の真骨頂を示す逸話である。斎藤はあの『FOCUS』を創刊して一世を風靡した人物、さもありなん。
1981年(昭和56年)6月、新潮社専務取締役に就任。同年10月、自らの企画で写真週刊誌『FOCUS』を創刊し、やはり記事の全タイトルを自ら決定した。なお『FOCUS』を創刊する際のエピソードに、部下に「君たち、人殺しの顔を見たくはないのか」と発言したとされる。
古本についての記述も拾っておきたい。
私の勤務先から神田の古書店街までは歩いて十分ほどのところだから、昼休み時間の古本探しにはまことに好都合だった。持って行った大風呂敷を一杯にして帰ることがあった。買った古本は役所の私の机の上に積み上げられたり、書棚の気象関係の書類や文献などと一緒に置かれた。そういう本がたまり過ぎて置きどころが無くなってから、やっと家へ持ち帰ることにした。満員電車の中へ古本の入った大風呂敷を持ちこむといやな顔をされた。
読書についてこんなところもメモしたくなる。昔の人(明治生まれ)は音読がふつうだった。
祖母は本が好きだった。私に読んで聞かせる時も、自分で読むときにも声を出した。静かに霧が流れている夜に遠くの寺の鐘の音を聞いているような余韻のある読み方だった。祖母は冬は炬燵の上に本を置いて読み、夏は机の上にそれを置いて読んだ。
あるいは、新田次郎全集の第一巻を手にしたとき。
この夜、私はこの全集第一巻を枕元に置いて寝た。子供のころ、祖母に新しい本を買って貰うと枕元に置いて寝たものである。だが、この本は人が書いた本でも、買って貰った本でもなく私自身が書いた本である。これと同じような美しい本が、これから毎月一冊ずつ出版されて全部で二十二巻になるのだ。私はこの出来たての銀色の本に柏手でも打って拝みたい気持だった。
たしかに枕元に置いて寝ますね、好きな本は。ただし、小生の現状として、枕元は本だらけなのだが……。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
