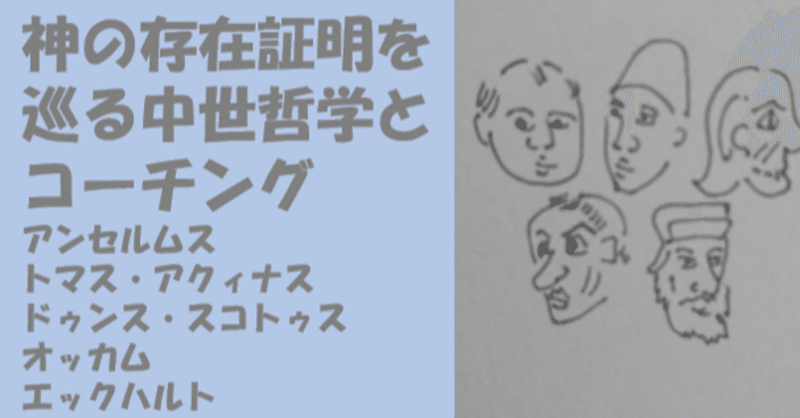
②トマス・アクィナスの神の存在証明とコーチング
今日は中世ヨーロッパ最大の哲学者と言われるトマス・アクィナスと、信仰・哲学を巡る主張について書いていきます。
信仰と理性の優位論争において調和の立場をとった
キリスト教がローマ帝国の国教になった後、古代ギリシャ哲学の遺産は東方のイスラム文化圏に流入・保存され、ヨーロッパ世界からは一時的に知られることがなくなりました。
1095年にローマ教皇ウルバヌス2世がエルサレム奪還を訴え、1207年に至るまで断続的に十字軍が遠征をする中で、ヨーロッパ世界はイスラム世界との交流を開始し、その流れの中で主にはアリストテレスの思想がヨーロッパ世界に逆輸入される現象が起きました。
アリストテレスの研究をしていたイスラムの哲学者イブン・ルシドは、神への「信仰」は哲学の「理性」に従属すべきだと説き、やがて「信仰にとっての真理」と「理性にとっての真理」は別次元のものであるという「二重真理説」を提唱するラテン・アヴェロエス派をキリスト教世界に誕生させます。
「二重真理説」は矛盾する二つの命題が、一方が哲学の原理で真理であれば、真理であり、他方も宗教的信条によって真理であれば、真理であるという立場で、パリ大学を中心に広がりました。
この勢力はキリスト教の教義や神学に対する哲学(実際にはアリストテレスの哲学)の優位あるいは自律を強く志向する方向に傾倒していたため、神学の哲学に対する優位を絶対視する伝統的神学者や教会から断罪され、キリスト教会からは度重なる異端宣告を受けた思想だったようです。
トマス・アクィナスはラテン・アヴェロエス派のこのような考え方に真っ向から反対し、キリスト教の「信仰」とギリシャ哲学の「理性」との調和を目指した哲学を展開しました。彼は、「自然の光(理性)」によって、我々は真理を類推することはできるが、これには限界があり真理そのものに到達することはできない。そこで「恩寵の光(神の啓示)」によって、我々は類推の先にある真理に到達できると主張したのです。
一連の信仰と理性の優位論争、私にとっては論争それ自体に現代につながる示唆が大いにあるかというと、疑問はあります。しかし、歴史の中では大きな必然があったのだろうなとは思います。
キリスト教神学の絶対性を教条的に語る教会が統べる思想界において、アリストテレスの哲学という人間の知的好奇心や理性を刺激する思想が流入し、その間でヨーロッパ世界で思想的せめぎ合いが起こったことはある種必然だったのだろうなと思います。成人発達理論的に言えば、ヨーロッパの思想界の中枢では、神話的合理性段階(他者依存段階の別名)と合理性段階(自己主導段階の別名)の間で激しい葛藤が生じ、合理性段階が橋頭保を得ていく最初のプロセスだったのではないでしょうか。
トマス・アクィナスは神学者でありながら哲学者でもありました。彼は当然に信仰深くはあったのでしょうが、キリスト教神学の絶対性を教条的に語る教会世界という厳しい制約の中で、何とか哲学の、人間の理性の居場所を確保したいと思ったのではないでしょうか。信仰と理性の優位論争の中には、そうした意図、人間の理性を拠り所として生きるあり方を社会の中に芽生えさせたいという思いが込められていたのかもしれません。
コーチング的に考えると
トマス・アクィナスの信仰と理性を調和させる考え、すなわち
「自然の光(理性)」によって、我々は真理を類推することはできるが、これには限界があり真理そのものに到達することはできない。そこで「恩寵の光(神の啓示)」によって、我々は類推の先にある真理に到達できる
とする考えは、コーチングに引き寄せても価値ある示唆があると感じます。この構造はコーチングを通じて我々が主体的真理(自分にとって生きがいになる理想、自分固有の生きる目的)に近接する時の状況とよく似ているからです。ちなみに主体的真理を解説しているnoteはこちら。
我々はコーチングの中で、自分が人生において本当に求めていること(主体的真理)を内省し、手掛かりを得ていこうとしますが、それは理性という類推を重ねていく思考機能においてはうまく機能しません。
自身の主体的真理への近接は概して深い内省状態であり、思考を止めて、イメージを駆使する中で、身体感覚として「これだ!」と感得する瞬間に起こるものです。ちなみにそのような意識状態へクライアントを誘うのがコーチの役割だったりします。
これはおそらく、トマス・アクィナスの言うところの恩寵の光(神の啓示)の感覚に近しいものがあるのだと思います。
ただ、身体感覚において感知した自身の主体的真理は、間違いなく真理をとらえているという感覚が芽生えたとしても、抽象度が高いものだったりします。そのため、次の工程として理性的な類推を駆使して、その具現化の方法を考察していく必要が生じるのです。
そのように具現化し、実践を重ねてくれば、身体感覚において新たな違和感などが生じ、さらに自己の言葉にならない主体的真理に近接するための内省が促される契機が生じます。これは紛れもなくある種の恩寵と言っても良いでしょう。
トマス・アクィナスが生涯をかけて努力してきたキリスト教と古代ギリシャ哲学の調和という思想的営みは、我々の心の原理を捉えたものだったのかもしれません。その意味では重要な仕事をした人だなと思います。
さて、トマス・アクィナスですが、最晩年の1273年に教会のミサに参加した後、友人に対して「私が今まで書いたものは、わらくずに見える」と語ったそうです。彼はその前に何らかの神秘体験をしたと伝えられ、その後大著である「神学大全」を断筆してしまいました。
何があったのでしょうね?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
