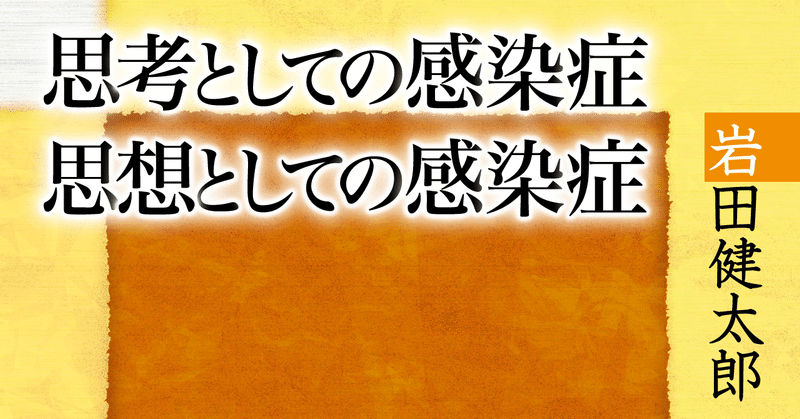
思考としての感染症 思想としての感染症[第一章](中外医学社アーカイブス)
『思考としての感染症 思想としての感染症』(2008年04月発行)
岩田 健太郎 いわた けんたろう 著
哲学の目的は思想の論理的な明晰化である
哲学は学説ではなく、活動である
心理学が他の自然科学のいずれかより一層哲学に近縁である、ということはない
哲学は自然科学が論議可能な領域を限界づける
日常言語は人間という有機体の一部であり、そしてそれに劣らず複雑である
――ウィトゲンシュタイン「論理哲学論考」より
Who never climbed high never fell low.
高きに伸びることのない人は、低きに落ちることはない
――Thomas Fuller
本書は臨床感染症の教科書の中では、「上級」と位置づけている。従って、基本的な勉強を済ませた読者を対象としており、青木眞先生の「レジデントマニュアル」や「サンフォードガイド」といった定番のツールが使いこなせていることを前提とする。
このようなプロセスを踏まずに本書を読むことは、おそらくは時間の無駄であろうし、場合によっては読者、さらには患者に有害である可能性すら、ある。万が一、初学者の方が本書を購入してしまった場合は、古本屋に売るか他人に譲るか、あるいは他書で勉強してから本書を開くことに決めるのがよい。
かといって、本書は「いわゆる」感染症の専門家だけを対象にした本でもない。むしろ、感染症診療に従事している医師全体をターゲットとしている。すなわち、ほとんど全ての臨床医である。感染症と関わり合いにならずに診療行為を続けていくことは、不可能、と断言していいほど難しいからである。
本書は、超稀な専門家チックな感染症の解説書ではなく、どこにでもあるような感染症をどこまで質を上げて診療することができるか、練度を上げることをできるか、コモンな問題の解決ルートの進化、そして深化を目指した書物である。対象とするのは、例えば、かぜ症候群のようなコモンな疾患である。
かぜ症候群をもっともシンプリスティックに記載してしまえば、
「上気道のウイルス感染症、鼻汁、咳嗽、微熱などを伴う。自然治癒するので対症療法のみ。抗菌薬は不要」
程度の記載でおしまいにすることもできよう。ワシントンマニュアル的な教科書であれば、むしろ簡潔にして要を得た、このような短い記載の方が多忙な診療医にとっては便利なことだろう。その効能はもちろん否定しないし、私自身、入院・外来診療においてこのようなマニュアル本の恩恵を強く受けている。
とはいえ、このようなマニュアル的な診療で対峙したかぜ症候群の場合、その成果は70点くらいである。従って、「まあ7割くらいのそこそこの診療でも俺はいいや」くらいを目標にしている場合には本書は適さない。
それが、悪いというわけではない。感染症だけが診療なのではなく、むしろこの分野だけに殊更に知性や情念を振り向ける方がバランスの悪い行為であろう。なるほど、赤点はつかないが満点ではない。しかし、合格点をとれるケアを幅広く行うのも大事なことであるが、せっかくよく見るコモンな疾患のことである。できれば100点満点を目指したいではないか。もちろん、100点満点のかぜ診療は私自身がまだ見たことのない未知の領域ではあるが。
本書は、感染症のことを深く考えつつ、その外部にあるもの、アウトサイダーの存在も強く意識している。感染症のことばかり考えていると、逆説的に、しかし必然的に感染症診療の質も下がってしまう。感染症オタクは良い感染症医にはなれない。むしろ感染症医は自分たちの領域を一歩離れたところから、一歩立ち止まって見るもう一人の自分を必要とする。もう一人の自分探しが、本書の最大の目標の一つである。
自分探しとは、アイデンティティーの確立のことではない。むしろ、しなやかさや腰の軽さが重要視される臨床行為においては、強固なアイデンティティーの確立は足手まといになる可能性が高い。俺は感染症の○○太郎だ、なんて大声をだしたとたんに、まともに感染症をみることができなくなってしまう。
もう一人の自分とはもう一つの視点に過ぎず、決して「立ち位置」のことではない。立ち位置なんて作るべきではなく、よく学会シンポジウムで見られる「○○の立場から」という表題くらい陳腐なタイトルは、ない。
感染症という分野はへんてこなもので、その診療行為には医師であれば誰でも参加できる。脳外科医以外が開頭手術を行うのは、通常の医療環境であれば、ほとんど犯罪行為と言っても良いが、感染症医以外が抗菌薬を処方するのは内外から許容された当たり前の行為で、まっとうですらある。多くの医師が、感染症医と同じくらいの感染症を経験している。感染症は、例えば変性疾患などと異なり、一般医家にとって稀な事象、例外ではなく、日常そのものといって良いであろう。
その日常たる感染症診療なのにもかかわらず、いや日常的であるが故になのかもしれないが、我が国ではこれまで系統的に教育が提供されてこなかった。いや、過去形で言うのは間違いであろう。現在でもほとんどの大学では医学生に系統立った感染症の教育を提供していないし、卒後研修病院のほとんどもそうである。
しかし、それでもここ10年で事態は大きく変動している。私が医師になった頃は、日本語で書かれたまともな感染症の教科書は皆無であった。この「皆無」という言葉は誇張ではなく、文字通りそうであった。青木眞先生の「レジデントマニュアル」がこの閉塞的な状況に終止符を打ち、独学でがんばる医師にも、妥当な感染症診療を可能にするツールが与えられた。
現在では、感染症の教科書が雨後の竹の子のようににょきにょきと出版されており、選ぶのに困るほどである。やる気のある医師にとっては幸福な時代がやってきた。しかし、残念ながら現在に至っても「勉強している人だけが分かっている」状況は打開できていないし、真面目な診療医が、不真面目で不勉強な医師から「俺たちと違うことをやっている」と理不尽な白眼視をされかねない環境も温存されている。格差社会の黒白が明白になった、とシニカルに見ることすら、可能だ。
が、それでも前進は止まらない。良貨が悪貨を駆逐するのも、そう遠い話ではなかろう。感染症暗黒の時代は、ベクトル的には向上の一途をたどっている。
一方、「サンフォードガイド」やそれに類似する教材が定着していく中で、感染症診療のフィールドでは一種の困惑が生まれ始めてきたのも確かである。これは、一つのステップアップを経験したあとで、初めて生まれる焦りであるから、一種、贅沢な悩みである。ある高さまで登り詰めて、はじめて俯瞰できる光景といってもよい。それは、スタンダードと呼ばれる得体の知れない何かが、あたかも実在するかのような幻想が生じてきたときに、必然的に生じた疑問点である。
言い換えるのならば、レベルを上げたことが、レベルを下げたのである。ボトムアップを図るためのマニュアル化は、後に指摘するように、あらゆる構造において同じ誤謬を繰り返している。
「結局尿路感染はシプロですか?」
「とりあえず血液培養は2セットですか?」
マニュアルが「スタンダード」と称されるものを提供し、感染症診療は「容易」になる。しかし、現実は異なる。どんなにマニュアルが整備されようとも、感染症診療は実に難しい。その事実そのものは変わりない。マニュアルの存在が、それをあたかも「容易であるかのように」表現しているだけなのである。
稀な、一生見たこともないばい菌が相手の感染症の話ではない。むしろ、そういう希有な感染症に対峙する方法はあらかた決まっている。いったん診断さえつけてしまえば、さして迷うことはない。カラ・アザール(リーシュマニア感染症)の治療法なんて、あまりオプションはないのである。
超重症感染症の場合も、ほとんど選択肢は限られている。敗血症性ショックであれば、水の入れ方からなにから、いまやプロトコルは決まっている。困難が伴い、労働量は多いが、アルゴリズム的には比較的シンプルだ。「うーん。このショックの患者さん、抗菌薬使おうか、やめようか」などと悩むことは、あり得ないだろう。
むしろ問題になりやすいのは、微妙な熱とか、かぜとか、そういった日常的な疾患である。これらを上手にやりくりするのは、容易なことではない。そこには不確定性、曖昧さ、複雑さ、そして確率論的な世界が周囲を取り巻いているからである。押すべきか、引くべきか? このような場合、感染症診療は極めつけに難しい。
こういう場合、サンフォードガイドに記載されている事項を丸写し、という診療も芸がないものである。目の前の患者は複雑な社会背景を持つ複雑な既往歴を持つ、複雑な病態を持った微妙な存在である。そのような存在に対して、クリアカットな判で押したような一律な医療がフィットする、と考える方がむしろ不自然な態度であろう。
このような場合には、複雑なものを複雑なままに受け入れるのが、自然な姿と言えまいか。複雑なものには複雑に対峙するより他、ないのである。従って、この時点で、一回マニュアルを捨てる覚悟を決めなくてはならない。シンプルでイージーで便利ではあるが、画一的で無感情で融通の利かないマニュアルを、である。
もちろん、これは過去への回帰の薦めではない。かつてのような「なんでもあり」の時代への回顧ではない。マニュアルは読まなければならない。少なくとも、一度は読まねばならない。60〜70%はカバーするであろう「スタンダード」と称されるものの存在も十分に意識しなければならない。マニュアルを読まずにマニュアルを捨てるのは暴挙である。だから、初学者は本書を読まない方がよいのである。
マニュアルをじっくりと読み、その背景にあるものも理解し、しかし目の前の患者においては、一度マニュアルを離れる。剣豪が一度剣を捨てることによってさらなる進化を遂げるように、である。一度得てから、捨てるというのは大事な態度である。キリスト教をかすりもしないで、ニーチェのようにキリスト教のルサンチマンから解放されようと試みても、単なるつまらない無神論者になるだけなのだ。格に入りて格を出でざるは時に狭く、又、格に入らざる時は邪路にはしる。格に入りて格を出でて初めて自在を得べし、とは松尾芭蕉の言葉だそうだ。
本書は「分かりやすい」本ではない。私はこれまで、デフォルメ、誇張、簡略化を意図的に用い、誰にでも分かるような説明を追求し、講義や文章を用意してきた。しかし、それは複雑な事象が複雑である、という事実から目を背けた行為でもあった。私はそれを確信犯的にわざと行ってきたものであり、後悔するべきものではないし、それはそれで一定の役割を果たしている。今後も、このようなスタイルでの情報提供は継続しなくてはならないだろう。
しかし、ものごとには必ず作用と反作用がある。簡潔明瞭な情報提供は有用だが、それに対するアンチテーゼは当然必要であり、それなくしては良質なバランスがとれないだろう。
別に、難解な用語をことさらに用いたり、ひねくれたり、ほのめかしたり、読者を困惑させて喜ぶ意図は持っていないが、かといって本書は決して分かりやすくはない。読んでもよー分からん、という読者が少なからずいることは、覚悟の上で書いている。他に、表現の仕様がなかったからである。
本書を読んで「よく分からん」という読者は、まだ本書を読むレディネスができていない可能性がある。同時に、「よく分からん」は、実は本書の本質をある程度理解しているからなのかもしれない。後者の場合は、心配ない。本質的に難解な感染症診療を理解するのに「難解だ」と感じるのは健全だからである。難しい、と感じた読者の半数は、それほどがっかりしなくても良いだろう。
本書を読んで「なんだ、たいした話をしてないな、別に難しくもないや」と感じた読者もいるかもしれない。その場合は、その読者がすでに感染症診療について十分な理解ができているからなのかもしれない。逆に、感染症診療を全く理解できていないから、「むずかしくない」のかもしれないが。
いずれにしても、読み手の手に渡った瞬間から書き手は全てを読者にゆだねるのが筋であるから、私がこれ以上立ち入ることはない。
能書きが長くなった。早速、我々が遭遇する最もコモンな感染症、「かぜ」の考え方からスタートしたい。
※本コンテンツは2008年刊行『思考としての感染症 思想としての感染症』(岩田健太郎)を再テキスト化したものであり、以下は有料となります。
※本コンテンツでは『思考としての感染症 思想としての感染症』の第一章(書籍時157ページ)を読むことが出来ます。
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
