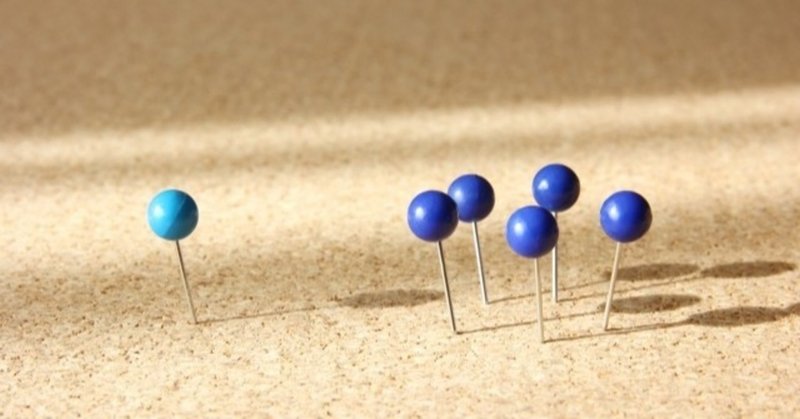
ぼくのなかの日本(第10回、いじめられっ子)
いじめられっ子
はたして、ずっと同じクラスにいた子供から見て、転校生はどのように映っているのだろうか。一年生のときから一緒に遊び、おそらく家も隣近所という幼馴染たちになかに、小学校高学年から入り込んだ異分子が溶け込むことは、本当に可能なのだろうか。元からいた子は、自分たちこそがこのクラスの主だと考え、転校生を受け入れるとしても、結局気前のいい主人が賓客をもてなすのと同じ気分ではないだろうか。ましてやぼくの場合、言葉の壁が加わる、彼らの仲間になるのは無理だーー日本に来てから半年後、隅っこ暮らしに慣れたぼくはこんな考えに支配され、それならそれでいいと思っていた。
ところが、有栖川くんは、ぼくの考えのはるか斜め上を行く行動によって、転校生の生き様とでも言うべきものを、教えてくれた。
「今日から転校生が来ます。みんなで暖かく迎えましょう。有栖川くん、どうぞ!」ととも教室に入ってきた男子は、誰がどう見ても人気者になれそうになかった。黄ばんだ顔に出っ歯、やつれた頬に尖った顎、洗濯したかどうかも不明な薄汚れた服、服の下の腰は曲がっていた。目だけは妙にくりっとしていたが、他の容姿と相まって、逆に彼をネズミっぽく見せていた。自己紹介も惨憺たるものだった。有栖川くんは終始どもり続け、名前以外の情報をほとんど伝えることができなかった。まだ日本語と苦闘していたぼくでさえ、「この人、本当に大丈夫か」といぶかしがり、不謹慎にも「まさか障害でもあるんじゃ…」などと考えていた。
初日からそんな調子の有栖川くんの元には、好奇心で同級生が集まり質問攻めにしたが、あまりにも会話が進まないため、午後の時点でもう誰もいなくなった。ぼくも有栖川くんに自己紹介くらいはしたはずだが、会話を交わしたかどうかは全く覚えていない。しかし、当の有栖川くんはというと、転校デビュー大失敗に終わったにもかかわらず、落胆した様子もなく、登場時と同じヘラヘラした笑顔を浮かべ、出っ歯を惜しげもなく見せつけてきた。
こりゃだめだ、絶対ハブられる。ぼくはそう思った。実際に女子はすぐに興味を失い、あからさまにいやな顔をし、これみよがしに「フケツ」と言う人さえいた。しかし、たとえ耳に入っても、有栖川くんはあくまでヘラヘラしており、誰に対しても頭を下げた。仲間はずれの対象であるぼくでさえ、「何だこいつ」と気味悪く思い、無関心を決め込むことにした。
しかし、一ヶ月くらいすると、有栖川くんがなぜかいつもクラスでも人気者の男子と一緒にいることに気がついた。サッカー部のエースでもあるその子は、昼休みになるとよく有栖川くんのところに行き、同じサッカー部の仲間と一緒に教室を出てどこかに行っていた。戻ってきた頃には、全員が清々しい顔をしており、有栖川くんのヘラヘラでさえ心なしか明るく見えた。
やるじゃん。しかしどうやったんだろう。特段興味があったわけではないが、一応クラスにいるもうひとりの中国人・向井くんに聞いてみることにした。「ちょっと違うよね」に一緒に顔を真っ赤にした彼は、その後サッカー部に入っていたからだ。
「なあ、向井、最近有栖川とサッカー部仲いいじゃん。」ぼくは中国語で聞いた。
「仲がいい?はは、それ誤解だよ。有栖川はただ殴られているだけだよ。」中国語なら誰にもわからないことに安心したからか、向井くんは何のためらいもなく答えた。
「はあ?嘘だろ?だって有栖川は喜んでるように見えるけど?」
「あいつはそういうやつなんだよ。殴られたら喜ぶの。お前もやってみる?」
ぼくがなんと答えたかは覚えていないが、向井くんはその日の放課後、ぼくを誘って一緒に有栖川くんを呼び出したことからすると、少なくとも拒否はしなかったはずだ。二人が一緒に通っていた帰国子女クラスの部屋の近くは人通りが少なく、有栖川くんはその前で、ぼくたちに挟まれる格好で、ヘラヘラしながら言った。
「な、なんですか…」
「ううん、なんでもないよ。」向井くんはそういいながら、ゴツンと有栖川くんの頭を拳で小突いた。その後も肩、胸、背中、腹…上半身にまんべんなくパンチやチョップを浴びせ、有栖川くんはそのたびに体をよじらせ、しかし逃げる様子は一向になく、むしろできるだけ表情を向井くんに見せるようにしているようにさえ見えた。確かに殴るといっても、ぼくが想像したような強さではない、怪我をする恐れはないだろう。それでもこんなに何回も小突かれたら嫌に決まっている。あいつはなんでこんなのに耐えられるんだ?
「お前もやってみろよ。」向井くんは気が済んだのか、ぼくのほうに押しやるように有栖川くんの肩を押した。有栖川くんはくりっとした目で上目遣いをしてきて、その小動物のような表情に似つかわしくない出っ歯と汚れた肌が目に入ったぼくは急に嫌悪を覚え、思わず彼の顔を小突いた。
「や、やめてください…」弱々しく、目には涙のようなものさえ湛えながら、しかしやはり逃げる様子はなく、有栖川くんはぼくを見つめながら言った。ぼくはその目に耐えられず、もう一度彼の顔に向かって手を上げた。
数カ月後、親の転勤で転校してきたという有栖川くんは、またもや親の転勤でこの学校を去ることになった。盛大な送別会が催され、彼を無視していた女子も、その後も繰り返し殴っていたであろうサッカー部も、温かい寄せ書きと拍手を送った。感涙した有栖川くんは掉尾を飾る挨拶をするように先生に促され、初登場の日とは比べ物にならないくらいしっかりとした口調で言った。
「短い間でしたけど、このクラスにいることができて、本当によかったです。前の学校では、誰も相手をしてくれませんでした。でもここでは、みんな相手をしてくれます。本当に、ありがとうございました。さようなら。」
それを聞いたぼくも、教室の隅っこで、一人で泣いていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
