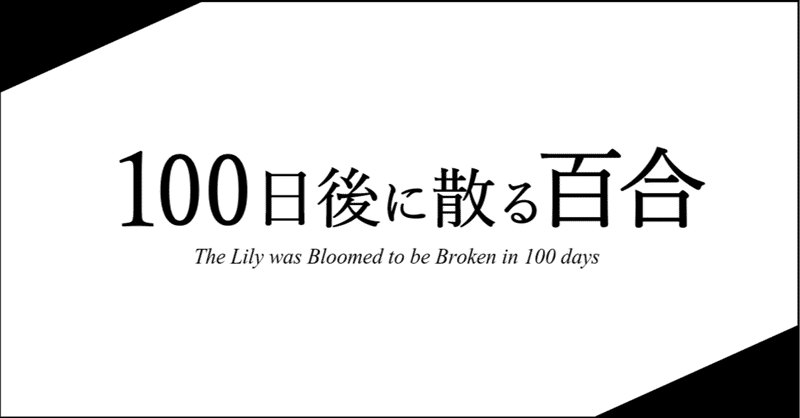
100日後に散る百合 - 72日目
「スカウト?」
「そうだ」
「誰を?」
「立川を」
「なにに?」
「だから、さっきから言ってんだろ」
口元にメロンパンの食べカスを付けたままの風薇は、一度折りたたんだ紙を開いて、机に叩きつける。
無駄に広い囲碁将棋部部室に、硬い音が響いた。
その紙には、”ミスコンテスト出場依頼”と書いてある。
「まあ、うちの学校のレベルは総じて低いわけではない」
風薇は咲季を指さし、
「しかし立川、お前の頭は顔一つ、あ、間違えた。お前の顔は頭一つ抜けている」
「風薇、指ささないの」
「おう、悪い」
立てた人差し指を仕舞うわけではなく、すべての指を伸ばして手を広げた。
ミスコンテスト。
うちの文化祭のひとつの大きなイベントで、5人くらいが候補者に選ばれて、来場者の投票によってグランプリが決まるというものだ。
出場者は自薦・他薦、両方受け付けているそうだが、実行委員会が直々にオファーというのは一体どういうことだろう。
「聞くところによると、立川の噂は学校中でもそこそこ広まりつつあるみたいだぞ」
「え、どういうこと?」
「2年3組に顔の良いやつがいる、と」
なんてことだ。
まったく、咲季をそんな見世物みたいに扱わないでほしい。
「で、どうだ?考えてくれたか、立川」
「んー、誘ってくれるのは嬉しいんだけど……」
風薇は、昨日から咲季に出場を打診しているらしい。
昨日咲季が送って来た写真はその時のもので、私に「風薇ちゃんがね」と話そうとしていた内容もこのことだったようだ。
「立川なら、グランプリ間違いないと思うんだけどな」
”出ようとしない理由が分からない”とでも言いたげに、風薇は不思議そうな顔をしている。
私は率直な疑問をぶつけた。
「ていうか、なんで実行委員が直接依頼に来てんの?」
「それがなー、まあ、実は毎年こんなもんなんだ。自薦で出てくれる人なんてまずいないし、他薦で来る人も、正直言うと微妙だったりするらしいんだ」
「それで、スカウト?」
「そうだ」
企画自体がままならないならミスコンなんてやらなきゃいいのに、とも思うのだが、実情はそうもいかないのだろう。
「頼むよ、立川~。このままだと企画がおじゃんになるんだよ~」
「いやあ……………」
「立川が出てくれたらきっと皆も盛り上がるし。な?どうだ?」
風薇が咲季の肩を掴んで懇願する。
おい、近いぞ風薇。私の彼女だぞ。
ブーブー ブーブー
「お、すまん」
電話だろうか、風薇がポケットからスマホを出す。すると画面を見るなり、あどけない子供の様に目を輝かせた。
「はい、もしもしお姉様!」
ん、お姉様?
風薇は一人っ子だったはずだが。
「お姉様の方はどうですか?……………はい、あ、そうですか…………いや、こっちも、ですね、はい」
ずっと黙っている璃玖(描写されてないけどずっといた)の方を見遣るが、お姉様なんて知りませんといった感じで首を横に振られる。
「え!?あ、はい、今からですか!?は、はい、囲碁将棋部の部室ですけど……あ、はい、わかりました」
通話が切れて、耳からスマホを離した風薇が変な顔をしている。可愛いというか、乙女っぽいというか。
ていうか、
「風薇、”お姉様”って、誰?」
「え、あー、えと、先輩で」
「なんか、メロメロじゃなかった?」
「メ、メロンパンさっき食ったからな!!」
「何を言ってるんだ」
ガラガラ
背後で扉の開く音がした。
建付けの悪いここの扉を、いともスムーズに開けた人とは、
「あらあら、ここは天国かしら」
背が高い。
栗色のふんわりカールした髪、長い睫毛、垂れ目。
胸が大きい。お尻も大きい。
綺麗な人だ。
うーん、確かに、
「お、お姉様!!」
確かに、お姉さんだ。
「もう、フーラったら、そんなに喜んでどうしたの?」
「いえ、べ、別に喜んでは……」
「あら?喜んでくれてないの?お姉さん悲しいなあ」
「あぅあぅぁ、喜びました!!お姉様と会えてうれしいです!!」
「それよりフーラ、パンくずが付いてるわよ」
「あっ……」
何を見せられているんだろう。
ていうか、どうした風薇。やっぱりメロメロじゃないか。こんな風薇知らないぞ、怖い。
でも、どうもこのお姉さんに弄ばれているようだ。珍しいものを見た。いい気味だ。
「ふふ、ごきげんよう。私、3年の新美杏。文化祭実行委員会の副委員長なの」
そう言うと、杏先輩は聖母のような微笑みを見せた。
頭につけた大きくて白いリボンが揺れる。
「いつもフーラがお世話になってるわ」
指先で風薇のサイドテールをいじる。風薇が「ぅにゃぁ」と変な声を出す。
「それで、あなたが、立川咲季さんね?」
その顔のまま、咲季に近づく。
え、なんか近くね?
咲季も思わず強張っているようだ。
「ほんとに綺麗な子ね…………」
まるで独り言のように呟く唇は、妙な色気があった。
なぜか悪寒がする。落ち着かない。
「えーと、フーラから話は聞いてると思うけど、立川さん、ミスコンにぜひ出てほしいの」
杏先輩の声は落ち着いていたが、
「あの、ごめんなさい、私、あんまりそういうの興味なくて……」
咲季が断るのを見ると、やや挑発的な口調で、
「そう、興味ないかあ。でも、”自信がなくて”とは言わないのね?」
「えと…………?」
小首をかしげる咲季。だが、発言の意図が分からないのは私たちも一緒だ。
「オファーを断る子たちはね、だいたい”自信がないので”って言うのよ。でも、あなたは”興味がなくて”と言った。自分にミスコン出れる素質があることは重々承知なんじゃないのかしら?」
「え、いや、そんな、私は」
「いいの。それはまったく恥ずかしいことではないわ。自分の強みを知っているということは、とても素晴らしいことよ」
「は、はあ」
「あなたが自分のポテンシャルを自覚していないと言い張るならそれでもいいわ。それなら私が保証してあげる。あなたは、ほぼ確実にグランプリよ」
何が言いたいんだこの人は。
「ねえ、立川さん。試してみない?自分のこと」
じっと目を見て離さない。
「今あなたの中に自信があろうと不安があろうと、ここでグランプリを獲ることはあなたにとって、すごく大きなものになると思うの。あなた、部活は?」
「いや、入ってないです……」
「バイトは?」
「してません……」
「そうだ、フーラから聞いたわ。転校生なのよね」
「はい……」
「高校生活っていうのは、一瞬で終わってしまうものよ。あなたが大の勉強好きなら文句は言わないけど、部活もバイトもやっていないとなると、思い残すことが出てくるかもしれないわ」
咲季の目が、少しずつ思慮深いものになっているのに気付いた。
「それにね、あなたが自分の素質を生かさずにいるのは、とても勿体ないと思うの。ねえ、皆もそう思うでしょう?」
急にこちらに話を振られて、思わず頷いてしまう。
まあ、嘘でも何でもない。咲季はスタイルだったり顔の良さだったり、活かした方が良いとは思う。
「もちろん他の4人も、きっと良い子たちが揃うはずよ。うちの学校だもの。それでも、あなたはきっと頂点に立つ。あなたが高校を卒業して、どういう道を歩むのかは分からないけれど、ここで得た経験はあなたの大きな糧となるし、生き方を考える上でも絶対に役に立つと思うわ」
そこまで言って、杏先輩は咲季から離れた。
当の咲季は、口をきゅっと結んでいた。
私は、このまま彼女がどんな答えを出すのか、少し分かってしまったような気がした。
でも、心がどこかチクチクして、その予想が外れてほしいとも思っていた。
「咲季」
「あ、うん? 萌花?」
「あの、自分の最初の気持ちは大事にして…………」
「モカ、お前」
「先輩が言っていること、確かにそうだと思うけど、でも、ごめんなさい。どうしても口車に乗せられているような気がして」
気持ちの矛先が杏先輩に向く。
「風薇から聞きましたよ。ミスコン、出場者がなかなか集まらないそうですね。それで咲季にスカウトしたと」
「ええ、まあ、そうよ」
「…………ミスコンをやる理由って、なんですか」
「理由?」
先輩は特に考えるでもなく、
「だから、ステップアップというか、自分の魅力を出せるようにとか、強い女性になれるようにみたいな、そういうお手伝いのつもりで―――」
「じゃあ、スカウトなんてしなくてもいいでしょう。ミスコンに出たいって言った人のサポートだけしてればいいでしょう。わざわざ”興味ない”って言ってる人を引き込むなんて、余計なお世話だと思いますけど」
私も大概だ。
それっぽいことを言って、相手を説得しようとしている。口車に乗せようとしているのと一緒だ。
「自分たちで勝手に企画して、頓挫しそうだからスカウトして。あなたたちはミスがいて初めて成功できるんですよね。それでお客さん集めて、ミスの評価させて、順位付けして。運営側はそれで”思い残すことのない高校生活”が送れるかもしれないですけど。なんか、自分勝手すぎませんか?自己満足でやってませんか?」
「ちょと、萌花?」
「咲季は……客寄せパンダじゃないんだよ……………」
きっと、これが本心じゃないことは分かっていた。
私はただ単に、咲季がミスコンに出るのが嫌なんだ。
実行委員会の理念とかはどうでもいい。
咲季が出場することで、色んな人に知られるだろう。学内からも、学外からも。
それで、恐らく皆が咲季に選んで投票する。
それがなんか許せないんだ。
皆、咲季のことなんか全然知らないくせに、評価されてしまうのが嫌なのかもしれない。
他人が咲季を見て、可愛いと騒ぐのを見たくないのかもしれない。
誰かが咲季に惚れてしまったらどうしようとか、言い寄られたらどうしようとか、そういう懸念だってある。
もしかしたら、咲季が皆に認められるようになった時、また自分の愚かさをまざまざと見せつけられることへの恐怖なのかもしれない。
なんにせよ、咲季が誰かに選ばれる様子を、私は直視できないと思った。
「そういう意見があるのは知っているわ」
杏先輩の声は、意外にも優しかった。
「ちょっと私たちも焦っているところがあった。反省しているわ。ええと、」
先輩が、何かを促すように見てくる。名前か。
「あ、金子です。すみません、なんか」
「いいのよ。少し私たちの方でも見直そうと思う。ね、フーラ?」
「そ、そう、ですね」
「立川さん、無理やり誘ってしまってごめんなさいね。でも決して虚言ではないの。あなたは”持ってる”わよ。また気が向いたら、フーラに連絡して?」
「は、はい…………」
「じゃあ、私は失礼するわ。どうもありがとう、金子さん」
建付けの悪いはずのドアをすんなり開けて、先輩は去っていった。
「……………」
「……………」
「……………ごめん、風薇」
「なにがだ」
「いや、なんか、なんとなく」
「意味もないのに謝るな」
「ごめん」
広い教室で反響する自分の声は、後悔に似たざらつきがあった。
風薇は、机の上に出した紙を畳んで、ポケットにしまう。
咲季は、じっとそれを見ていた。
「モカは変わったな」
「……………そう?」
「初対面の相手に、あんなこと言わなかっただろ、今まで」
その変化を歓迎するでもなく拒むでもなく、それをただの事実として、淡々と言った。
「立川」
「ん、なに。風薇ちゃん」
「強制はしないが、気が向いたらよろしくな」
「あ、うん……」
煮え切らないようだった。
それで帰ろうとした風薇だが、
「そして、それを決めるのはモカじゃない。立川だ」
そう言い放って、璃玖を連れて出ていった。
つられるようにして、咲季と私も席を立つ。
特に何も言わなかった。
ドア付近まで来て、その足が止まる。
この建付けの悪いドアは、どちらが閉めればいいのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
