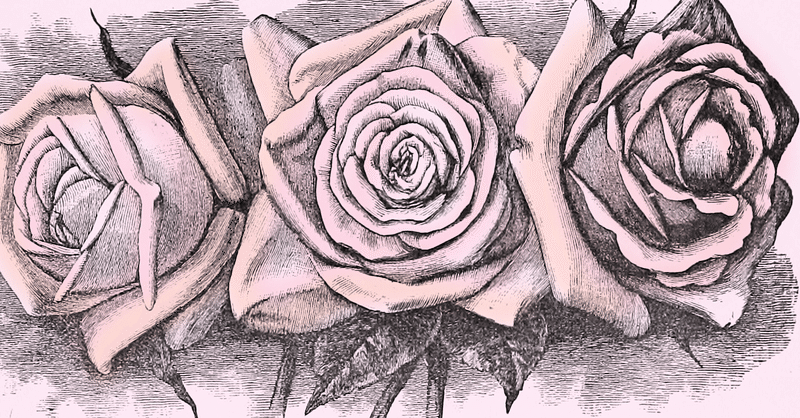
7-3 下僕、気になり過ぎて眼すら逸らしていた箇所を愛撫す 小説「女主人と下僕」
マーヤがベッドに仰向けになって身をくねらせるたびに、薄菫色のシルク のネグリジェ越しにではあるが、マーヤの大き過ぎるふわふわの柔らかい胸が右に、左にたゆん、たゆんと揺れるのが分かる。シルクのすべすべした布の上からそのたゆんたゆんの大きな盛り上がりの真ん中に小さな小さなつん、と尖った部分も見える。たゆんたゆんが揺れるたびに、その可愛らしい小さな突起がシルク越しにつつーといっしょに滑っていくのが見える。
「その、胸…も、触って、良い…だろうか?」
またディミトリは、いまさらにもいまさらな事をいまさら尋ねた。
さっき頭にきて勢いでマーヤをベッドに引きずって来た時に、勢いに任せて一度はマーヤの胸をそっとまさぐったディミトリだったが、実はあれ以来ディミトリはマーヤの胸を触っていないのだった。
人一倍にそこに弱い性癖のディミトリであったが、そういう性癖が強いからこそ、却ってそこは触れてはならぬ禁断の個所のような気がして、勝手に触るどころか、さっきから触っていいかと聞く事すら出来ずにいたのだった。
「もう...ばかッ」
マーヤが喘ぐようなかすかな甘い声で微笑してディミトリを叱った。
(もう、変なところで生真面目なんだから…)
「ぇ、す、すんません」
さっきまでの手慣れた色事師ぶりはどこへやら、ディミトリはいかつい図体を縮こまらせるようにして、謝った。
「違うの、お願いですわ、もうここまで来ていまさらそんなこと、お尋ねにならないで下さいませ…!だって、わたくしいちいち了承させられるのが、心底、恥ずかしいんですもの…」
「そ、そうか。で、その…結局…触って…良い…ですか?」
マーヤは顔を赤らめたまま顔を背け囁いた。
「もぅ…!…だから!これ以上わたくしをいじめないで!私の口からいちいち言わせないで下さいませ…先日茶亭で、貴方になら何をされても…その…嬉しいですって、すべてを観念しておりますと、はっきり申し上げましたではないですか...」
ディミトリの瞳が当惑と興奮で揺らいだ。
「はっ?えっ?…あの日のあれ…?あれがそういう意味だと?まさか…」
(あの日、茶亭ではじめて口づけしたときに仰ったあの台詞...あれはマジもんの本気だったと、あの時点で、ご自分のお身体すべてを俺の好きにしていい、と面と向かって言い切ったと...仰るか!?…マジかよ?!)
マーヤは顔を背けたまま震える小声で
「…もぅ!…まだお解りにならないの?…ならばもう一度申し上げますわ…今後マーヤの身体は全部ディミトリ様おひとりのものです。さっきのディミトリ様のご希望どおり、痛い時はちゃんとお伝えします。だから、後はディミトリ様の…その…どうにでも…いくらでも勝手に襲い掛かるでもなんでも…好きになさって下さいませ!お願い、解って…!もうこれ以上、言わせないで…!」
と言って真っ赤になった。
「う…ぁ…しかし…」
ディミトリは言葉に詰まったまま薄菫色の絹のネグリジェ越しのマーヤの乳房を盗み見た。
高貴の人の身体。一生、絶対に触れる事はできない、じろじろ見る事すら許されない、と思っていたものが目の前にあって、全てお前のものだ、おまえの好きに弄り倒せ、何をしても構わないぞ、とこの方は仰るのだ。
「マ、マーヤ様...あなたは、そのう…マーヤ様のお身体が全部、俺一人のもんだって...俺が何しても構わんと...あの日あの茶亭で、すでに俺に面と向かって仰ってくださったつもりだったと...そしてたった今もダメ押しでもう一度仰ってくださったと...そう仰るのか...?」
「ディミトリ様、ですから!もう!勘弁して!ですから!...」
マーヤは、抗議の表情で、小声で声を荒げたが、途中で真っ赤になって、目を固くつむって思いっきり顔を背けて、力なく俯き、
「...そうです...」
と震えてそれだけ言って黙り込んだ。
ディミトリははじめ呆然とマーヤを見つめていたが、顔を背けるマーヤの頬に自分のごつい手を添えて正面に向けさせ、困り顔で目を逸らそうとするマーヤをじッと見つめながらマーヤのおでこに自分の額を押し付けた。
「...わかった。...マーヤ様の大切な大切なお身体、俺が一生預かった」
ディミトリは絹のネグリジェ越しに、そのたゆんたゆんの大きな乳房の小さくとんがった先の部分をこわごわそっと触った。
「ぁ!」
そしてゆっくりと、ゆっくりとその大きなふわふわを鷲掴みに掴んで揉みしだきはじめた。
ディミトリが繰り返しシルク越しに小さな突起を自分の鼻先でそっとそっと嬲り始めるとマーヤも甘い溜息を繰り返し吐くようになった。
そのうちディミトリは一度喘ぐように吠えたかと思うと、急にマーヤを横向きにぐるんと寝返りを打たせ、自分も横になってマーヤをぐいと引き寄せて、乳房をより悪目立ちするように突き出させ、あくまで、つるつるのシルクのネグリジェ越しではあるが、豊かすぎる乳房と突起を繰り返し自分の鼻や唇でねぶるように口づけし始めた。
「あ、ディミトリ様...だめ、くすぐったいような…いいような...でもやっぱりくすぐったくて...!だめっ…!」
マーヤは、ディミトリの動きを抑えようと、いきなり白く華奢な両腕を伸ばしてディミトリの頭を抱えて自分の両の乳房にぎゅうと押し付け埋もれさせた。ディミトリは、本気でぎゅっとすれば余裕で窒息できそうなたゆんたゆんの中に深く埋もれた。
「うぉ!」
女の、マーヤの、甘いにおい。
「…っそれ以上は...くすぐった切なくて無理…です…!お願い、ちょっと、休憩させて下さいませ」
どうやらマーヤはディミトリを胸に抱きしめることでディミトリの動きを止めようとしたらしい。
だがマーヤのたゆんたゆんに埋もれたディミトリは1分ほど頭をまっしろにして固まっていたが、そのあと突如けだもののような唸り声じみた荒い溜息を吐き、ネグリジェを引き裂けんばかりに押し下げ、マーヤの大きすぎる、肌質がなめらか過ぎてまるで濡れて光っているかのようにも見える乳房を片方ぶるん、と、剥き出しにして、それでいて少女のような色の薄い小さめの突起ごと、乳房に食らいつくように、口づけし、突起を舌で転がすように舐め回した。
「きゃあっ!…ぇ?...ぁ、ぁ、ぇ?…同じ場所なのになぜ…?直接、その、されると…身体の奥まで……あ!…だめ…だめ…熱いのが…じんじん来ますわ…!」
マーヤは息も絶え絶えに途切れ途切れになりつつも、ディミトリに躾けられたとおりに素直に言った。
「…まさかマーヤ様の口からこんなお言葉をおっしゃって頂けるとはなあ…」
「!…ごめんなさい!はしたない事を…っ…だめ!」
「違うんだよ…嬉しいんだよ…じつに俺好みだ…もっと、もっと、もっと、はしたなくなってくれ。俺の前でだけは、もっと、もっと、街一番の、いんらん娘になってくれよ」
「すこしくすぐったいのが却って…びりびり痺れて…だめ、だめ」
「ん…?『だめ』なのかい?それはつまり…止めた方がいいって事かい…?」
「ちがうっ…そうじゃなくて…」
ディミトリは目をぎらぎらさせながら囁いた。
「じゃあ、おめえ、そりゃ『だめ』じゃないだろ!それは…だめじゃない!だめじゃない!お願いだ、違う言葉で言ってくだせえよ!ほら!」
ディミトリは再びマーヤの突起をねちねちと舐った。マーヤは、しばらくの間、何も答えずにただ必死で声を殺して絞り出すような小さなあえぎ声を洩らしつつ黙っていたが、ついに、小さな小さな囁きで、絞り出すような声で
「…本当は…いいの…!ディミトリ様のそれ、いいっ、いいっ、いいです…!」
と囁いた。
ディミトリはそれを聞いた瞬間、返す言葉もなく目を見開いて肩を震わせ荒い息を吐いたのみだった。
そもそも、マーヤがこんなに素直になんでもかんでも言い出したのは、ディミトリがかなり強引にマーヤをそう躾けたせいなのだが、それでも服装も言動もすべてにおいて「お堅い」としか言いようのないマーヤが自分の誘いにやすやすと乗ってまさかこんな事まで言い出すとはディミトリにとっては正直なところ予想外であった。
「…いい加減…我慢ができねえッ!」
ディミトリはがばと起き上がって、ついに、マーヤのネグリジェを、下から一気に剥ぎ取った。
マーヤは腰の小さな小さな白いレースの下着1枚の裸にされ、両の乳房はぶるんと剥き出しになり、ネグリジェはマーヤの両腕に引っかかって、マーヤは、上に伸ばした真っ白な両腕を、手首のところでネグリジェを手枷のように絡められたまま、囚われの囚人のようになってベッドの上に横たえられた。
「え?え、え、...ディミトリ様?」
「…やっと見ることができたなァ…」
ハッとして身体を隠そうとするマーヤだったが、腕にずり上げられて引っかかったネグリジェが両腕に絡まってただ身をくねらせもがいただけであった。
「大丈夫…そのまま…隠さないで…なんで隠す必要がある…どうか見せて下せえ…どうか…」
ディミトリはマーヤの腕を、絡まったネグリジェごとそっと上に押しやり、上から下まで舐めるように見回した。そしてふたつのふくらみはもちろん、それどころか脇腹やら肋骨のあたりやら、脇の中、へその中まで、厚い舌で舐め回した。
「ーーーーーーーッ!」
マーヤは羞恥と、痺れるような感覚で、声にならない悲鳴を上げた。
そして、ディミトリはがばと起き上がり、自身の灰白の粗末なシャツを脱ぎ捨て、鍛え上げた軍人のような精悍な半身を晒して再びマーヤにのしかかった。
「まって!まってディミトリ様、お願い、どうか、あの、あまり、痛く、しないで下さいませっ」
マーヤがうろたえるのも無理はなかった。というのは、目の前にいる男の表情も、声も、態度も、もう、マーヤの見知っているあの、近所のこどもすら怖がらず悪戯を仕掛けてくるほどに、おだやか過ぎるほどにおだやかな、あの朴訥としたザレン茶舗のディミトリではなかったからだ。
「ん…?どうしたんですかい急に…?もちろんですよ…?大丈夫ですか?なんだか気のせいか、不安そうなお顔だが…まてよ、ひょっとしてそのお顔、こ、怖いんか?ち、ちょっと休憩するか?俺は構わんぞ?それとも止めるか?止めてもいいんだぞ?おい、だ、大丈夫…なのか?」
ディミトリはそう言って焦ってマーヤの髪を、両頬をやさしくなんども撫でた。ディミトリには急にマーヤがどうしてそんなにおびえたようにうろたえ出したか、いまいち理解できていなかった。
マーヤは両手を上に投げ出してネグリジェが自然に絡まった手枷をはめられた先ほどの姿のままで答えた。
「大丈夫ですわ、急に、ほんのちょっとだけこわくなってきて…なんだろう…急にがばっと動かれるとなんだかディミトリ様が別の人になったみたいでこわくなるみたいなの…だから…お願い…ゆっくり…ゆっくりした動作で」
「…わかった…心がけます…あの、まだ耳だって聞こえてるし、俺はこないだよりよっぽどまだまだ正気ですよ?今日は痛いことなんか絶対ないから、その…なんで言えばいいか…」
「…ディミトリ様…心配なさらないで?大丈夫よ…続けて…止めないで…」
ディミトリは気付いていなかったが、ディミトリは極度の欲情の高まりのために、普段の職場でかぶっていた羊の皮…恐ろしげな首輪といかつい外見で人に必要以上に嫌われない為に、長年無意識にも意識的にも作り込んだ、やわらかい態度や、やさしい雰囲気…を明らかにどんどんと失ってきて、けだものめいた荒い息を吐きけだものめいた眼光を光らせはじめていた。
マーヤはそれにおびえていたのだ。
続きをみるには

マヨコンヌの官能小説『女主人と下僕』
昔々ロシアっぽい架空の国=ゾーヤ帝国の混血羊飼い少年=ディミトリは徴兵されすぐ敵の捕虜となりフランスっぽい架空の敵国=ランスで敗戦奴隷に堕…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
