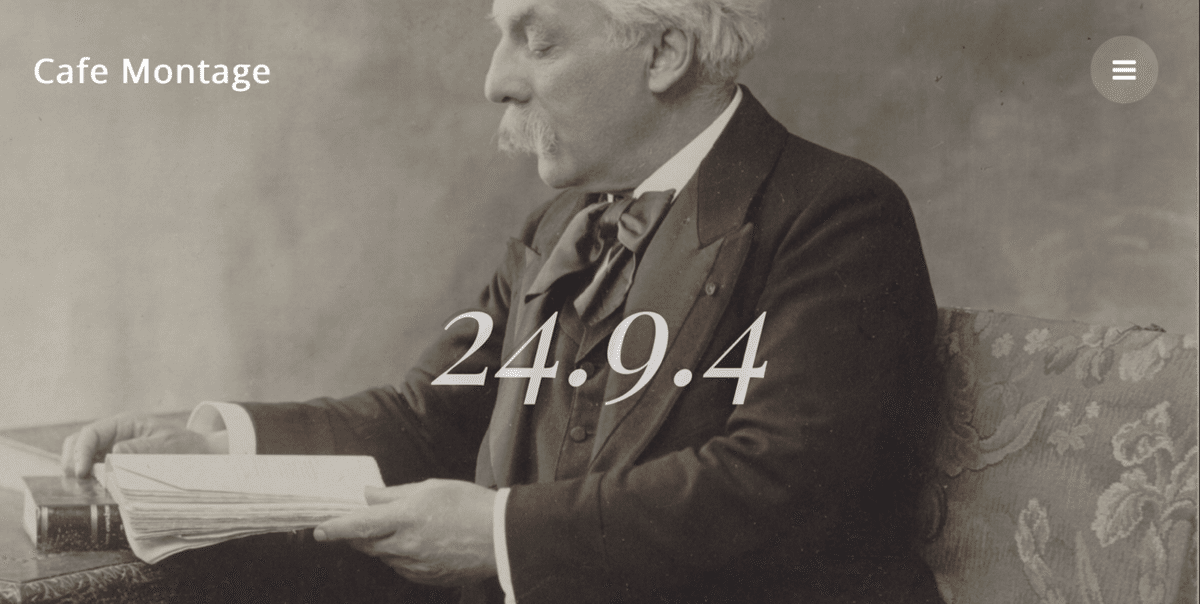音楽のように、読む、プルースト
優雅で複雑な、捉えどころのない楽想が生み出す思いがけない響きによって耳をとらえたり、惑わせたり、長い間無関係だった調性と旋法性とを不意に結びつけたりする ……
散文の領域では、このように複雑で高度な技巧は、マルセル・プルーストの誇り高き、曲がりくねった文章の中にしか見られないといってよい。
フォーレ研究の第一人者ネクトゥーもこう言っているのだから、フォーレの没後100周年に、いまこそプルーストを読むべきだと思った。
フォーレの音楽を追体験する、そのつもりでプルーストの文章を読む。
そのようなことが可能だとすれば、プルーストの文章をここで誰かと共有することで、フォーレの音楽をも同時に共有できるのではないか。
音楽を聴かずして、音楽を共有する。
空想にすぎないことでも、プルーストの文章に対するアプローチの方法、もしくは小さな手がかりのひとつでも見出すことが出来るかもしれない。
それだけでも少しは意味のあることだと思ってくれる人が、ひとりでもいてくれたらと思って、ここからは『失われた時を求めて』からの引用を、音楽作品のように並べていくことにする。
引用元は井上究一郎訳のちくま文庫。
引用する文章としては、作曲家ヴァントゥイユの作品が登場する『スワンの家のほうへ』と『囚われの女』からプルーストが音楽について書いている部分。
ネクトゥーの言う「誇り高き、曲がりくねった文章」によって、音楽を聴く人であれば、おそらくは寄り添うことの出来る感覚を引き出すことができればと思った。
音楽を聴く時に感じるあの、自分にしかわからない感覚。
手元に本がなくても、音楽を聴くように、何かを見出してくれる人がいればと思う。
・・・・・
いまや、明確に彼は音の波の上に数分間浮かびあがった一つの楽節を識別したのであった。それは彼にただちに特殊な官能のよろこび、それを耳にする以前には考えたこともない官能のよろこびを提供したのであり、その楽節よりほかの何物も、そうした官能のよろこびを彼に知らせることはできないだろうと感じられ、彼はその楽節に未知の恋のようなものをおぼえたのであった。
その楽節は、ゆるやかなリズムで、スワンをみちびき、はじめはここに、つぎはかしこに、さらにまた他のところにと、気高い、理解を越えた、そして明確な、幸福のほうに進んでいった。そしてその未知の楽節がある地点に達し、しばし休止ののち、彼がまたそこからその楽節についてゆこうと身構をしていたとき、突然、楽節は方向を急変し、一段と急テンポな、こまかい、憂鬱な、とぎれない、やさしい、あらたな動きで、彼を未知の遠景のかなたに連れ去っていった。それから、その楽節は消えた。
スワンは、彼がきいたあの楽節の回想のなかに、またもう一度それが見つけだせるのではないかと思って演奏してもらったいくつかのソナタのなかに、彼がもう信じることをやめてしまったあの目に見えない現実の一つが現存しているのを見出すことがあった、そして、あたかも彼が苦しんでいた精神の渇きの上に、音楽が一種の親和的な影響をもたらしたかのように、彼はそうした現実にたいして、彼の一生をささげてみたいという欲望、ほとんど活力ともいうべきものを、あらたに感じるのであった。しかし、彼のきいたものがはたして誰の作品なのかわからないので、それを手に入れることもできず、ついには忘れてしまったのであった。
演奏がはじまった。なんの曲が演奏されているのか私にはなじみがなく、未知の国にきているようだった。どこにそれを位置づけるべきか?どんな作曲家の作品のなかに私はいるのか?それを知りたいと思った。
ある土地にはいって、どうも見おぼえがないと思っていたら、じつは新しい方向からはいってきたのであって、一つの道路をまがって、突然もう一つの道路に出ると、そこは隅々まで親しくおぼえているが、そこへはその方向からやってくる習慣がなかっただけだった、というようなことがある。そんなとき人はとっさにこう自分に言いきかせる、「やあ、これは親しかった友人の家の庭の裏門に通じる小道じゃないか、おれはあの家から二分とはなれていないところにいるんだっけ」、はたして、その家の娘がそこにいるではないか、ちょうどそこを通りかかって、私にこんにちはを言いにきたのだ。あたかもそのようにして、突然私は、自分にとってあたらしいこの音楽のなかで、自分がヴァントゥイユのソナタのただなかにいるのを認めたのだ。
小楽節にめぐりあった私のよろこびは、それが私に呼びかけようとして一段と友情をよみがえらせる調子をおびたことによって倍化していった。
…… 小楽節は、思いだされたとたんにきえてしまった、そして私はふたたび未知の世界にはいりこんだ、
新しい作品は、嵐をはらむ朝まだき、無限の空間のひろがりのなかの、無気味な沈黙のただなかで、海面のうねりのように一様で平ないくつかの表面の上にはじまるのであって、しかもその未知の宇宙が私のまえに徐々に形成されてゆくのは、その宇宙を沈黙と暁闇とからひきだすあけぼのの薄あかね色のなかなのであった。 …… その新しい赤は、神秘な希望をただよわせて、空全体をあけぼのの色に染めだした。と見るまに、空気をつんざいて、早くも一つの歌がきこえてきた。 …… 空気をひきさきながら、曲の冒頭をひたしていた深紅の色あいとおなじように力強い、雄鶏が時を告げるような何か神秘的な歌、永遠の朝の、言いあらわしえない、しかも鋭く高い呼びかけ。急に大気が冷えて、沛然と雨が洗い、稲妻の電流が走った、その大気は ― あけぼのが約束したあかね色を消しながら、刻々に変化してゆくのだった。
彼の歌ならどの歌にも似ている歌、ヴァントゥイユはそれをどこからまなび、どこでききとったのか?芸術家は、そのようにして、その一人一人が、ある未知の祖国に生まれついた人間であるように思われる、彼は自分でその祖国を忘れてしまった、
この失われた祖国、それを音楽家たちは自分に思いださない、しかし、彼らの各自がつねに無意識のうちにこの祖国とはある種の斉唱をなしてつながっているのである、
ヴァントゥイユの音楽のなかには、いわば表現することが不可能な、じっと見ることが禁じられているとでもいった、そんなもろもろの視像があった、というのも、ねむりにはいろうとして、人がもろもろの視像の非現実的な魅惑に愛撫されるとき、まさにそのようなときに、理性はすでにわれわれをすてさり、目はとじられ、表現しえぬものどころか目に見えぬものさえつかむ余裕を失っていて、人はもう眠りこんでいるからである。 …… 音楽がつたえうる歓喜は、いい天気や一夜のアヘンがもたらす単なる神経的な歓喜以上のものであるばかりか、すくなくとも私の予感したところでは、もっと現実的な、もっとみのりゆたかな陶酔であるように思われた。 …… あるいはもっと早い話がこの作品の冒頭で、ふと何かのお茶を一杯飲んでいたときに味わった快感である。
ヴァントゥイユの諸楽節は、私が一杯の紅茶にひたしたマドレーヌを味わいながら感じた魂の状態に類似の諸状態の表現のように見えても、要するに、そんな諸状態の漠然としているのはむしろわれわれがまだそれらを分析するすべを知らなかったことのしるしであるにすぎないかもしれない、したがってそんな諸状態のなかには他の場合以上に現実的なものは何もないかもしれないだろう、 …… しかしながら、私が一杯の紅茶を飲んでいたときの、私がシャンゼリゼ公園で古い木材の匂を嗅いでいたときの、あの幸福、幸福のなかのあの確信感、あれは錯覚などというものではなかった。
「文学でもおなじことでしょうか?」とアルベルチーヌはたずねるのであった。―「文学でもおなじことですよ。」そういって、ヴァントゥイユの作品の同一調のことを思いかえしながら、私はアルベルチーヌに説明した、― 偉大な文学者たちは、ただ一つの作品しかつくらなかった、というよりもむしろ、彼らがこの世界にもたらすおなじ一つの美を、さまざまな環境を通して屈折することしかしなかった、と。
・・・・・
『失われた時を求めて』を読みながら、いまそこに書かれていることの意味が、そこではなく、まったく違う箇所に書かれていることに気がついた、ということがたびたびあった。まだ見出だせないところの意味については、もしかしたら、この本ではないどこかに書かれているのかも知れない。
フォーレによる言葉の引用で、最後としよう。
私の音楽はしばしば、真の喜びも苦しみも描き切れていない、と言われてきました。でもただ一つ、思慮深い、やや曖昧な微笑みを含んではいないでしょうか。その人となりが無意識のうちに作品に現れるとするなら、あなたも私と同じように人生を見ておられるのであり、そのことを大変嬉しく思います。