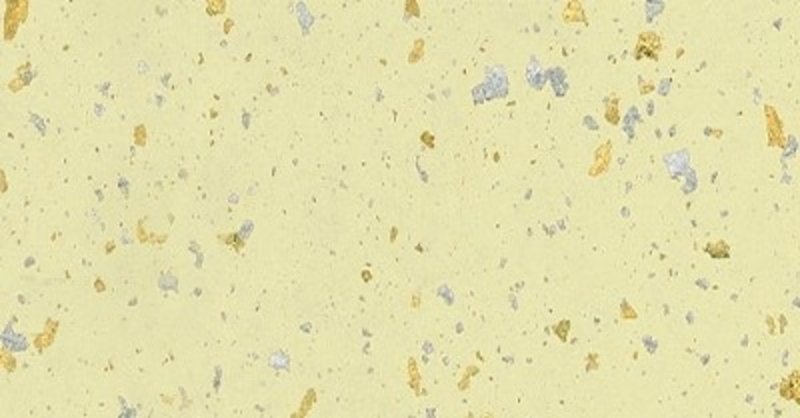
金扇
1-3
公武と弓子の住む屋敷は、北鎌倉にあって、山を背にして、前を水路ほどにも広い渠が流れている。こうして縁側に出てみると、その渠を流れる清らかな水音が聞こえるのだけれども、さっきは海鳴りに紛れて、この渠のことを忘れていた。
別荘を持つ人間が多いからか、辺りには古びた西洋の洋館じみた屋敷が軒をつらねている。公武の家も古い普請で、まだ三十そこそこの男には、高い買い物であったけれども、住み慣れた長谷からも近かったし、弓子の静養にいいと思い、決めた場所だった。
梅雨時は、明月院だけではなく、この辺りもあじさいで満ちる。庭には、白あじさいが咲き誇って、雨上がりで、花びらに露を含んだとき、やわらかに膨らみを帯びて、ことにかわいい。
今は夏で、もうあじさいはひなびているけれども、代わりに、マリーゴールドの花が、庭に橙色の小さな太陽だった。
庭は小さな宇宙のようで、そこに立つ公武は神のようなものだろうか。しかし、その神には、この庭で行われている殺し合いなどは、感情もないものだから見えないだろう。石をひとつどければ、虫が虫を殺しているだろうに、公武には、その死は遠いものとして、見えなくなっている。
公武は米を炊いて、塩鮭を焼いた。食事はいつも公武が作る。卵を割って、溶いて、みりんを入れて、フライパンに流し込んで、だし巻きを拵えた。
簡単な朝食だが、弓子はいつも喜んで食べる。まだ結婚もしていない二人が、このような生活を送って、もう半年は経つ。弓子は舞台に立つことができないから、一日中家の中で過ごす。公武は、長谷にあるダンス教室の講師として、通うことが多くなった。所属していた、東京のバレエ・カンパニーを退団して、今はフリーランスだった。海外に遠征して羽振りがよかったころに貯蓄していた貯金も、屋敷を買って今はもうない。借金だけはなかったが、経済的には困窮していた。弓子の医療費もかかる。
ダンス教室は、鎌倉で電車からバスに乗り換えて、五つ目の停留所で降りる。その日も、バスの中で公武は、弓子の花がまた少し増えてきたことを思った。時折、仕事に疲れた電車の中で見る夢に、身体の全てが花になってしまった弓子が現れる。その弓子は、もう喋ることもせず、ただ花の美しさだけを残して、風が吹くと、さらさらと消えてしまう。
(恐ろしいことだね……。)
あの夢を見た日、一散に駆けて弓子の元へ戻ると、弓子は小鳥を手に乗せて遊んでいた。弓子の白い爪にやさしく啄む青い小鳥だった。マメルリハという品種で、瑠璃色の羽根があざやかに公武の目に映った。家には二羽のマメルリハがいて、牡と牝だった。
「どうしましたの?すごい汗……。」
布団の中からきょとんとした顔で、つぶやくように弓子が言った。顔は朗らかに笑っていて、二羽の鳴き声だけが聞こえた。公武は息をついて、ゆっくりと弓子の側に近寄ると、腰を下ろした。指先で、弓子のほほに触れた。弓子のほほは、火の子が舞うように赤い。
「いやな夢を見たものでね。」
「どんな夢ですの?」
「いや……。この二羽が、花になる夢だよ。」
「まぁ。怖い夢。」
弓子はほほ笑んだ。そうして、人差し指に留まった一羽を顔に近づけて、ささやくように、
「あなたは花になるんだそうよ。」
「青い花だね。青い薔薇だ。」
「青い薔薇ね。きれいでしょうね。」
「二羽とも、青い薔薇だよ。でも、あじさいのようにも見えるね。」
「瑠璃色がね。紫も濃いから……。でも、薔薇の方がいいわ。薔薇の方が、ずっといい。」
弓子の指がマメルリハの頭に触れると、小鳥は気持ちよさそうに目をつむって、身体を膨らませた。
「この子は牡?それとも牝?まだ見分けがつかないんだ。」
「男の子ですわ。女の子は、私の肩にいるわ。」
牝のマメルリハは、弓子の肩の上で、鳴き声一つ立てることもせずに、公武を見つめていた。公武が静かに指先を伸ばすと、牝は大きく嘴を開けて、公武を威嚇した。
「怒っているね。」
「この子は警戒心が強いのね。女の子ですから。」
弓子が笑って、今度は牝のマメルリハを左手の指先に導いて、二羽を顔の前で向かい合わせた。そうすると、牝と牡が向かい合って、次第に牡が、身体を蠕動するように左右に震わせた。公武はおどろいて、
「これは何?」
「求愛ですわ。求愛のダンスですわ。」
「小鳥のバレエだね。」
青い薔薇が踊るようで、美しいおどろきだった。小さな青い花束だった。
弓子はほほ笑んで、
「男の子と女の子だから、きっともう恋がはじまるわ。そうして、愛になるのね。」
そう言う弓子は、さきほどの夢の余韻だろうか、小鳥の宿り木のような、花に思えた。
公武が気付くと、もうバスは長谷についていて、慌てて下りると、海風だった。空は澄み渡っていたが、遠くに雨雲が見えた。しぐれるかもしれない。
ダンス教室に着くと、中からストラヴィンスキーの『ぺトルーシュカ』のテーマが聞こえた。十五歳未満の子どもたちだけで行う、秋の文化芸術大会の演目の一つである。この演目に決めたのは、公武だった。講師たちからアイディアを求められて、公武は、バレエ・リュスの演目で固めるのがいいと、そう答えた。それは、公武がバレエ・カンパニーを退団して、弓子の病のことしか考えられない現状に、ぽっと咲いた火のようで、公武の心を、少しだけ照らすアイディアだった。講師たちは、そのアイディアを喜んで、結局演目は、『火の鳥』、『ぺトルーシュカ』、『薔薇の精』に決まった。それぞれ、少年と少女たちが踊るには、大人びているように思えたけれども、そのアンバランスなものが、味わいになるように、公武には思えていた。
レッスン場へ行くと、レオタード姿の子どもたちが、一心に集中している。その輪の中にいるのは、教室長の佐山だった。佐山は公武を認めると、直ぐさま駆け寄って、
「弓子さんは大丈夫かい?」
佐山の挨拶だった。公武は頷いた。
「ほんとうなら、今頃ロシアかパリにでも行って、踊っていたんだろうがね。」
「エトワールになれる才能が、彼女にはありましたからね。」
「『ぺトルーシュカ』のバレリーナを踊ったこともあったろう。子どもたちには、子どもたちの良さがあるんだけど、今はちょうど一番心が動く時期だろう。だからかね、魂のない人形を演じるのがね、一番難しいんだね。でも、弓子さんは、ほんとうに人形だったね。少しだけの、嫌みのある魂を、うまく体現していたね。」
そう言われて、公武の目ぶたの裏側に、刺すように鋭い目差しにつらぬかれた思い出のいくつもが浮かんだ。弓子は、天才の習いだろうか、役柄そのもののになってしまって、『ぺトルーシュカ』のムーア人に恋するバレリーナや、洗礼者ヨハネの首を欲する、『サロメの悲劇』のサロメのように、恐ろしい目差しをする役を、嬉々として演じて、それは彼女そのもののようでもあった。
『サロメの悲劇』を演じた舞台に、公武は出演せずに、客として誘われていた。その前に弓子に会ったときは、『眠れる森の美女』の主役を演じて、まだ幼い色だった。サロメを演じると電話で聞いたとき、弓子にサロメが出来るだろうかと、公武は思ったものだが、その姿は、異常な女のそのもので、見事なサロメだった。
楽屋で、サロメに扮した弓子は、踊り終えた公武を見つめたまま、何も言わずに、黙ってほほ笑んで、
「まるでサロメそのものですね。」
「公武さんにそう言われるなら、光栄ですわ。」
「観客の視線は、ほとんど全部弓子さんのものでしたね。」
「ほとんど一人舞台でしたもの。」
弓子はそう言って、右手で白粉のついた首筋をゆっくりと撫でた。公武は立ち上がって、タオルを取り出すと、それを弓子の首筋に当てて、汗を拭いてやった。
「ギュスターヴ・モローの『出現』のような振付がありましたね。」
「存じ上げませんわ。また公武さんの絵の講釈?」
弓子は嬉しそうにほほ笑んだが、どこかお高い空気があった。まだ役にいるようだった。
「洗礼者ヨハネの宙に浮かぶ首を指さすサロメです。演出家が知っていたんでしょうね。僕も好きな絵です。」
「聞くだけでも怖い絵ですわね。」
「怖いし、不気味なものですよ。でも、荘厳な美しさがある。ゴヤの『ユーディットとホロフェルネス』にも近いものがありますね。どちらも怖い絵ですけど、首を刎ねる、もしくは首を欲しがる女の絵です。」
弓子は何も言わずに、脣を軽く噛んだ。紅が弓子の白い前歯を塗った。
「サロメそのものって仰ったわね?それはどのあたりなのかしら?」
鏡の中に浮かぶ仄白い弓子の顔がしゃべり出して、宙に浮かぶ首だった。カラーコンタクトを入れた目が、トルコ石のようにきらめいて、一層鋭い矢のように思えた。
「その目ですよ。その目が、怖いですね。サロメはヨハネの首を欲したでしょう?僕には何故なのかわからない。でも、あなたがサロメを演じると、それが自然と胸に来るんです。胸に迫るんですね。」
「私には分かる気がするもの。サロメがヨハネの首を欲した気持ち……。」
「それは何故?」
「踊るときはね、わかるのよ。でも今はわからないわ。不思議ね。踊るときだけ、サロメになっているのかもしれないわ。」
「女性は感情で踊るでしょう。踊ると感情が動くでしょう。頭で考えると、やはりサロメは理性的ではないのかもしれない。」
そう言われて、弓子はかすかに口元を緩めると、足を差し出した。これには公武もおどろいたが、遊びのように思えて、直ぐさま傅くと、弓子の足を自分の足に乗せて、トゥを脱がしてやった。しなやかな足で、触れると羚羊のようだが、足に乗せると、遊絲のようにも見える。
「まだサロメのようですね。それとも、エロディアードですか。」
「エロディアード?」
「サロメの母です。美しい女性。薔薇のように美しい女の人。」
「知らないわ。」
「演目を踊るときは、他の役者や、その原典にも遡るのが、一番いいでしょう。振付を覚えるだけじゃなしにね。」
「覚えることが多すぎるんだもの。」
「詩から入ると、わかりやすいかもしれません。詩は心に謡っていますから、複雑で退屈な物語も、わかりやすいでしょう。バレエの題材も、複雑な背景のものが多いですから……。」
「そのエロディアードを主役にした詩もあるのかしら。」
「ステファヌ・マラルメという、フランスの詩人が謡っています。それに、オペラもありますから、今度DVDを貸しましょうか?」
「嬉しいわ。ありがとうございます。」
そう言って、弓子は身を乗り出して、微笑んで見せた。また、トルコ石のような目が光った。歯に付いた紅は、いつの間にか取れていた。そうしていると、弓子ははっと気がついたように、天翔るようにつらなった睫を指先で弄んで、
「ご存じ?付け睫の始めって、『サロメの悲劇』だって、タマーラ・カルサヴィナは言っていたのよ。私が一番に始めたんですって。」
「しかし、公武君も勿体ないですな。折角のバレエ・カンパニーを退団するなんて。」
佐山の言葉に、過去のまぼろしが破れて、公武の目に、目の前で踊る少女たちが映った。トルコ石を目に入れた、今よりもわずかばかり若い弓子は、ちょうどこの少女たちより大人で、その狭間だった。そして、そのトルコ石の目差しを思い出すと、今度は、猫目石の金色を目差しの弓子も浮かんでくる。弓子は目の色が自由だ。今は星空の黒で、流星が流れていて、猫目石を身につけると、月の色だった。色々な目を入れるたびごとに、七色の目だった。
「公武君?」
呼ばれて、公武はかぶりを振った。何度も何度も、過去に呼ばれている。
「すいません。何でしたか?」
「随分疲れているんだな。やっぱり、弓子さんの看病で?」
「いえ、考え事をしていたんですよ。バレエをしている少女たちを見ていると、色々と昔のことがね。」
少女たちは真剣な眼差しで、演舞に集中していた。佐山は頷いて、
「そうですね。一心になっているバレリーナたちは、自分に重なるようですな。」
「僕も、ほんとうに小さい頃から、それこそ、思い出せない頃から踊ってきましたから……。」
「それは弓子さんもだね。あの子も、ほんとうに小さな頃から、踊ってきたね。その頃から、他の子とは違ってね、ああ、血統なのかもしれないと思ったね。あの子の両親は、特別バレエに親しんでいた訳ではないけれどね、しかし、踊り子としての素質みたいなものが、古い昔からあるのかもしれない。日本の古い伝統の中からね。」
「それが西洋と結びつくものでしょうかね。」
「結びついたのが弓子さんかもしれないね。」
公武は頷いた。弓子は、たしかに幼い頃から他の少女たちとは違っていた。初めて会ったとき、公武は二十で、弓子は七歳だった。まだ小学生で、小さかったけれども、しかし、一度踊ると、もう大人に近い蕾だった。そういえば、田中一村もまた、七歳の頃の『菊図』が大人の蕾だったことを、公武は思い出していた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
