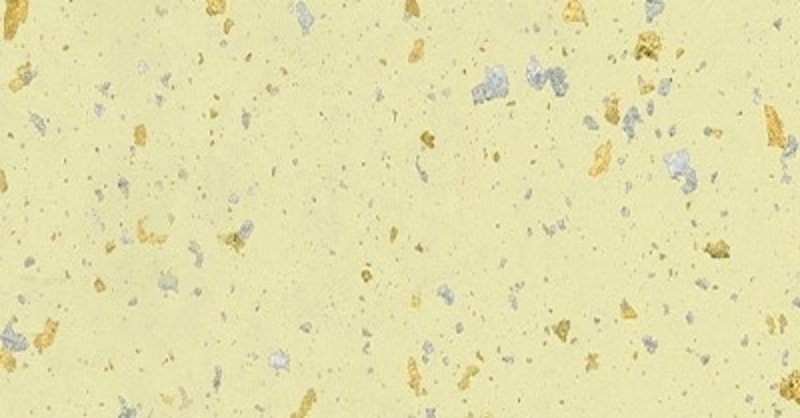
金扇
1-4
練習が終わり、事務所に向かうと、佐山のデスクの後ろには、大きな絵が飾られていた。小磯良平の『踊子』だった。その絵を観ているうちに、また公武の胸に、幼い頃の弓子が迫るようだった。西洋画の『踊子』は生々しい肉体で、触れれば、肉体の感触がありそうだった。
佐山が事務所に戻ってきて、公武を認めると、ソファに座るように促した。公武は頷いてソファに腰掛けると、佐山と向かい合って、
「小磯良平がお好きなんですね。」
「オークションでね、買ったんだよ。もちろん複製画だが。」
「あれはたしか六甲アイランドに本物がありましたね。」
「あそこには、いくつものバレリーナの絵が置かれているね。人が少なくて、ときどき大きな館内が貸し切りになるだろう。そうすると、ほんとうに踊子と向き合える時があってね、幸福な気持ちになるね。それも魅力なんだが、偽物でもいいから、自分の近くにも置いておきたくてね。妙なことだが……。」
佐山が美術に興味があるのにおどろいて、しかし、納得もいった。芸術家であるのならば、芸術を愛するだろう。公武も例に漏れず、美術が好きだから、絵や小説に興味深いのだけれども、時折、そういう自分を弓子が揶揄することがある。踊りを踊っていないときですら、他の芸術に興味のある自分を、美しいものが好きな獣のようだと、からかうように言っていた。
「小磯良平も、ドガも、バレエを題材にする芸術家は多いですね。」
「そうだね。川端康成も、バレエやダンスが好きだろう。いくつかのバレエ小説も書いているし、梅園龍子を囲って、プリマにしようとしていたね。」
「恋心もあったんでしょうかね。」
「それはあるだろう。美しいプリマを育てるのは、最大の芸術だからね。」
「でも、プリマは人形じゃありませんからね。魂がある。病にも罹る。」
「弓子さんは気の毒だ。踊れないのは辛いだろうな。家では何を?」
「小鳥たちと遊んでいます。小鳥たちがバレエをするんですよ。それから詩を読んだり、書いたり。彼女は文筆も才能があるようですね。」
「詩を書くのかい?」
「自分が花になる前に書くんだと、息巻いていましたよ。それなら花になることを書けばいいだろうと言うと、怒ってね。」
「そりゃあ質の悪い冗談だね。しかし、詩とはおどろいたね。」
「僕が教えたんです。ステファヌ・マラルメがいるでしょう。」
「フランスの詩人だったかな。」
「彼も、バレエに対する散文を書いていました。踊子の踊りは、つまるところ、詩を書くことです。文字を書くことです。僕たちバレリーナは、踊ることそれ自体が文字を書くこちで、詩を詠っていることだと、マラルメは書いていますね。マラルメは、たった一つの書物に辿り着くために、世界はあると言っていますが、僕たちが踊るのも、その書物に至るためかもしれませんね。」
「バレエの振付が、詩になっているということかな。」
「まぁそういうことのようです。彼にはそういう考えがあったみたいですね。とりとめのない散文で、読んでいて少し意味のわからないこともありますが。」
公武は苦笑した。佐山は立ち上がって、流しにあるコーヒーメーカーの場所まで近づくと、コーヒーを淹れようとした。すると、ノックが聞こえて、
「失礼します。」
少女が一人、事務所に入ってきた。何の化粧もない素顔で、端正な顔立ちだった。はじめ、公武は少女を少年かと思ったが、しかし、服装は少女だった。少女は愛らしい顔を公武に向けると、静かにほほ笑んで、お辞儀をすると、
「あら、先生、私がやりますわ。」
佐山の元に小走りで向かうと、すぐさま佐山の手からカップを奪い取り、コーヒーを淹れ始めた。
「どなたですか?」
「やはり疲れているようだね。君も何回か練習を指導しただろう。『薔薇の精』で、乙女を演じる八代百子さん。」
その声に、百子は振り返り、ほほ笑んで、もう一度公武にお辞儀をした。百子の顔を見ているうちに、『薔薇の精』の練習をしていた百子が浮かんできて、公武はああ、と膝を打った。
『薔薇の精』は、舞踏会から帰った乙女の前に、持ち帰った一輪の薔薇の精が現れて、彼女の部屋で舞を舞う。二人の美しいパ・ド・ドゥが魅力の舞台で、最後には乙女は夢から覚めて、薔薇の精がまぼろしであったことを知るという物語で、公武はこの舞を、タイトルロールとして何度も演じていた。
それは、この作品がニジンスキーの十八番で、彼に似ている公武には、お誂えの舞台だったからである。そして、公武が薔薇の精を舞うときに、何度か弓子が乙女を演じて、二人で舞ったパ・ド・ドゥでもある。それが、この作品を公武に特別なものにしていた。思えば、弓子とパ・ド・ドゥを踊ったのは、この他には『ジゼル』や『遊戯』くらいで、そう思うと、弓子の踊子としての生命は、思いもよらぬほどに短かったのかもしれない。弓子の他に、公武の腕の中に抱かれたダンサーたちとの踊りを思い出すと、それこそ、数多の夢のようにあふれ出てくる。それが、弓子との少ない踊りを、公武にいっそう哀しくさせた。
「的場先生に教えてもらえるなんて、光栄ですわ。」
百子は、コーヒーカップを公武の前に置きながら、ほほ笑んで見せた。白い歯がきらめいて、愛らしい。化粧もないのは子供だからだろうけれども、身体の曲線は滑らかになっていて、もう女のしるしは始まっているのだろう。
「八代さんは十五で、最年長なんだが、来年中学を卒業したら、宝塚歌劇団を受けるそうです。」
「へぇ。バレエじゃないんだね。てっきり留学が何かするのかと。」
「バレエは教養の一つですわ。私、日舞もやってますし、それから茶道も、華道も。宝塚の男役で、月組のトップスターになるのが夢なんです。」
そう言う百子の顔は、一層少年じみて見えた。青年の色香もある。それも化粧もないせいだろうか。すらりと伸びた足は白樺の枝である。背も、弓子よりも三寸は高いだろうか。弓子も背は低い方ではなかったが、この少女の方が細身で、並べば男と女であろうか。公武は、百子と弓子が『薔薇の精』を踊る姿を思い浮かべて、奇怪な空想に苦笑した。
「先生はほんとうにニジンスキーにそっくりですわ。」
「君くらいの年の子が、ニジンスキーを知っているの?僕の年でも、バレエ関係になければ知らないよ。」
「だって私だって、バレエ関係者ですもの。」
「そういえばそうだね。」
「でも残念ですわ。私、もっともっと弓子さんと踊りをご一緒したかったんですの。」
「弓子を知ってるの?」
「知っていますわ。憧れでしたわ。」
「何かで一緒に踊ったの?」
「弓子さんが、『火の鳥』を踊ったときに。私、その時は十三人の乙女の一人で、まだ十四歳でしたわ。そのときが、初めて弓子さんと一緒の舞台でしたの。でも、それからご病気になられて……。」
十三人の乙女のうちの誰かが、この百子だったのだろうが、その舞台を観ていたはずの公武の記憶にはなかった。そのとき、火の鳥を演じていた弓子は、サロメのようにつらぬくような目差しで、観客席の公武を射貫いたのだった。
今思えば、あれが弓子の芸術の、一番の頂だったのかもしれない。そして、今目の前にいる、この百子は、あのとき埋もれていた十三人の乙女の中には収まらない、伸び盛りの美しさが感じられた。指先は、硝子細工の人形で、頬が透けるように血が流れているのが見える。
「弓子さんの踊りは、不思議なものを感じました。踊るというよりも、より一層きれいなものになろうとしているような、脱皮かしら。胡蝶になるような……。詠うような……。」
「ふぅん?そう?」
公武がカップに口をつけると、
「今まさに、公武君とそういう話をしていたんだよ。彼が言うには、バレエというものは、文字を書くことで、詩を詠うことだとね。」
「まぁ。そうなんですの。」
「僕の言葉じゃありません。昔の詩人の言葉ですよ。」
「でも、そう言われたら分かる気がしますわ。弓子さんの踊りは、詠うような、ほんとうに、詩を詠うような美しさでしたわ。」
感慨深いように、百子が言うと、公武は、弓子の色々の踊りを思い出していた。バレエの天才が花咲くときに、踊子は皆そのような踊りを舞うのであろうか。
この、目の間にいる娘も、今まさに蕾が花咲こうとしていて、そうするとなると、弓子の踊りのような美しさを見せるのだろうか。
また硝子細工のような指先が動いて、
「お注ぎ致しましょうか?」
「いや、結構だよ。もう帰ろうと思っていたところだ。」
公武は立ち上がると、カップに残っていたコーヒーを全て飲み干した。
「弓子さんに、よろしくとお伝えください。」
百子はそう言って、お辞儀をすると、佐山の方を向いた。まるで、もう弓子と百子との立場がくるりと反転したかのように、さっぱりとした物言いだった。
公武に、百子の妖精のような美しさが心に残った。
部屋を出る際に、佐山と嬉しそうに話す百子の後ろ姿が見えた。うなじがかすかに桃色に染まっている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
