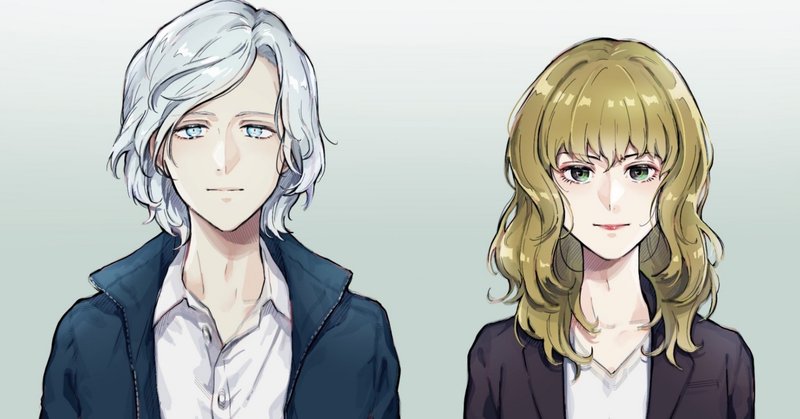
ふたのなりひら
2-2
ドライバーへのインタビューをすっぽかしたことに、編集者は激怒したが、しかし、彼の尽力もあって、別の日にインタビューを受けることに、ドライバーは了承した。森は礼を言って、そのインタビューまでの準備のために、彼の著作を深更まで読み込んだ。
様々な論文、様々なインタビュー音源も耳にした。そうして、その折々に、彼女(彼)の心に瑕疵を作った、狼のことを思い出した。名前を識らない。捜しようがない。いや、フタナリヒラは、少ないのだから、その気になれば、あれほどに特徴のある男、いや女を捜すことは、容易かもしれない。データベースに登録されている筈だ。しかし、夢は夢のままでいいのかもしれない。夢の続きを見ようとすると、それが悪夢へ変じるのかもしれない。それが、森は怖い。森に、あの日視た、幸福な光景を、目ぶたの裏側に遊ばしておくほうが、よっぽど楽に思える。
ドライバーは、誇大妄想家だと、狼は言っていた。そういえば、狼は、なぜドライバーの講演会に来ていたのだろうか、森は、ドライバーのことを、何も識らない。たくさんの本を読んでも、その実像が見えない。
東京駅からタクシーで三十分。AIベースに行き先を入力し、森は窓外に目を向けた。窓を流れていく人々は、やはりほとんどが男女である。子供のフタナリヒラなど、見たことがない。それなりにはいるのだろうが、自分が教育機関の扶養から抜け出してからも、フタナリヒラのルールは変わりがない。変わったとすれば、通常の徒弟制度のようなものから、グループ単位での教育機関も生まれたということだけだろうか。その校長は、今はもう四十代を迎えて、マダムと呼ばれているが、森にその敬称はおかしかった。
李先生がマダム。辞書でマダムの意味を紐解くと、フランス語で既婚女性や、地位の高い女性への呼びかけとある。それがまずおかしくて吹き出してしまう。確かに、マダム・李は女性寄りのフタナリヒラだ。若い頃、狐めいていたけれど、今はどうだろう。もう数年も会っていない。便りもない。
マダム・李は結婚していない。しかし、恋人はいる。それは、フタナリヒラではない。森の父親だ。そのような関係になってから、もう二十年近くが経つが、マダム・李を、森は母親(父親)だと思った事はない。マダム・李は、あくまでも先生で、大切な人ではあるが、別個の、切り離された、悩める人間である。母親の顔は、写真でしか見たことがない。正確には、見たことはあっても、覚えていない。靄がかかっている。まるで、自分のことのようだと思う。しかし、時折、朝の怠い夢の中で、蝶々のように羽根をはためかせて眠る母の寝顔を見る。幽かに目を開いて、森を見るのだ。そこで目が覚める。そうして、枕元に置かれた写真に手を伸ばして、その顔を見ると、フェイクじゃないかと思う。写真の中の母と、夢の中の母、二つの母の顔が重なるが、正しいのは夢の母ではないかと、記憶の曖昧さは美しい思い出だと、そう思える。
都内は雨が降っていて、郊外に出るにつれて、どんよりと、ただの曇り空へと変わっていく。そうして、タクシーから降りて、山の手を登っていくと、デ・ジャビュを覚えた。講演会で、モノリスと、ドライバー博士が口にしたのを思い出した。研究所兼彼の自宅は、モノリスのように黒い。ブルータリズム建築だが、しかし、スターリニズムでもある。コンクリートか、それとも別の素材だろうか、黒いモノリス壁は雨に濡れて、宇宙のように光っている。玄関で呼び鈴を鳴らすと、スピーカーから声が聞こえた。女性の声である。
「どなたですか?」
「ああ、スフィンクス社から来ました、相馬森です。本日、ドライバー博士へのインタビューで、三時にこちらに伺うようにと……。」
腕時計を見ながらそう言うと、数秒、沈黙があり、どうぞと、自動ドアが開いた。
「そのままお進みになってください。玄関フロアでお待ちしています。」
そう言われて、森はスピーカーに向かって頷くと、そのまま敷地内へと歩を進める。空を見ると、今にも泣き出しそうだ。そうして、敷地内はコンクリートで固められていて、植物の匂いがしなかった。時折、生き物の鳴き声が聞こえた。犬か、猫か、鳥か、それとも猿だろうか。いずれにせよ、哀しい声である。
モノリスの前に立つと、その存在の威圧感に押しつぶされそうになる。呼吸が苦しくなるようで、これは一種の教会かもしれないと思えた。そうして、研究所の入口には、一人の女性が佇んでいた。片手には傘、真っ赤な傘。けれど、雨は降っていないから、念のためだろうか。女性は森に向けて頭を垂れると、どうぞと、さきほどのスピーカーから流れる声と同じ言葉を呟いた。機械を通していないに、機械めいて聞こえた。
女性について、モノリス教会の中を歩いていく。そういう名前を、森は頭で思い浮かべていた。フランスの、サン・テ・ミリオンという街に、石を彫って作られた、モノリス教会という場所があることを思い出した。それは、マダムが教えてくれた知識だ。
「私は白い教会が好きだね。アンリ・マティスの作った教会、美しい白い教会、ヴァンスの礼拝堂。青と白の、光の教会だ。」
幼い頃の授業の光景が頭を掠めて、気が付くと、もうドライバーのオフィスだった。
「先生、御客様です。雑誌社の方。」
「ああ。開いています。お入りください。」
女性はドアを開けて、森を中へと促した。森がオフィスへと足を踏み入れると、ドライバーは、深いソファに腰を下ろして、入ってきた森を見上げた。そうして、驚いた口を開けて、
「なんと、フタナリヒラですか。」
「スフィンクス社の、相馬森です。」
森が名刺を差し出すと、ドライバーは座ったまま手を伸ばして、それを受け取った。名刺に書かれている肩書きを、見つめている。灯りの下、近くでドライバーを見ると、目が白濁しているのがわかった。
「スフィンクス社。リマージュを刊行されていますね。季刊誌の。あの手の雑紙では、ナショナル・ジオ・グラフィックの次に老舗でしょう。読んでいますよ。」
「ありがとうございます。」
「ゴシップ誌に毛の生えたような、つまらない記事が多かったと、そう記憶しています。」
そう言うと、ドライバーは名刺を机において、森を見つめた。白濁とした目が、森を射貫くようだった。どこを見ているのか、森にはその視線の先がつかめなかった。
「ゴシップは大事ですわ。」
森がそう言うと、ドライバーは頤をさすりながら、何度か頷いてみせた。
「フタナリヒラの記者が働いているのは珍しい。」
「フタナリヒラの社会進出は、ここ数年はめざましいものですから。」
「私も職業柄、フタナリヒラには何人も会ったことがある。知り合いにも、何人か。彼らは神秘的だ。ああ、つまり、あなたも同様にだ。」
「まぁ。普通の人間と変わりませんよ。」
「両性具有者。フタナリヒラ。神の奇蹟。子供を授からない、塩の大地。」
何か、呟くように、本の目次を読み上げるように、ドライバーは喋った。森は、録音用のレコーダーを取り出して、次いで資料を鞄から取り出した。
「神の奇蹟。先日、講演会でもそのようなことを仰有っていましたね。」
「ああ、君がすっぽかした講演会。」
「その節は失礼を。」
「構わない。ちょうど、ホテルの部屋で待っていたんだ。最上階、九十階。そこから地上を見ていると、灯りが火のようだね。」
「何を待たれていたんですか?」
「インスピレーションだよ。」
森は頷いた。もう、インタビューは始まったらしい。森は、レコーダーのスイッチをオンにした。
「インスピレーション。科学的な、つまり、あなたの研究にまつわること?」
「ああ、それもあるし、そうじゃないことも。」
「つまり?」
「宗教的なこと。僕はキリスト教徒でもなければ、仏教徒でもない。禅は好きだが、つまり、僕は過去を愛しているが、過去は過去でしかなく、もう仏陀もキリストも互いに古い、遺物でしかないのかもしれない。」
「あなたはどんな宗教を信じているのですか?」
「学問だよ。学問を宗教と定義するのであればね。学問だけは、いつも信じるに足る。けれど、やはり神の領域というものはあると思う。学問では計り得ないね。それは、生命の起源であったり、様々だ。僕らの心が、ニューロンによる刺激、ただそれだけだとは、常人には俄に信じがたいようで、そういう人間は、神を作り、宗教を作り、人間を特別視するんだ。円環だよ。まずはそれを破壊したい。」
「だからあなたは、ヒトラーを作り、キリストを作り、仏陀を作る。そのようなことをして、新しい命として彼らを複製させて、その、今まであった大きなサークルを壊そうと、そういうことですか?」
「うん。そうだね。簡単に言えばね。例えばキリストが第三の降誕を現世でしたとして、他の人間がそれを信じるかどうか、そういう問題もある。完全に、DNAは一致したキリストであったとしても。彼らは盲目的だから、自分たちに都合の悪いものから目を逸らそうとするだろう。つまらないことだが、学問とはそういうものだ。大抵は宗教と対立する。けれど、彼らは非常に敬虔でもあるから、敬虔というのは愚かであり、強固なことでもあるが、その彼らを黙らせる道具を、今は手に入れようと躍起になっている最中なんだ。」
「材料?何です?」
ちょうど、オフィスまで案内をしてくれた女性が、トレーにカップを持ってきて、森の前に置いた。湯気が立って、ドライバーは目を細めた。
「聖遺物。聖骸布。キリストの骨、仏陀の血。彼らを再生させる、命の種。」
「聖遺物は眉唾だと聞きます。私も少し調べたことがありますけれど、大抵は偽物ですよ。例えば、トリノの聖骸布もそう。」
「大抵はね。全てではない。」
夢想家、そういう言葉が頭に浮かんだ。誇大妄想家。狼の声が聞こえた。
「その、聖遺物を手に入れて、そこから、新しい命を作ると?」
「新しい、というと語弊があるな。複製人間。複製だよ。」
「キリストの複製。或いは、仏陀の複製。」
「もちろん、その聖骸布が、真に彼らのものや、彼らに縁のあるものだと検査して、確かであればだが。」
「では偽物の可能性もあると。眉唾の可能性も。」
「無論ね。けれど、本当なら面白いだろう。神の言葉を、二千年越しに聞くことが出来る。悟りというものが何か、生きた人間から聞ける。さぞ陳腐だろうね。」
そう言って、ドライバーは長い指先を遊ばせた。ドライバーの目は、話す内に、白濁とした中から、濾過したような綺羅星がちらりちらりと覗いてくる。それは、科学者の宿痾であろうか、森に、不安定な心地が募った。これは、森がフタナリヒラであるからだろう。彼のような、人を人と思わぬ、所謂マッドサイエンティストにありがちな、研究対象を見る目。森は、視線を窓外に向けようとして、この部屋に一つも窓がないことに思い至る。黒い教会なのだ。しかし、天井は高く、見上げると、空から人魂めいた橙の光が、連なったレースのようにおりている。そのせいで、森は自分の身体が重く沈んでいるかのように見えた。
「そのための研究をあなたは続けている。最終的には偉人の複製。今は動物たちを?」
「あらゆる動物を。」
「良心は痛まない?」
「ああ。自分が可愛がってきた命なら別だろうが、所詮は出荷された命だ。」
「その命に愛はないと?」
「いや。私が愛を持てないだけだよ。」
「愛は相関関係が必要ということね。」
「その通り。愛情は、まず互いの認識が必要になる。それがないのなら、或いは一方的であるのならば、愛情は成立しないだろう。」
「片思いは?」
「女学生みたいなことを聞く。麻疹みたいなものだ。恋心は動物に向くものでないし……。ああ、君は動物みたいなものか。」
「はい?」
「フタナリヒラだよ。動物みたいなものだろう。」
「ひどく差別的な発言ですね。前時代的です。」
「国が守るから、そのような意見が出るのだろうな。生意気なフタナリヒラもいる。もう少し昔、近代以前なら君たちは乱獲されて絶滅危惧種だ。そうなれば、今のこの時代に、私が複製してあげただろうね。それならば、私は君たちの神か。君たちは天使かな。」
怖ろしいほど傲慢な男に思えたが、しかし、森は冷静に彼の言葉を書き写して、
「今お話されたことをそのまま掲載したら、大変な抗議の数ですよ。」
「構わない。資本主義は私を神にしてくれたし、民主主義は私の自由を保障してくれている。」
嬉しそうに、そう言って、白濁とした水晶体を輝かせて、笑う。気味の悪い、ビジュアル骸骨だ。森は頷いて、レジメに書かれた質問を続けていった。終始、ドライバーは嬉しそうに持論を語る。その最中、時折遠くで獣の声が聞こえる。それは、憂いを帯びているように聞こえる。空耳かもしれなかった。ドライバーの話す声以外、僅かな空調の振動しか聞こえないのだから。ドライバーの話に出てくる、合成生物の実験、そのなれの果て、その末期の声かもしれない。森は、動物たちが涙を流す写真を思い出していた。象牙を目当てに乱獲されて、もはや絶滅の手前に来たアフリカ象。象は、情動的な動物だと聞く。そして、あの小象の涙も、自分の感情と変わらないものだろうと、森に写真を見たとき、思えたものだ。
そうして、ドライバーの話す傍らで、議事録でも取っているのか、案内係の女性が、女豹のような目で、森を見つめている。森は、その視線には気付かないふりをして、素知らぬ顔でドライバーへのインタビューを続けた。締めくくりに、ドライバーに、複製人間以外、何か興味のある事柄はあるのかと問うと、魂の入れ子だと、そう答えた。魂の入れ子とは何か、そう聞いた森に、ドライバーはほほ笑んで、魂だけを移す人形だと、そう言った。
「マトリョーシカみたいなものだ。魂を何層にも入れておく。そうして、身体が朽ちると、新しく小さい命に移し替える。そうすれば、永遠に生きられる。脳が問題だ。脳を、どうアップデートしていくか……。」
オフィスから出ると、案内役の女性がスーツのポケットから名刺を取り出した。マヤ、と書かれている。中国人か韓国人だろうか。しかし、中東の人のようにも見える。うっすらと、冷たい白色の肌。
「東トルキスタン共和国です。父が、若い頃にアムール地方にわたって、そこで母と結婚したの。」
マヤは、感情も何もない、抑制された声で森の質問に答えた。自動同期機器を解しているせいかもしれない。英語はほとんどの単語、文法、スラングを瞬時に翻訳出来るが、中東圏の言葉は、森の持つ安手の機器では取りこぼす言葉が多い。そのせいか、幾分か会話にノイズが走った。ケチると、碌なことがない。
「あなたは、教授のことをどう思われます?」
「ドライバー博士?とても素晴らしい頭脳をお持ちでしょう。」
「忌憚のない意見を。」
「そうですね。少し、過激かな。けれど、面白い研究だとは思う。ただ、聖骸布。それだけが、私には少し夢物語のように思えます。」
「その存在が?」
森は頷いた。マヤも頷いて、
「この研究所にはいくつかの聖骸布があります。それは、エルサレム縁のものもあれば、菩提樹縁のものの。ただ、全て偽物です。今のところはですけれど。」
「あなた方のパートナー企業がそれをお持ちなのですか?」
「そこからはシークレットですわ。ああ、そう言ってしまうと、もう答えを言うようなものね。」
マヤは、抑揚のない言葉の端から、僅かに昂揚を覗かせた。そうして、彼女に玄関まで案内されると、森は振り返ることもなく、元来た山を下って行った。
聖遺物。聖人の肉体や、その縁のものであるけれど、確証のない伝説に過ぎない。これはもうオカルトの範疇だろうと、森は苦笑したけれど、事実彼の研究は最先端で、合成生物・合成食料は、今後の世相で懸念される食料問題、生物学の発展に大きく寄与している。彼は、ビリオネアで、もう世界の全てを掌握したような気分だろうが、恐らくそれは間違っていない。彼にとって、フタナリヒラは面白い素材だが、ただの奇形に過ぎないのだろう。あの、見下したような言葉の端々に、彼の人間性の欠如、或いは、人間性の再確認が認められる。
キャラクターイラストレーション ©しんいし 智歩
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
