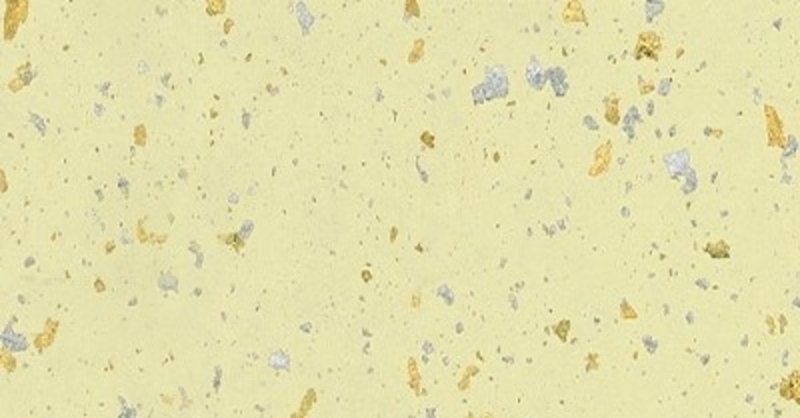
金扇
1-5
北鎌倉駅についた頃にはもう八時を回っていて、夏の夜が訪れていた。暑さは退いて、涼しい風だった。雲間から月が出ていて、月光に道が青かった。
家に帰る道中、何匹か白い犬にすれ違った。月の色に染まって、犬の毛は青い火の指先だった。夜になると、緑の色が濃くなって、山や森が大きくなったように思える。木菟の鳴き声が聞こえて、秋の夜のようだった。
潺の音が聞こえて、渠を超えると、家の灯りが見える。虫の音がなかった。
「おかえりなさい。」
弓子は少女のように浴衣のまま公武を出迎えて、ほほ笑んだ。そのほほ笑みに、公武は聖少女の面影を見た。『薔薇の精』の乙女のようである。サロメのような、エロディアードのような、つらぬくような目差しが消えて、男に縋る女の目差しである。反対に、あの少年のような百子に、それは流れようとしているように思えた。
「夕食をお作りしていますわ。」
「ありがとう。」
公武は頷いて、廊下の先を行く弓子を見つめた。うなじに、かすかにまた赤い椿のような紋が見える。また新しい花が咲き始めたのかと、公武におどろきが浮かんだ。そして、そのうなじを見つめるうちに、ダンス教室の事務所で見た、百子のうなじの桃色に染まるのを思い出した。
二人の立場が回転したことを、公武は改めて思った。これから、百子こそが、サロメのように、美しく伸びていくのだろうか。女の不思議だった。
夕食の後、リビングで公武は小説を読み、弓子は考え事をしながら、筆を走らせていた。それはいつもの日課で、夏の夜のふたりの時間だった。公武が本に読み耽る間、弓子は、踊れなくなった自分の代わりに、指先と、ペンを踊らすかのように、紙を舞台に見立てて、新しい踊りだった。そして、紙に青い月の光が満ちると、指先が弓子である。目端に映るそれを見つめているうちに、次第に自分の読む小説に書かれた文字のひとつひとつが、人間のように思え始めて、踊る指先に、歓声を送るまぼろしだ。漢字やひらがなのひとつひとつが、意志を持ち、掌を動かして、拍手を贈るようにも見えた。
「指先で踊るみたいだね。」
公武がつぶやくと、弓子はほほ笑んで、
「素敵ね。私の指先が、新しい足ね。」
「バレエは文字を書くことらしいよ。踊ることの全ては、物語を語ることらしい。」
「じゃあ、私は今、手の指で物語を書いているのね。」
自分の指先を見つめて、弓子はつぶやくように言った。
「それでも、この指先にもいつかは花が咲いてしまって、踊ることが出来なくなりますわ。」
人差し指と中指と薬指とを三本の矢のように束ねて、弓子は公武に差し出した。公武はその三本を、右手で握りしめると、
「まだ咲いていないだろう。」
「咲きますわ。愛する人に触れられると、花が咲くと、そう言ったでしょう?あれはきっと本当で、きっと明日にはこの指先も、花になりますわ。」
「ばかげた幻想だね。子供の夢だね。そんな夢みたいなまぼろしみたいなことは、僕の前では言わないで欲しいな。」
公武は指を離して、弓子を見つめた。弓子は目を細めてほほ笑んだ。眦が撓る弓のようになった。
「今、指先が踊る話をしていて、思い出したことがありますわ。」
「何を思いだしたの?」
「私があなたに始めてあったときのことですわ。もう干支が一巡りしてしまって、今は昔のことに思えますけれど。」
「もう十二年も前だね。それから君は、こんなにもきれいになったね。」
「あなたはおかわりになりませんわ。いつまでも変わらないままですわ。それで、私の思い出したこと……。私が七歳で、まだ小さくて、上手く踊れない日に、レッスン場のバーの横の姿見の前で、一人泣いていたんですわ。お母様に叱られて、バレエがいやになったんですわ。今でもよく覚えています。あなたもあるでしょう。そういう、幼い頃の消えない思い出が。一つだけ、心の何処かに雪洞のように灯っていて、ときどきそれに触れる事があるの。触れるとその雪洞の火がこころにひろがってね、それだけで胸がいっぱいになるの。私の雪洞も、いくつかありますけれど、その中でも幼心が温まるのは、そのときのお話ですわ。そう、それでそのとき、私は自分の小さなトゥを拇と人差し指でつねりながら、泣いていましたの。周りの女の子たちは、みんな自分のことに夢中で、私のことを気にもかけなかったのを覚えていますわ。一人で泣いていると、私のトゥのその先に、二本の指が現れましたの。大きな指で、人差し指と、中指です。その二本の指が、レッスン場をすぐさまダンスホールに変えましたわ。人差し指が男のダンサーで、中指がバレリーナ。私にはすぐにわかりましたわ。その指たちがとても素敵なパ・ド・ドゥを踊るものですから、私はすぐに夢中になって、もう泣くことを忘れていましたわ。私は指先の行くほう行くほうに導かれて、目はずっとくるくると回っていて。踊りが終わると二本の指が私にお辞儀をしましたの。それで私、嬉しくなって拍手をしたんですの。周りに聞こえると、夢から覚めてしまいそうで、とても小さな拍手。そうして、指が宙に飛んで、掌に生まれ変わると、私の頭を優しく撫でてくれましたの。顔を上げると、あなたがいましたわ。今でも、フィルムのようにそのときのお顔が心に焼き付いていますから、そのフィルムと、今のあなたのお変わりないのが、ほんとうに不思議。私はこんなにも変わってしまったのに。」
「大きくなって、きれいになった。目だけは変わらないね。夜空のままだね。」
弓子はほほ笑んで、自分の指先を見つめた。
「愛する人に触れられて、花になるのであれば、これほどに嬉しいことはありませんわ。私は、生まれ変わるのならば、花か小鳥がいいと思いますの。でも、もう小鳥はここにおりますから、だから、花がいいわ。」
「僕一人を残してかい?それならば僕は心中の夢を見るね。」
「まぁ。物騒ね。」
「物騒でもなんでもいいさ。君の病が進行して、完全な花になる前に、君が人間であるときに、心中してしまいたいのさ。屋敷の前に流れる渠があるだろう。あそこの水は、とてもきれいで、冷たい。元々畑に水を引くための水路だからね。だから、あの渠に入水して、君と二人で死んでしまいたいね。」
「私はあなたにはずっと踊っていて頂きたいわ。」
「ずっと踊っていたら、それこそニジンスキーの二の舞だろうね。君がいなくなって、僕は絶望で狂うかもしれない。」
「踊子はたくさんいますわ。たくさんの少女たちが、美しく育ちますわ。あなたは美しい身体で、美しい少女たちを抱くように、踊り続けるんですわ。」
弓子はそう言うと、目を閉じた。弓子の書いた、詩篇のいくつかが目の入ってきた。そこには、日本語や英語、読めない文字もあった。公武は詩から目を逸らした。
弓子はまた頭を捻りながら、詩に取りかかった。その姿を、公武は後ろから見つめた。そして、自分の指先に目をやった。あのときの少女が、これほどまでに生い立って、今自分の目の前で物を書いているのが、公武に不思議だった。
公武は小説を置いて、立ち上がると、そのままトイレに行こうと、リビングを出た。縁側を歩いていると、庭に白い犬がいて、思わず声を上げそうになった。先程の、青い火の指先である。その指先がちろちろと動いて、夜風だった。犬はつらぬくような目で、公武を見つめると、そのまま駆けだして、姿を消した。虫の音がかすかに聞こえた。
どこから犬が入ったのか、公武にはわからなかったが、あの犬は天使かなにかのように思えた。青く白い毛は、折りたたまれた天使の翼ではないかと思えた。いやに啓示的な空想を働かせる自分を、滑稽なものだと公武は思った。
トイレで用を足し、手を洗っていると、鏡に映る自分の顔に、深い陰があるのが見えた。この陰は、病に冒された妻を持つ悲哀かなにかだろうか。それとも、ニジンスキーのように、踊りから遠ざけられて、心が狂いの方向へと向かおうとする力だろうか。
鏡に映る自分を見つめるうちに、百子の事が思い出された。百子のうなじを染める桃色の血を思い出した。あの美しい少年のような娘の硝子細工を流れる血が、いつか花の種子になって、彼女を蝕む空想が浮かんだ。弓子の次には、百子が同じように、女のしるしを受け継ぐように、花になってしまうのではないだろうか。
そして、花になった弓子は枯れるのだろうか。大きく実っても、永劫ではなく、枯れていき、朽ちていくのだろうか。
部屋に戻ると、弓子は詩を書きながら、テレビを点けていた。画面には、朽ち果てた門の奥に見える教会の絵が映し出されていた。カスパー・ダヴィッド・フリードリヒの絵である。自然の緑の中に、朽ちた教会があって、それは、この北鎌倉の家の未来を予覚させた。それから、連想が続いて、水の神殿のような、佐川美術館も思い浮かべた。あそこも、人間が滅んで百年と放置されてしまえば、この絵画のように、緑に囲まれた廃墟と化すのだろうか。そうすれば、あの美術館にいた蝦夷鹿の像も、命を帯びて動き出すのかもしれない。
弓子は何を考えているのだろうか、目は画面に釘付けになっていて、その目には、また花々が星のように浮かんでいるのだろうか。ふいに、弓子の中を流れる赤い血までもが、花になったのではないかと、そういう空想が公武に浮かんだ。
「きれいだけれど、怖い絵ね。」
渠を流れる水音がふいに、公武の耳に届いた。雨音か、しぐれかと思えた。それは、この絵が見せるこの屋敷の未来が、渠の中で朽ちていくことになるだろうかと思えたからであった。遠雷ともに大嵐が押し寄せて、水嵩が増した渠が屋敷まで浸入してくる。妙なまぼろしだった。しかし、それも公武のただの夢で、もう一度耳を澄ますと、なにかの炸裂音である。夏の夜の遠雷かと思えたが、
「テレビを消してくれ。」
弓子がテレビを消すと、また遠雷が聞こえた。しかし、それは遠雷ではなく、花火の音である。花火が炸裂する音である。
「あら、花火ね。花火がどこかで鳴っているのね。」
嬉しそうに言う弓子を見ていて、ふいに、公武の目ぶたの裏に金色の光が瞬いた。それは、弓子の言うところの心の中の雪洞であった。
「どこか…江ノ島かしら。あそこの海岸で花火が上がっているのかしら。」
公武は答えずに、籐椅子に腰を下ろすと、何も言わずにそのまま電灯を消した。弓子はおどろいて、
「暗いわ。何も見えないわ。」
「慌てないで。僕はここにいるよ。それに、今思い出したんだ。花火の音でね。君の言うところの、心の雪洞かね。」
「何を思い出しましたの?」
「江ノ島の沖に、花火を見たのを覚えているだろう。」
「覚えていますわ。」
「ちょうど夏の夜で、凪だったね。風がなくて、波は静かで、でもどこかからは海鳴りがしていた。あれは何だったんだろうねと、僕らは話し合っていたわけだが、そのときに、君は白い巻き貝の貝殻を浜辺で見つけて、嬉しそうに拾った。そうして耳にそれをつけると、ここから海の音がしたのね。渚はここだったのねと、そう言って、僕の耳にも貝殻を近づけた。どこか異国の夜の渚が僕の耳に現れて、僕は自分がどこにいるのかわからなかった。夜の中でも、君の浴衣から伸びる手と巻き貝は夜光虫よりも輝いていて、絹のように白かったから、その光に虫が集うんじゃないかと心配になったものだよ。そんなことを考えているうちに、花火はいよいよ最後になって、打ち上げ花火はお開きで、水上花火になったんだ。花火師の乗った舟が沖に二艘出ていて、右と左に別れて、左右徐々に近づく形で、水上花火を始めだした。始めに上がった花火は、日本的なもので、小さな打ち上げだった。舟の上から上がったんだね。緑や青や赤色や橙や桃色でとりどりだったんだが、水上花火は金一色だった。黄金だけでね。金色の花火が海から上がって、金の火だった。二艘の舟が近づくにつれて、炸裂音が響くのが大きくなった。あの音は、僕には戦場か何かで砲弾が炸裂する音に聞こえた。四方八方で爆弾が爆発する戦場だよ。戦場に行ったこともないのにね。でも、震えるような戦きがあったね。戦場の光のように思えた。当然そんなことはない。平和な江ノ島だ。そして、舟が交わるときに、花火はいよいよ盛り上がって、海の上で金色の扇になって、僕らの目のまで瞬いた。扇が開いて、その上に金の花が咲いた。金色が何度も何度も咲いた。そうして、火の扇を見つめている君の頬にも、金色の灯りが灯って、脣だけは赤かった。」
「金色の扇。そうですわね。あなたはあのとき、何度も何度も、扇が開くようだ。扇だ。扇だと、言っていましたわ。今、花火の音を聞いていて、あなたの言葉を思い出すと、この暗闇にも扇が開くようですわね。」
「あのときの、金色に染まる君の頬色が、僕の中の雪洞かもしれないね。バレリーナとしての君の美しさとは違う、女の君の美しさだったね。」
その言葉に、弓子の女は動いて、花火の音が遠くで聞こえる闇の中で、公武にしなだれかかって、甘い匂いだった。弓子の頬色は、夜目でも透き徹るほどに赤く白い。弓子の息も、花の蜜で、公武は、バレエを舞っていたときよりも、いっそうふくよかに変わった弓子の肌を、月光の光の中で始めて知った。それは、バレエとは違い、獣の美しさだった。公武は、腕の中の弓子を見ているうちに、この営みも、物語を語ることなのだろうかと、そのような考えが頭に浮かんだ。
目が覚めると、また花火の音が聞こえた。公武は枕元に置かれていた貝殻を手にして、それを、耳に当てると、目を閉じた。花火の音と渚が彼の耳に蘇った。公武が寝室の襖を開けると、月光が差した。隙間からのぞく月は青い満月で、その青い光が寝室にひろがっていくと、公武はあっと声を上げた。美しい花々が公武の横で眠っている。眠っているのか、もう意識がないのか、公武にはわからなかった。
しかし、おどろいたのは、小さな禽獣が、その花に留まっていることである。番の青い小鳥が、公武を見つめている。愛情を確かめるかのように、花を啄んでいる。いつの間にか鳥籠から抜け出したのだろうか。
月の光を受けて、花は揺れていた。花は、椿やさくらや芍薬や牡丹、リンドウやマリーゴールド、それからラベンダー。多様な花が無数に咲いていて、この中にいるであろう娘は、もうその姿を残していないかもしれない。
花の手触りは、人間とは違うようで、花びらのふくよかなのは、たしかに弓子の肌触りである。青い光の中で、眠るような花を見つめていると、自分が薔薇の精であるならば、この花とパ・ド・ドゥを舞って、そのまま花になりたいと公武には思えた。それは、公武には心中である。
花を傷つけないように、手折ることがないように、公武は静かに手を伸ばした。そうして花びらに触れると、花は砂がくずれるようにさらさらとこぼれて、たちまち青い月の浜辺になった。
青い鳥たちは飛び立って、部屋の中に代わりの宿り木を探した。
公武はそれにはかまわずに、青い浜辺からのぞく一輪の花を見つけた。掬い上げると、月あかりよりも白い薔薇の花だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
