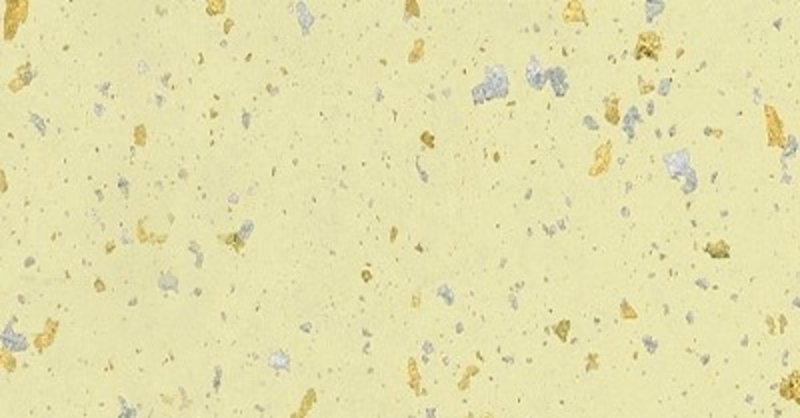
金扇
1-1
波音に目を覚ましたが、ここは渚ではない。白い巻き貝の殻の海の声だった。
毎朝の弓子の悪戯である。公武は目を覚まして、弓子の方を振り返りもせずに、手を伸ばして襖を開けた。かすかに開いた襖から、朝露で湿った草花が見えた。
「起きましたか?」
弓子の息が、公武の耳たぶにかかって、それも海の声だった。
「まだ少し寝たりないね。」
弓子は天井を向いた公武の肩に頤を乗せると、公武と共に、庭を見つめた。四つの目が、いちどきに咲いた庭の薔薇を見つめていた。赤の色が褪せていて、かすかに虫に喰われている。花びらに力がない。
「夏の薔薇はみじめなものだね。」
公武は、姿勢を変えることもせずに、ぼんやりと口にした。まだ夢見心地だった。
「あの薔薇を手折って、あなたの耳に、こうやってつけてみると、どんな音がするんでしょうか。」
「花の音か。どうなんだろうね、心臓の鼓動のような……。生き物の、獣の。そんな気がする。」
弓子の白い手が薔薇に手を伸ばすようになって、五本の指のそれぞれは、陶器で出来た白蛇のように美しく滑らかに泳いだ。しかし、公武のほほに触れると、肉体の温かさがある。
弓子は、もう一度、貝殻を公武の耳に優しく置くと、何かを口ずさんだ。それが愛の言葉だとしても、渚の音に呑まれて、今の公武には聞く術はない。
夏の陽はのぼりはじめていて、しぐれがぬらした草花も起き出すと、かすかに虫たちの声も聞こえるようだった。
「夏の薔薇はすぐに萎れてしまうのね。」
「今は開花の時期も調整することができるらしいから、夏でも美しく咲くものがあるそうだよ。僕はそのあたりに、詳しくないけれどね。」
そう言いながら、公武が起き上がると、弓子もそれに重なるように起き上がり、はだけた胸を浴衣で隠した。
今は浴衣で隠れているけれども、彼女の右の乳房に、愛らしい彼女自身の女のしるしと、そして、これもまた愛らしい花びらが咲いている。その花びらは、ほんとうに花びらである。薔薇の花のようにも見えるし、そうじゃないと言われれば、そうなのかもしれない。全く新しい花びらなのかもしれなかった。
とにかく、公武には知る由もない、新しい病気だった。東京の病院で診てもらうと、『人体花粧症』という、類例が乏しい奇病だった。
この病気のことを知る医者は限られているということで、公武と弓子は、二人で医者巡りをした。東京にも何度か足を運んだけれども、しかし、無駄だった。全ての医者は匙を投げて、自然に任せるしかないだろうと答えた。欧州や北米の医者も、それに倣うばかりだった。
花びらは、弓子の身体のそこここに咲いていて、それは踵や、うなじや、腰のあたりだった。花の数は日増しになって、それは切ろうとも、抜こうともしても、弓子の身体を傷つけてしまうのだった。花は、肉体の一部として根を生やしていて、処置のしようもなかった。
弓子が片膝を立てると、そこから白い素足がのぞいた。美しい白色が、指先の付け根にある薄桃色の花と同じように、花の匂いだった。
しかし、あのように花にまみれていては、もうバレエは踊れないだろう。
十九の弓子は、プリマだった。おしゃまな少女の頃から、何度も公武と踊ってきた。『北極座』というバレエ団のプリマドンナは、ほんとうの花を宿して、踊ることが出来なくなった。
公武は立ち上がると、襖を大きく開けて、窓の外を見つめた。青い山に囲まれていて、海の音など一つも聞こえない。しかし、ふいに、公武の耳に、また渚が戻ってきた。弓子が、自分の右耳に、貝殻を当てている。公武の耳は、弓子の耳だった。
公武が振り向くと、弓子がはにかむようにほほ笑んだ。肩まで美しい髪は、そこだけ夜のようで、いや、黒い双眸もまた、夜だろうと、公武には思えた。その中には白々と星が瞬いている。睫は黒い弓が折り重なるようだった。その撓る弓の頂は、青い月の光のように白く輝いていて、脣は薔薇である。
公武は弓子のもとまで行くと、しゃがみこんで、彼女の髪に隠れた、もう一つの耳に触れた。耳たぶに触れると、やわらかく、赤いのが見える。その柔らかさは薄い皮膜のようで、もしやと思い、指先でさすると、それはさくらの花びらのようだった。
「また花になったね。昨日までは、ほんとうにただの肌だったのに。」
「好きな方に触れられると、花になるのかもしれませんわ。」
「馬鹿。」
「馬鹿ですわ。」
公武は、弓子の耳からぽとりと落ちた花びらを拾い上げた。それを指先でさすると、さらさらと星の砂のように崩れていった。流星は畳に落ちて白い小さな浜辺だった。
「汚いですわ。」
「女から出るものだからかね。」
その言葉に、弓子は形の調った眉をきっと固めて、目を閉じた。
「言い過ぎたね。男だって、汚いけれど……。」
弓子が目ぶたを開くと、目の中に花だった。小さな夜空に浮かぶ星座が見えた。
「目の中にも、花があるんだね。」
「鏡で見ると、不思議ですわ。見える日と、見えない日があるの。」
「それは君の体調が関係しているの?」
「わかりませんわ。でも、身体には少し違和感があるだけで、変なところなんてないわ。」
そう言われて、公武は頷いた。しかし、違和感があろうとなかろうと、弓子の身体は花になっている。花になってしまっている。大勢の医者が長い時間をかけて理解できないものが、公武に理解できるはずはないだろう。あるとすれば、愛の力だろうかと考えて、公武は自嘲ぎみに笑った。
公武は立ち上がると、朝飯を作るために、部屋を出た。
縁側を歩いていると、隣の家から、幾本かの日まわりが顔をのぞかせているのが見えた。まだ緩い朝の日を受けて、黄金色に輝いている。その黄金色を見つめているうちに、公武の目ぶたの裏に、金色の人魚が思い出された。それは、昨年弓子と行った、佐川美術館に置かれていた、人魚のブロンズ像だった。
ちょうどそのときに、佐川美術館では、田中一村の展覧会が開かれていて、奄美の美術館でしか観ることの出来ない画家であったから、公演で神戸に寄ったのを幸いに、車で二時間ほどの道のりを、ドライブを兼ねて、二人で向かったのだった。よく晴れた夏の日で、ちょうど、今から一年ほど前のことである。
琵琶湖沿いを、延々と国道を走ったのを覚えていた。太陽が頂点にきていて、湖面が白い宝石だった。木々もまた白く輝いていた。
佐川美術館は、水を湛えた神殿のようで、その水灯りが、外廊下に反射して、黒い光がゆらゆらと、天井に映っていた。その廊下を通る折、弓子が嬉しそうに声を上げて、
「鹿がいますわ。」
弓子が指さした先には、鹿のブロンズ像が置かれていた。水の中央にいて、川の中を行くかのようである。
「蝦夷鹿だね。」
「なぜわかるの?」
「ここに書いてある。」
公武が足下を指さすと、そこに茶色のプレートがあって、作品名と作者名が書かれていた。
「ずるいですわ。」
「よく見ているだけだよ。」
公武はそう言って、蝦夷鹿を見つめた。蝦夷鹿は、今にも動き出しそうである。公武は、蝦夷鹿のほんとうを見たことがない。あれほど立派な角を持ち、蹄を持つのであろうか。鹿は、凶暴な森の王だと聞いたことがあった。牝を奪い合うために、角で殺し合う。蝦夷鹿も、牝を奪い合うために角を剣のように使うのだろうか。
弓子は、立ち止まったままの公武を置いて、先に進んでいた。公武は、蝦夷鹿に後ろ髪を引かれながら、弓子の後を追った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
