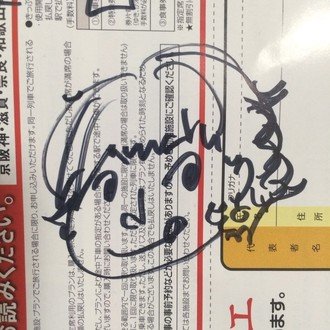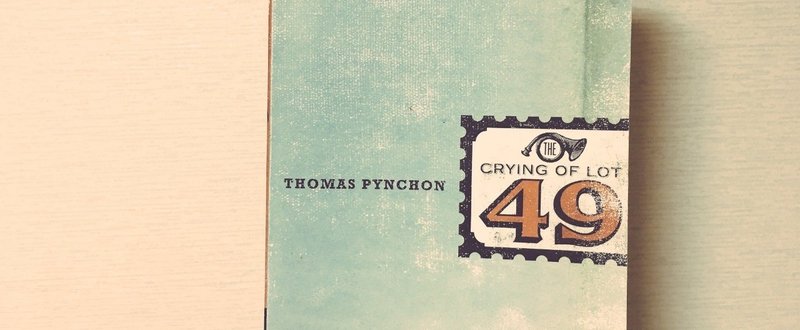
【第3回】「狂気的な文体」をいかにして翻訳するか/作家性の反映──Thomas Pynchon "The Crying of Lot 49"冒頭
ピンチョンという大きな存在
素人が決して手を出すべきではない作家トマス・ピンチョンの『競売ナンバー49の叫び』を今回の題材に選んだ理由をまず先に書いておきたい。
まず第一に、ぼくはトマス・ピンチョンがめちゃくちゃ好きだ。実際に読んだのは小説を書きはじめてからしばらく経ったあと、たぶん24,5歳くらいのときだったけれど、めちゃくちゃな想像力と圧倒的にエネルギッシュな文体に完全にやられてしまった。
良い小説とはなにか──この問いに対して、いかなる読者も、そしていかなる実作者も明確な回答を出すことはできないだろう。小説の価値は本対個人のプライベートな関係性で決まるものだし、共感できて嬉しいとか、知的な想像力に触れられて嬉しいとか、そういうさまざまなよろこびっていうのを他者が否定することなんてできやしない。そうしたむずかしさが存在するなか、ぼくにとってピンチョンが特別な作家である理由をいうなれば「個人を圧倒する暴力的な文章」だ。ぼくにとって、共感や理解をはるかに超えた領域、ぼく個人の脳みそだと絶対にたどり着けない場所へと連れて行ってくれる腕力が「良い小説」のひとつの条件になっている。ピンチョンの腕力はすさまじく、それはもう「暴力」ということば以外に適切な形容が思いつかない。読者を完全にねじ伏せる、圧倒的な力が宿った文章を書ける唯一無二の作家だ。
そう敬愛するピンチョンの文章に近づきたいとはそこまで思わない。「ぼくが好きな文章」と「ぼくが書ける文章」はちがうのはいうまでもないし、いい加減もう8年か9年も小説を書いていればじぶんの文章をある程度は客観的に読めるようにもなってくる。もちろん、ピンチョンをはじめとする多くの作家の影響をどうしようもなく受け続けていることは否定できない。だからである。その強い影響を受けてきた作家の文章が、どのような構造をもち、どのように作られたのかというメカニックの部分をきっちり検討しておきたい。だからこそ今回、無謀にも『競売ナンバー49の叫び』を取り上げることにした。
ピンチョン作品における「パラノイア」と「メタファー」
翻訳の実践に入る前に、説明しておかなければならないことがたくさんある。
ピンチョンといえば科学的事実やオカルト、ド下ネタ、しゃべり出す犬、常識が通用しないキテレツな人間、絶望的にダサい歌、何が面白いのか全くわからない挿話、SF、ファンタジー、スパイ小説、探偵小説……などなど、雑多にして広範囲に渡る事象を怪物的な筆力で小説にしてしまう作風で知られている。小説として「ぶっ壊れている」という評価ももちろんあるのだが、それでも彼が描き出す有象無象が「小説」という統一性を(かろうじて)与えているものとして「パラノイア」がある。
とりわけデビュー作の長編『V.』や今回取り上げる中編『競売ナンバー49の叫び』、20世紀文学の金字塔ともいえる大長編『重力の虹』において、このイメージは作品の中核をなしている。Vという文字、ラッパのマークが示すトライステロという謎の組織、主人公の勃起に呼応してぶっ放されるV2ロケット──小説の駆動力となる特定のイメージへの執着が、隔絶されているはずの幾多の世界を隔てる壁をぶち破り、ひとつの巨大な世界へと向かおうとするようである。
しかしこうしたパラノイアによる「象徴」は、実は小説の実作においてはもっとも基本的な技法にすぎない。物語が教訓めいたなんらかの「意味」を伝えるためのものであるという立場をとるならば、語られる世界は隠喩(メタファー)によって象徴化される必要性を帯びる。それを踏まえてピンチョン作品をみると、世界の隠喩化が過度に強調されている。しかしピンチョンが一筋縄ではいかない理由は、この「メタファー」に対し懐疑的なスタンスをとっているという点にある。すなわち、想起されたメタファーは”ほんとうに”実在するのかということ。そのメタファーが存在しないとすれば、わたしたちが実在しているこの世界の真実性はどうなるというのだろうか。
『競売ナンバー49の叫び』は、そのように宙吊りにされた「トライステロ」という象徴をめぐるエディパ・マースの物語だ。
「作品の尺」と「文体」
というわけで、今回の課題文。"The Crying of Lot 49"の冒頭のパラグラフより引用する。
課題文
One summer afternoon Mrs Oedipa Maas came home from a Tupperware party whose hostess had put perhaps too much kirsch in the fondue to find that she, Oedipa, had been named executor, or she supposed executrix, of the estate of one Pierce Inverarity, a California real estate mogul who had once lost two million dollars in his spare time but still had assets numerous and tangled enough to make the job of storing it all out more than honorary. Oedipa stood in the living room, stared at by the greenish dead eye of the TV tube, spoke the name of God, tried to feel as drunk as possible. But this did not work. She thought of a hotel room in Mazatlán whose door had just been slammed, it seemed forever, waking up two hundred birds down in the lobby; a sunrise over the library slope at Cornell University that nobody out on it had seen because the slope faces west; a dry, disconsolate tune from the fourth movement of the Bartók Concerto for Orchestra; a whitewashed bust of Jay Gould that Pierce kept over the bed on a shelf so narrow for it she’d always had the hovering fear it would someday topple on them. Was that how he’d died, she wondered, among dreams, crushed by the only ikon in the house? That only made her laugh, out loud and helpless; You’re sick, Oedipa, she told herself, or the room, which knew.
引用:THOMAS PYNCHON "THE CRYING OF LOT 49"
この短い英文の中にも多数のイメージが埋め込まれ、ただ事でない狂気を感じずにはいられない。第一文だけでも、
One summer afternoon Mrs Oedipa Maas came home from a Tupperware party whose hostess had put perhaps too much kirsch in the fondue to find that she, Oedipa, had been named executor, or she supposed executrix, of the estate of one Pierce Inverarity, a California real estate mogul who had once lost two million dollars in his spare time but still had assets numerous and tangled enough to make the job of storing it all out more than honorary.
というように、かなり煩雑で長い文章になっている。
技術的なことについては後述するとして、まずピンチョンがこの中編小説においてなぜこのような荒れ狂った文体を採用したのかを検討する。これはどちらかといえば、翻訳的問題でなく実作的問題だろう。
ぼくも一応は実作者だ。むしろ、翻訳よりもずっとはるかに実作のほうで文章を考えてきた。それはまぁいいとして、実作における文体の決定では、作品の尺も重要な要素になるとぼくは考えている。
原稿用紙400枚を超える長編小説を書くならば、全部が全部「強烈な密度の全力の文章」を使うことはあまり得策ではない。もちろん、あくまで「基本的には」という意味であって、ガルシア=マルケス『族長の秋』のようなすさまじい密度による圧倒的な作品も世の中には多数ある。しかし、長編小説はよく言われるように「マラソン」のようなもので、文章の速度や密度のペース配分が重要になる。
しかし『競売ナンバー49の叫び』の特異なところは、本来なら長編として書かれるべきだっただろう内容を、強引に200枚〜300枚程度の中編として書かれているということだ。この小説ではメタ構造や雑多な物語の挿入など重ための内容でごった返していて、そもそも手短にできる話ではない。それを文体の力によって怒涛の圧縮を行っている。いわば、ハーフマラソンを100メートル走のペースで走り抜けているような狂いで書かれているわけだ。
今回はいわば第1回のデリーロの文章で解説した内容の発展形になる。同格や分詞構文による並列や関係節によって同時多発的に描写された事象を、いかにスピードを落とさずに訳出するかがポイントだろう。
以下で実際に翻訳してみた。そのときの思考過程と訳例をできる限りそのまま書いていきたいと思う。なお、志村正雄訳と佐藤良明訳とも比較を行っている。
例によって、遊び・実験要素を取り入れた訳例になるのであらかじめご容赦ください。
現代的に単語を解釈してみる
最初からえらく厄介である。
One summer afternoon Mrs Oedipa Maas came home from a Tupperware party whose hostess had put perhaps too much kirsch in the fondue to find that she, Oedipa, had been named executor, or she supposed executrix, of the estate of one Pierce Inverarity, a California real estate mogul who had once lost two million dollars in his spare time but still had assets numerous and tangled enough to make the job of storing it all out more than honorary.
まずは参考のため句読点をできるだけそのままにした直訳を出しておく。
(直訳)
ある夏の午後、エディパ・マース夫人は女主人がやたらキルシュ酒が多すぎたフォンデュを振る舞ったタッパーウェア・パーティから帰ってきて、そのこと(キルシュ酒が多すぎた)に気づいた彼女、エディパは、遺産整理執行人に、彼女は遺産整理執行女性かとふとおもったのだが、その遺産はかつてひまつぶしに200万ドルほど無駄遣いしてしまったこともあるピアス・インヴェラリティというカリフォルニアのとんでもない大御所の資産家のもので、その推定される額はとんでもなくそして複雑で名ばかりの資産管理の仕事ではないととらえるのにじゅうぶんだった。
ここまで原文がややこしいと直訳するほうがむしろむずかしいというのはさておき、このままだと文章の焦点がまったく合っていない。だからえらく読みにくいだけの文章になっている。
この一文の訳で大事なのは「最初の一文でなにをはっきりさせるか」ということだ。かつ、原文の騒々しい感じが消えてしまってはピンチョンにならないので、そこへの配慮も忘れないようにする。
物語の筋としては、「エディパがある日突然、超金持ちの男の遺産整理をすることになった」という不可解な出来事がメインだ。一種の不条理小説のように捉えるならば、エディパのもとに届いた報せは「ザムザが虫になった」ようなもので、第一文ではここに着地したい。というわけで、ピアスの人物説明の手前くらいでいったん「。」を打つ方向で翻訳したい。
ここで単語の確認をしておく。「Tupperware party」とは、一般のひとをたくさん呼んで行う製品の実演販売みたいなやつだ。「これをあなたも打ってみませんか!?楽してお小遣い稼ぎできますよ!」的な雰囲気も想起される、ネズミ講みたいなソレとも解釈できる。
個人的に訳にこだわりたかったのは、このパーティーの主催者である「hostess」だ。ぶっちゃけこだわるまでもない細部で、無理に訳出する必要もないのだが、「ネズミ講じみたパーティーを主催するフォンデュにキルシュをいれすぎる女性」というのはなかなかパンチが効いている。おふざけが大好きなピンチョンを考慮すると、ここでひとつ翻訳としても「ぶっ込み」をやっておきたい。ちょっと考えてみると「ババア」という声に出して読みたい日本語があったのでこれを採用する。
あと、エディパにかかった「Mrs」だが、これはあとで出てくるピアス・インヴェラリティとの「不適切な関係」を想起させるためにも訳出しておきたい。ここもちょっとふざけて「人妻」というエロさの漂う声に出して読みたい日本語をあてておく。
(訳例)
ある夏の午後、タッパーウェア・パーティから帰ってきたエディパ・マース(人妻)が主催のババアがふるまったフォンデュにキルシュ酒が効きすぎていたと気づいたそのとき、彼女、ほかならぬエディパのもとに、あのピアス・インヴェラリティの遺産整理執行人(エグゼキューター)──女性だから「エグゼキュートリクス」なんじゃないかと彼女はおもった──に指名されたという通知が届いていた。
そして後半のピアスのくだり。特に解説することもないけれど「real estate mogul」はちょっとカジュアルなことばをあてたい。「マジで」とかそういうことばもあるけれど、最近の日本の若者ことばでも「リアルに〜」なんてものがあるから、今回はそのまま「リアルに」を採用することにする。
(大滝訳)
かれはカルフォルニアのリアルにやばい資産家で、生前は暇つぶしに二百万ドルをドブに捨てるような男だったが、その遺産といえば莫大な額でありいろんな事情も絡んでくる。となればこれは名ばかりの執行人として白羽の矢が立ったわけではないのは明白だ。
佐藤良明訳で使われたテクニック
というわけで序文の訳のまとめがこちら。
(大滝訳)
ある夏の午後、タッパーウェア・パーティから帰ってきたエディパ・マース(人妻)が主催のババアがふるまったフォンデュにキルシュ酒が効きすぎていたと気づいたそのとき、彼女、ほかならぬエディパのもとに、あのピアス・インヴェラリティの遺産整理執行人(エグゼキューター)──女性だから「エグゼキュートリクス」なんじゃないかと彼女はおもった──に指名されたという通知が届いていた。かれはカルフォルニアのリアルにやばい資産家で、生前は暇つぶしに二百万ドルをドブに捨てるような男だったが、その遺産といえば莫大な額でありいろんな事情も絡んでくる。となればこれは名ばかりの執行人として白羽の矢が立ったわけではないのは明白だ。
比較のために志村訳と佐藤訳も。
(志村訳)
ある夏の日の午後、エディパ・マース夫人はタッパーウェア製品宣伝のためのホーム・パーティから帰ってきたのだが、そのパーティーのホステスがいささかフォンデュ料理にキルシュ酒をいれすぎたのではなかったかと思われた。家に帰ってみると自分──エディパ──が、カルフォルニア州不動産業界の大立者ピアス・インヴェラリティという男の遺産管理執行人に指名されたという通知がきていた。死んだピアスは暇なときの道楽で二百万ドルをすってしまったこともあるような男だが、それでもなお遺産はおびただしい量で、錯綜しているものだから、そのすべてを整理するとなればとても名義だけの執行人というわけにはいくまい。
(佐藤訳)
ある夏の午後、タッパウェア・パーティから帰宅したミセス・エディパ・マースは、フォンデュの中にたっぷり入ったキルシュ酒の酔いもまだ醒めやらぬ頭で、自分が、このエディパが、ピアス・インヴェラリティの資産の遺言執行人(エグゼキュター)──女だからエグゼキュトリス?──に指名されていたことを知った。インヴェラリティといえばカリフォルニア不動産の超大物。お楽しみの時間に二〇〇万ドル無駄にしたこともあったけれど、それでも彼の遺産となれば、数量的にも複雑さにおいても圧倒的であるに違いなく、それを整理配分するとなれば、お飾りの執行人というわけにはいかないのは明らかだ。
ここで佐藤訳は解説の必要がある。佐藤訳がぼくや志村先生の訳と大きく違っている点は、エディパ一人称視点の導入だ。
ピンチョンの原文でも話に割り込んでくるかのような並列文が埋め込まれているけれど、佐藤訳ではこの並列を「三人称の語りとエディパ一人称の実感」で分裂させている。これによってピンチョンの文章の錯綜する感じを強調しつつ、エディパ視線の臨場感も文章に反映しているわけである。これは個人的にかなり恐れ入った。
セミコロンで並列する断片的な回想の処理
次の文章はなんてことはない。
Oedipa stood in the living room, stared at by the greenish dead eye of the TV tube, spoke the name of God, tried to feel as drunk as possible. But this did not work.
(大滝訳)
リビングに立ち尽くすエディパをブラウン管の緑がかった死んだ眼が彼女をじっと見つめていた。マジかよ、と彼女はいった。キルシュ酒の酔いに身をまかせようとしてみたのだが、そうはいかなかった。
「tried to feel as drunk as possible」では冒頭のキルシュ酒に絡ませて訳出してみることにした。また「spoke the name of God」も訳出パターンは解釈により複数ある。直訳的に「神の名を口にした」でも詩的で大きなリアクションが出せて悪くない。ぼくは今回、訳をカジュアルでポップにしたいという意図があるので「マジかよ」にしてみた。
先生二人の訳はこちら。
(志村訳)
エディパは居間に立ち尽くしていた。スイッチの入っていないテレビの緑っぽいスクリーンの目にねめつけられて、エディパは神のご加護をもとめる言葉を口にし、何とか酔っ払っている気持ちになろうとした。しかし、これはうまくいかなかった。
(佐藤訳)
居間にたたずむエディパを、ブラウン管の緑がかった死んだ目が見つめる。「オーマイガッド!」エディパは神の名を口走り、あたう限りの酔っ払い気分を演じてみたが、効果はなかった。
さて、問題は次だ。
She thought of a hotel room in Mazatlán whose door had just been slammed, it seemed forever, waking up two hundred birds down in the lobby; a sunrise over the library slope at Cornell University that nobody out on it had seen because the slope faces west; a dry, disconsolate tune from the fourth movement of the Bartók Concerto for Orchestra; a whitewashed bust of Jay Gould that Pierce kept over the bed on a shelf so narrow for it she’d always had the hovering fear it would someday topple on them.
ここは「She thought of」の目的語に当たる節がセミコロンにより並列されている。ここまでエディパとピアスの関係はなにも言及されていないが、彼女が思い出しているのは「ピアスと過ごした日々」であり、その記憶はどこか曖昧で現実離れしている。特に最後の「them」は重要で、エディパとピアスのこと。ここまで読んだ時点で読者に「エディパとピアスがベッドをともにする仲だった」とわかるようにしておかねばならない。
マサトラン(メキシコの都市)のホテル、コーネル大学の日の出、バルトーク、グールドの胸像、そうした断片的な記憶がぶわっと溢れ出すような勢いを殺さないように注意しなければならない。
また「whose door had just been slammed, it seemed forever, waking up two hundred birds down in the lobby」は若干テクニックがいる。slammedは音を伴う激しい打撃を含む動詞なので、「その音で鳥が目覚めた」と読む。そして挿入された「it seemed forever」は音と鳥の目覚めの連動を邪魔しないように訳出しないと文章全体の鮮やかさが損なわれてしまう。
(大滝訳)
彼女は思い出していた。マサトランのホテルを。バタンと永久に閉じられたかのように扉がとじられ、階下のロビーでは二百羽の鳥が目を覚した。またはコーネル大学の図書館の坂の向こうに登る日の出を。しかし坂は西側なのでこれはありえない情景だ。あるいはバルトークの『管弦楽のための協奏曲』の第四楽章の乾いた、この世の終わりみたいな旋律。そしてジェイ・グールドの石膏の胸像だ。ベッドの上のあまりにもせまい棚の上に置きっぱなしにされていたので、いつか彼女とピアスのうえに落ちてくるんじゃないかという漠然とした恐怖をエディパは常に抱いていた。
(志村訳)
メキシコのマサトランのホテルの一室のことを思い出した。その部屋のドアがバタンと激しくしまったところだ。永遠にしまったのかと思われた。下のロビーの二百羽の鳥がそれで目を覚ました。また、コーネル大学の図書館がある斜面の、その向こう側の日の出を思い出した。その斜面が西向きなので、そこに立っているかぎりだれにも日の出が見えはしないのだ。また、バルトークの『管弦楽のための協奏曲』の第四楽章の乾いた、やるせない調べ。また、大富豪ジェイ・グールドの石膏の胸像。ピアスはそれをベッドの上の狭すぎる棚の上に置いていたので、エディパはそれがいつの日か二人のところに落ちてくるのではないかと、そこはかとない不安を抱いていた。
(佐藤訳)
ピアスと一緒の旅で入ったマサトランのホテルの部屋が思い浮かんだ。あの部屋のドアは、閉まるとき、もう二度と開かないかと思うくらいの音を立てて、ロビーに眠る二〇〇羽の鳥の目を覚ましたっけ。コーネル大学図書館の建つ丘の向こうから朝日が昇るところも記憶に浮かんだ(あれは西向きの景色だから、そんな日の出、だれ一人見た者はいないのに)。次に浮かんできたのが、バルトークの「管弦楽のための協奏曲」第四楽章。その、やるせない乾いたメロディに続いて、ピアスのベッドの上の、狭すぎる棚に置かれたジェイ・グールドの石膏胸像が思い出された。いつか二人の上に落ちてくるんじゃないかと気が気でなかったその胸像に、もしかしたらピアスは潰されたのだろうか。
※この訳には続く文章「Was that how he’d died」も含まれている
ここでも佐藤訳では「エディパ一人称」を巧みに使うことで、一連の回想を鮮やかに処理している。原文では回想の断片の列挙に近いが、それを縫合するようにエディパのひとつなぎの回想として解釈している。
関係代名詞の非制限用法と先行詞
受験英語っぽい章題になってしまったが、まずは原文のチェック。
Was that how he’d died, she wondered, among dreams, crushed by the only ikon in the house? That only made her laugh, out loud and helpless; You’re sick, Oedipa, she told herself, or the room, which knew.
もちろん訳のポイントは末部の「, which knew」という関係代名詞の非制限用法だ。エディパが「あんたは病気よ」ひとりごちるのだが、「これを聞いていたのはだれ?」ということを考えて訳さなければならない。文法上考えられるのは、「the room」のみか、「herself」と「the room」の両方にかかるのかだ。
ぼくは両方にかかると解釈したが、「the room(=誰でもない誰か)」という不特定多数の意味をも持たせるため、主語を省略して不明瞭にする方針をとった。
(大滝訳)
それで死んだの? と彼女は夢見ごこちに思いをめぐらせた。あの家でたったひとつのあの聖像に頭をかち割られたの? だとしたら笑うしかなかった。声をあげて笑い、同時に死にたくなった。エディパ、あんたはイカれてる。彼女は自分自身に、あるいはリビングに向かってひとりごちる。そんなことはわかっていた。
(志村訳)
それで死んだのだろうか? 夢また夢を見ながら、あの屋敷のなかの唯一の聖像(イコン)に押しつぶされて? そう思っても笑うばかりだった。声を出して笑い、当惑した──病的だわ、エディパ、と彼女は自分に言い聞かせた。それとも居間に言い聞かせたのだろうか。居間はエディパが病的になっていることを知っているにちがいない。
志村訳の先行詞は「居間」ですね。
(佐藤訳)
夢のままに、自宅にあった唯一の聖像に殺された?──そう思うとエディパは無力な大声で笑うしかなかった。あんたは病気よ、と自分に向けて言い放つ。それとも部屋に向けて言ったのか。知ってるよ、と声が帰ってきた気がした。
佐藤訳も「居間」を先行詞にとっているようですが、ちょっと工夫している。しかし、その所在を不確かにして、亡霊的な不気味さに配慮している。
まとめ──現代の翻訳技術は進化しているのか?
という訳で、今回の訳例をまとめてみる。
(大滝訳)
ある夏の午後、タッパーウェア・パーティから帰ってきたエディパ・マース(人妻)が主催のババアがふるまったフォンデュにキルシュ酒が効きすぎていたと気づいたそのとき、彼女、ほかならぬエディパのもとに、あのピアス・インヴェラリティの遺産整理執行人(エグゼキューター)──女性だから「エグゼキュートリクス」なんじゃないかと彼女はおもった──に指名されたという通知が届いていた。かれはカルフォルニアのリアルにやばい資産家で、生前は暇つぶしに二百万ドルをドブに捨てるような男だったが、その遺産といえば莫大な額でありいろんな事情も絡んでくる。となればこれは名ばかりの執行人として白羽の矢が立ったわけではないのは明白だ。リビングに立ち尽くすエディパをブラウン管の緑がかった死んだ眼が彼女をじっと見つめていた。マジかよ、と彼女はいった。キルシュ酒の酔いに身をまかせようとしてみたのだが、そうはいかなかった。彼女は思い出していた。マサトランのホテルを。バタンと永久に閉じられたかのように扉がとじられ、階下のロビーでは二百羽の鳥が目を覚した。またはコーネル大学の図書館の坂の向こうに登る日の出を。しかし坂は西側なのでこれはありえない情景だ。あるいはバルトークの『管弦楽のための協奏曲』の第四楽章の乾いた、この世の終わりみたいな旋律。そしてジェイ・グールドの石膏の胸像だ。ベッドの上のあまりにもせまい棚の上に置きっぱなしにされていたので、いつか彼女とピアスのうえに落ちてくるんじゃないかという漠然とした恐怖をエディパは常に抱いていた。それで死んだの? と彼女は夢見ごこちに思いをめぐらせた。あの家でたったひとつのあの聖像に頭をかち割られたの? だとしたら笑うしかなかった。声をあげて笑い、同時に死にたくなった。エディパ、あんたはイカれてる。彼女は自分自身に、あるいはリビングに向かってひとりごちる。そんなことはわかっていた。
(志村訳)
ある夏の日の午後、エディパ・マース夫人はタッパーウェア製品宣伝のためのホーム・パーティから帰ってきたのだが、そのパーティーのホステスがいささかフォンデュ料理にキルシュ酒をいれすぎたのではなかったかと思われた。家に帰ってみると自分──エディパ──が、カルフォルニア州不動産業界の大立者ピアス・インヴェラリティという男の遺産管理執行人に指名されたという通知がきていた。死んだピアスは暇なときの道楽で二百万ドルをすってしまったこともあるような男だが、それでもなお遺産はおびただしい量で、錯綜しているものだから、そのすべてを整理するとなればとても名義だけの執行人というわけにはいくまい。エディパは居間に立ち尽くしていた。スイッチの入っていないテレビの緑っぽいスクリーンの目にねめつけられて、エディパは神のご加護をもとめる言葉を口にし、何とか酔っ払っている気持ちになろうとした。しかし、これはうまくいかなかった。メキシコのマサトランのホテルの一室のことを思い出した。その部屋のドアがバタンと激しくしまったところだ。永遠にしまったのかと思われた。下のロビーの二百羽の鳥がそれで目を覚ました。また、コーネル大学の図書館がある斜面の、その向こう側の日の出を思い出した。その斜面が西向きなので、そこに立っているかぎりだれにも日の出が見えはしないのだ。また、バルトークの『管弦楽のための協奏曲』の第四楽章の乾いた、やるせない調べ。また、大富豪ジェイ・グールドの石膏の胸像。ピアスはそれをベッドの上の狭すぎる棚の上に置いていたので、エディパはそれがいつの日か二人のところに落ちてくるのではないかと、そこはかとない不安を抱いていた。それで死んだのだろうか? 夢また夢を見ながら、あの屋敷のなかの唯一の聖像(イコン)に押しつぶされて? そう思っても笑うばかりだった。声を出して笑い、当惑した──病的だわ、エディパ、と彼女は自分に言い聞かせた。それとも居間に言い聞かせたのだろうか。居間はエディパが病的になっていることを知っているにちがいない。
(佐藤訳)
ある夏の午後、タッパウェア・パーティから帰宅したミセス・エディパ・マースは、フォンデュの中にたっぷり入ったキルシュ酒の酔いもまだ醒めやらぬ頭で、自分が、このエディパが、ピアス・インヴェラリティの資産の遺言執行人(エグゼキュター)──女だからエグゼキュトリス?──に指名されていたことを知った。インヴェラリティといえばカリフォルニア不動産の超大物。お楽しみの時間に二〇〇万ドル無駄にしたこともあったけれど、それでも彼の遺産となれば、数量的にも複雑さにおいても圧倒的であるに違いなく、それを整理配分するとなれば、お飾りの執行人というわけにはいかないのは明らかだ。居間にたたずむエディパを、ブラウン管の緑がかった死んだ目が見つめる。「オーマイガッド!」エディパは神の名を口走り、あたう限りの酔っ払い気分を演じてみたが、効果はなかった。ピアスと一緒の旅で入ったマサトランのホテルの部屋が思い浮かんだ。あの部屋のドアは、閉まるとき、もう二度と開かないかと思うくらいの音を立てて、ロビーに眠る二〇〇羽の鳥の目を覚ましたっけ。コーネル大学図書館の建つ丘の向こうから朝日が昇るところも記憶に浮かんだ(あれは西向きの景色だから、そんな日の出、だれ一人見た者はいないのに)。次に浮かんできたのが、バルトークの「管弦楽のための協奏曲」第四楽章。その、やるせない乾いたメロディに続いて、ピアスのベッドの上の、狭すぎる棚に置かれたジェイ・グールドの石膏胸像が思い出された。いつか二人の上に落ちてくるんじゃないかと気が気でなかったその胸像に、もしかしたらピアスは潰されたのだろうか。夢のままに、自宅にあった唯一の聖像に殺された?──そう思うとエディパは無力な大声で笑うしかなかった。あんたは病気よ、と自分に向けて言い放つ。それとも部屋に向けて言ったのか。知ってるよ、と声が帰ってきた気がした。
個人的な好みや印象をいえば、佐藤訳がつくろうとしている「ピンチョンの表現」には(偉そうな言い方で恐縮だが)大きな才気を感じずにはいられない。こうした訳を読むと、現代の翻訳家の技術のめざましい進化を感じる。
しかし、それは当然ながらこの難しい題材に勇敢に向き合った志村先生の翻訳が貴重な資料としてあったのはいうまでもない。古典作品なんかではしょっちゅう「新訳」が登場するけれども、「そもそもなぜ新たな訳をしなければならないのか」というのは翻訳の範囲にとどまる問題ではない。学術的な再検討はもちろん、読書の多様なありかた、ひとつの「読書」を具体的かつ詳細に示すということばの運動それじたいの尊さがそこにある。それは絶対に無視されてはならないとぼくは思う。
それに、現代ではインターネットの一般化はやはり大きいだろう。ピンチョンのようなあらゆる分野を横断する百科全書的手法を駆使する作家の翻訳というのは、情報インフラが整備されていない時代ではほぼ不可能だったのではないか。『重力の虹』が提示した現代のインターネットのようなハイパーリンク的なテキストが、インターネットが普及していなかった時代に翻訳されたという事実はいま思えば事件的な出来事で、どれほど翻訳が困難だったかは想像を絶する。
しかして翻訳小説の読者は決して多くない。そして個人的な印象の域を出ないのは承知だが、実際に原文を読んだことのない読者ほど「翻訳が合わないから苦手だ」ということをよく口にしているようにおもう。なかには「翻訳者は表現者ではない」というひとさえ存在する。
今回のピンチョンの翻訳研究を通して、翻訳という仕事に使われた技術や想像力の水準の高さをぼくは知ってもらいたかった。特にピンチョンは小説を読みなれたひとでさえ「難しい」と挫折することも珍しくない作家だ。だからこそ、ピンチョンの文章のメカニックを詳細に解説することで、もう一度ピンチョンに挑んでもらいたい。
最後に、"The Crying of lot 49"でもっとも好きな一節を原文で紹介したい。ぜひじぶんの力で翻訳してみて欲しい。
In the Golden Gate Park she came on a circle of children in their nightclothes, who told her they were dreaming the gathering. But that the dream was really no different from being awake, because in the mornings when they got up they felt tired, as if they'd been up most of the night. When their mothers thought they were out playing they were really curled in cupboards of neighbors' houses, in platforms up in trees, in secretly-hollowed nests inside hedges, sleeping, making up for these hours. The night was empty of all terror for them, they had inside their circle an imaginary fire, and needed nothing but their own unpenetrated sense of community.
頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。