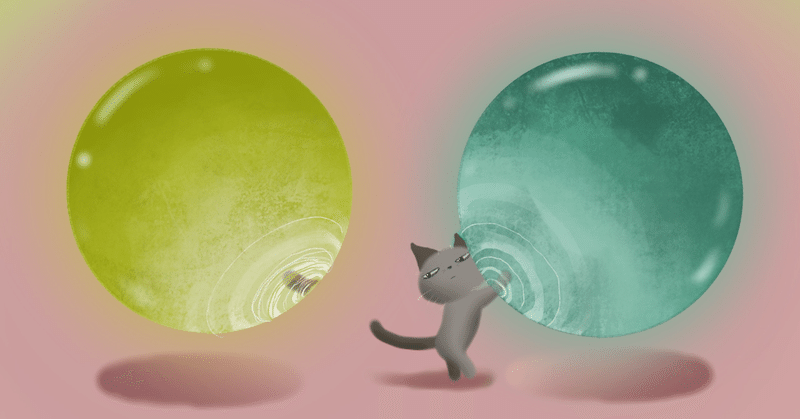
18禁じゃないスピリチュアル 緑のドア 〜表面張力
こんばんは。id_butterです。
今日もただの脳内妄想、自己満足100%でお届けするので、必要のない人は全身全霊をもって逃げてください。。。
▼前回
▼ザイオンside
アーニャと呼ばれるその女を見て、全身の細胞が沸きたつ。
探して求めてきたのは、間違いなくこの女だ。
渇望、といってもいい。
その女が俺と同じような力を持っていることは一目瞭然だった。
周囲の空気が陽炎のように揺らめいて見える。
本当にいたのか。
数十年、半信半疑のまま、生きながらえてきた。
内に飼っていた憂鬱が嘘のように晴れていくのを感じる。
運命を信じるたちではない、けれど目の前の存在は本物でしかなかった。
驚くを通り越して感動していた。
馴染みのある絶望や孤独、諦観が、その女を巣食っている。
俺と同じ匂いだ。
けれど、想定をはるかに超えて進んでしまっている。
漏れ出ているのだ。
誰も、この危うさに気づかないのか?
一般人にも見えそうなレベルにまで達しているように見える。
それとも、目を瞑っているのか。
だとしたら、だからこそやばいのかもしれない。
サキという旧知の女と話しながら、頭を駆け巡っていたのは全く別のことだった。
見渡して、ふと気づく。
アンとかいう侍女がこっちを怪訝そうに見ている。
その女はこの女の異変のみならず、俺の能力に気づいているようだった。
感応能力が高いのか?
いや、というより防衛本能が働いているのかもしれない。
その女の下腹部にどす黒い影が見えた。
この女を先に抱き込んでおいた方がいいかもしれないな。
邪魔されたくなかった。
それにしても、ひどい。
影は下腹部から女の全身を支配している。
見ているだけでも息が詰まった。
この女をかわいそうだと思う心と、懐柔しておけばことが有利に運べそうだという計算の両方が俺の頭をかけ巡る。
女が俺を部屋に案内するという。
このチャンスは逃すべきじゃない。
そう判断した。
普通の人間の持つ「良心」という枷が自分の中に存在しないことに感謝する。
俺は、ここで欲しいものを手にいれる。
ためらう気はなかった。
女の腕を掴んで、引き止める。
▼アンside
わたしの体に男が直接手を触れたのは最初だけだった。
「やはりこの辺りが一番ひどそうだ。」
という声と同時に、男の手が下腹部の上にかざされた。
触れていないのに、不思議と温かい。
不覚にもホッとしてしまいそうになり、気を引き締めた。
おなかの中がコポコポと音をたて始める。
恥ずかしくなるが、わたしの表情を読んだのか、男が説明を挟んでくれる。
「体の中で滞っていたものが流れ始めてるだけだ。」
滞っていたもの?
わたしの中で何が滞っていたというのだろう。
男がさらりという。
「いつだ?相手は例の死んだ薬師か。」
言いたくなかったので、黙っていた。
「そのときサキに診てもらわなかったのか。何日くらい血が流れた。」
なおも喋り続ける薬師を無視した。
「お前も我慢ばかりしてるタイプか。言いたいことも言わないで。」
人の気も知らないで、と叫びそうになったのに、実際に口から漏れたのは吐息だった。
「はぁっ…」
熱い気のようなものが、子宮のあたりから胸の方にすごい勢いで流れていく。その勢いは、子宮についている固いかさぶたみたいなものを剥がそうとしているようだ。熱さと、痛みにも似た切なさでおなかがいっぱいになる。
苦しい、それに。
「痛くないか?」
男に聞かれて、本音が漏れた。
「やだ、こわい…こわいよ。」
どうして。
なんでわたしばっかり。
もう終わったはずなのに、なんで。
あの日の記憶が鮮明に蘇ってくる。
痛みや恐怖や、自分の悲鳴や冷えた部屋の空気があの時のまま迫ってくる。
はがれ落ちようとしているかさぶたは、当時に毎晩見た夢、もう忘れたはずの記憶だった。
「お前は悪くない。」
突然耳に飛び込んできた台詞に反応したのは、わたしというより、わたしの中の誰かだった。急に胸のあたりがトクトクと音をたて始める。
……本当に?わたしのせいじゃない?
「お前くらいは、お前をかわいそうだって思ったっていいんじゃないか。」
こらえていた涙が溢れるのを、もう止められそうもなかった。
お腹の中の熱は嵐の後に増水した川のようにすごい勢いで流れ続けている。
もう、怖くはなかった。
その熱の流れは全身を巡っていく。
あのときのわたしの痛みの記憶は、全身に散らばっていた。
小石のようにこわばった痛みが、自分を傷め続けていることにわたしは今まで気づかなかった。
今、その痛みが熱により溶かされていく。
ほどけていく。
痛みは嘘のように消え、体がふわっと軽くなったのがわかった。
▼ザイオンside
こちらを見る女の目が、熱っぽく潤んでいるのがわかった。
女の体から、力は抜けていた。
警戒心はもうかけらも残ってないようだ。
いつものことだった。
傷ついた女はみんなこうだ。
毎度のことなので、慣れている。
けれど、一時的なものだ。
一定期間、適当につきあえばいい。
最後に一度だけ、直接下腹部に触れる。
女の体がビクッと震える。
手から気を送る。
いつもはしない、今回は特別だった。治療ではない。
この女には利用価値がある。
コントロールしたかった。
女が期待を込めて見上げてくる。
いや、お楽しみは後にしておこうぜ。
焦らしたほうが効果的だ。
結局のところ、例の薬師と俺はなんの変わりもなかった。
苦しめるつもりはないが、支配して利用しようとしている。
「施術は終わった。また、つらくなったらいつでもくるといい。」
▼続きます。
サポート嬉しいです!新しい記事執筆のためシュタイナーの本購入に使わせていただきます。
