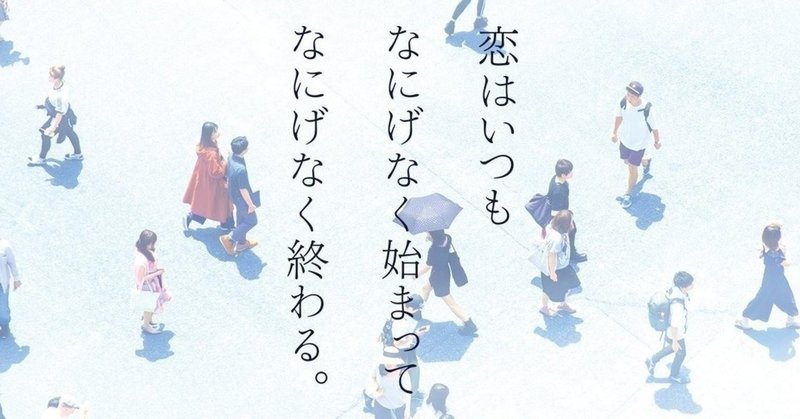
『恋はいつもなにげなく始まってなにげなく終わる。』全文公開⑳伝えられなかった恋
四月になると渋谷は新しい人たちを迎え始める。新しい学生、新しい社会人が街を歩き、渋谷をまた新しい街に変える。
バーテンダーとしては、こんな時期にこそ、ゆっくりとくつろいだ時間や空間を作ってお客様を待ちたくなる。艶やかな大人のための時間を作ってくれる歌手を考えてみたら、ジュリー・ロンドンを思いついた。
彼女が歌う『エヴリタイム・ウィ・セイ・グッドバイ』という曲がある。「さよならを言うたびに少しだけつらい。どうしてもっと一緒にいさせてくれないのだろう」と歌う曲だ。
私はこの歌を聴くたびに、この歌の主人公は恋する相手とどんな関係なのだろうと考えてしまう。
好きだという気持ちは伝えているのだろうか、愛し合っている仲なのだろうか、考えれば考えるほど謎が深まる歌詞だ。
わかっていることがひとつだけある。この歌の主人公は本当にその相手のことが好きなのだろうということだ。
レコードをターンテーブルの上に置き、針をのせる。
そこに灰色のジャケットに紺色のパンツのソフトな印象の男性が入ってきた。年齢は三十代前半くらいだろうか、背は少し低めで丸顔、神経質そうに見えるが私と目が合うと明るい笑顔を見せた。
私が「お好きな席にどうぞ」と伝えると、しばらく迷って奥から二つ目の席に座り、「ペルノーをロックでください」と注文した。
昔アブサンというリキュールが十九世紀末のフランスの芸術家たちの間で愛飲された。詩人のヴェルレーヌや画家のロートレックやゴッホも愛したそうだ。しかし、ニガヨモギに由来する含有成分が幻覚を引き起こすとされ、フランスでは一九一五年に製造禁止となった。
そのアブサンの代替品として生まれたのがペルノーをはじめとするパスティスだ。そういう経緯からなのか、絵を描く人やフランスにしばらく滞在していた人はこのペルノーを好んで飲む。
「このバーは氷が三つなんですね」と男性が言った。
私はオン・ザ・ロックの氷が一個だけなのが好きではない。バーテンダーズ・ルールの類の本を開くと必ず「氷は一個の方が溶けにくい」という理由からオン・ザ・ロックには氷は一個だけと推奨されているが、私はオン・ザ・ロックには氷を三個入れることにしている。グラスを傾けた時に氷と氷がぶつかりあう音がバーに響くのを聞くのが好きだからだ。
「バーって面白いものですね。僕がペルノーをロックでと注文したら、ミントを添えてくれるお店もあれば、ライムのカットを搾り入れてくれるお店もあります。ペルノーが真っ白になるまでステアするお店もあれば、ほとんど透明のままのペルノーを出すお店もあります。お客としては同じ注文をしたはずなのに、出てくるものが少しずつ違ってそれが本当に楽しいですね」
「そういう意味ではバーの飲み物はよくクラシック音楽にたとえられます。バッハのゴルトベルクも、楽譜は同じでも、演奏家によってまるで違った曲に聞こえます。それと同じでバーテンダーが扱う氷やグラスによっても酒は大きく変わります」
「ああ、絵にも似ていますね。絵描きが見ている対象は同じなのにまったく違う絵が生まれます。いえ。絵だけじゃないですね。詩もそうだし、料理もそうですね。同じものを見ていても、生まれてくるものは人によってまったく違いますね。人生もそうなのかもしれないですね」
「そうですね。たぶんそうなのでしょう。ところでお客様は絵を描かれるんですか?」
「はい」
「どういう絵を描かれるんですか?」
「思い出の中の女性だけを描いているんです」
「思い出の中の女性だけって、どういうことですか?」
「まあバカな男の話ですが。聞いていただけますか。
僕、女子校で美術の教師をやってるんですね。絵が売れてそれで生活できればいいのですが、まずそんなことは不可能な、僕のような人間は美術教師をしているってわけです。
普通は女子校で教師をしていると、早く結婚しろって言われるんですけど、僕はまだ美大を出てすぐで、学生時代の彼女とはすごい失恋をしたところで、しばらく恋愛なんてする気がなかったんです。
そんな僕が美術部の女子生徒に恋をしてしまったんです。
最初に美術部の部室で会った時、『あ!!』って思いました。
ご存じのように、女子生徒との恋は絶対にご法度なんです。女子校の教師になる時に、校長や周りの教師たちからも何度も何度も言われました。
人生を棒に振ってしまった男性教師の話も何度か聞かされました。
本当にそれはわかっていたのですが、彼女を一目見た時に『あ!!』って思ってしまったんです。彼女がいるあたりが輝いていたんです。
それからは絶対にそんな気持ちは見せないようにしました。
出来るだけ彼女とは会話をしないようにしよう、出来るだけ目も合わせないようにしようっていろんなことを決めたのですが、やっぱり近くにいるとドキドキします。
僕はその時、二十三歳で、彼女は高校三年生で十七歳だったので、普通の社会なら恋愛をしても普通の年齢差ですよね。でも、ちょっとでもそんな気持ちを見せたら、僕はその場で解雇です。
美術の教師でもやっていきながら、展覧会に出品し、いつか賞をとって、という小さな希望も、そこで壊れてしまいます。
『あいつは女子生徒に手を出した卑劣なロリコン野郎だ』って一生言われ続けてしまいます。
僕は一年が過ぎ去るのをじっと待ちました。校内で彼女を見かけるともう口の中がカラカラになってしまうくらいの気持ちでしたが、ジッと我慢しました。
夏休みは自由に部室に来て、絵を描いても良かったので、彼女はよく登校して、部室でずっと絵を描いていました」
「彼女は上手かったんですか?」
「はい。すごく才能がありました。
ああ、彼女ともう少し絵の話がしたい。今、こういう美術展をやっているから行ってみたらいいと思うよ、なんて言いたくなるのですが、ぐっと我慢しました。どこかを越えるともう自分の気持ちが抑えられなくなると思ったからです。
夏休みの彼女の私服はとても新鮮でした。ああ、たぶんこれから一生、こんなに好きな女性はもう現れないだろうなあと確信しました。
でもそんな表情もまったく見せませんでしたし、彼女に質問をされるまでは絶対にこちらからは話しかけませんでした」
「苦しいですね。彼女の進学の相談なんかにはのらなかったんですか?」
「彼女は父親が単身赴任でフランスにいて、高校を卒業したら、母親と一緒にフランスに行くことが決まっていました。
だからフランスの美術の学校に行きたいというので、僕は美大時代の教授や友達に連絡して、フランスの美術の大学の情報を彼女のために集めました。
彼女は両親と話し合いフランスの大学に進学することになりました」
「そうなんですか。彼女とは本当にプライベートなことは話さなかったんですか?」
「はい。それだけは決めていましたから。フランスへの進学の手続きを進めている時に、ちょうど二月十四日が来て、彼女からチョコレートを貰いました」
「どんなチョコだったんですか?」
「手作りでしたが、手紙がついてて、『先生、お世話になりました』って書いてありました」
「ああ、義理チョコっぽいですね」
「そうですね。もしかして何か書いてあるかなってすごく期待したのですが、僕の空回りでした。
卒業式の時も普通でした。もちろんこれで一生の別れになると思うとつらかったのですが、大事にならなかったので、ホッとした方が大きかったです」
「そんなものなんですね。その後は彼女と連絡はとったんですか? だってもう教師と生徒じゃないですよね」
「実は少しだけそれについて考えてしまいました。国内にいたらこちらから何か理由をつけて会うこともできたのですが、フランスに行ってしまったので、そんなことも無理でした。
ある日、彼女の名前を検索したら彼女がブログを始めているのに気がつきました。
フランスでの学校のこと、美術展に行ったこと、友達のこと、最近描いた絵もアップしてありました。
一週間に最低一回は記事をあげていて、僕は彼女のブログの更新が唯一の楽しみになりました。
残念なことに彼女は自分の写真は一枚もアップしませんでした。ですから彼女のイメージはいつまでたっても高校生の時のままでした。
ある日、彼女に恋人が出来ました。彼女の日本の友達にも知らせたかったのでしょう。フランス人でブルゴーニュ出身のカッコいい男性でした。彼も美術を専攻していて、一緒に絵を描いていました。
僕はやっと目が覚めました。僕も自分の絵を描こうと思いました。彼女の真似をして僕もブログを書き始めました。
今までよりも積極的にたくさんの美術展にも行って、その感想をブログに書いて、自分の新しい絵もブログにアップするようになりました。
はい。全部、彼女の影響でした。
彼女の絵もどんどん上達して、フランスのコンクールに入賞することもありました。
ある日、彼女が結婚しました。
僕も恋愛しなきゃ、誰かを好きになって結婚しなきゃって思ったのですが、でも無理でした。
僕はずっと絵を描き続けました。
ある時、思い出の中の彼女を描いてみました。
驚いたことにその彼女を描いた作品が入選したんです。僕は決めました。思い出の中の彼女の絵だけを描こうと。
彼女の絵がたくさん描けたので、青山でこぢんまりとした展覧会を開きました。僕のキャリアが始まった。これで良いんだ。ずっと彼女の絵だけを描き続けていこう、それで良いんだと思いました。
自分の小さな展覧会でお客様と話し終えた時、後ろから女性の声が聞こえました。
『先生、入選おめでとうございます』
振り返ると彼女でした。ずっと思い出の中だけだった彼女が目の前にいました。
『お久しぶりです。覚えていないかもしれないのですが、高校の時に美術部だった石井です』
僕は思わずこう言ってしまいました。
『ああ、石井さん。あ、でも今は石井さんじゃないんですよね。結婚おめでとうございます』
『先生、どうして知ってるんですか? あ、誰か友達が教えたんですか?』
『いや。実は石井さんのブログをずっと見ていて』
『え、そうなんですか? 私も実は先生のブログをずっと見ていて。どうしても会いたいと思って、今日、展覧会に来ました』」
「そんなことがあるんですね」
「はい。それで展覧会が終わったらお茶でもと話して、その後、彼女が泊まっているホテルのラウンジでコーヒーを飲みました。
僕はもう時効だと思って、石井さんのことを好きだったと伝えました。ブログをずっと見ていたこと、思い出の中の石井さんをイメージして絵を描いたこと。ストーカーみたいでごめんなさい。でもどうしてもこの気持ちを伝えたかったってことも言いました。
彼女も実は高校時代、僕のことをすごく好きだったと言ってくれました。でもすごく冷たいし、絶対にそんなことは無理なんだろうなあって思っていたそうなんです。
僕たちはみんなが見ているホテルのラウンジで、少し泣いてしまいました」
「それでどうしたんですか?」
「彼女は次の日、飛行機に乗ってフランスに帰りました。それからはたまにメールをやり取りするようになりました。彼女はブルゴーニュに引っ越して、子供が生まれて、相変わらずフランスで自分の絵を描いていました。彼女が嫁いだ先はワインを作っていまして、レザムルーズというワインがあるそうなのです。そのワインのエチケットは彼女が描いていて、日本でも飲めるそうです。
もういいや、僕はこのまま一生、彼女のことだけを思って生きるって決めました」
「それから?」
「たまに彼女からメールが来ると嬉しいです。今でも思い出の中の彼女を描き続けています」
「いつか、彼女が旦那さんと別れないかなとか、旦那さんが死なないかなとか、そんなことは思わないんですか?」
「もちろんちょっとは思いますけど、そしたら彼女、落ち込むだろうな、悲しむだろうなと思うとね。そんなことより彼女の笑顔が描けたら僕は幸せなんです。絵の中では彼女は僕のことだけを見ていますから」
「そうですか」
「はい。あ、マスター、僕、また彼女の絵で入選したんです。やっぱり彼女の絵を描くと僕の才能は開花するみたいなんです。ぜひ、何かおいしいワインで乾杯してください。そういう人のためのワインって何かありませんか?」
私は二〇〇三年のレザムルーズを取り出して、彼にそのエチケットを見せた。
すると彼はそのエチケットの絵を見て、「あ!」と言った。そのエチケットは美術室で女性が男性にプレゼントを渡している絵だった。
「マスター、この絵、僕と彼女ですね」
「そのようですね。チョコレートでこのワインを飲みましょうか」
私たちの後ろではジュリー・ロンドンが「さよならを言うたびに少しだけつらい」と歌っていた。
SNSでシェア等していただけると助かります。「もう早速、全部読みたい! 待てない!」という方、本、売ってます。こういう短い恋の話が、あと20個入ってます。GWの読書にいかがでしょうか? キンドルだと今、お安くなってます。プレゼントにも最適です。あの人に贈っちゃいましょう。
#ファーストデートの思い出 というハッシュタグで、あなたのファーストデートのあれこれを募集しています。ファーストデートのことを書いてくれたら、僕、全部読みます。是非。詳しくはこちら↓
サポートしたいと思ってくれた方、『結局、人の悩みは人間関係』を買っていただいた方が嬉しいです。それはもう持ってる、という方、お友達にプレゼントとかいかがでしょうか。
