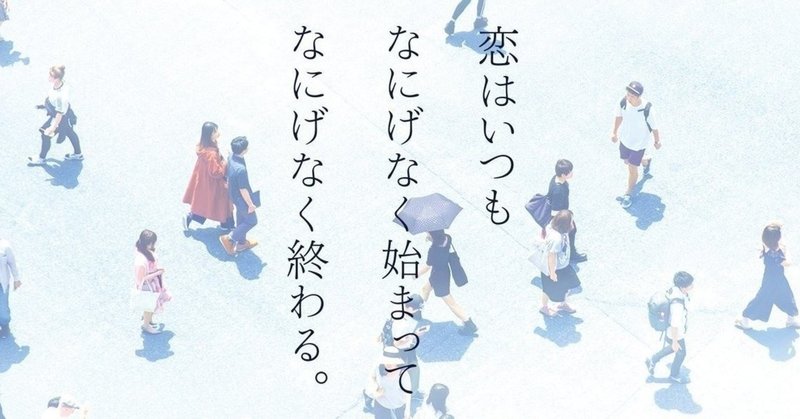
『恋はいつもなにげなく始まってなにげなく終わる。』全文公開⑲恋は風邪と同じ
渋谷のスクランブル交差点は一度の青信号で多い時には三千人が行き交うらしい。
三月、春の訪れを知らせる温かい雨が降る日のこと。私はスクランブル交差点を行き交う人たちの青、赤、黄、白、紺、緑とたくさんの色の傘の花が咲き乱れるのを眺めていた。
この傘を持った人たちそれぞれに人生があり、このスクランブル交差点を渡っているんだと思うと、少し切なくなる。
こんな温かい雨が降る夜にはボサノヴァが聴きたくなる。
『イパネマの娘』というボサノヴァの有名な曲がある。
イパネマの海岸へと向かって歩いている美しい女性がいる。歌の主人公の「僕」はただ見ているだけで、彼女には声をかけられない。どうして「僕」は彼女に声をかけられないのだろう。ただ臆病なだけということでもなさそうだ。この世界には「好きだ」と伝えられない恋もある。
スタン・ゲッツとジョアン・ジルベルトが共演したアルバムを取り出し、針を置くと、ジョアン・ジルベルトが声をかけられない切ない恋の曲を歌い始めた。
バーの扉が開き、以前はよく来店されていた女性が傘を閉じながら入ってきた。
年齢は今はたしか四十三歳。長い髪の毛を後ろでまとめて、濃い紺色のセーターを着ている。四十をこえているのに相変わらず若々しく見えるのは背筋の伸びた姿勢とちょっとはにかんだ笑顔のせいだろう。成熟した大人の女性特有の少しかすれた声で「お久しぶりです。ちょっと近くに寄ったもので」と言った。
お仕事はイタリアの食材やワインを輸入している小さい商社の営業で、私のバーにも仕事がきっかけでよく来店していただいていた。
彼女のご主人がその会社を経営している。他にイタリアの美術や音楽を紹介する仕事もされていて、業界ではちょっとした有名人だ。
ご主人とは大学生の時からの付き合いで、卒業後すぐに結婚したと聞いている。いわゆるおしどり夫婦で、パーティやイベントにも必ずお二人で出席している。
彼女は席につくと「ふう、やっと落ち着けた」と言い、小さなため息をついた。
「お飲み物はどうなさいますか?」
「マスター、お寿司屋さんに行ったら、コハダを頼むとそのお店の味がわかるっていうじゃないですか。バーだとそれはやっぱりマティーニでしょうか?」
「そうですね。マティーニはお店によってスタイルが違いますが、そういう意味でしたらジン・トニックの方がお店によって、あるいはバーテンダーのちょっとしたこだわりによって、ずいぶん違ってきますよ」
「マスターがバーにお客さんとして行ったら、何を注文しますか?」
「私ですか。私がそのお店やバーテンダーのことを知りたい場合はジャック・ローズを注文しますね」
「ジャック・ローズ?」
「はい。世界六大カクテルのうちのひとつなのですが、あまり有名ではありません。カルバドスというリンゴのブランデーと、ライム・ジュースとグレナディン・シロップをシェイクしたカクテルです」
「お店によって味が違うんですか?」
「違うと言いますか、こだわろうと思えばどこまでもこだわれるんです。グレナディン・シロップはザクロのシロップなのですが、自家製で生のザクロから作るバーテンダーもいますし、カルバドスもこのカクテルのためにあらかじめ冷やしておくバーテンダーもいます。お店によっては一年に一杯も出ないカクテルなのですが、その時に特別においしいジャック・ローズを出すために準備をしておくわけです」
「なるほど。じゃあそのジャック・ローズをお願いします」
私は、シェイカーに冷やしたビュネルとライム・ジュースを注ぎ、本来のレシピより少し少なめのモナンのグレナディン・シロップを足し、強めにシェイクして、口径の広いカクテルグラスに注いで、彼女の前に出した。
「うわあ、可愛い色ですね。おいしい!」と彼女は言うと、こんな風に話し始めた。
「マスター、今日は主人がいないんで、恋の話をしていいですか?」
「え、恋なんてするんですか」
「私、三年くらい前にひどく恋に落ちたことがあるんです」
「相手はどんな方なんですか?」
「若いんです。当時でまだ二十四歳だったんじゃないかな。大学を出て、バイトしてたビストロでそのまま働くことになって二年って言ってたから」
「飲食の方なんですね」
「ええ。大学では法律を勉強してたのに、料理の世界が面白くて、そっちの道で食べていこうって決めたらしいんです。その彼、料理の才能がすごくあるんです。働いているお店はどっちかというと内装とかワインのコンセプトとかの方が有名なんですけど、彼の料理が独創的ですごく面白いんです。ワインや食材のことで何度か会って、ヨーロッパのいろんな料理の話をしたり、小さいパーティのケイタリングをお願いしているうちに、ひどく好きになってしまったんです」
「気持ちは伝えたんですか?」
「まさか。絶対に伝えないです」
「そうなんですか。恋って『初恋の人と似てます』とか『味の趣味がすごく似てますね』とか、思わせぶりに気持ちを伝える瞬間が一番ドキドキして楽しいと思うのですが」
「いえ。もしそんなことを少しでも匂わせてしまったら何かが一気に始まってしまいそうで、すごく怖いから、絶対にそんな素振りは見せないって決めたんです」
「苦しくないですか?」
「もちろんすごく苦しいです。彼からメールが来たらすごく嬉しくなって急いで返信しようと思うんですけど、そこをぐっと我慢して、一日おいて次の日に用件だけの短いメールを返したりするんです。会わなきゃいけない用事があって、彼と二人っきりでカフェで打ち合わせしたりする時、その場で『あなたには料理の才能がすごくあるから、あんなお店でずっと働いてたら才能がすり減っちゃうと思うの。私が貯金下ろすから二人でフランスに行きましょう。あなたはレストランで修業して。私はワインの勉強するから。それで二人で戻ってきて日本のどこかで小さいレストラン始めない?』って言ったら、彼どうリアクションするだろうって想像すると、もう息が苦しくなっちゃうんです」
「彼の方も気がついてるんじゃないですか?」
「いや、絶対にそんなことはないです。私ももう子供じゃないんで、そういう感情は見せないって決めたらそのくらいは可能です」
「その恋はどうなったんですか?」
「マスター、やっぱり恋ってひどい重症の風邪と同じなんです。風邪をひいている間、恋に落ちている間はずっと苦しいんです。彼のメールを見るだけで、彼と話すだけで苦しくて苦しくて、もう『好き』って言ってしまおうかなって何度も思うんです。でも、やっぱり風邪と同じでずっと耐えているとやがては治っていってしまうものなんですよね」
「その後はどうされたんですか?」
「恋に落ちた以前と同じように、忙しい毎日に戻りましたよ」
「それでいいんですか?」
「はい。マスター、そういう恋の終わり方もあるんです。すべての恋がお互いに気持ちを伝える必要なんてないと思うんです。心の中に鍵をかけて一生懸命しまっておいて、伝えないまま少しずつ消えていく恋もあると思うんです」
「そんなものなのでしょうか」
「まあ正直、まだ病み上がり状態と言いますか、時々彼のSNSなんかを開いたりして、まだちょっとだけ好きだなあなんて思ったりもしますけどね。でももう大丈夫です」
彼女はそう言うと、ジャック・ローズを飲み干した。後ろではいつまでも「好きだ」と伝えられない「僕」がイパネマの娘を眺め続ける歌を歌っていた。
SNSでシェア等していただけると助かります。「もう早速、全部読みたい! 待てない!」という方、本、売ってます。こういう短い恋の話が、あと20個入ってます。GWの読書にいかがでしょうか? キンドルだと今、お安くなってます。プレゼントにも最適です。あの人に贈っちゃいましょう。
#ファーストデートの思い出 というハッシュタグで、あなたのファーストデートのあれこれを募集しています。ファーストデートのことを書いてくれたら、僕、全部読みます。是非。詳しくはこちら↓
サポートしたいと思ってくれた方、『結局、人の悩みは人間関係』を買っていただいた方が嬉しいです。それはもう持ってる、という方、お友達にプレゼントとかいかがでしょうか。
