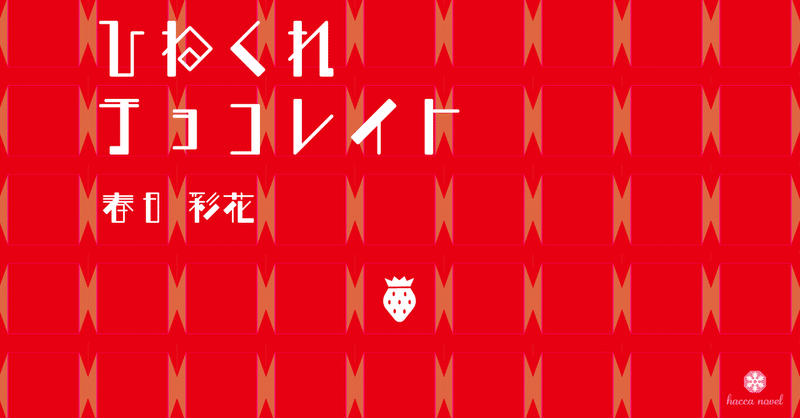
ひねくれチョコレイト3
そんなことが続いて三週間ほど過ぎた水曜の夜、だったと思う。
その日はギャル店員と眼鏡くんがバイトの日で、なんだ、そうか今日は彼のいない日か、なんて気付くとがっかりしている自分がいた。ハッとしてそんな気持ちを振り払い、缶ビールの並ぶ冷蔵庫の前に立つ。
冷蔵庫のドアに手をかけた私の耳に、コツコツとガラスを小さく叩く音が聞こえた。
音のした方を見ると、雑誌の並ぶラックのむこう、通りと駐車スペースに面した広い窓を外から冬真くんがノックしていた。
チョコレートをもらったあの日のように照れたようにはにかみながら、ビールの缶がうっすら透けて見えるビニール袋を掲げている。
驚いて首を傾げた私に、おいでおいでと手招きした。
躊躇う気持ちもあったけれど、私はその時の彼の笑顔を可愛いと思ってしまった。前まではそう思う対象は寝ぐせだけだったのに。
あれ、そういえば今日は寝ぐせがない。ちゃんと真っすぐで、風になびいている。
いそいそと何も買わずに店を出ても、ギャル店員は意外と律儀に「ありがとうございました」と声をかけてくれた。
店の外に出た私に駆け寄った冬真くんがぺこりと頭を下げる。
女の中でも小さいわけでもなく、五センチのヒールを履いている私よりも随分大きい。頭が下がった瞬間に髪がさらりと足元に向かって揺れた。
「すいません、突然。今日もお疲れ様です」
「ちょ、ちょっと……頭上げてよ。おつとめご苦労様ですってシャバに出てお出迎えされてる気分になっちゃうから」
「っぷ。けっこうおもしろいんすね、若村さんって」
「あ、違っ、これは、その。同僚の趣味で」
同僚の木嶋に半ば押し付けられるように見せられたVシネマで慣れ親しんでしまったことであって、私の趣味では断じてない、と吹き出した冬真くんにまくしたてた私の顔はきっと茹蛸のように真っ赤になっているに違いない。
家のテレビラックに並ぶ彼女の持ち込んだVシネマのDVDを明日こそ突き返そうと心に誓う。
まだ笑いを含んだ彼がもう一度、缶ビールを掲げて見せた。
「よかったら、なんですけど。そこの公園で一杯どうすか? 奢らせてください」
ビールを買わずに店を出てきた時点でなんとなく予想はしていたくせに、このまま彼の誘いにのっていいのかどうか、すぐに判断ができない。
こんなに年の離れた彼と誘われるがままについていって、一体どうしようというのか。
それでもこれまでの時間で少しずつでも彼に親しみをもってしまった自分が「いいじゃん、別に。一杯飲むくらい」なんて脳内で囁いてくる。
「やっぱ、ダメっすか」
そう言って落胆を隠すように顔をくしゃっとさせて笑う彼に、心臓の辺りがぎゅっとなった。
なんて顔するのよ。
堪らず、つい「いいよ。一杯だけね」と言ってしまい、「よっしゃ!」とあからさまにガッツポーズをした彼のあとについて、二軒の民家を隔てた公園へと移動した。
この辺りの十戸ほどの分譲地のために作られたブランコと滑り台、ベンチしかない猫の額ほどの公園は周りを囲む住宅よりも随分と狭い。人気もなく、しんと夜の闇の中にぽつんと投げ出されたようにそこにあった。
入り口を入ってすぐのベンチに並んで腰かける。先に座った私の左隣に腰を下ろした冬真くんの距離が思ったよりも近くて、パーソナルスペースの狭い子なんだと無理やり自分を納得させた。
差し出された缶ビールのプルタブを押し上げて、乾杯する。缶と缶の触れ合う鈍い音すら、なんとなく気恥ずかしかった。
ぎこちない会話がしばらく続く。
聞くと、冬真くんは電車で四十分ほどの場所にある大学で社会学を学ぶ三年生だった。年はハタチで、これから就職活動を開始するのだという。
私も彼に問われるがままに横浜で働いているとか、休みの日は友達と旅行したり飲みに行ったり出かけることが多い、なんてことを話した。
十分ほど経ちビールが半分ほどに減った頃、どちらからともなく言葉が途切れ、くすぐったい空気だけを残して沈黙が落ちた。
きっと一分にも満たない短い時間。
きっとあの日から。
彼との間に、ある予感はしているのにその口火をきりたくはないし、不思議なことに逃げ出したくもない。
きったとして、なんて言えばいいのか。どんな顔して、彼の心を覗けばいいのか。
アラサーで、彼より七つも年上で、それなのに大人の余裕なんて、これっぽちもありはしない。それがなんだか私の方が必死みたいで恥ずかしい。柔らかい風が吹き抜け、足元で咲きかけのたんぽぽのつぼみを揺らしていく。
冬真くんが思い切ったように切り出した。
「あの、若村さんは彼氏さんとか、いるんですか?」
明るい声色が、敢えて何気ない風を装っているように感じてしまう。これは自意識過剰? それとも。
「ううん。いないよ。なんとなく友達と過ごす方が楽しくて」
「そうなんすか。良かった」
「よ、良かったって……」
「あ、えーと……」
あぁ、もうこの空気感、堪えられない。どうにかして。
頬が熱いのは絶対ビールのせいだけじゃない。
「えーと、前にも言ったと思うんですけど、俺、ずっと若村さんのこと、気になってて」
「……うん」
「気になってるというか、好き、なんですけど」
冬真くんの顔も赤い。きっと彼もまた酔ってるからっていうだけじゃ、ないと思う。
座ったまま半分、身体を捻って私の顔を覗き込む。
ち、近いってば……!
「好きって、なんで」
「なんでって、一目惚れは理由になりませんか?」
「ひ、一目惚れって……ハタチの大学生がアラサーOLに一目惚れなんて現実味がなさすぎるっていうか……なんかの詐欺? 私、騙されてる? なんか、あなたに恩を売るようなことをしたとか? これ! っていう理由がないと、ちょっと、ねぇ、ありえないっていうか、信じられないっていうか」
「一目惚れなんで、特にそういう理由はないですし、別に詐欺とかじゃないっす! うーん、でも強いて言うなら……」
「強いて言うなら?」
心底困ったというような顔で頭をがしがし掻く彼を、私はじっと見つめる。
こんな時でも彼はかっこいい。やっぱり現実味ないって。大学でモテモテでしょ、きっと。
「強いて言うなら、若村さん、落ち着いてる大人の女性ってかんじがするし、いつも会計のあと、ちゃんとお礼言ってくれるじゃないすか? そういうところ、同年代の子たちにはない魅力かなぁ、なんて。疲れてる姿も色っぽいというか」
「はぁ?」
「あ、すみません。やべ、しくじったかな」
「な、なによそれ……」
冬真くんが缶をぐっとあおる。街灯に照らされた細い首にくっきりと浮かぶ喉仏が上下に動くのが見えた。
私も緊張を紛らわすように彼に倣う。すっかりぬるくなったビールは、いつもより美味しくない。
「あのね、私、あなたが思っているより全然大人なんかじゃないの。仕事と遊びを熱心にやってたら、いつの間にかこの年になってただけで、中身なんて大学を出たての頃と大して変わっていないと思う。疲れてるのも、ただのくたびれたおばさんじゃない。なんか勝手に美化してくれてるかもしれないけど、そんな良いもんじゃないの」
「でも、俺……」
「私もさすがに次に付き合う人とは結婚したいと思ってる。アラサー女に手を出して遊びのつもりでした、では済まないのよ」
「こ、怖いっすね」
この会話の流れで、それ言う?
彼は苦笑いしながら、また頭を掻いた。
「だけど俺はもっと若村さんのこと、知りたいっす」
そう言うと冬真くんは急に真面目な顔になって、私の心を掴もうとするように、じっと私の目を覗き込む。
「若村さんの下の名前も、連絡先も、何が好きで何が嫌いか、どんな子供だったのか、どんな場所に旅行したことがあるのか、どんな店によく行くのか、どんな男が好きなのか」
ふっくらとした涙袋の上の、色素の薄い瞳から目が逸らせない。
彼の空気に飲まれて、惹きつけられて、逃げられなくなる。
「先のことは正直、分からないです。もしどうしても早く結婚したいと思ったり、そういう相手ができたら、そっちに行ってくれても構いません」
「そ、そんなの無責任じゃ……」
「ですね、そう思います、我ながら。でもそれまででもいいから、一緒にいてほしいんです」
「そんなの……」
「若村さん、好きです」
ふわっと制汗剤みたいな、爽やかな香りが濃くなって、唇に熱いものが触れる。
柔らかくはまれて、背中に冬真くんの腕の力強さを感じた。
本当に無責任で、先の見えない告白。
結婚を意識せねばならない年の女に、なかなか酷な提案だ。
フリーの状態じゃなきゃ、結婚相手なんて探しようがないし、新しい男だって作れない。
ずるい。そんな、未来のない関係でいいだなんて、ずるい。
だけど。
気持ちいい。
心臓は壊れそうなほど激しく鳴っているし、いやっていうほど冬真くんにときめいている。柔らかい唇も、細いくせに男らしい腕も、あの目も、このために寝ぐせを直してきたのだろういじらしさも。
あぁ、こんなこと聞いたら、お母さんぶっ倒れるだろうな。家族には秘密にしなきゃ。
もし遊ばれているんだとしても、もういいや。
未来はどうなるか分からないけれど、このまま冬真くんに飲まれたい。可愛い彼と戯れたい。
そう思ってしまうと、もう止まることはできなかった。
なかなか自分でも勇気があるというか、ただの馬鹿というか、本能のままに生きているというか……。
いつの間にか私の方から深く口づけていた唇を離すと、ぷはっと息を継いだ。
「うち、来る?」
「え」
「来なさい。冬真くんが悪いんだからね」
「わ、若村さん、目が座ってる」
「うるさい。……優美」
「え?」
「優美。私の、下の名前」
間近で見開かれた冬真くんの目が、すぐに優しく笑って、鼻が触れそうな距離に迫る。
「優美、さん」
「優美でいい」
「じゃぁ、優美」
「あ、でも年下くんに好かれてるっぽくて、さん付けも悪くないかも」
「難しいっすね」
私たちのクスクス笑う声が夜の公園に浮かんで溶ける。またやんわりと温い春の夜風が私たちを撫でていった。
その夜、初めて、私はコンビニで食べ物ではなく人間の男の子をテイクアウトした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

