
父と母と家と
母のこと
私の母は昭和の初め5歳の時に、結核で実母を亡くしている。
保育所もなく、電子レンジ・洗濯機・掃除機、コンビニや冷凍食品もなかった時代。
残された2歳の弟と5歳の母を、仕事が忙しい父親ひとりで育てることは困難であった。
親戚の家を転々とし、実母が生きていたなら経験しなかったであろう辛い目にもあったという。
2年ほど経ち後妻さんをもらうことで、母と弟は実父と再び暮らせることとなる。
実父を大切に思う気持ちは、頼れる者がひとりしかいなかったことへの見捨てられ不安があったのかもしれない。
母と弟は2人目の母との折り合いが悪く、まもなくして腹違いの妹が生まれたこともあり疎外感を強くしていったようである。
弟は男の子だからと大学まで進学、腹違いの妹も大学に進学したが、母だけは尋常小学校を卒業し15歳で家から通えるところに就職している。
母は亡くなるまで「わたしも大学に進学したかった」と愚痴をこぼしていた。
また、ピアノにも強いあこがれがあり「ピアノを習いたかった」とも話している。
この時代、女性は19~20歳くらいで結婚することが多かったが何度か見合いをしても断り、母が家を出て結婚することはなかった。
いつまでも実父のそばにいたかったのだろう。
27歳になっても結婚しない娘を心配し、なかば強制的に何度目かの見合いで「この人と結婚しなさい。」という実父の命令でしぶしぶ家を出て結婚している。
結婚し3人の子どもを産み育てながら、脳卒中で寝たきりの姑の自宅介護を4年間同時進行で行った。
年金制度や老人ホームなどがなく、親の老後は長男、主に長男の嫁が同居しみることが当たり前の時代であった。
結婚した当初はかなり貧しく、家庭菜園で野菜を育て、味噌を手作りし、家族全員の洋服から布団・子どもたちの玩具まで全て手作りをしていた器用な母であった。
紙オムツもなかった時代。
小さな布おしめは可愛いが、大きな布おしめを替え手洗いするのは地獄の日々だったと何度も話している。
子どもたちの夜泣きと同時に、寝たきりの姑が夜になると元気が良くなり大声で呼ばれることも辛かったようだ。
自分が歳をとり介護が必要になったとき、子ども達にだけは同じ苦労をさせたくないと語っていた。
その言葉どおり20年前、母は子どもたちの介護を必要とすることなく病院にて末期癌で亡くなった。
幼くして実母の愛情を受けずに育ったからか、自分の子どもたちに不器用な接し方しかできない人であった。
「勉強ができる環境にあることは幸せだ。」
「勉強はできるうちにしておいた方がいい。」
小学生の時から夕食後は親がつきそい、歯みがきの習慣をつけるように家庭学習の習慣を身につけた。
私たちにはピアノを5歳頃から習わせ、自分がやりたくてもできなかったことを子どもを通して実現していた人だった。
勉強を頑張り大学に行くこと。
これからは、女性も働きながら結婚し子どもを産み育てる時代になること。
共働きでの子育ては大変なため、祖母となる自分が家事・育児を助けること。
人生のレールを敷かれその上を走らされていたが、なぜか反抗できなかった。
すべて母の望み通りの人生を歩んできたわけではなかったが、恨みつらみの気持ちは不思議にない。
毎朝、毎晩、新聞を端から端まで読む習慣がある人で、言葉や知識は大学を出た私たちより豊富であった。
病院のベッドでは、芥川龍之介の『蜘蛛の糸』を好んで何度も読んでいた。
最期まで孫たちをかわいがり、孫たちの中に自分の幼くして亡くなった母親の面影をさがしているような人だった。
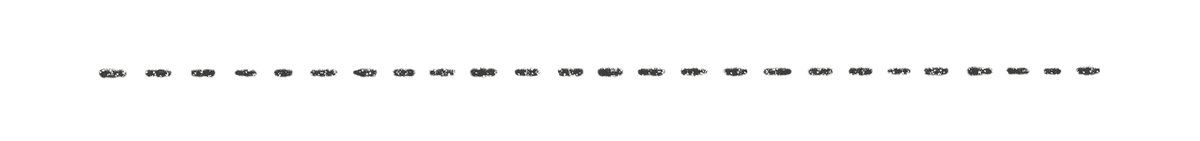
父のこと
わたしの父も貧しい家に生まれ育った人で、尋常小学校を出た後、上の学校に進みたかったがお金がなく断念。
16歳で就職し両親を養っている。
ほぼ自給自足の生活をしていたようで、畑で野菜やイモ類を育てた。
借家の敷地内では鶏を数羽飼い卵を産ませ、卵を産まなくなった鶏は処分し肉として食べたという。
自分の父親からよくお金を無心されたことがとても嫌で、自分の子どもからお金をたかる親にだけはなりたくないと話していた。
その言葉通り若い頃から身の丈にあった生活をし、無駄遣いをせずお金の管理をしっかり行い、コツコツと節約や貯蓄に励んだ人だった。
生涯を通してお金の計画性は見事であり、金銭面で子どもたちを頼ることは一切なかった。
父と母は転勤のたびにボロボロな借家を転々としてきたこともあり、自分たちの力でマイホームを建てることが夢であった。
その夢が叶い、大きくはないが新築の家を建て、大切に手入れをしながら綺麗に住んでいた。
自分にも他人にも厳しく、存在そのものが恐い昭和の親代表のような人だった。
自宅の和室に呼び出される時は決まって勉強をさぼりお説教される時で、子どもながらにとても怖かったことを覚えている。
「お父さんは外で働きお金を稼ぎ家族を養っている。お母さんは家の仕事をし子育てをしている。お前たちの仕事は何か。勉強することではないのか。」
父の話すことは筋が通っており、逆らうことはできない威圧的な雰囲気があった。
家電好きで、大きな家電店に立ち寄ることを好んだ。
特にカメラ、ワープロやパソコン、携帯電話に興味を示し、若い頃は自分で暗室をつくり写真の現像までこなしていた。
会社を定年退職してからは、母と二人で旅行に行くことが多かった。
国内の人気スポットはほとんど行ったのではないかというくらい、あちこち旅を楽しんでいた。
思いがけず突然、母が先に病気で亡くなりひとり暮らしとなり、寂しくなったようでよく「自分のこれからのことを相談したい。」と子どもたちが呼ばれた。
あの厳格な父が「寂しい、寂しい」と弱音を吐き、「会いに来てほしい。孫たちの顔も見たい。」というメールも頻繁にきていた。
仕事と家事、育児で忙しい私たちだったが、待ち合わせをしてしばしば通った。
「家を出て大きな街のマンションに住んだ方が、買い出しも病院に行くのも便利だよ」と助言すると、いつも激怒された。
「この家は自分が苦労して建てた家だ。お前たちが育った家だ。この家を出ろというのか。そんなことはできない。」
では父のこれからをどうしたらいいのか分からず、いつも喧嘩別れになることもあり実家から足が遠のいてしまった。
次に父に会ったのは、末期癌で病院に入院したと電話が入った時だった。
そこからは坂道を転げおちるように早かった。
母が亡くなる前に「お父さんの世話をしてあげてほしい。みんな仲良くしてほしい。」と頼まれていたのに、出来なかった。
今思い出しても、年老いてひとりになった父に冷たい仕打ちをしてしまったと後悔している。
父が幼かった頃、お正月でつくお餅だけがご馳走で楽しみにしていたらしく、年を取っても大福餅を好んで食べる人だった。
にぎやかな人が集まる場所を好んだ。
よく自宅に会社の部下を呼んでは母が作った料理をふるまい、共にお酒を飲み、家庭用カラオケを購入し夜遅くまで歌い笑う人だった。
ラジオを好みベッドの枕元にはいつもラジオを置き、イヤホンで声を聴きながら眠る人だった。
