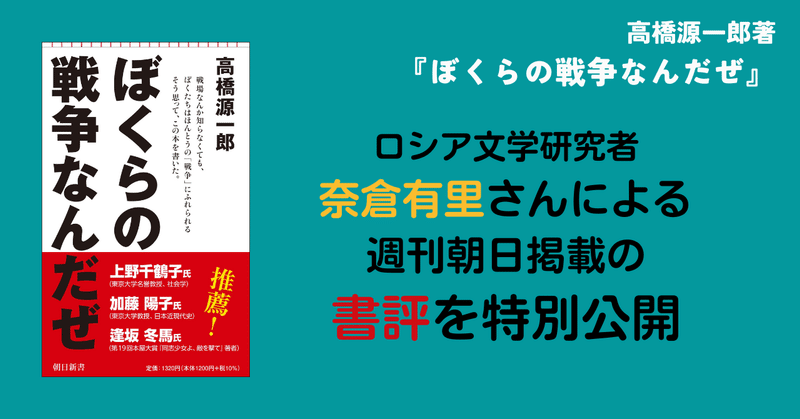
高橋源一郎著『ぼくらの戦争なんだぜ』週刊朝日掲載の奈倉有里さんによる書評「『怖い』の正体を直視する」を特別公開!
高橋源一郎さんの『ぼくらの戦争なんだぜ』(朝日新書)が刊行されました。かつてなく「戦争」が身近に迫るこの時代に、遠い国の「彼らの戦争」ではなく、「ぼくらの戦争」にふれるために。人びとを戦争に駆り立てることばの正体とは。もし戦場に行ったとして、正気にとどまるには。週刊朝日 2022年9月9日号に掲載された、ロシア文学研究者・奈倉有里さんによる書評を特別に公開する。

私たちは人生のなかで、戦争のことをどのくらい考えてきただろう。子供のころ「昔、大きな戦争があった」と知る。学校の歴史の授業では人類が繰り返してきたたくさんの戦争を知り、ニュースではいつも世界のどこかで起きている戦争を知る。でも戦争についてほんとうに考えるのは決して易しくはない。自分が殺したり殺されたりする可能性が目の前にあるくらいの「近さ」で戦争を考えると、身がすくむような恐ろしさがある。この「怖い」の正体はなんだろう。
この本は丁寧な本だ。私たちが「遠い」とか「近い」と感じるのはどういうことかを立ち止まって掘り下げる。日本の戦前戦中戦後の教科書、ドイツやフランスの歴史教科書を読み、歴史の語られかたを考える。読者と一緒に戦争の詩を一篇ずつ、本を一冊ずつ読み込み、読者が考えるための余白をいろんなところに少しずつ残しながら「考えるって、そういうことかもしれないよね」と語りかけてくれる。有名な本や読んだことのある作品にも、一般的な内容紹介とは違った文脈がみえてくる。
知らないことがたくさんある。戦前の日本で地理や算数や音楽の教科書までもが国の栄誉と戦争の賛美を語り教えようとしていたことを、当時の教室を覗き見るような臨場感で見せてくれる。戦時中にひっそりと書かれた詩集の内容を知り「佛さまのやうな」顔をした中国人兵士の詩に泣いてしまう。読みながら旅をする。戦時中の日本や中国を、フィリピンを、赤道の下のジャングルを。そして「遠い」知らないはずの人たちの内面を流れる詩のことばのなかを。
知っているはずのこともある。独裁者は「大きなことば」を使うのが好きだ。この本の最後でウクライナ侵攻がはじまる。ロシア政府はこの十数年、途方もなく「大きなことば」を繰り返し、「威勢のよさ」がことばの定義を凌駕して、人々が対話のすべを剥奪されていくのを私は見てきた。どうしてそんなことになったのだろう。
第2次世界大戦について知る人はどんどん減る。戦争についてのドキュメンタリー番組が減り、戦争の痛みを想起するものが減る。
数年前の夏に私が広島県の似島(にのしま)を訪れたときにはまだ語り部の人に話をきくことができた。「ああ、自分はなにも知らない」と思い知らされ、見知ったもののなかにある戦争の記憶に気づかされた。
「ぼくらの」というこの本の題名は、私たちが戦争を自らの「内」に見出すことの難しさと大切さを、繰り返し訴えかけてくる。理解できない「他者」の企てた戦争を批判するのは簡単だし、そうするうちは「自分(たち)は決してそんな愚かなことはしない」という前提に立っていられることになる。
けれども戦争のことばはいつも、人間が「近く」に感じている、愛しいもの、大切なもの、失いたくないものを味方につけようとする。やっぱり怖い。でも戦争とそこに向かうことばとの細やかなつながりが見えてくると、「怖い」の正体が少しずつわかる。
戦争のことばのなかには「なんかあやしい」ものがたくさんある。でも大きな不安が社会にあると、人はなるべく簡単で手っ取り早く安心できることばが欲しくなる。「なんかあやしい」にも気づきにくくなる。そうしてほんとうに戦争が起きると、想像していたよりもずっとたくさんの人が憎悪や攻撃性や排他性にのまれ、そこにはなぜだか、「愛」とか「守る」とかいういかにも大切そうなことばと「無理もない」「当然だ」というあきらめのことばがつきまとい、それらが「大きなことば」に飲み込まれていく。だからこの本と一緒に考えたいのだ。「怖い」ものを直視することで見えてくる、私たちの内部にある戦争の火種を。
