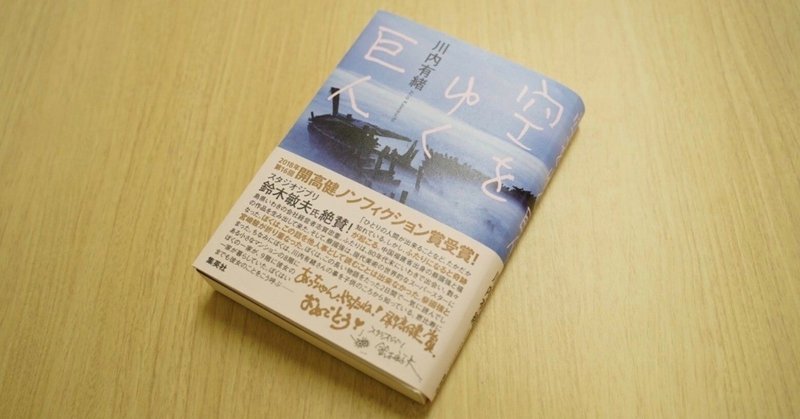
全文公開『空をゆく巨人』 第三章 空を飛んで、山小屋で暮らす
第16回 開高健ノンフィクション賞受賞作『空をゆく巨人』(集英社)をnoteで全文公開中。今回は第三章です。
第三章 空を飛んで、山小屋で暮らす(サンフランシスコ・一九七六年)
アメリカの空を飛びたい
「おーい、忠平!」
アパートの玄関で満面の笑みを浮かべる友人・志賀の姿を見つけた藤田忠平は、嬉しさで胸がいっぱいになった。「よく来たなあ!」
藤田は、横浜の大学を卒業したあと、一度は外国で生活をしてみたいとサンフランシスコにやってきていた。
「カルチャーショックという言葉は、ああ、こういうことかあって思ったよね。町には、穴が空いたズボンをはいていたり、裸足の奴がいたり、頭に羽をさしたりして歩いてる人間がいるんだもの」(藤田)
一九七六年当時のサンフランシスコといえば、カウンターカルチャーの発信地で、飛び抜けてヒップな場所だった。
「グレイトフル・デッドのコンサートも見たよね。ちょうど、『ジャニス』というドキュメンタリー映画が大流行してた」
ジャニスとは、二七歳で夭折(ようせつ)した天才歌姫のジャニス・ジョプリンのことだ。
そんな開放的な時代の空気のなかで、藤田は、皿洗いのバイトをしながら、カレッジに通った。アメリカ人のガールフレンドもでき、一緒に彼女の故郷のオレゴンまで旅行に出かけた。
藤田に久しぶりに会った志賀は、あれっと驚いた。
「忠平は、人間が変わったなあ、田舎もんがアメリカ風になったなあ、みたいな! かなり人生を謳歌(おうか)してたよね」
志賀も、朝から晩まで町を歩きまわり、その自由な空気を胸いっぱいに吸い込んだ。休みの日には、みんなで藤田の車に乗り込み、どこまでも続く一本道を走った。
「初めてマクドナルドのマックシェイクを食べて、こんなにうまいものあるのかあ、ってびっくりしたよね。街なかには、平日でも遊んでいる奴がいっぱいいたな。公園でコンサートしてたり。気楽なかっこうをしてやりたいことをやっている人が多かった。世のなかの決まりごとみたいなのが何にもねえ、みたいに感じたよね」(志賀)
アメリカに来た志賀には、ひとつの野望があった。それは、長年憧れていた「空を飛ぶ」ことだ。以前、漫画雑誌の裏表紙に、なぜか竹でできたハンググライダーの写真が掲載されていて、そこに、アメリカにはハンググライダーの学校もあると書かれていた。
アメリカでならば、自分も空を飛べるかもしれない——。
そんな話を聞いた藤田は、志賀をサンフランシスコ郊外にあるハンググライダー・スクールに連れていった。近くまで行くと、海岸線を悠々と飛ぶハンググライダーが見えてきた。
「えー! 本当に飛ぶんだーって、びっくりしたよねー」
志賀は、アメリカ人の若者に囲まれて講習を受けた。
英語もわからないのに、講習をちゃんと理解できたのだろうか。
「そりゃあ自分の命がかかってるから、言葉わかんなくても、やるべきことはわかるよなあ!」
ひと通りのレクチャーが終わると、「最初にトライしたい人は?」と講師が聞いた。
「イエス!」と志賀はためらうことなく手をあげた。
海岸に出て、五メートルほど高くなった場所で助走をつけ、地面を蹴った。すぐにふわーっと体が宙に持ち上がる。
「気持ちよかったよねー、うわあ、飛べたー! って」
初フライトは、ほんの一五メートルほどだったが、これが、志賀の「空飛び人生」の始まりとなった。
アメリカの青い空。マックシェイク。地平線の先へのドライブ。すべてが最高だった。
旅の終わりに、志賀はハンググライダーを買って帰った。帰国後は、ろくに仕事もせずに空に夢中になった。傾斜のあるところを見かけると、どこででも飛んでみたくなった。農家の実家暮らしなので、収入がなくても食べるものには困らない。
ハンググライダーを初めて見た近隣の人々は、「飛んでいるところが見たい」と口々に言いだした。
「ええどー! じゃあ、見せてやっから」
志賀は答え、小高い丘がある土の採取場に向かった。
実際に丘の上に立ってみると、そこは狭くて助走がつけにくいうえに、まるで風も吹いていなかった。条件は悪かったが、もはやあとにはひけない雰囲気だ。覚悟を決め、ハンググライダーを装着。そして深呼吸し、できるだけ助走をつけ、崖からジャンプ。
すると……ふわりと浮いたかと思ったものの……ドサッ!
見ている人には、おもちゃの飛行機が墜落したように見えた。
「あーあ」
落胆と心配が混じった表情で、人々は志賀のもとに駆け寄った。幸いハンググライダーは壊れていなかったが、激痛で息もまともにできない。そのとき志賀は大きな教訓を得たという。
人の期待に左右された決断はダメだ。条件が悪ければ、すぐに撤退しよう。
お金を使わない優雅な生活
「わがんねーな」
志賀は自分が描いたスケッチの前で首をひねった。今度は父が所有する山林のなかに自力で小屋を建てて暮らそうと思いついたのだ。ハンググライダー三昧で、仕事をしないで過ごすうちに、お金がなくても生活できるのかを試してみたくなった。
建築学科を卒業していたものの、在学中はほとんど勉強してこなかったので、設計や建築の手順がまったくわからない。そこで、大工になった先輩に聞きにいこう、と思いついた。
このあたりが、志賀の生来の実行力だろう。本当にできるだろうかとか、無理かもしれないなどとは考えない。やると決めたら、ただ行動に移す。知識が不足していれば、誰かに聞くことも厭(いと)わない。
こうして、近所に住む大工の先輩から、家づくりのいろはを習った。教えられた通りに杭を打ち込み、基礎をつくり、水平をとって土台を載せた。柱を立て、ハリを渡し……と、試行錯誤でやってみると、だんだんと家らしくなってくる。
ちょうどそのころ、成人学校以来の友人の品川も、会社を辞め、志賀の実家にころがり込んできた。志賀の母は、家族のように品川を迎え入れ、毎日みんなで食卓を囲んだ。あまりに居心地がよかったのだろう、この居候生活はそのあと二年間にも及ぶ。
暇を持て余していた品川も小屋づくりに手を貸してくれ、ふたりでコツコツと作業を続けた。そうしてできあがったのは、小さな山小屋だ。煮炊きや暖房は薪で、水は古い山の井戸からパイプでひいてきた。トータルの建設コストは一五万円ほどで、一番高かったのは洋式便器の二万円。
「山のなかでも快適に用を足したいと贅沢してしまった」
というわけで、品川を実家に残したまま、志賀はさっさと山小屋に引っ越した。
窓の外には美しい木立があり、その風景を見ているだけで幸せだった。車のバッテリーを使って音楽を聴く装置も自作した。
「聴いていた曲は、イーグルスの『ホテル・カリフォルニア』とか、ビートルズの『ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード』。とにかく、お金を使わずに楽しむ方法を徹底して考えてたよね。会社で働かなくてすむし、そうすれば自分の思い通りに時間が使えると思って」
アメリカから戻った藤田も、よく山小屋に遊びに来た。藤田もまた、やりたいことを見つけられないままだった。渡米する前は、いずれは英語を使って就職しようと考えていたが、いまや「そういうのはどうでもよくなった」。結果、トビ職の見習いをしながら、夜は英語を教えて生計を立てていた。
ある日、藤田と志賀は「薪のサウナをつくろう!」と盛り上がった。つくり方はまったくの自己流だったが、ちゃんと暖かくなった。サウナで汗を流したあとは、水風呂に飛び込んだ。
志賀は、満たされていた。
お金がなくとも、人は生きられる——。
当時の志賀、品川、藤田の三人は、山小屋でどんな話をしていたのだろう。
「会話はなかったよねー。品川くんは全然しゃべんない。藤田くんも全然しゃべんないし」
志賀がそう私に言うと、それを聞いた品川も相槌を打った。
「んだ、俺ら、別にそんな仲良ぐねえし、別に一緒にいてもしゃべんねえどー。しゃべることも、特にねーもんなあ! ハハハ」
そう言いながら、いまでもふたりは毎日一緒にお茶を飲む。
「話さなくても一緒にいるんだから、さすが親友ですね!」
と私が言うと、「親友? そんなんじゃねえ!」と品川に一蹴された。
それにしても、時代は高度成長期を経て、消費社会に向かって爆走する七〇年代である。七四年には、セブン-イレブン一号店が東京でオープン、翌年には福島県の郡山にも同店が出現した。二四時間消えない光に人々が熱狂するなか、こんなヒッピーもどきな暮らしは珍しかったはずだ。近隣の住民は、志賀をどう見ていたのだろう。
「さあ? 俺は、他の人がどうとか、ぜんぜん気にしたことねえから、わがんねえ」
そのあとも、鶏を飼い、原木なめこを栽培し、とお金を使わない生活を加速させた。番犬としてシェパードを飼い、夏はその犬と海水浴に行き、冬は雪を見にいった。
すると、近くでガソリンスタンドの開業準備を進める兄の武親から「そんなに時間があるなら、ガソリンスタンドを手伝ってくれないか」と声をかけられた。当時は、七〇年代初頭から始まった空前のマイカーブームである。
それもいいか、しばらく手伝うよ、と気軽に返事をした。そこに、居候生活を続けていた品川も加わることに。志賀は、シェパードと一緒に山小屋から歩いて出勤。品川は、志賀の母がつくった弁当を持って出勤。
「お弁当は、当たり前みたいに朝、『はい』って志賀のお母さんに渡されたっぺ」
兄のガソリンスタンドは、当時としては珍しい深夜営業と無料の手洗い洗車サービスを売りにしていた。冬場の洗車は、水の冷たさで手の感覚がなくなり、「あれは本当にきつがったなー」「んだ! きつがったなあ」と志賀と品川は思い出す。
マイカー神話の向こう側
無料の手洗い洗車は大人気で、ガソリンスタンドは常に大忙しだった。しかし、最初は「ありがとう!」と感謝されたこのサービスも、だんだんと当たり前になってしまい、あまり感謝もされなくなった。
すると、生来の商売人魂がむくむくと蘇ってきたのか、この無料洗車サービスをベースに、新たな商売を展開できないかと考えるようになった。そして思いついたのは、世のなかに出回りはじめたばかりのアンプつき高級カーステレオの販売だった。町のカーショップに偵察に行くと、新製品のカーステレオがずらっと並んでいる。「これは、きっと売れる」という感触を持ったものの、ガソリンスタンドでも売れるかどうかは疑問だった。
そこで役に立つのが、無料の洗車サービスである。手順は、シンプル。洗車を待つ客に「ぜひ店内でゆっくりお休みください」と声をかける。客が店に入ると、無料のコーヒーが準備され、音楽が流れている。コーヒーを飲み、周囲を見回すと、カーステレオの箱が燦然(さんぜん)と積み上がっているではないか。
「あれは何ですか」と聞かれれば、しめたもの。
「ああ、こちらはですね……」
これが志賀の戦略だった。
カーステレオは面白いように売れた。同じ要領で、高額のホイールやタイヤも売れた。こうして兄のガソリンスタンドは、市内でも有数の高額商品が売れるガソリンスタンドに成長していく。
その間にも、日本のエネルギー源は、石油のみならず、原子力へと全速力で疾走していた。いわきの北の双葉郡では、すでに一九七一年の三月から東京電力福島第一原発一号機の営業運転が始まり、二号機、三号機と運転開始が続いていた。
志賀はこのころすでに放射線測定器を持っていたと聞いて、私は「えっ、すごいですね」とうなった。それは、ある友人の言葉がきっかけだったという。
「川内(かわうち)村(福島県双葉郡)の山中で自給自足生活をしている友だちがいたんだけど、その人がある日、『原発ってのは、えらい危険なものらしいぞ。でも、何か大変なことがあっても東電や政府は情報を隠すだろうから、放射線測定器を持っていないと逃げ遅れるぞ』と忠告してくれたんだ」
忠告を真正面に受けとめた志賀は、すぐに放射線測定器を購入。
「東芝製で一台八万円くらい。高いなあと思ったけど二台買って、山小屋とガソリンスタンドにセットして、時々数値をチェックしてた」
ということは、やはり原発に反対していたのだろうか。
「いんや、原発はよろしくねえぞ、危ないものだぞ、っていうのは、わがってたけど、反対まではしなかったよねえ」
それは、いわき市民としてはごく一般的な反応だったという。もちろん一部の近隣住民は反対運動を展開していたが、多くの人は、原子力は得体が知れないと感じながらも、声高には反対しなかった。きっと、時代の空気感も影響したのだろう。〝成長〟や〝好景気〟に向かって競走馬のごとく突き進む島国は、何が何でも新しいエネルギー源が必要だという雰囲気に支配されていた。
志賀と同じくいわき市平(たいら)に住む六〇代の夫妻は、当時の原発に対するいわきの空気感をこう説明した。
「あのころ、いわきはさあ、〝北〟(双葉郡)は見てなかった。“南”(東京)しか見てなかったよね。〝北〟に原発ができても、自分たちには関係ないというかんじだよね」
そうですか、なるほどと私は頷いた。工業化に向けて努力してきたいわきの視線の先にあったのは、あくまで東京。
「あのときは『明るい未来のエネルギー』の安全神話を信じたよね」と語るのは妻のほうだ。
目の前に差し出された「安全神話」に対し、盲信派から懐疑派まで「信じる」気持ちの濃淡は人それぞれだったことだろう。多くの人は、その濃淡のどこかに属しながら、忙しい日常のなかで少しずつ原発を受け入れた。ただ、志賀は、いざというときのためにと放射線測定器を買った。これは、あとでちゃんと役に立つことになる。
ほんの一時期のつもりだったガソリンスタンド勤務はもう七年にも及んでいた。たまに「このまま一生こうやって働くのかなあ」という漠然とした不安が頭をもたげた。
その間に起こった大きな変化といえば、あれほど好きだった山小屋生活をやめたことである。理由は、結婚。相手は、お嬢様育ちで七歳年下のゆう子だった。
茨城県高萩(たかはぎ)市出身のゆう子は、いわゆる「おかたい家」に育ったそうだ。
「小さいころからピアノを習っていて、いつも母親のお手製のワンピースを着せられてたの。高校生になっても門限が厳しくって。本当は大学では美術をやりたかったんだけど、美大に行った友だちはみんな、何ていうの、ラッパズボン? みたいな格好して帰省するようになったのを見て、絶対にダメって言われて。しょうがなくピアノを続けて音大に入ったのよね」
それでも、ゆう子はきっとたくさんの愛情を受けて育ったのだろう。六〇代になったいまでも、春風のようにおおらかな雰囲気を纏(まと)っている。
ふたりの出会いは、山小屋だった。好奇心旺盛なゆう子は、「山小屋に住んでいる面白い男がいる」と友人から聞いて、茨城県からわざわざ遊びに来た。パーマをかけた髪をセットし、お化粧をして、青いワンピースを身につけていた。パンプスで苦労して山道を登ると、無骨な小屋から顔を出したのは、髭をぼうぼうと生やしたクマのような男だった。男は、ゆう子の顔をまじまじと見た。
「何でわざわざ金かけて髪縮らせてんだぁ? 何でわざわざ肌になんか塗ったくってんだぁ?」
何て失礼な!
ゆう子はショックを受けたが、嫌な感じはしなかった。むしろ、周囲にはいないタイプで、その自由な雰囲気に惹かれた。
一方の志賀は、どうだったのだろう。
「どこに惹かれたのかって? うーん、とにかく、正反対だったよねえ。何も知らないっていうか。そういう違うところが、よかったのかなあ」
確かに、ゆう子は、ピアノの腕はプロ級だった半面、米の研(と)ぎ方ひとつ知らなかった。
とにかく、正反対のふたりは、ほどなくして結婚を決意する。問題は、ゆう子の厳格な両親を説得できるかどうかにあった。
「ある日、父親にこんな人と結婚を考えてますって説明したら、父はショックで吐血したの!あははー!」
いよいよ、ゆう子の両親へ挨拶をする日、「頼むから、こざっぱりしてきてね」と念を押した。するとどうだろう。志賀は髭をすっぱりと剃り落としてやってきた。
「別人みたいでびっくりしちゃった!」
色々とありながらも無事に挨拶が終わり、ふたりの結婚は何とか許された。
新婚旅行は、行き当たりばったりのドライブだった。
「どこに行ったかしら? 確か鎌倉や千葉に行ったわね。そのとき、志賀さんの格好があまりにもむさ苦しかったので、親子に間違えられたこともあったの」
空に太陽がある限り
こうして所帯を持った志賀は、実家の土地の一角に新居を構えた。大工の棟梁(とうりょう)と一緒に自作したものだ。
「まさか自宅まで自分で建てるなんてびっくりした!」(ゆう子)
引っ越しのとき、志賀はシェパード、そしてヤギまで山から連れてきて、庭先ではミツバチを飼った。一方のゆう子は、新居にグランドピアノを運び込み、自宅でピアノ教室を開いた。教室で稼いだお金は生活費の足しにした。志賀は、ハンググライダーや自作のキャンピングカーづくりなど趣味も多いので暮らしには余裕がなかった。ゆう子は新聞の集金に居留守を使うこともしょっちゅう。いつも同じ服を着ているゆう子を見て、「新しい服も買えないのかい」と母親がそっと一万円札を握らせてくれたこともあった。
そんな志賀家に、長女の織恵(おりえ)が誕生する。志賀は子煩悩な父親になり、織恵が大きくなると、キャンプや磯遊びに連れていった。
そして、長男の忠広が生まれるころ、志賀に大きな転機が訪れた。
たまたま読んでいた雑誌に太陽熱温水器(通称「ソーラー」)という商品を紹介する記事を見つけたのだ。それは、屋根の上に設置したパネルで水を温め、水道から出す仕組みで、作動に電力も要さないエコな商品だった。
ええ? 電気もガスも使わずにお湯が沸かせるって?
食い入るように記事を読んだ。
それまでの山小屋生活では、湯を沸かすのは大変な作業だった。それなのに、太陽熱温水器をセットすれば、何もせずに蛇口から湯が出るというのだ。
欲しい! しかし、値段は約三五万円(当時)と高額である。貯金もない志賀には、まったく手が出なかった。
そこで、ガソリンスタンドの社長である兄に「お湯が出たら冬の洗車が楽になる」とかけあい、一台設置してもらった。
晴れた空を見上げながら、本当に湯が出てくるのかなあと半信半疑だった。夕方になり蛇口をひねると、本当に熱湯がどんどん出てきた。
これは、すごいぞ!
志賀は、この商品をガソリンスタンドで売ってみたいと思い、試しに何台か仕入れてみた。さっそく周囲の人に勧めると、ふたりの知り合いが購入を決めた。何と一日で七〇万円分の商品を売り上げてしまったのだ。
そこで翌日、兄に話した。
「夜の当番から外れて、本格的にソーラーの営業をしてみたい」
限りある石油資源を販売するよりも、エネルギー資源を節約できる太陽熱温水器を世に広めることにやりがいを感じていた。兄も同意し、ガソリンスタンドにソーラー部門を設立、本格的に販売を開始した。
三三歳にして、ようやくやりたいことが見つかった。
こうしてソーラーの営業活動を開始すると、一ヶ月で二四台もの契約を取ることができた。その総売上は八四〇万円。こうなると、がぜん仕事が面白くなった。志賀は、自分が売ってもこれだけ売れるのだから、他の人でも売ることができるだろうと考え、友人や知人に「一緒に営業をやってみないか」と声をかけた。
ガソリンスタンドは、増築サンルームの訪問販売を行う営業マンたちがよく利用していた。そのひとりである斎藤という男に声をかけると、「〝横尾さん〟がやるなら、やる」と答えた。「横尾さんは、営業の世界の神様のような人。彼が加われば、他にもたくさんの営業マンが加わってくれると思いますよ」
横尾さんって、あの人か……。志賀には複雑な感情が湧き上がった。横尾道夫は、ガソリンスタンドの常連客のひとりだった。
「横尾さんはいつも革ジャンを着て、キザでかっこつけてたよね。鏡ばっかり見てて、どちらかというと嫌いなタイプだった」とその第一印象は散々なものだ。
しかし、「営業の神様」と聞くと、逆に興味をそそられた。そこで、ガソリンスタンドに現れた横尾に、「一緒に太陽熱温水器を売ってみませんか」と声をかけた。商品の素晴らしさを熱弁しても、横尾はクールな態度を崩さない。
「その話は斎藤くんから聞いた。考えてみる」と言うだけだ。
そこで「ちゃんと話したいです。家に伺っていいですか」と食い下がると、横尾は無表情に「いいよ」と答えた。
志賀は、手土産にウイスキーを買い、横尾のアパートを訪ねた。完全なる下戸(げこ)の志賀にはウイスキーの良し悪しがわからず、とにかく高い物を選んだ。
畳の部屋にあがり込み、ふと壁を見て、ぎょっとした。大きな文字が書かれた紙が額装してあり、そこには「苦越」とあった。
苦しみを越える……。どういう意味なんだろう?
その大書を横目に見ながら、再び「営業をやってみませんか」と切り出した。すると横尾は「やるのはいいけど、いくら〝バンス〟してくれますか」と聞き返す。
バンスって? その言葉を知らない志賀はきょとんとした。すると、バンス(アドバンスの略)とは、営業の世界の俗語で、将来の売り上げの一部を前払いする制度だと説明された。
「いくらバンスできるかで、良いセールスマンを確保できるかどうかが決まります」
「なるほど……。 具体的にはいくらを準備すればいいですか」
「まあ、私の場合、相場は二五〇万円。斎藤くんは一五〇万円。合わせて四〇〇万円もあればいいでしょう」
志賀は、その金額に仰天した。そんな大金が手元にあるわけがなかった。しかし、これはひとつのチャンスである。バンスはあくまで前払い。横尾は、それを営業で取り返せると考えているのだ。
「苦越」という文字が、志賀を睨んでいた。
考えたのち、「すぐには用意できないけど、まずは一ヶ月間仕事をしてくれれば、一ヶ月後にはその額をバンスします」と約束した。すると、「それでもいいけど、とりあえず五〇万円ずつ明日までに準備してください」と横尾は静かに迫った。
ふたりの間に、緊張が流れた。
——横尾さんは営業の神様——
ひと言、「わかりました」と答えた。とはいえ、貯えはほとんどない志賀である。帰り道は、明日までにどうやって一〇〇万円を工面するかで頭のなかがいっぱいだった。
考えたあげく、父親に相談した。
「新しい仕事で必要になった」と頼むと、ほとんど質問もせずに「わがった、一緒に農協に借り入れにいくべ」と言ってくれた。志賀は、生まれて初めての大きな借金をした。無事に一〇〇万円を手にすると、すぐに横尾と斎藤に会いにいき、帯がついたままの札束を手渡した。ふたりはその場で五〇万円ずつを分けあった。
こうして、横尾と斎藤を含めた四人の営業マンを迎え、ソーラーの訪問販売事業が始まった。しかし、新たな営業マンたちは思わぬ苦戦を強いられた。なぜか? 振り返れば、それまで志賀がソーラーを販売した二十数人は、すべて友人や知人だった。彼らは、志賀の人柄を信頼し、購入を決めた。ところが、いったん知人のネットワークから飛び出してみれば、対応は一変した。
「こんな時間に何の用事だ!」「いんねえ、帰れ!」と罵声を浴びせられることもしばしば。いやがうえにも足取りが重くなる。
そうか、訪問販売ってこんなに苦しいものだったのか、と志賀は初めて思い知らされた。
こうなると、一ヶ月後に約束した残りの三〇〇万円を準備できるかもあやしい。志賀は必死の営業活動を続け、何とか約束の額を前払いした。
それを見て横尾も考えたようで、ある日、「モデル地区をつくろう」と言い出した。ひとつの団地に集中して営業をかけ、連鎖反応を起こすというアイデアである。はたしてうまくいくのかは志賀にはわからなかったが、〝神様〟を信じることにした。
さっそくある団地に目をつけ、志賀と横尾のふたりで、団地の自治会長の家のドアをノックした。
「ここを省エネ推進のモデル地区にしたい。会長のお宅にはサンプルとして無料で設置させていただく」
横尾はスムーズな口調で話を持ちかけた。それを聞いた会長は、「セールスマンの話を聞いたうえで各々判断してほしい」と一筆を書いてくれた。ドアが閉まると横尾は、「忙しくなるぞ!」と目を輝かせた。
この戦略は、その後の流れを変える突破口となった。一軒が契約すると、「うちも欲しい」という家が現れ、あとはドミノ倒しのようにことが進んだ。しばらくすると、団地の屋上には温水器がずらりと並び、その光景は壮観だった。志賀は山の高台からその様子を写真に収め、営業マンに持たせた。一枚の写真の説得力は、言葉とは比較にならないほど絶大だった。
こうして志賀は、ガソリンスタンドから独立し、「東北機工(株)」を開業した。いったん「この商品は売れる」と知られると、「自分も売りたい」という人が続々と現れた。横尾は他のセールスマンにも親切で、セールスのコツを丁寧に伝授した。
「横尾さんは、教えんのもすんごい上手で。何だろうね、やっぱり神様みたいな感じだよね。横尾さんには、絶対に折れない心みたいなのがあったよね」
事業がうまくいくにつれ、横尾と志賀の収入も飛躍的に増えた。志賀たちは、貸し切りバス六台で、営業マンや技術者とその家族三〇〇人を連れ、岩手の温泉に出かけて宴会を開いた。
「せっかくだから誰かスターを呼ぶべ! ってことになって、俺らの商売は『空に太陽がある限り』だから、にしきのあきら(歌手、現在は錦野旦)呼ぶべ! って」
志賀たちのラブコールに答え、にしきのは岩手までやってきて、『空に太陽がある限り』を披露してくれた。波に乗った志賀と横尾は、六年間で一〇〇億円分の温水器を販売したという。
苦しみの先にあるもの
しかし、商売というものは、やはり「山」のあとには「谷」がある。空に浮かぶ太陽を隠す暗雲は、すぐそこまで迫っていた。
販売した温水器には一〇年保証がついていたのだが、やがて不具合が報告されるようになった。最初は単発的な故障かと思ったが、どうやら同じ部品に問題が集中している。志賀は、商品には構造的欠陥があるのではないかと疑うようになった。
そこで、メーカーに対し「不具合のある、なしにかかわらず、取り付けた機器のすべてにおいて改良部品と交換したい」と主張した。せっかく取り付けた高額な温水器だ、長く使ってもらいたい。しかし、メーカー側は「あくまで問題が発生したら修理する」というスタンスを崩さない。それは、根本的な考え方の違いだった。
そんなジェットコースターのような日々のなか、志賀がのめり込んだのは、やはり空を飛ぶことだった。もはやハンググライダーではなく、ウルトラライトプレーン、エンジンを装備した簡易構造の軽量飛行機である。
乗り方を教えてくれたのは、茨城県の会社経営者、鈴木武だった。
鈴木は、「JON72」というFRP(繊維強化プラスチック)製品などをつくる会社を経営しているのだが、もともとは大好きなサーフボードを制作するために興した会社だった。海だけではなく空も愛し、独学でウルトラライトプレーンの乗り方を覚え、いつか自作の飛行機で空を飛ぶことを夢見ていた。
「磯原の海岸でいつも飛行機に乗っている人がいる」という噂を耳にした志賀は、ある日、海岸で鈴木を捕まえた。「自分も乗ってみたい、乗り方を教えてください」と頼むと、快く「いいですよ」と答えた。それからというもの、ふたりは毎週のように一緒に空を飛んだ。志賀も自分の飛行機を買うと、しまいには宙返りの練習もするようになった。教科書などないので、戦時中の軍隊の教則本を入手し、参考にした。
あんな簡単な乗り物で宙返りって……、と私は絶句した。そもそも、この飛行機で事故にあった人とかはいないのだろうか。
「そりゃあ、死んだ人はいっぱいいっから!」
それでも、志賀は空を飛びたかった。広い空に身を委ね、重力からも解放されると、地上でのあらゆるトラブルを忘れられた。
メーカーとの話し合いは続いていた。そのうち、先方は突如として商品の出荷を停止した。怒りが沸点に達した志賀は、内容証明付きの手紙を送りつけ、弁護士に訴訟の相談をした。しかし、大手メーカーと争っても勝てないと弁護士は及び腰である。ほどなくして、手紙を受け取ったメーカーの社員がいわきまでやってきて、ホテルの会議室で話し合いが持たれた。
「自分らはこれで儲けようなんて思っていない。ただ修理コストを出してほしいだけだ。うちも相当な損害をかぶっている」と志賀が交渉を続けると、最終的にはメーカーが折れ、損害に相当する額を別の形態で補填してもらえることになった。
このとき、志賀はどっと疲れを感じた。
「そろそろ潮時かもしれないと思うようになったよね。売り上げは伸びたけど、ソーラーを売るのは、ずっと生きるか死ぬかのような感じで、もう自分がすり減ってきたみたいに感じた。あー、くたびれたなって。だから、金を稼ぐのはもういいやって思ったよね」
故障のアフターケアがいち段落すると、東北機工はソーラー事業から撤退。横尾もあっさり、他の町へ引っ越していった。そして、その後のアフターケアはメーカーが責任を持つことになった。
横尾は、年に一度ほど、ふらりといわきに立ち寄るだけになった。
「ねえ、横尾さん。あの当時の横尾さんの営業は本当にすごかったですよ」
あるとき、志賀が懐かしくなってそう言うと、横尾は静かに首を振った。
「そんなことねえ。俺は何千人に営業を教えたかもしれないけど、結局は志賀さんに一本のウイスキーでその気にさせられちゃったんだからなあ。志賀さんのほうがよっぽどすごいよ」
しかし横尾は、ある年を境にふっと姿を見せなくなった。
「生きてんのか死んでるんか。もしかしたら、もう二度と会えないのかなと思うと、いまでも横尾さんの夢を見るよね」
苦越。その言葉と一緒に暮らした横尾。彼が苦しみの先に見たものは何だったのだろう。はたして喜びや幸せだったのか——。
こうして志賀のもとには、六年間で成した財産と二台のウルトラライトプレーンが残された。
さあて、次は何をやるかなあ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
続きはこちらからどうぞ。
書籍でお読みになりたい方はこちらからどうぞ。
空をゆく巨人 目次
プロローグ
はじめに
第一章 生まれながらの商売人 いわき・一九五〇年
第二章 風水を信じる町に生まれて 泉州・一九五七年
第三章 空を飛んで、山小屋で暮らす サンフランシスコ・一九七六年
第四章 爆発する夢 泉州・一九七八年
第五章 ふたつの星が出会うとき 東京・一九八六年
第六章 時代の物語が始まった いわき・一九九三年
第七章 キノコ雲のある風景 ニューヨーク・一九九五年
第八章 最果ての地 レゾリュート ・一九九七年
第九章 氷上の再会 レゾリュート・一九九七年
第十章 旅人たち いわき・二〇〇四年
第十一章 私は信じたい ニューヨーク・二〇〇八年
第十二章 怒りの桜 いわき・二〇一一年
第十三章 龍が駆ける美術館 いわき・二〇一二年
第十四章 夜桜 いわき・二〇一五年
第十五章 空をゆく巨人 いわき・二〇一六年
エピローグ いわきの庭 ニュージャージー・二〇一七年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
