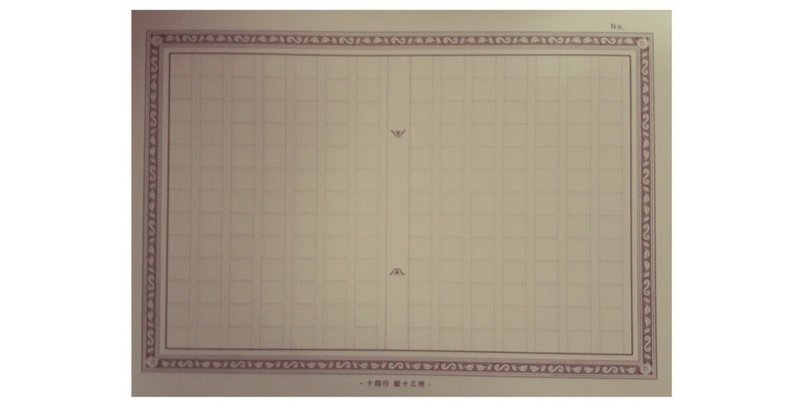
(完)冬は灰色やうやう⑧【連続短編小説】
※前回の「冬は灰色やうやう⑦」はこちらから
虹が綺麗だと感じるのは、多色があるからではないか。
そしてその多色とは、人で言うところの『表情』のようなモノだと思う。たとえ満面の笑顔であっても常時そうであるならばまるで張り付いたそれの様で不気味である。たまに涙を見せ、驚いたり困ったり見せるその方が良いと僕は思う。一色よりも多色、それが綺麗なのではないか。
虹を見ていたトヨさん、彼女自身が本当は虹なのだと思った。
僕が忘れ物を取りに部屋に戻ったとき、彼女は空を見上げて小さく微笑んでいた。いつだって表情を見せない彼女がわずかでも微笑んでいるのだ。一瞬間、確かに僕は見惚れていた。
ビー玉に何を映していたのか、少しして、彼女が涙を流したので僕は動揺した。動揺しすぎて、彼女に駆け寄る際に転んでしまったが、結果オーライである。
僕は、トヨさんに触れた。
触れて、知る。
彼女もまた、誰かを探し、それが僕であることに気づいたようだった。
窓を開けているせいで部屋は冷えている。そのはずなのに、僕も、おそらくはトヨさんも暑くて仕方なかった。氷を拳に握り込んでお風呂に入るような、自分の手が今熱いのか冷たいのか、一瞬にして混乱する。
それが熱だと、教えてくれたのもトヨさんだった。
彼女は僕に、形見にとビー玉を渡した。それはよくあるビー玉だった。もしかしたら家にもあるかもしれない。そのくらい、よくある透明のビー玉。それを彼女は虹だと言った。
お返しに僕も形見をと、彼女の部屋に忘れたはずの虹色鉛筆をあげると約束した。彼女は見つけたら貰っておくと言ってくれた。
こうして、僕と彼女は同じ虹を持つことになった。
僕は大層興奮していた。
ああ、これで僕は大丈夫。僕はきっと何があっても大丈夫、僕にはトヨさんがあるし、トヨさんには僕がいる。
その夜は心地よく眠りについたことを良く覚えている。
そして実は同じ頃、トヨさんも心地よい永遠の眠りについていたのだと、後日にクラスの担任から知らされた。最後に会ってから3日ほどが経っていた。
僕は動揺し、学校の鞄を自分の部屋のドアに投げつける。すると鞄の中から、彼女の部屋に置き忘れてきたはずの虹色鉛筆が転がり出てきた。あの日、虹色鉛筆が見つかったらそれを僕の形見にしてくれと伝えたその鉛筆だった。 彼女と僕は同じ虹などもっていなかったのだ。僕だけが、彼女の虹をもっている。
以来、僕はトヨさんに虹色鉛筆を渡そうと探し続けているのだが、うまく行かない。同じ様な年齢の同じ様な色を持つ『トヨさん』を探すのはなかなかに困難である。これまでに彼女に似たトヨさんを3人見つけるも、結局虹色鉛筆は渡せないままだ。
今回だってうまく行かないだろう。高齢ホステスのクラブでやっと見つけたトヨさんだが、1度会ったきり会えないでいる。今日も出勤しないらしい。せめて虹でも見ようとビー玉をかざすもこの曇り空では陽の光を受けることが出来ずに色もない。
灰色。
もう、諦めた方がいいのかも知れない。
クラブの店員の言うとおり、虹を混ぜれば灰色になるのだろう。僕が混ぜないと言っても、混ざってしまえばそれまでで、きっとぐるぐると灰色になっていく。まるで僕だ。
誰かを求めて、勝手に期待して、いなくなればそれに縋って追い続ける。もういないのだから、そこにゴールがあるわけもなく、僕は延々と追い続ける。追い続けて追い続けて、現実を直視しない。誰かではなく僕が僕を見なくてはならないのに、僕はいつまでも僕を見ない。
虹はなく、灰色の空を、僕はいつまでも見ない。今の僕では、きっとビー玉にだって虹は映らない。
「アケルさん?」
曇り空にかざしかけたビー玉の中、僕を呼ぶ声と彼女の姿が映る。
「・・・・・・トヨさん」
1度会ったきりのホステスのトヨさん。
「お店に来てくれたとき、あなた、随分と嬉しそうに私とお話ししてくださったから、気になっていたのよ。また会えて嬉しいわ」
彼女の笑顔に、僕は少しだけ泣きそうになる。それに気づいたのか、少しお話しましょう言われ、僕らは近くのベンチに座った。
元気そうに笑う彼女に僕は安心した。
ここ数週間、彼女は検査入院や自宅安静などでなかなか外にも出られないとのことだった。子供たちが過保護なのよと言って彼女は照れくさそうに、けれど嬉しそうに笑う。
「これを、もらってくれますか」
唐突に、僕は虹色鉛筆を彼女に差し出した。
僕は、多分きっといろいろなことに疲れていたのだと思う。もう、終わらせたい気持ちが僅かでも芽生えているのは事実であり、もしかしたらそれだって表情にいくらか滲んでいるかも知れない。彼女は僕の顔をじぃっと見て、そっと受け取った。
「私はもう、あのクラブには戻れない。あなたとも、きっともう会うことはないでしょう。この鉛筆があなたの大切なものであるならば、私も大切に受け取ることにします」
澄んだ目で、僕を真正面から見て彼女は言う。
「はい、大切なものです。受け取ってもらいたい」
「わかりました」
彼女はそう言うと、鞄の中から真っ白なハンカチを取り出し、それで鉛筆を包み始めた。「あなたの形見として受け取るわ。私の形見は必要かしら」
鉛筆を包み終え、鞄にそっとしまうと、彼女は微笑んで僕に言う。僕はうっかり涙を流し、首を横に振る。
「アケルさん、虹が好きなのよね」
僕は今度は首を縦に振る。彼女は小さく息を吐いた。
「綺麗なままの虹を延々に持っておくことは出来ないと思うわ。だから一度、あなたの中で虹を混ぜてしまうといいと思うの」
「でも、混ぜると灰色になってしまう」
僕は半ば助けを求めるように反論した。彼女はそれさえ分かっていたように笑う。
「いいえ、虹を混ぜると白色になる」
「え」
「絵の具なんかは灰色や黒になるわね、きっと。虹色鉛筆は、うーん、どうかしらね。でもたとえば本物の虹の光を混ぜると白色になるわ」
そう言われ、僕は僅かに動揺する。灰色ではなく、白色になる。詳しくはインターネットで調べてみてと言う彼女が可愛らしく微笑む。
「いったん白にして、また虹を作ればいいのよ」
トヨさんは僕の手をそっと握りしめた。
「あなたは大丈夫。他の誰かがいなくても、他の誰かを求めなくても、あなた自身がそこにいればそれで大丈夫よ」
ぎゅっと握られたその手の温かさがあの日のトヨさんの熱と重なる。
けれど僕は気づくのだ。
温かいと感じたその熱は、もしかすると彼女の熱ではなく僕自身の熱なのかも知れない。今触れている彼女の手の温かさだって、それは僕の温かさかも知れない。
雲の切れ目から僅かに陽の光が指した。僕は思わずビー玉を掲げ、それを透かして見る。自分の涙で光の屈折も揺れ、虹も何もそこに映りはしない。けれど、ちらちらとビー玉に映る白色が虹のそれなのだと分かる。
「空に虹があるなら、別にビー玉に透かさなくてもいいのよ」
トヨさんがそう言い、僕の指からするりとビー玉を取る。
ぼんやりと空に滲むような薄い虹が見えた。
「何だって、だいたいは曖昧なものよ」
トヨさんがまた笑うので、僕も思わず笑った。
それは灰色でも白色でもない、かといって綺麗な多色でもない。
ただ僅かに色のある曖昧な空だった。
虹色。
~完~
☆2ヶ月に渡りご購読頂きありがとうございました。これにて『冬は灰色やうやう』は終わります。
2022年4月はお休みをいただき、次回作は5月2日(月)12時に公開いたします。
引き続きよろしくお願いします。
冬が終わり、春が来ます。
お忙しい時節、どうかご自愛のほど心地よく、日々をお過ごしくださいませ。
byあにぃ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
