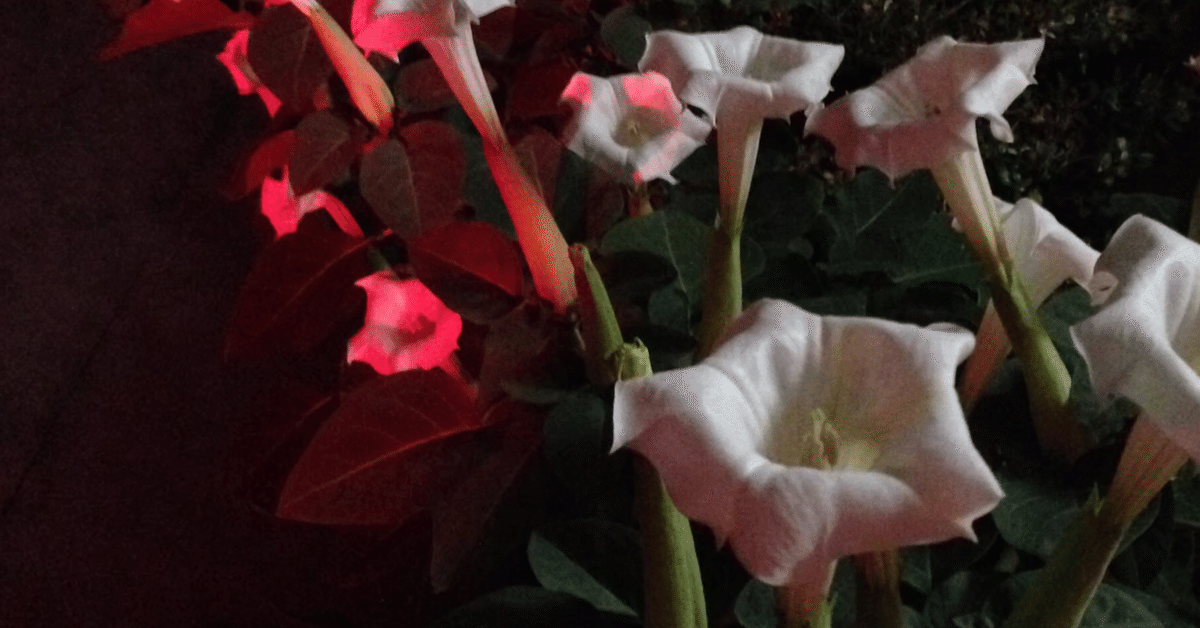
「冷たい舌」
まだ太陽が沈みきらない黄昏時、
私はめずらしく 仕事へ行く支度が
早く終わり、行きつけのカフェで
時間をつぶすことにした。
このカフェは、昼間は珈琲や軽食を
出し、夜になるとbarに変わる。
丁度、カフェからbarに変わるころに
お店に着いた私は、天井の灯りが暗くなり、それぞれのテーブルに小さなロウソクが配置されたタイミングで、珈琲を注文した。
いつものカウンター席に座って、マスターとお喋りをしながら珈琲を飲むのが、
私の出勤前のルーティンであり、息抜きだ。
今日はいつもより早く来た私に、マスターが珍しく「昼間に出したかき氷が美味しいと評判なんだ、食べてみないか?」とすすめて来た。
私が甘い物を食べないことを知っている
マスターがすすめるかき氷を「食べてみたい!」とすぐさま注文した。
薄暗いbarで、かき氷を食べるのは、なんだか不思議な気分だった。
マスターが丁寧に削った天然氷のかき氷は、苦めの珈琲にミルクとシロップを
少しかけた大人の甘さで、氷の細やかさ
が泡のように口の中で溶けて、とても舌触りが良かった。

私の仕事は夜の商売で、舌が冷たいと
嫌がるお客さんは多い。
私の思惑を知ってか知らずか、
マスターは、熱い珈琲をもう一杯
黙っていれてカウンターに差し出した。
「珈琲味のかき氷に、また珈琲?」
私は笑いながら、冷たくなった舌を
温めるように、ゆっくりと、珈琲を
口に流し込み、しっかりと外が暗く
なるのを見届けてから、レストルーム
で口紅を丁寧に塗りなおし、barを出た。
かき氷の優しい甘さや冷たさはもう
無い。
懐かしい夏休みの思い出が胸の中で
溢れそうになり、慌ててかき消すように、空を仰いで月を探した。
半分の月が私を見下ろしているのが
見えた。

私が生きるのは、夜の街だ。
夜の月が私の仕事へ行く時間を
知らせてくれる。
月が私の居場所を教えてくれる。
私はヒールの音をわざと大きめに
鳴らしながら、仕事場へと足を急がせた。
サポートしていただけたら生きる希望になります。
