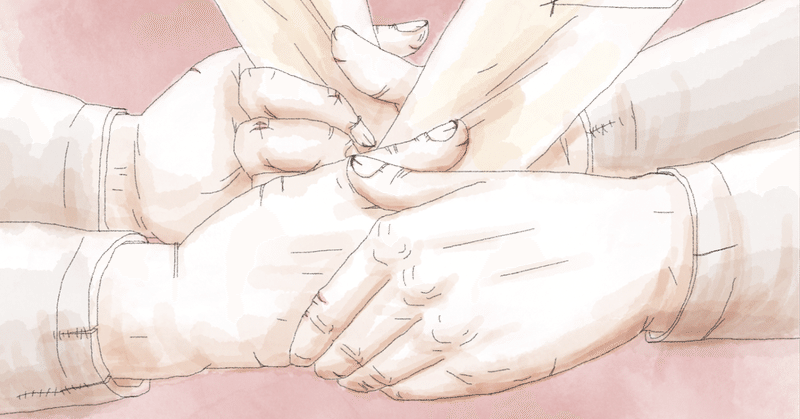
文房具屋のおじいさん
2015年の春のこと。
わたしはまだ青木杏樹ではなく、ただ趣味で小説を書いている人でした。毎日毎日、400字詰め原稿用紙を20枚ワンセットを消費しては、文房具屋に買いに行きました。帰宅するとまた明け方まで20枚消費し、日が高くなる頃には買い足しに行く日々が続きました。
小説とは応募するもの、小説とは他人に読んでもらうもの、という考えがわたしにはありませんでした。
わたしの中には小さな世界がごまんとあり、その世界で生きている人たちはたえず呼吸をしていて、畑を耕し、水を飲み、作物を売ったり買ったりしていました。ときには殺し合って世界は消えてしまうこともありました。そうした流動する世界線がいくつも走り、絡み、まじり、繰り返す、衝動にも近い意識と妄想がするすると動くものですから、歴史をつむぐように彼らの証をのちのちまで残せないものかと考えたのがどうもわたしの執筆の原点のようです。つまり応募する、評価される、そういった考えには至らなかったわけです。
さてその2015年の春に、わたしを呼び止める人がいました。文房具屋の店主さんでした。髪の毛は真っ白でぶあつい眼鏡をかけたしわくちゃのおじいさんでした。いつも難しい顔をしていて、お釣りを「ん」と言って渡してくる気難しい雰囲気の店主さんなので、わたしも臆病なものですから、買うだけ買ってお礼のひとつも言わずに出ていくわけで、もちろん滞在時間はものの1分。いえ1分もなかったかもしれません。無愛想。ぶっきらぼう。文房具屋は万引きが多いというけれど万引きなんて恐ろしくて考えることすらできない、商品を触るだけでも緊張するお店でした。従業員はおじいさんただひとりでした。他の人を見かけたことはありません。万年筆のショーケースに囲まれたレジカウンターの内側でいつも戦争の本を読んでいました。なぜ戦争の本だとわかるのかといいますと、わたしは文房具屋に通うのと同様に本屋にも毎日通っていたからです。なにか面白い本はないかなとぐるりと店の中をまわり、カバーの写真やイラストを眺めるのが日課でした。戦争の本は戦争の本だと書いてなくても見ただけでわかるのです。おおかた赤みを帯びた茶色か灰色なのです。もしかしたら店主のおじいさんは戦争経験者なのかもしれません。青春を戦争で過ごし、戦争の中に友達がいたのかもしれません。だからいつも読んでいるのは戦争の本で、つまり青春小説なのかもしれないなどとわたしは思っていたのでした。
戦争の本を読みながら怖い顔のおじいさんがどかりと腰掛けている文房具屋。まぁなんとも入りづらいではありませんか。しかしわたしが頑なにその文房具屋で原稿用紙を買う理由はふたつありました。
ひとつは、スタンプカードです。買い物をするごとにポコンと「松」のスタンプが押してもらえて、50個たまると500円の割引券になるのです。どうして「松」なのかはのちほど。
もうひとつは原稿用紙の種類が豊富だったからです。原稿用紙といっても何種類かあります。レポート用紙のように綴られているもの。これは筆がのりにのったときに良いものでした。それから二つ折りにされて袋に入っているもの。これは紙の質も良くなによりサイズが大きいので字を書いている感覚が長く続き、筆が遅いときに良いものでした。すこしクリーム色が強い原稿用紙もありました。これは目が疲れたときに良いものでした。サイズの小さいもの、これは出先でさらっと書けて携帯用でした。覚えているだけでも四種類。原稿用紙をここまで揃えている文房具屋さんはそうないでしょう。その日の気分で原稿用紙が変えられました。
「なに書いてんだい」
わたしは驚いてお釣りを取り落としそうになりました。
「小説でも書いてんのか」
しわだらけの顔が難しそうに歪み、わたしをぎろぎろと睨んで言うものですから、返事ができませんでした。その日は逃げるように帰りました。
帰宅したわたしは、ちゃぶ台に突っ伏し、ばくばく鳴り続けている心臓をぎゅうぎゅう押し付け、自分の中でたえず流れ走っている世界線に指を引っ掛けられた気持ちでした。恥ずかしいという気持ちでした。恋文を書いているわけでもなしに、なにを恥ずかしがることがあるのでしょう。まぁ当時のわたしはシャイだったのです。せっかく原稿用紙を買って帰ったのに、その日は一枚も書けませんでした。わたしの中の小さな世界はどくどくと波打ってしまい、形にならなかったのです。
目を開けると朝でした。
書きためた小さな世界はおそろしいほど巨大な塊となっていました。わたしの背後には実にさまざまな種類の原稿用紙で紡がれた物語がめちゃくちゃに積まれていて、ばらばらになっていて、部屋の中で銀河になっていました。
わたしはその中から戦争ものを取り出しました。養父から伝え聞いていた戦地で焼いて食べた青いバナナの話でした。おいしかった、養父は生前、思い出してはきいてもいないのに言っていました。なのに第一線で失った戦友の話はひとつもしませんでした。わたしがいまも大切に持っている養父の遺品、血染めの日の丸の話も、尋ねても答えてもらえませんでした。
きりで穴をあけ、紐でくくり、わたしは青いバナナの短編を持って文房具屋に行きました。
なぜ持っていったのか。わかりません。たぶん、恥ずかしかったけれど、嬉しかったのかもしれません。わたしの筆に興味を持ってくれる人に、初めて出会えたからかもしれません。
店主のおじいさんはやっぱり戦争の本を読んでいました。表紙には日の丸がありました。
わたしは新聞配達でもするみたいに、さっと目の前に置いて、小走りで原稿用紙の棚に行きました。今日は二つ折りにしようか。そんな囁くような声で別に意味もないことを呟き、背中でおじいさんの反応をうかがっていました。
いつもならすぐに買って帰ってしまうところを、今日は熱心に選んでいるふりをしました。
「バナナか」
驚いてわたしは振り返りました。
おじいさんは戦争の本を横に置き、わたしの小説を読んでいました。
どきどきして、顔が熱くて、足が震えて、口が閉じられなくなりました。
「バナナはそのまま焼くんじゃない。輪切りにして棒に刺して焼くんだ。そのほうが早く焼けるしうまい」
「火は長くたけん」
「それでも食いたくて朝にたいた。朝なら太陽が焼けて明るい、ばれん。そんでもばれるのがおそろしくてばらすやつがおって結局怒られた」
わたしの小さな世界はぽろぽろと音をたてておじいさんの胸の中に入ったようでした。おじいさんは険しい顔のまま楽しそうに青春を話してくれました。その日はとっぷり夜になるまで話して帰りました。ずっと青いバナナの話でした。人が殺し合う話でもなければ、憎しみ合う歴史の話でもなく、時代の流れに流れ流されて、わけもわからぬまま外国で青いバナナを頬張り上官に叱られる話でした。
これが現地の人まで巻き込まれて、現地の人まで一緒に怒られたということですから、わたしは布団の中で思い出しては笑いました。
2016年。
文房具屋に小さな世界を持っていく日が増えました。スタンプカードは「松」まみれで、たまっていくいっぽうで、なんだかわたしは使えなくて、毎日100円とちょっとのお金をポケットに突っ込んでは小脇に小さな世界を挟んで通いました。
おじいさんは食べ物の話が好きでした。フルーツの話が好きでした。桃の缶詰の食べ比べをする少年たちの話を読んだ次の日には、桃の缶詰を買って食べたと教えてくれました。
警察ものも好きでした。特にはぐれ刑事ものが好きで、組織からのはみ出し者が犯人を追い詰めていく話はおじいさんのツボだったようです。この続きはないのかとせっつかれたこともありました。
2017年。
文房具屋は臨時休業する日が増えました。
わたしはKADOKAWAでのデビューが決まり、店主のおじいさんはそれが警察ものであることを期待していると言ってくれました。内容は言えなかったのですが、警察ものではないんですと遠回しに伝えれば、「いまのやつらは見る目がねぇ」としきりに首を横に振りました。検察ものだったのでまぁさして遠くはなかったのですが、おじいさんが読んでも楽しめる内容になればいいなと思っていました。
2018年。
文房具屋のシャッターが降りました。休業と殴り書きで貼られていたので、閉店ではないことに安堵しながら不安でした。原稿用紙は別の店で買うことにしました。駅ナカの文房具屋は綺麗で整然としていましたが、原稿用紙は一種類しかありませんでした。スタンプカードは財布の中でぱんぱんになっていました。
2019年。
デビュー作にサインと手紙を添えてポストに入れました。キャラクターに癖があるキャラ文芸だから、戦争ものが愛読書のおじいさんにはちょっとよくわからない小説かもしれない、と思いました。
すぐに2巻が出ました。それもポストに入れました。おじいさんの手元に届いているのかはわかりませんでした。なぜならわたしはお店の場所こそ知っているけれども、おじいさんの名前も住まいの住所も電話番号も知らなかったのです。唯一の手がかりは「松」だけです。もしかしたらこの判子は名字なのかもしれないと思い、近所の表札に松さんはないかと見てまわった日もありました。
2020年、4月。
わたしは3冊目の本を持って文房具屋に行きました。もう原稿用紙は駅ナカで買うことにしていました。文房具屋のシャッターには近々取り壊しの紙が貼られていました。
慌てて手紙の裏に住所と名前と電話番号を書きこみ、連絡ください、と短く用件を伝えることにしました。
その翌週のことです。
娘さんとおっしゃる方から電話がありました。
おじいさんは、急に亡くなったのだそうです。娘さんは思いました、もしやあのコロナではないか。とはいえ判断がつかないなんとも曖昧な、思い込みで言い出すのも憚られる、そういう時期でした。おじいさんの様子がおかしくなって入院する前日まではご飯も食べて散歩もして元気だったのだといいます。とはいえ2017年の後半からなんとなく風邪をこじらせては寝込んでいて、娘さんからはお店を閉めて隠居生活するべきだと説得され続けていたおじいさん。でも毎日くる客がいるんだと言って頑として閉店しないでいたのだそうです。文房具を毎日買う客なんているもんですか、と娘さんは思ったそうです。
お店の裏には大量の原稿用紙の段ボール。
わたしのために、切らさないようにと仕入れ続けていた原稿用紙。
もういっそ、臨時休業明けに箱で買えばよかったのでしょうか。具合が悪いのですか、どこか痛むのですか、休んでくださいねと言えばよかったのでしょうか。毎日箱から出して、1束ずつ買っていく変な客のためにこんなに仕入れる必要はなかったはずです。お線香をあげることもままならない情勢で、写真と動画で伝えてくださった娘さんに感謝を伝え、わたしは原稿用紙を引き取りました。お金はいらないと強く言われたので、代わりにとたまりにたまったスタンプカードを送りました。
「松とはなんですか?」
最後に娘さんとスタンプカードの判子のお話をしました。松とは、女性の名前ではないかと娘さんは冗談半分におっしゃいました。
随分前に亡くなった、おじいさんの奥様は松という名前ではないそうです。
当時の男性はほらねぇ、いろいろ、緩くて広かったでしょう?と笑う娘さんの声はすこしばかり疲れた様子でした。「大丈夫ですか?」とたずねれば、娘さんは、
「あなたこそ」
と言いました。わたしはそのとき初めてスマホを握り締めながら泣きました。はらりと涙が落ちました。本は読んでもらえたのでしょうか、書いてある意味はわかったのでしょうか、おもしろいと思っていただけたのでしょうか、わたしの小さな世界に興味を抱いてくれたおじいさんはあの世で青いバナナを焼いて食べているのでしょうか、松とはなんですか、初恋の方のお名前なのですか……もっと、もっと話せることはたくさんあったはずなのにわたしは肝心なことをなにもきかなくて、おじいさんも肝心なことをなにも話さなかったのです。あんなに時間はあったのに。
わたしが失ったもの。
皆さんが失ったものも、きっとたくさんあるはずです。流され、逃し、消えたものがこの半年で山のようにあることでしょう。
これから生まれるものもあると思いたいです。
わたしは今日も、夜の闇の中で、原稿用紙と向き合っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
