ALFA+アルファ #3
〜はみ出した歌唄い ③ 小坂忠〜
Text:金澤寿和
皆さんご存知のように、昨年末にアルファミュージック公式サイトに開設された“ALFA MUSIC YouTube Channel”に於いて、第1回のゲストに登場した小坂忠さんが、4月29日、天上の星になられた。5年前の大腸癌ステージ4から見事に復活を遂げ、以前にも増して張りのある歌声を聴かせてくれた時には、牧師でもある忠さんゆえ、音楽ファンの多くが「奇跡」や「神のご加護」を信じたはず。しかし、しばらくして転移が発見され、何度かの手術を経たものの、とうとう力尽きてしまった。それでも常に前向きに病気と戦い、可能な限り、魂の歌を届けてくれたその姿には、感動を禁じ得なかった。
そんな小坂忠の歩みを振り返ってみる。すると、GSグループに始まり、ジェイムス・テイラー風シンガー・ソングライター・スタイルを経由して、やがて和製ソウルに辿り着いたことが分かる。彼の前にレールはなく、その後ろに道ができた。そしてそれが時を経て、いつしかシティ・ポップと呼ばれるようになり、最近になって急速拡大するターミナルへと吸い込まれていった。
しかし忠さん自身は、最初にレールを敷いただけで、いつの間にかゴスペルという引き込み線に入ってしまい、約25年もの間、ポップス本線には戻ってこなかった。彼がクリスチャンになった76年当時、ゴスペル/教会音楽はまだ閉鎖的で、ポップスとの間には明確な境界があった。だから徐々にゴスペルの世界で歌うことに専念。でもその一方で、信仰を架け橋に世界中で歌うチャンスに恵まれ、別の方向に線路が伸びていったのも事実である。同時にポップ・フィールドで自前の事務所やスタジオを持った経験を生かし、78年に日本初のゴスペル・レーベル:ミクタム・レコードを設立。それ以降コンスタントにオリジナルのゴスペル作品を送り出し、岩渕まことや元ゴダイゴのスティーヴ・フォックス、久米小百合(=久保田早紀)など、ポップスからゴスペルにシフトしていくアーティストたちの先駆になった。
小坂忠がアルファ・ミュージックに深く絡んだのは、ソロの最初期である。細野晴臣、松本隆、柳田ヒロらと組んでいたエイプリル・フールが解散し、はっぴいえんどに進化していく過程で、ミュージカルに興味を持っていた彼は、流れに乗らずオーディションを受けて『ヘアー』に参加した。ところが出演者や関係者が問題を起こし、興行は中断。行き場に困った彼は、誘われるままに日本コロムビア傘下に創られた新しいレーベル:マッシュルームと契約する。マッシュルーム設立は1971年で、音楽出版社アルファミュージックの村井邦彦、『ヘアー』のプロデューサー川添象郎、内田裕也にミッキー・カーチスなど5人が絡んでいた。そこで彼は『ありがとう』(71年)、『もっともっと』(72年)、『はずかしそうに』(73年)、そして日本のポップス史に燦然と輝く名盤『ほうろう』の4枚を作っている。それを順に追っていくと、小坂忠というシンガーの成長のプロセス、自分の歌探しの道筋がハッキリ分かる。
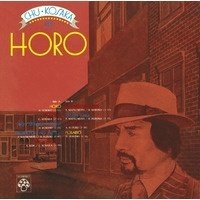
そのアイコンが、ソウル・バラード「機関車」である。一般的には「ほうろう」の方が知名度が高いかもしれない。が、あれはアルバムをプロデュースした細野晴臣の楽曲。対して「機関車」は忠自身の詞・曲で、オリジナルは1st『ありがとう』に収められている。しかも当時は、スティール・ギターをフィーチャーした軽いカントリー・テイストで歌われていた。曲が書けずにライヴ・アルバムになったという曰く付きの2nd『もっともっと』にも入っているが、バック・バンドになったフォー・ジョー・ハーフ(駒沢裕城・松任谷正隆・後藤次利・林立夫)の外連味のない演奏で、コク深いカントリー・バラードに進化している。それを三たびアルバム『ほうろう』に、今度は細野アレンジで収めているのだから、相当なお気に入りだったのだろう。当然ステージでの定番曲でもあったから、ショーボートのライヴ盤などへの収録も少なくない。しかし何よりこの曲の進化が、そのまま小坂忠というシンガーの成長、歌い手としての自分探しの旅を代弁していると思うのだ。
忘れものは もうありませんねと
機関車は走るのです
君はいつでも僕の影を踏みながら
先へ先へと走るのです
『ありがとう』というアルバムは、試行錯誤の中で作られた。レイ・チャールズやオーティス・レディング、アル・グリーンなど、外人シンガーのシャウトを一生懸命コピーしていたから、ソロになっても、最初は自分の歌をどう表現すればいいのか、見当がつかなかったという。そんな時にジェイムス・テイラーを聴き、アコースティックなシンガー・ソングライター・スタイルに可能性を見い出して、自分流の表現を模索し始めた。ただ、アコースティック・ギターで弾き語れば、それだけですべてフォーク・ソングと見なされてしまうご時世。それを潔しとしなかった彼は、その迷いを細野に相談。細野と共にたどり着いた境地が『ほうろう』だった。彼らは事前にソウルやファンクを演ると決めていたワケではなく、ティン・パン・アレーと一緒にスタジオ入りし、そこで自然にそうなっていったのだ。ティン・パンは元々ファンキーなテイストを持っていたが、シンガー次第で変幻自在。例えば、元来シンガーではない細野が歌えば、演奏は自ずと抑えめになり、フォーキーな仕上がりになった。つまり、ティン・パン・アレーがいて忠さんが歌ったからこそ、名盤『ほうろう』が生まれたのだ。予定調和ではなく、まったくの自然発生的に。
「やっと自分の歌が思い切り歌えた…」
彼が抱いたであろう喜びが、「機関車」のこのヴァージョンに表れている。
『ほうろう』で大きく生まれ変わった「機関車」は、それ以降のデフォルトになった。ただし、程なくして彼のゴスペル移行があったため、広くシーンに浸透したのは、忠さんがポップ・シーンに復帰した2000年以降といっていい。25年も世俗音楽から離れ、細野がどんな活動をしているのか、それこそYMOも聴いたことがなかったというから徹底している。それなのに、久しぶりに細野のスタジオを尋ねると、偶然にもティン・パン再結成のタイミングにぶつかった。これもやはり“神様のお導き”だったとの思いを禁じ得ない。かくして彼はティン・パンのライヴにゲスト出演し、翌01年に細野プロデュースによる復帰作『People』をリリース。小坂忠がJ-POPレジェンドとして扱われるようになるのは、それ以降のこと。こうして機関車は、また本線に戻って駆動を始めた。
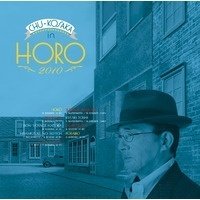
2010年『ほうろう』は、『HORO 2010』として再製される。16chのオリジナル・マスターテープが発見されたため、演奏はそのままに、ヴォーカルだけを録り直したのだ。そこには、長きに渡って魂の歌であるゴスペルを歌ってきた小坂忠の、現在の表現スタイルがあった。“円熟”と言ってしまえば簡単だけれど、それだけでは済まされない表現力の豊かさ、説得力の深さが加えられていたのだ。以前と同じオケで歌う際に一番の難関だった「機関車」も、当然ながら、以前にも増して心動かされる。
きっとこの曲は、作った主を失ってからも、日本のソウル・スタンダードとして、長く歌い継がれていくことだろう。ヒット・チャートには残らずとも、心あるシンガー、ミュージシャンたちから、大きなリスペクトを受けながら…。
忠さん、改めて 安らかに…
