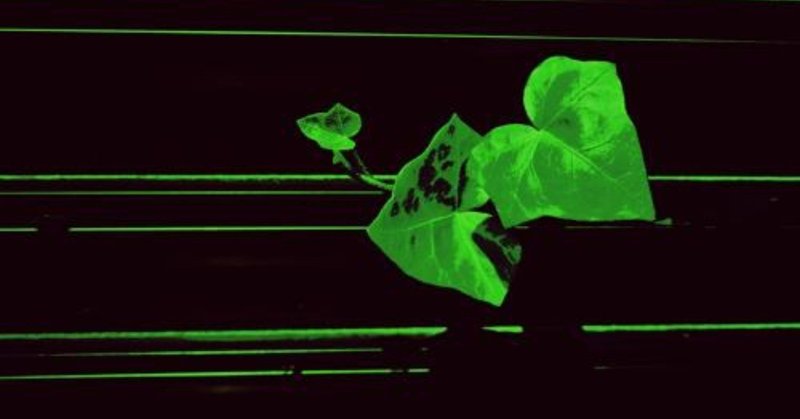
柳の下で
大学三年の冬休みに入ってすぐの日曜日のことだった。
土曜日は前夜(から未明に掛けて)の夜間清掃と五日間の疲れを取る為に、十時くらいまで眠ることにしている。だからエミは午頃に来るのだが、日曜日は午前中から押し掛けてくる。
エミはおれが普段は滅多にしない親切心を起こしたばかりにつき合う羽目になった女の子である。
童女にように幼い外見なのだが、二年半もつき合っているとかなり性根の据わったというか、(見た目よりは)大人の部分もある娘だということが判ってきた。それだけつき合っていれば情も湧くし、周囲に云わせると、見ている方が気恥ずかしくなるくらい仲が良かったそうだ。
だが、今になって思うと、おれはエミに母親の姿を重ねていたのかも知れない。子供の眼から見ても、美しく頼りなくて、何も出来ずに殻に篭ってしまった母親に。
夫が子供に殴る蹴るの暴行をするのを見ていながらも、自分の目の前で繰り広げられている状況から精神的遁走をすることしか出来ず、息子を守ることが出来なかった弱い母を恨んだ訳ではない。
おれの顔は母に似ていた。
母親が美しかったと云っておいて似ていたとは、己れの面が良いと云っているのも同然だが、おれとしてはその顔を剥がせるものなら剥がしたいとまで思っていたのだ。
父は、母に手を上げたりはしなかった。財産目当てで好きでもない女の家の婿養子になり、会社を経営する祖父におべっかを使い、その凡ての鬱憤をおれに向けたのだ。
母親似の己れの顔が余計に父の感情を逆撫でしていると知った時から、母ではなく自分の顔を見るのが厭になった。子供の浅知恵で髪を伸ばし、その顔を隠した。世の中の凡てが恨めしかった。俯いて歩き、他人を睨みつけるように見遣り、どんなことでも受け入れてやろうと自棄糞に生きていた。
中学校に上がって、今井に会うまでは。
おれは、悪意を持って齎される暴行の痛みはまったく感じなかった。父はこすっからい人間だったので、傍から見える処に痣が出来るような殴り方はしない。水泳の教科には、知り合いの耳鼻咽喉科の医師に診断書を作らせ、躰を晒さないようにさせた。
だが、普通の体育の教科だけは、そうもいかなかった。
おれは他の者と時間ずらして更衣室へゆき、いつもひとりきりで着替えていた。制服に隠れた処は痣だらけだったからだ。そこへ或る時、同じクラスの今井という奴が這入ってきた。彼はおれの躰を見て息を呑んだ。
「誰にも云うなよ」とだけ云って、おれは更衣室を出た。
その後、逆に今井の方から呼び出しを受けた。屋上へ来てくれとのことだった。彼は、泣きそうな顔で立って居た。
なんの用かと訊ねたら、あの痣はどうしたのだと彼は云った。おれは「親父の趣味でね」と、半ば茶化して答えた。
「そんなになるまで、なんで黙って受け入れてんだよ。母親は何してんだよ」と、今井は怒鳴るように云った。痛くないんだよ、と本当のことを云うしかなかった。
「痛くない訳ないじゃんか。すげえ痣が出来てるじゃねえか。なんで黙ってるんだよ」
今井はそう云って、おれを抱きしめた。同性愛とか、そういうものではなかったと思う。彼は彼で女の子に興味があったし、おれも男に恋愛感情など抱く人間ではない。
高校時代は無茶苦茶だった。
大学に入って、電車の中でエミに出会った。色々なものが変転してゆき、自分でも戸惑うことが多くなってきた矢先である。
そんなことはどうでもよくて、問題はエミが午飯を持ってアパートを訪れた日曜の午前十一時過ぎのことだ。小便をして便所から出ると、「ケンジ君、見て見て」と云うエミの声に、そちらへ五、六歩進んだと思ったら、いきなり目の前が真っ暗になってしまったのだ。
水滴のようなものが顔に当たって、おれは意識を取り戻した。聞こえてきたのは、「水尾ぉ、ミナオぉ」と喚く男の声だった。うるせえな、と思って目を開けると、今井の顔がどアップで迫ってきている。涙と鼻水でぐしょ濡れになった今井は、おれの名を何度も叫んでいた。そんな近くで大声出さなくても聞こえるよ、と云おうとしたが、何故か声が出ない。そして今井が呻くように云った言葉におれは愕然とした。
「水尾ぉ、なんで死んじまったんだよお」
は? おれ、死んだの? え、うそ。
まじまじと今井の顔を見た。鼻水が垂れて顔にかかりそうだったので、思わず避けたらころんと地面に転がり落ちた。痛みとかはまったく感じない。立ち上がってみると、今井が棺桶に向かって嗚咽している姿が目に見える。周囲のひとびとは皆、喪服を着用していた。
「こんな変梃な七、三分けにしやがって、こんなの水尾じゃねえよ。誰だよ、こんな風にしやがったのは」
彼は中腰になって叫んだ。そりゃどんなんだろう、と思って棺桶の中を覗き込んでみたら、慥かに生きていた時とはまったく違う髪形にされたおれが横たわっている。更に今井は、「大学三年の男になんで高校の制服着せてんだよ。巫山戯てんのか」 と喚いた。
彼の云う通り、棺桶の中のおれは高校の制服を着ていた。しかしそれは高校二年の二学期後半に新調したものだから、現在のおれでもサイズは合っている。小山や伊井垣ら映画研究会の仲間が今井を抱え込むようにして、周りのひとにお辞儀をしながら今井をおれの入った棺桶から遠ざけようとした。が、おれの親父の傍まで来ると、彼は仲間たちの手を振りほどき、
「てめえ、かみさんと二号両手に葬儀に列席とは余裕じゃねえか。息子に謝れよ。土下座しろよ」
と、また喚きだした。おいおい、身内の恥を大声で云うなよ、と声を掛けようとしたが、やはり声は出ない。さすがにこの騒ぎを放ってはおけないと思ったのか、葬儀屋らしき男がふたり寄ってきたが、小山がいつもの愛想笑いで、大丈夫ですから、此方でなんとかしますんで、と云って寺の外に今井を連れ出した。
ところでエミは何処に居るのだろうと思っていたら、「今井さん、大丈夫ですか」と云いながら小走りでやってきた。
彼らの後をついて行こうとした時、ふと微妙な違和感を覚えた。
おれは死んでいる、それは判った。しかし幽霊ってもんはふわふわと浮遊しているものだと思っていたのに、おれは先刻からてくてく歩いている。はて、と思って自分の体を見てみたらば、なんと素っ裸だった。
周りの人間どもはおれの姿を認知していないようだったが、公衆の面前で丸裸というのはどうにも落ち着かないものである。何か身に纏うものはないかと周囲を見廻していたら、はい、という声がして目の前にトランクスが現れた。なんだかよく判らなかったが、取り敢えず一番肝心なところは隠せることに安心し、それを手に取り急いで身につけた。そして更に、はい、という声がして、青い半纏が現れた。
一応それも手にしたが、背中に染め抜かれた赤丸の中にくっきり太字で書かれた「祭」の字。死人、というか幽霊がこんなもん着てたら変じゃねえのか、と思ったが、裸よりはましか、と思い直して羽織った。
映研の仲間らは寺の門の処で今井を落ち着かせようとしていた。エミは、「今井さん、しっかりして下さい。悲しいのはみんなおなじなんですよ」と、今井を宥めていた。えれえ落ち着いてやがるな、と思ったが何しろ声が出ない。しかも、そのむっとした感情が長続きしない。
仕方がないので、一番近くに居たエミの肩に肘を乗せて様子を見ることにした。すると、彼女が頻りに肩を払う仕草をしだした。試しに、「おい、エミ」と呼んでみた。
彼女は弾かれたように斜め後ろ——つまりおれの方を見た。 彼女は目をまんまるにして「ケンジ君?」と云う。他の奴らは今井の方に集中していて彼女の言葉には気がつかなかった。
「おまえ、おれが見えんの?」と、逆にこっちが吃驚して、エミに訊き返した。彼女は大きな瞳に涙を溢れ返らせ、おれに抱きついてきた。やっとエミの異変に気づいた映研の奴らは、「エミちゃん、どうしたの、大丈夫?」と口々に云っている。彼女はそんな声など聞こえていないようで、おれに抱きついたまま、「ケンジ君、ケンジ君、よかった」と云っていた。
よかったのは当人だけで、今井を含め三年の映研部員(総勢おれを除いて四名)は、狂ったようにしか見えないパフォーマンスをしているエミを呆然と眺めていた。
「エミ、ちょっと待て。他の奴らには見えねえみたいだから、もうちょい別んとこ行こう、な」と、おれは彼女の肩を抱いて境内にあるベンチに座らせた。
彼女はいつものようにベンチの端っこに座り、おれはその横に膝を抱えて座り込んだ。それを見てエミは、あはは、と笑った。そして、いつもと一緒だ、と云ってくすくす笑い続けた。そんな彼女の小さな肩を抱き寄せて、「おれ、本当に死んだの」と訊ねた。エミの笑い声がぴたりと止まった。そんなことなど訊かなくても、皆や彼女の黒尽くめの服装で判ってはいた。
別の場所だったらヤクザの集会かとも(無理矢理にでも)思い込むことは出来たが、場所が寺で、自分で見た自分は白木の棺桶に収まっていたのだ。なんともシュールな感覚だなあ、とおれは他人事のように思っていた。
もともと自分自身の肉体的感覚と精神的感覚が遊離しているきらいはあったが、此処までひどい状況に陥った例しがない。というのは今まで死んだことがないからであって、まあ、それは万人がそうであると思う。
「ケンジ君はあたしの目の前で仆れて、お父さんの病院に運ぶ途中……、っていうか、救急車の中で死んじゃったの」
死んじゃったの、っておまえ、ひと事だと思って軽く云ってくれるじゃねえかよ、と思ったが、その軽い怒りも風に吹かれるように消えてしまった。そしておれは、「そうなんだ」とぽつり呟いていた。もっとショックを受けろよ、おれ。
おれの死因は急性心不全で、そんものは中年か年寄りがなるビョーキじゃねえのかと思ったら、若者の突然死の原因は、心不全や心筋梗塞などが多いとのことである。そんなことを話していたら、映研の奴らがエミが心配になったのか近寄ってきた。
すると、いきなり素っ頓狂な声で「ミナオぉ!」と今井が大声を上げた。
「水尾、生きてたのか。なんだよ、おまえー」と、今井はおれに抱きついてきた。明白地に死んでるのにそんな訳ねえだろうが、と思ったが、彼の友情の厚さに今更ながらおれは感激していた。勿論、他の者はぽかんとしている。どうやらおれを認知出来る人間は今のところ、エミと今井だけらしいことが判った。
「今井、しっかりしろよ。そこには誰も居ないぜ。エミちゃんが居るのはその隣だ」冷静に井伊垣が指摘する。周りの者も尤もだと頷いている。
「おまえら見えねえのか。此処に……」
今井が言葉に詰まるのも当然である。おれは祭半纏にトランクスという、幽霊にあるまじき恰好をしているからだ。
「此処に水尾が居るじゃねえかよ」と、ついに今井は云いきった。皆は「はあ?」という顔をしている。エミに続いてこいつも狂ってしまったか、という顔だ。
ところが、一番こういう(現実的な)事態に鈍そうな小山が、「あ、青い服着てる。ミナオが居る」と云った。おれが小山に向かって「よう」と云ったら、「よう、って云ったよ。ミナオが、ミナオが、ようってさあ」と他の奴らの服を摑んで大声で云った。
「ぼんやりとしか見えないけど、ミナオ、おれ見えるよ、おまえのこと。 『ムー』に投稿してやるよ、幽霊は本当に居るってさ」と涙ぐみながら云った。
「それにしても、なんでおまえこんな恰好してんだよ」と、不思議に思って当然のことを今井が訊いてきた。ああ、これか。とおれは半纏の襟元を摘み、
「おまえが びゃーびゃー騒いでるもんで起きたらさあ、棺桶から転げ落っこっちまって、なんだか自分でも訳判んなくてよお。おまえらの後ついていこうとしたらやっと自分が素っ裸だってことに気づいてさ、いくらなんでもこんな姿でうろうろしたくねえなあって思ってたら、トランクスと半纏を誰かから渡されて……」
そこまで云うと、「誰かって、誰よ、っつーかナニよ。宇宙人? 幽霊?」と興奮気味に小山が訊ねた。それしか頭にないのか、こいつは。
仕方なく、「あー、判んねえ」と答えたら、「しょうがねーなあ、おまえ、それでも映研?」と小山は云う。すると残りのふたりが、「おれたちに感知出来ないっていうことは、未確認の知的生物に変化したってことじゃ……」「いや、幽体物質だよ」とか云い合っている。別にどっちでもいいじゃねえか、とおれは思った。
この辺りの感覚は生きている時と変わらないんだな、と不思議な感慨に浸る。ふと横を見ると、エミがおれに凭れて悲しいような満足したような、なんとも表現しがたい面差しで皆を眺めていた。
おれを乗せた黒い車が火葬場へ向かうのを、今井とエミと三人で見送った。他の奴らは葬儀社のひとたちが後片づけをしたり、親族があれこれと動き廻っている処に居ても仕様がないので、帰って行った。
「なんか妙なもんだな、自分の屍体を見送るってのもさ」おれがそう云ったら、「好きなひとが焼かれようとするのを見送るのよりましだよ」とエミが呟いた。おれはエミが葬式の為にひとつに結わえた髪に触れた。こうやって触れるのに、本当は実態のない幽霊だということが、我ながらよく判らなかった。
おれは彼女の髪をひとつに結わえているヘアゴムを、まったく似合っていないので外してやった。彼女の髪から離れた途端、ヘアゴムはおれの指先をすり抜け地面に落ちてしまった。生きている人間に附属しいているうちは触ることが出来るが、ただの無機物になると体を通り抜けてしまうらしい。
エミは落ちたヘアゴムを拾い、「なんで落としたの」 とおれに訊ねた。彼女の前に手のひらを差し出して、「それ、乗せてみな」と云った。彼女は不思議そうな顔をしておれの手のひらにヘアゴムを乗せた。
彼女の手が触れているうちはちゃんと感触があったが、手を離すと奇術のようにおれの手をすり抜けてしまう。エミも今井も、それを見て硬直してしまった。
「どうして? ベンチには座れたのに、なんでこれはすり抜けちゃうの」
エミがやっと口を開いた。
「判んねえなあ。そんなこと云ったら、どうして此処に立ってられるのかってのも不思議だよ」
おれは努めて呑気な口振りで答えた。
「なんでおれとエミちゃんにだけ、おまえがはっきり見えるんだろうな」
今井がひとりごとのように云った。気持ちの問題なのかな、彼は俯いて呟く。エミは涙ぐんだ瞳でおれを見上げた。
「ってことは、おまえはエミは同じくらいおれのことを思ってんのか」からかうように今井に向かって云ったら、「気持ち悪いこと云うなよ」と、おれを小突いて言葉を返した。
でも、おれのことを一番知ってる他人はおまえだけなんだぞ、と思った。
おれの家庭環境、おれの高校時代の滅茶苦茶な私生活、それを知っているのはこいつだけだ。寺の表階段を降りた処で彼は軽く手を振り、じゃあな、と云って去って行った。また会えるかのように。
おれは此処が何処の寺なのか判らないので、エミが手を引く侭ついて行った。結構歩いて地下鉄に乗り、東三区の夢の島ハイツに着き、ああ、おれの菩提寺はあんなに遠かったのかと思った。エミは手を離したら、風船のように何処かへ行ってしまうと思っている子供のように、おれの手をずっと握っている。
エミは合鍵を使って部屋のドアを開けた。その鍵についている赤い鈴は、高校生の頃つき合っていたアキという女がくれたものだった。アパートの建っている辺りは少々物騒だったので、何かあったら勝手に這入れと彼女に渡した時には、特になんとも思わなかった。何かがくっついていれば失くしたりしないだろうくらいにしか思わなかったのである。
それは何処かの縁結びの神社の鈴だった。それを買った時のアキの気持ちを考えなかった。そして引っ越した自分のアパートの合鍵に、特に意味もなくつけた。鈴が鳴れば見つかり易いだろうという、ただそれだけの理由である。 エミはそんな事情も知らずに、それを「ケンジ君のおうちの鍵」と思って後生大事に持ち歩いていた。
アキの気持ちを顧みなかったのと同じように、おれはエミの純粋な気持ちを踏みにじっていたのだと今更ながら思い知った。死んでから思っても仕方がないのだが。
部屋に這入ると、「ああ、救急車呼んだ時のまんまだ。散らかってる」とエミは云った。
「どうせ誰かが来て片づけるからいいだろ」
「駄目だよ。あたし、此処に住むんだもん」そう彼女は膨れっ面で応えた。思わずおれは「は?」と訊き返した。
「そんなことおまえの親が許す訳ねえだろ。こんな旧市に近い処のアパートに住まわす訳ないって。おれだって許さねえよ」
強い口調で云おうとしたが、何故だか穏やかな口ぶりになってしまう。死ぬと激したりするような強い表現が出来なくなってしまうのだろうか。どうしていいか判らず立ち竦んで居たおれにするりと抱きついてきた彼女に対して、一日だけだからな、と云っていた。
二年半つき合っていながら、彼女をこの部屋に泊めたことはない(一度、勝手に泊まってはいるが)。高校時代、必要以上に堕落した生活を送っていた自分を戒める為にも、彼女の親が決めた門限通りに家へ帰していたのである。
エミはおれの送っていた生活と別の次元に生きている存在だった。世の中の汚いものも、不条理も何も知らない無垢な存在におれには思えた。好きでもない男に身を任せたり、好きでもない女を抱いたりという汚らしくて反吐が出そうな世界から遠く離れた世界に住んでいる、妖精のような存在だと思っていたのだ。だが、そんな人間など居る筈がないことも判っていた。
だからエミがおれの自分への態度に不満を漏らした時、別にそれは自然なことであって(つき合ってから一年以上経っていたこともあるし)彼女を地に墜ちた天使だと蔑んだ訳でもない。でもおれは幻想にしがみつき執拗に拒んだ。
男が、しかも十代後半のやりたい盛りの青年が、一年以上も目の前の人参を無視して毛並みを整えていたなんて誰が信じるだろうか。しかし、おれはエミを犯さざるべき聖女のように思っていたのだ。
今井にはエミが同じ大学に入るまで話さなかった。理由は自分でも判らない。彼に隠し事をしたのは、それがはじめてだった。彼に云ってしまうと、エミが「守るべき妹」から「恋人」に変化してしまうような気がしていたのかも知れない。
結局夜になってしまい、「明日は家に帰るんだぞ」と云ってエミを寝室に連れて行った。疲れていたのか、彼女は半時も経たずに寝息をたてはじめた。床に放り出したままになっていた携帯電話を手に取ろうとしたが、川の中のメダカを掬うように実態はすり抜けてしまう。
窓を通り抜けてベランダに出ると、さわさわと人間ではない何かの気配がする。誰か居るのか、とおれは云ってみた。何処からか、
——あなたは死んだのよ、という声が聞こえた。
知ってるよ、と云ったら、
——じゃあ、なんでひとに拘ろうとするの。
「おれには相手が見えるし、向こうもおれを感知してるんだよ。自分と深いつながりがあるから拘らずを得ないじゃねえか」
——生きている人間に此方側の存在が見える訳がない。
「でも、見えてんだよ」
おれがそう云うと、それはおかしい、異例だ、あり得ない、という声がざわざわと聞こえてきた。おまえたちはなんなんだ、そう問うと、我々は死んだ人間の、所謂魂だ、と答えた。お化けか、とおれが呟いたら、まあそういう云い方もある、と誰かが答えた。おれもそうなのか、と訊ねるとさわさわしていた空気が静まってしまった。
暫く経ってふわりと風が起こり、
——生きている人間たちは、我々に幽霊とか妖怪とか適当な名前をつける。しかし、それは生きている者同士の勘違いから起きる錯覚であって、我々は実態を持たない。だから我々を認知出来る者は神というものが存在したとしても有り得ない。我々は何処にでも居るが、生きている者ら、そして我々死する者らにも感知出来ない。
説教師のような口振りの男の声が云う。
「えーと。つまり、生きていても死んでいても幽霊は認知出来ないってことなんだな」と、おれが暗闇に向かって云った。
——そうだ、という返事が何処からか聞こえた。
「じゃあ、エミや今井が見たおれはなんなんだよ」
——それは判らない。おまえは我々の世界の異端なのだ。おまえは生きている人間に自分の存在を現すことが出来る、それは死者にあるまじきことだ。死んだ者同士は自分の隣に居る者が誰であるか、隣どころか重なって居る者すら誰だか判らない。そしておまえのように執着も持たない。おまえは風がそよとも吹かない時に空気を感じたことがあるか、ないだろう。我々はそういった実態を持たないものなのだ。それなのに、おまえは生きた人間に実体を持った者として存在してしまった。おまえを見なかった者にも、見た者からの口伝えにより存在したことになってしまう。
再び説教臭い男の声が云った。
「で、おれはどうすりゃいいんだよ。好きこのんでこんな中途半端な状態でいる訳じゃねえんだよ。成仏するなら成仏するで、あの世とやらにやってくれよ」
——だから、おまえは例外だと云っているだろう。成仏などという言葉は人間が勝手に作ったものだ。三途の川もなければ黄泉の国もない。おまえは焼かれる前にたまたま目を覚ましてしまっただけの、それだけの存在だ。わたしだって万能ではない。その辺をうろついている霊魂に過ぎない。たまたまおまえの問いに答えただけだ。おまえに衣服を与えたのも、たまたまそこに居合わせた霊魂が気が向いて差し出したに過ぎない。それだけのことだ。
慥かに自分の纏っている衣服を見れば、偉そうに喋っている奴が云う通り「たまたま」「気が向いた奴」がくれた服だということがよく判る。なにしろ赤と黒の格子縞のトランクスと祭半纏だ。死装束とはかなり懸け離れている。
いくらなんでもこの身装はねえだろうと思い、「あんたたちがそうやってうろうろしてるんだったら、おれが生きてた頃のことを知ってる奴くらい居るだろ。せめて普段着てた恰好になりたいんだけど」とおれが何もない空間に向かって云うと、寺の時と同じように目の前にカーキ色の作業ズボンと長袖のTシャツが現れた。
悪いね、と云いながらおれはズボンを穿いて祭半纏を脱いでTシャツを着込んだ。半纏はふと見ると、何処かに消えてしまっていた。
普段通りの服装になって、やっと落ち着いてきたおれは、「で、例外のおれはどうすればあんたたちと同じ普通のユーレイになれるのさ」と訊ねた。さわさわと空気が動き、別の声が答えた。
——あなたは、わたし共の想像を遥かに超えた次元に行ってしまっているのです。わたしたちではどうすることも出来ません。
「なんだよそれ。じゃあ、もっと偉い奴連れて来いよ」
そうおれは云った(本当は大声で云いたかったのだが、幽霊の世界では何もかもニュートラルになってしまうようだ)。
——我々の世界では上も下もありません。皆同じレベルにいます。だから重なって、重なって、重なって存在しているのです。いえ、存在しているという表現は誤解を招くかも知れません。わたしたちは……。
「なんだって?」
と、誰だか判らない奴に訊き返した瞬間に、自分の部屋の中に引き戻された。おれのベッドにはエミが布団をかぶって眠っていて、安らかな寝息を立てていた。 暫くその寝顔を見ていたが、時計を見るとまだ四時半だったので、当分起きないないだろうと思い、ふと葬式で泣き喚いていた今井のことを思い出した。
すると、いつの間にか彼のアパートのごちゃごちゃした部屋の中に居た。彼はなにやら大判の本を開いて項垂れている。
「何やってんだ、おまえ」と声を掛けたら、彼は弾かれたように声のする方、つまり、おれの方を見遣った。おれの方を見ているということは、どうやらこいつにはまだおれが認知出来るらしい。
「ミナオぉ、吃驚させんなよー」と、今井はいつもと変わらない調子で答えた。
「なんだそれ、アルバムか」
「ああ、中学と高校の時の卒業アルバム見てたんだよ」と今井は答えた。古いフォークソングみたいだな、と云ったら、「まあな」と照れくさそうに彼は苦笑いを浮かべる。こんな明け方になんでまたそんなもん見てんだよ、と訊ねたら、「先刻までおまえの追悼会やってたんだよ」と今井は云う。
「木島の時みたいに単なる飲み会になったんだろ」からかうように云ったら、そうでもなかったよ、と彼は呟いた。
「おまえは、なんつーかその……、強烈な印象があるってーか、なんだ、その……」と口籠ってしまった。
「誰もおまえがこんな形でぽっくり逝っちまうなんて思いもしなかったんだよ、おれもだけどさ。なんかおまえは殺しても死なないような感じだったし……」今井は言葉を継いだ。随分な云われようだな、と思ったが、悪気があって云っているのではないことくらい判るので、それに関しては黙っていた。
「でも、おれは死んじまったんだし、それはどうしようもないじゃん。で、さっき他の幽霊に聞いたんだけど、こうやって生きてる人間に見えちまうのは例外なんだってさ」
おれの言葉を聞いて、今井は「おまえ、 幽霊と会ったのか」と、おれの腕を摑んで興奮気味に云った。
「いや、声が聞こえただけだよ。本来幽霊ってのは生きてる人間にも幽霊同士でも姿が見えねえんだってよ。だからおれは例外だって云われたんじゃねえか」
なんだ、と彼はつまらなそうに呟いた。
「あのなあ、おまえが見てるおれだってユーレイなんだぜ。 そこんとこ、判ってんのか」
「そんなこと云ったってよー、ミナオみたいに生きてる時のまんまの姿で膝抱えて座ってられたら、幽霊とは思えねえんだよ」と云って、おれをまじまじと見ると、「おまえ、どうやって服着替えたの」と今更ながら訊ねてきた。
「ああ、これか。いくらなんでもパンツ一丁に祭半纏羽織ってるのも調子が狂うっていうか、落ち着かねえから普段着てたような服くれっつったら、誰かがくれた」
それを聞いて、彼は気が抜けたように、はあ、と溜め息とも吐息ともつかない声を漏らした。
今井はひと息つくように煙草に火を点けた。そして、おれの方を見て「ミナオも喫うか」と煙草を寄越した。煙草の箱はおれの手をすりぬけて床に落ちた。彼は涙ぐんで、無理みたいだな、と呟いた。「いいよ、別に喫いたくねえから」と半分慰めるように云ったら、あんなにヘビースモーカーだったのにな、 と今井は目を擦った。
「なんかなあ、腹減ったとか、何したいこれしたいっていう慾求がまったくねえんだよなあ。幽霊だからかな」おれの言葉を受けて、彼は煙草の烟りを吐き出し、「まあ、そういうもんなのかな」と呟いた。
「ああ、そうだ。おれ、おまえに頼みたいことがあってさ。別に幽霊談義をしに来た訳じゃねえんだよ」とおれが云ったら、「おれはなんにも出来ねえぞ、云っとくけど」と、手を振って話を遮った。
「難しいこっちゃねえよ。エミがさあ、おれのアパートに住むって云ってんだよ。それを止めて慾しくてさ」それを聞くと彼は、腕を組んでうーんと考え込んでしまった。
「エミちゃんの気持ちは判らなくもないけど……。そういう後ろ向きな行動はどうかと思うなあ」
その言葉に飛びつくように、「そうだろ、健全な発想だとは思えねえだろ」とおれは彼の肩を摑んで云った。煙草の箱と違って今井の肩の感触は判ったが、体温を感じることは出来ない。自分の現在の状況が判らな過ぎて、どうにかなりそうだった。
「でもさ、おれじゃなくておまえが説得した方がいいんじゃねえのか。エミちゃんだってミナオの姿が見えるんだから」
彼の云い分は尤もだが、おれとしては死んだ人間が云うより生きている奴が云った方が説得力があるように思えたのだ。
なんとか今井の承諾を得て、エミの居るアパートに戻った。戻る、というより思い出す、という言葉の方が近い。移動している感覚はまるっきりないのだ。ああそうだ、と頭に浮かぶのと同じで、既に知っている物事を思い浮かべるのにいちいちああだこうだと考えないのと一緒である。
エミの寝ている部屋はまだ暗かった。時計を見たら六時近くで、冬なのだから夜明けまでまだ間があった。今井の処にそんなに長居していたのか、とおれは思った。幽霊だから時間の感覚が違うのだろうか、と思ったが、自分と同じように向こうも喋っていたのだからそういう訳でもないか、と思い直した。
ベッドを見ると、彼女はまだ眠っていた。ベッドの脇にしゃがんで彼女の顔をじっと視つめて、目を覚ましておれのことを認めなかったらどんな気持ちがするだろうかと考えてみた。辛いだろうか、悲しいだろうか、それともそんな感情など消えてなくなっているのだろうか。
頬に掛かった髪の毛をうしろへどかしてみた。エミの髪はちゃんとおれの手の動き通りにうしろへ流れていった。何故かそのことがものすごく切なく感じられた。
台所の方の部屋に行ってぼんやり壁に凭れてこれまでのことを考えてみた。おれはこの部屋に這入るか這入らないかの処で意識がなくなった。慥かエミに何かを見てと云われ、そちらへ向かおうとしていたのだった。何を見せたかったのだろう。ゴキブリか? ゴキブリだったらキャーとか云う筈だな。
で、気がついたら今井が泣き叫んでいて、鼻水が顔に掛かるのを避けたら棺桶から転がり落ちたのだ。そう考えると、こんなことになった元凶は今井にあるのではないか、と思えてくる。
あいつがあんなに大泣きしなければ、おれは幽霊として目覚めることもなく、火葬場で焼かれてただの骨の欠片になっていたのだ。恐らくそうなっていれば意識も何もなく、この世に生まれる前と同じ無に帰っていた筈だ。そうすると、普通にしていれば幽霊なんかにならずに済む訳か。
幽霊はうじゃうじゃ居るようなことを云っていたから、死んだらもれなく幽霊になるのかと思っていたが、そういう訳ではないようだ。
「誰か居る?」誰も居ない部屋で声に出してみた。なんとも滑稽というか、ちょっとアブないひとのようである。
——なんですか。
という返事を聞いて、自分で声を掛けておきながら、やはり吃驚した。
「あのさあ、こう色々考えてみたんだけど……」と、返事をした幽霊に自分の考えを伝えた。幽霊は(おれも幽霊なのだが)だいたいそれで合っている、と答えた。通常ならば死んだらそこで何もかも終わってしまい、意識も思考も、何も残らない。幽霊になる確率はかなり低いらしく、大抵の死人は静かにこの世から消えてゆくらしい。そして、幽霊と謂えども何処へでも出没出来る訳ではなく、生前行った場所にしか移動出来ないそうだ。
つまり、おれがエジプトの写真を見て、ちょっくら行ってこようか、と思ってもそれは無理なのだ。無機物をすりぬけてしまうのはそれを必要としないからで、床とか地面を突き抜けてしまわないのはただ生前の行動をトレースしているだけで実は浮いているのだそうだ。
「でも、おれは床とか地面の感触は判るんだけど。今だって壁に凭れてるし」と幽霊に云うと、なにしろあなたは例外ですので、と答えた。なんでも 例外だって云や済むと思ってるな、こいつら、とおれは腹立たしく思った。が、やはりそのむかついた感情はすっと消えてしまう。
「で、相手の考えが判ったりとかしないの」 と訊ねたら、幽霊同士でも生きている人間でも思考を感知することは出来ないと答えた。
「はあ、つまんねえもんだな幽霊ってのは。じゃあ、お化けを見たっていうのはあれか、『幽霊の正体見たり、枯れ尾花』ってやつか」そうおれが云うと、その通りですね、と幽霊は答えた。
「なに、ひとりごと云ってるの」と、エミがこちらの部屋に這入って来た。幽霊は、じゃあわたしはこれで……、と黙ってしまった。黙っただけでその辺に居ると思うと変な感じがする。
彼女はおれの隣に同じように膝を抱えて座り、「なに喋ってたの」ともう一度訊いてきた。幽霊と喋っていたと答えたら、「まだそこに居るの」と怯えておれにしがみついてきた。
「判んねえな、おれにも見えねえから」
見えないの? と彼女は不思議そうにおれの顔を見つめた。
「喋ってるのは聞こえるんだけど、姿は見えないな。それにおまえユーレイって聞いたら怖がったけど、おれもれっきとした幽霊だって判ってるのか?」
「判ってるよ。ケンジ君が仆れたのを見たのも、救急車の中で隊員のひとたちが必死に蘇生しようとしても駄目で、ご臨終ですって云うのを聞いたのもあたしなんだから」
泣きそうな声で話す彼女の肩を抱いて、「えらい目に遭わせちまったな。わざとやった訳じゃないんだから勘弁してくれよ」そうおれが云ったら、「許さないよ。一生許さない」と強い口調できっぱり答えた。
彼女がそんな口の利き方をしたことなど今までなかったので、少し驚いた。
「じゃあ、どうすりゃいいんだよ」彼女の顔を覗き込むようにして訊ねたら、「あたしの前から消えないって約束して」とおれの目を見据えるようにして云った。なんと答えればいいものやら見当がつかなかった。適当に「いいよ」と云える雰囲気ではなかった。
幽霊たちが云うように、おれが彼女や今井から見ると実体があるかのように存在してしまっているのは、あくまで「例外」なのだ。いつまでこの状態が続くか現役の幽霊たちにすら判らないのだから、おれに判る訳がない。
おれは頭を掻いて、「悪いけど、それは約束出来ない」と本当のことを云った。おれを視つめたままだった彼女の目に見るみるうちに涙が溜まり、ぽろぽろと溢れ出した。困った事態になったもんだ、とおれは溜め息をついた。
今井がやって来たのは、朝の九時頃だった。
「今井さん、どうしたんですか、こんな早く。それになんであたしが此処に居るって判ったんですか」と、エミは戸惑いを隠しきれない様子で云った。なんと返答していいか判らず、えーと、とか云っている今井に代わり、「おれが呼んだんだよ。おまえを説得してくれって」と説明した。
彼女はおれの方に向き直り、 「説得ってなに? あたし、説得される覚えなんかない」と怒って声を上げた。
「やっぱおれ、帰るわ」今井が玄関から出て行こうとするのを、おれは慌てて腕を摑んで止めた。
「今の聞いただろ、おれひとりじゃ無理だって」
壊れた炬燵を三人で囲み、ふたり掛かりで彼女に此処に住むのはやめろと説得したが、話は堂々巡りするばかりで埒が明かない。終いには、「エミちゃん、顔に似合わず頑固だねえ」と今井が感心したように云う始末だった。
そこへチャイムの音が鳴り響いた。彼女はおれたちから逃げるように立ち上がり、インターホンに向かってはい、と云った。ああ、エミちゃんだったのか、と云う低い声が聞こえてきた。
「ナオキさん、恰度よかった」ドアを開けようとしたエミに向かい、「馬鹿、開けるな」と云ったが遅かった。
「恰度よかったって、なんかあったの」と云って部屋を覗き込んだ隣人の来河池は、おれの方をじっと視て、バタンとドアを閉めてしまった。彼女は「ナオキさん、どうしたの? 這入ってきてよ」とドアの向こうに話し掛けた。ドア越しに、そこに誰が居るのかとクルは訊いてきた。
「大学の先輩の今井さんと……」いつも通りの口調で答えるエミの声を遮るように、「と、ってことは、まだ誰か居るんだな」と怯えた声でクルは訊ねた。
「ケンジ君が居るだけだよ」彼女はなんでもないように続けた。「ミナオは死んだんだぜ。おれは昨日の葬儀に列席して、棺の中のあいつをこの目でしっかり見た」と云うクルの声は、完全に慄えている。
へえ、あの図太いクルもこの手のことには弱いのか、と思うと可笑しくなってきた。とにかく上がって、と彼女は無理矢理ドアを開けた。色白の顔を更に蒼白にして、エミに手を引かれてよろよろとクルは部屋の中に這入ってきた。明白地におれから顔を背けている。
「ああ、思い出した。おまえが云ってた低音の美少女ってこいつか」と、クルを指さして今井が云った。
「ひとのこと指さすんじゃねえよ。誰だよ、あんた」クルは今井を睨みつけた。
「ああ、ごめん。おれはミナオの友達で今井というもんです」
ああ、そう、と答えたクルは、覚悟を決めたのか開き直ったのかどうか知らないが、やっとおれを直視した。「こいつは來河池っての」おれが今井に紹介すると、「呑気にひとのこと紹介してんじゃねえよ。なんでおまえが此処に居んだよ」と云って、來河地はポケットから煙草を取り出した。
おれがかい摘んでことの次第を説明するのを、クルは黙って煙草を喫いながら聞いていた。
「じゃあ、おまえは生き返ったんじゃなくて、正真正銘の幽霊なんだな」と頭を抱え、クルは呻くようにして云った。
「生き返られる訳ねえじゃん。おれの体は解剖されて、内蔵なんかむっちゃくちゃに詰め込まれてたんだぜ」と云うおれに向かい、手のひらを向け「そーゆー生々しい話はやめてくれ。おまえがユーレイだってことを受け入れるだけで、おれは気が変になりそうなんだ」と弱々しく呟いた。
「ところで、おまえみたいな何しても起きねえ奴が、こんな早くに起きてんのはどうした風の吹き廻しだよ」とおれは訊ねた。
「自分でも判んねえけど、なんか目が覚めちまってベランダに出たら、おまえの部屋の方から話し声がするから不審に思ってよ」はあ、そういうことか、とおれは納得した。
「で、朝っぱらからなにを揉めてたのよ」
クルの言葉で、やっと話が元に戻った。事情を説明すると、「なるほどね。で、エミちゃんとしてはおれに味方して慾しい訳だ」とエミの顔を意味ありげに視つめた。
「まあ、彼女も大学生なんだし、ひとり暮らしを経験してみるのも悪くないんじゃねえの」というクルの言葉に、彼女の顔はぱっと明るくなった。
「今はもう居ない恋した男の暮らしてた部屋に住むなんて、恋愛映画のヒロインみたいじゃん。それに、おれとしてもむさ苦しい男が隣に住んでるより、エミちゃんみたいな可愛い娘が住んでる方が色々と楽しいしね」
クルは彼女の目を覗き込んでにたりと笑った。 その口調と表情で、彼女の決意がちょっと揺らいだように見えた。こういう説得の仕方もあったのか。さすがひねくれ者のやり方は違うなあ、と変なところで感心してしまった。
「越してくればいいじゃん。おれが百人分くらい歓迎してやるよ」クルは駄目押しの一言を、エミにすり寄りながら囁くように云った。彼女はとうとうおれに縋りついてきた。おれと今井は顔を見合わせて笑い出した。そこへまたチャイムの音が鳴った。
彼女がインターホンで応対すると、エミちゃん、 やっぱり此処に居たのね、という聞き覚えのある女性の声がした。「お母さん……」と、気まずそうに云ったエミの言葉で、ああ、彼女のおっかさんの声だったか、と思い出した。エミが恐るおそるドアを開くと、ベージュの上品なコートを着た彼女の母親が立っていた。
「ケンジさんが亡くなって悲しい気持ちは判るわよ。でも黙って外泊するなんて、お母さんどれだけ心配したと思ってるの」
彼女の母親は怒るどころか、娘の髪を愛おしそうに撫でながら穏やかに話した。エミも素直に謝っている。さすが箱入り娘、とクルが小さい声で云った。
部屋の裡に視線を移したおふくろさんは、男がひとりと、黙っていたのでクルのことは女の子だと思ったであろうが、兎に角、娘がひとりで居た訳ではなかったことに少し動揺していた。どうやらおれの姿は見えないらしい。
「この方たちは、どなた」とおふくろさんはエミに訊ねた。
「大学の先輩の今井さんと、お隣の來河池さん」彼女が彼らを紹介すると、何を思ったのかクルはおれの腕を摑んで半ば引きずるように玄関へ行った。
床にべたっと横たわっているおれの腰に足を乗せて、「どうも、はじめまして。ミナオ君の隣人の來河池と申します」と、來河地はやけに丁寧に挨拶をした。
おっかさんが「まあ、ご丁寧に。わたくしはエミの母でございます」とお辞儀をしたら、クルがおれの腰に足を乗せているのが目に入ったようだった。しかし、おれが見えないおふくろさんには、目の前の男か女か判らない人間が意味もなく片足を上げているようにしか見えないのである。
「あの、何故片足を上げていらっしゃるんですか」疑問を口にしたおふくろさんに、「今に判りますよ」と、クルは何やら含みのある云い方をした。
こいつ、なに考えてんだ。幽霊を見て発狂したのだろうか。おれを横仆しにして踏んづけている状況が理解出来ないらしく(おれも何がなんだか判らなかったが)、エミはぽかんとしてクルとおれを交互に見ていた。
「つかぬことをお伺いしますが、あなたは……、男性?」そう訊ねられ、「ええ、男ですよ。なんなら証拠を見せましょうか」至って真面目な口調でクルは答えていた。おふくろさんはすっかり困惑してしまい、いえ、とんでもない、困ります、と云って顔を手で覆ってしまった。そこでクルは、いきなりエミの母親の腕を摑んだ。クルの行動の真意が計れず、部屋は暫く沈黙に覆われた。
「お母さん、おれの足許をもう一度見て下さい」やっとクルが口を開いた。云われた通りおふくろさんはクルの足許を見て、「ケンジさん、あなたどうして……」と云ったきり気絶してしまった。エミが母親の肩を揺すって、「お母さん、お母さん」と呼びかけている。
クルは漸くおれから足を降ろし、「吃驚して気絶する人間て、本当に居るんだなあ」と呑気に云っていた。「おまえだって先刻まで今にも気絶しそうな顔してたじゃねえか」おれは立ち上がってクルの肩をどやしつけた。
「で、なにが起こったんだよ。先刻までおれが見えなかったおふくろさんが、おまえが腕を摑んだだけで、どうして急に見えるようになったんだ」と訊きながら壊れ炬燵に戻った。
「あれは……、科学実験みたいなもんだよ。おまえを認識しているおれがおまえに触れた状態でエミちゃんのお母さんに触ったら、おまえからおれへ、おれからお母さんに一種の情報が伝わるんじゃないかと思ってさ。つまり、おれはおまえとお母さんの間を繋ぐ触媒の役目をした訳」
理屈は判らないでもないが、そう簡単にこの件が片づくとは思えなかった。だいたいクルのやり方がどの場合に於いても通用するなら、エミと手を繋いでそこら辺を歩き廻り、彼女が道行くひとに触れていけば、誰もがおれを認知するようになってしまう。そんなことにはまずならないと、根拠はないが確信出来た。
エミの母親はじきに意識を取り戻した。よく考えてみたら、おれはこともあろうに彼女の母親がぶっ仆れているのを玄関に放置していたのである。おふくろさんは彼女に促され部屋の裡に這入り、事情を聞かされて、
「じゃあ、此処に居るケンジさんはゆ……うれい、なの」と、娘に訊ねた。うん、とあっさり答えたエミを呆然と見つめた後、「で、あなたはこのアパートに住みたいと云って、ケンジさんを困らせているのね」とおふくろさんはやれやれといった感じで云い、おれに向かって 「すみませんねえ、我が侭な娘で……」と頭を下げた。
「いや、まあ、お母さんが来てくれたんならエミも云うことを聞くでしょうから」とおれは頭を掻いた。つき合っている女の子の親というのは、どうにもやりにくい。
「見ての通り、うちの隣にはこういう得体の知れない奴も住んでいますし、娘さんにとっていい環境とは云い兼ねるんで……」おれがそう云うと、「得体の知れないってどういう意味だよ。おれはおまえよりよっぽど得体が知れてるぜ」とクルが混ぜ返した。
「このどアホ、せっかく話が纏まりかけてるのに茶々入れるんじゃねえよ」と、つい普段通りの言葉遣いで喋ってしまった。目を丸くしておれを見ているエミの母親に、
「いえ、今の会話は置いといてですね、取り敢えず彼女を家に連れて帰って貰えませんか。此処もうちの親が引き払いに来るでしょうし」そう云ってから、彼女に「此処の鍵、出せよ」と促した。
「あなた、ケンジさんの部屋の合鍵なんて持っていたの」と、おふくろさんは素っ頓狂な声を上げた。彼女は黙って葬儀用の黒いバッグから赤い鈴のついた鍵を出して炬燵の上に置いた。
「あれ、この鈴……」と云いかけた今井の口を塞いで、「クル、この鍵、おまえから大家に返しといてくれよ」と来河池に頼んだ。ああ、それは構わないけど……、とクルは鍵を取り上げた。エミは、鍵が完全に自分の手から離れてしまったことに動揺しているようである。
「エミちゃん、此処に来たかったらいつでもおいでよ。別におれんとこじゃなくても、おばさんとことかさ」とクルは慰めるように云った。
タクシーを呼んでエミとおふくろさんはアパートを去って行った。三人でそれを見送って、何故かまたおれの部屋に戻った。鍵はクルが開けた。
「なんでおれの部屋に戻るんだよ」と云うと、ふたりして「いや、なんとなく」と答えた。
「で、おまえはこれで良かったのか」と、今井が云った。
「良いも悪いもねえだろ。おれは死んじまったんだし、あいつにどうしてやることも出来ないんだから」
そうなのである。いくら目に見えるとはいっても、おれは死人なのだから執着されても困るのだ。コードの千切れた襤褸い炬燵を囲んで、おれたちは暫く沈黙していた。
「おまえら、あんなに仲良かったのになあ」と今井は呟いた。遠い目をするなよ、と思ったが、まあ死んだ者を思う時は誰しもそういう眼差しになってしまうものなのだろうか。
「そうだよなあ、はたで見てても気色悪いくらい仲良かったもんな」とクルも同意した。
「おれがはじめてエミちゃんに会ったのは入学式の時だったけど、なんつーか、妖怪が天使連れて歩いてるみたいでさ、めちゃくちゃ違和感あったもんなあ」と云う今井の言葉に、「そうそう、おれがはじめて見た時もさ、どっかから誘拐してきたと思ったもん」とクルが応じた。もう、それからはおれとエミに対して感じたことを、ふたりで云いたい放題である。
「新歓コンパで居酒屋に行った時もさあ、別にベタベタしてるとかそんなんじゃないんだけど、なんかこっちが赤面しちまうっていうか、引いちまうくらいでさ。長年こいつとつき合ってきたけど、女の子にあんなに自然に優しく出来るとは思わなかったなあ」「何したのさ」「何って、うーん……。ああ、エミちゃんが焼き鳥のつくね喰ったらさ、口の端にタレがついたんだよ。それをフツーに、こう親指で拭ってぺろっと舐めてさ。おれたちどう反応していいか判んなくてよー。酔ってた勢いもあって、ぎゃーってなっちゃって。何やってんだよ、おまえ、みたいな」「はあ、そうか。ん、思い出した。あんた、あれだ、ミナオの元彼」「誰に聞いたんだよ、それ」「エミちゃんが云ってた」「サークルの奴らが巫山戯て云ってただけだよ。あの娘が入部するまではおれがからかわれてたけどさ、エミちゃんが来てからはもう、冷やかしまくりだったなあ。ミナオが彼女が入部するってんで部室を徹底的に片づけたんだよ、それで恨まれてた部分もあるけど」「なんかやばいもんでもあったの」「やばいっていうか、エロ本とかがあったんでそれを問答無用で処分したから。恋人同士っていうより、保護者が子供の相手してるみたいなところはあったけど」「ああ、判るわかる。この隣に引っ越してきたおばさんのとこに、なんでか必ず週末に晩飯喰いに行くようになったんだけどさあ、まあ、料理作んのはおれなんだけど。鍋作りゃかいがいしく鉢によそってやるし、いちいち旨いかどうだとか訊くし、もう見てる側としては勝手にやってくれよって感じだったもんな」「飲み会に行くと箸まで割ってやってたからなあ。そこまでする必要あるのか、ってことまでしてやってたから」「そうだよな、外見からはとてもそんなことするような奴には思えないんだけど」「高校時代はもう、外見通りの荒んだ生活してたからよー、こいつこの先どうなるんだろうって心配したからなあ。エミちゃんのおかげでやっと人間らしい部分を取り戻したかと思った矢先にこれだもんな。運命って残酷だよな……」
と、しんみりとなったところで、漸くおれは口を挟んだ。
「なんか色々云ってるけどよ、おれとしてはまだ生きている時とそう変わんない状態なんだから、ひとを肴にしてくっちゃべって慾しくねえんだけど」
それを聞いて、ふたりは「悪いな」と揃って云った。
「で、おまえはこれからどうするんだよ」と訊ねる今井に、「そうだな、取り敢えずエミの様子を見て……」と云ったか云わないうちに、おれは彼女の家のリビングに立っていた。こういうのは便利なようで便利じゃない。というか、この場合ははっきり云って困った。何故ならば、目の前に彼女の母親が居たからだ。
「ケンジ……さん?」と、おふくろさんはおれのことを怪訝そうに視つめて云った。ぶっ仆れなかっただけマシかも知れない。ああ、どうも、と間抜けな返事をして、その場を取り繕った。「どうして此処に?」と訊ねるおふくろさんに、いやあ、ぼくも幽霊の初心者なんでよく判んないんですけど、と答えるしかなかった。我ながら馬鹿みたいである。
エミはどうしてますか、と訊ねたら、「今、お風呂に入っているんですよ」と云っておふくろさんはぴたりと動きを止めた。 「まさかケンジさん、お風呂場にも自由に出入り出来るんじゃ……」と恐るおそるおれに訊き返した。
「いや、生前行った処にしか行けないらしいんで、風呂場を覗いたりは出来ないと思いますよ」とおれは答えた。例外的な存在だから必ずしもそうとは限らなかったが、そんなことを正直に云う馬鹿は居ない。そこへ風呂から上がったエミがタオルで髪を乾かしながらやってきた。
「あれ、ケンジ君、どうして此処に居るの」と訊いてきた。喪服から普段の恰好に戻っている。 タートルネックのセーターにスカートを穿いたいつもと変わらない彼女を見ると、ますます自分が生きていないのだということが実感しがたくなってきた。
「いや、なんとなくおまえのことが気になって」
「うちにも来れるんだ。じゃあ、無理にケンジ君のアパートに住まなくてもいいかな」と、彼女は嬉しそうにおれの腕に取り縋ってきた。そう考えるなら是非そうしてくれ、と云いたかったが敢えて黙っていた。
おれとエミが三人掛けのソファーに座っていると、おふくろさんが紅茶を運んできた。紅茶を卓子に置くと、向かい側の二脚置かれたひとり掛けのソファーに腰掛けて、「どうぞ、召し上がってくださいな」と云う。おれは頭を掻きながら、
「いや、ご親切は難有いんですが、ぼくはこういうものはもう必要ないんで……」と云って、ほれこの通りとばかりにティーカップの中に手を素通りさせてみせた。また気絶するんじゃないかと思ったが、興味深そうにその様子を眺めて、「まあ、そんな……。ああ、でも考えてみれば幽霊がなにかを飲んだり食べたりする訳ありませんわね」とすんなり納得してくれた。
前まえからちょっと変わったひとだとは思っていたが、それがこういう時に役に立つとは思わなかった。
「じゃあ、これはお下げしますわね。まるで陰膳みたいでケンジさんも気分が悪いでしょうし」と、おれの前に置いたティーカップを盆に乗せて台所へ戻って行った。おれはエミに向かって、「おまえのおっかさんって、だいぶ変わってるな」と云ったら、「そう? 別に普通だと思うけど」と答えた。あれが普通だと思っている人間に何処が変だとも説明しかねるので、まあそうか、と誤魔化しておいた。
彼女がおれのアパートに引っ越すのはやめるということを伝えると、ほっとしたようにおふくろさんはソファーに身を沈めた。
「よかったわ。あなたのような世間知らずがひとり暮らしなんて、まだ早すぎるもの」
そう云う母親を見て、あんたもおれからするとかなり世間知らずに見えるんだけどな、と思ったがそんな失礼なことは勿論云わなかった。そして、お父さんに連絡しちゃったけれど、諦めたっていうことは帰ってから云えばいいわね、とひとりごとのように呟いた。
しまった、とおれは思った。此処に居る以上は親父さんとも顔を合わせなければならないことを失念していた。あのおっさんは悪い人間じゃないのだが、どうも苦手だった。しかし、医者なんていう常に非情な現実と常に向き合っている人間が、おれを認知出来るとは思えない。まあ、心配する必要はないか、と思っていたらなんということだろうか。帰宅したエミの親父さんは、はじめのうちはおれを認知出来なかったが、愛娘の頭を撫でながら「おお、ちゃんと帰ってきたか」などと云って、何を思ったのか知らないが、ふとソファーの方を見遣った。
そして、自分の視線の先に居るおれの姿を認めてしまったのだ。この場合はエミが触媒の役割を果たしたことになるのだろうか。
「ケンジ君、君はいったい……」親父さんは鞄を取り落として立ち竦んでいた。おれは仕方なく「どうも、お邪魔してます」と云った。
四人で囲む食卓は実に奇妙な雰囲気に包まれていた。おれの前には何も置かれおらず、三人は黙々と食事をしている。膝を抱えてその様子を見ていたら、やはりおれはこの世に居なくて、彼らに見えていると思ったのはただの願望が見せた幻覚だったのかな、と思えてきた。そこへエミが、
「ケンジ君も食べられるといいのにね」
と要らぬことを云ってぶち壊しにした。親父さんは咳払いをして、おふくろさんは「エミちゃん、そんなことを云ったらケンジさんが困ってしまうでしょ」と云った。
この時ばかりは彼女の母親に賛同した。無邪気にもほどがある。食事が終わると、親父さんはケンジ君に話があるからエミは自分の部屋に行ってなさい、と云った。
厭な予感がする。
居間の卓子を挟んで向かい合い、暫くは互いに黙り込んでいた。
「ケンジ君」親父さんはやっと口を開いた。「君は死んでいる、そうだね」と、静かに云った。「ええ、そうですね。死んでます」と答えるしかなかった。
「では、何故そこに居るのかね」
まあ、しごく尤もな質問である。
「いやあ、実際のところはぼく自身もよく判らないんですが、どうも幽霊になってしまったようで……」
おれの言葉を受けて、親父さんは眉間に皺を寄せて考え込んでしまった。医師というリアリズムの世界にどっぷり浸かっている親父さんは、目の前の事実とこれまで築き上げてきた世界観の狭間で苦悩しているようである。
「まあ、君の遺体の解剖にも立ち会っているから、死んでいることには間違いないが、妻にもエミにも君が生前と変わらぬように見えていることも一時的な錯乱からくるものではないようだ。……しかし長年医療に携わってきたが、こういうケースにぶつかったことは一度もない」親父さんは苦虫を噛み潰したような表情で云った。
「はあ、そうですか」と答えながら、おれは少し失望した。医者なら死人を大勢扱っているのだから、直接でなくても噂くらい聞き知っているかと何処かで思っていたのだろう。
ううむ、と唸って、「この状態は、はっきり云って娘の精神衛生上、非常に良くない。 君もそう思うだろう」思います、と正直に応えた。
「君は見かけと違って、極めて常識的な人間だとわたしは思っていた。ちゃんと門限通りに娘を帰してくれる若者など今時おらんし、エミの口からも君については色々と聞いている」
色々って、あいつ何処から何処まで親に喋ってたんだ。
「答えにくいかもしれんが、君は……、その、なんだ、エミと同衾したのかね」
親父さんは身を乗り出し、小声でおれに訊ねてきた。ドーキン? ああ、同衾か。えらい古くさい云い廻しで訊いてくるなあ、と思ったが、親からしてみれば娘とセックスしたかとは訊き難いだろう。
「そりゃまあ、二年半近くもつき合っていればそういう事態にもなりますねえ」ついそう答えてしまった。親父さんは天井を見上げ、身も世もない、というような呻き声を上げた。
「あの、云っときますけど、お嬢さんが高校を卒業するまではいっさい手を出さなかったので安心して下さい」そう自分で云っておきながら、親にしてみりゃ安心もへったくれもねえか、と思った。
「云い訳するようで心苦しいんですが、ぼくとしては娘さんと関係を持つつもりはまったくなかったんです。 向こうから押し切られたというか、なんと云うか……」おれが口篭っていたら、「つまり、何かね。エミの方から……」と親父さんが顫える声で訊ねてきた。
「まあ、済んだことはいいじゃないですか。要するに同意の上でそうなったんであって、ぼくが手篭めにした訳じゃないんですから。それにぼくはこんな外見をしていますが、至ってノーマルな人間なので、彼女に変態的行為を働いたこともありません」
それを聞いた親父さんは、「へ、へ、へん……」と発狂しそうな顔つきになった。余計なことを云っちまったな、と思ったが、云ってしまったものはもう取り戻せない。
「してないって云ったんですよ、お父さん。だいたい、中学生が小遣い銭慾しさに売春する世の中じゃないですか。どちらかというとエミみたいに無菌培養されたような娘の方が珍しいくらいで……」
親父さんは落ち着いたようで、普段より少々気難しい顔に戻り、「うむ、ちょっとあの子を世の中の厳しさや汚さから遠ざけ過ぎていたことは判っている。親としては反省すべきかも知れん」と、腕を組んで云った。ちょっとどころじゃねえんだけどなあ、と思ったが、これ以上刺激するのは不味いと思って黙っていた。
「話は君のことに移るが、葬儀の時に君の学友がご両親に喚いていた内容が気になるのだがね。彼は病院でも解剖に反対して、土下座してまでやめてくれと云ったのだが、君はどんな育ち方をしたのかね」親父さんはエミとおれに関しては諦めたのか気が済んだのか、話題を変えた。
「ああ、あれはですね、あの喚いていた奴はおれ……、ぼくが中学生の頃からの親友でして、うちの事情も知っていたからあんな醜態を曝してしまっただけで、頭がおかしい訳じゃないんですよ」親父さんは身を乗り出し、「聴きの姿勢」になってしまったので、仕方なく我が家の事情を説明した。
中堅企業の社長令嬢だった母親に財力目当てに近づいた挙句、おれを孕ませて、まんまと水尾家に入り込んだ親父のこと。結婚してしまえば用がないとばかりに家庭を顧みず、外に女を作り、ことあるごとにおれを殴っていたあの男。そんなをことを話していたら、当時の様子がありありと思い浮かんできた。
ガキの頃、公園で蝉の抜け殻を見つけた。そのガラス細工のような美しさに心を奪われ、見つける度に持ち帰り、菓子箱に仕舞って大事にしていた。ある時それを見つけた母親に、気持ち悪いから捨ててきなさいと云われた。その頃はまだおふくろにも感情らしきものが残っていたが、子供ながらにその中の鬱屈とした思いを感じていたので、云われた通り蝉の抜け殻の入った箱を持って公園に行った。
しゃがみ込んでかさかさ音を立てる抜け殻をひとつひとつ地面に並べ、指で潰していった。それらはパリッパリッとあっけなく潰れた。抜け殻をひとつ潰すごとに自分の中から何かがこぼれ落ちてゆくようだった。
そしておれは、壊れてゆく家庭を膝を抱えて眺めるようになった。そんな姿が気に障るのか、座り込んでいるおれを引きずり廻し、平手で何度も叩いた親父に(平手で叩けば赤くなるだけで痣が残らないからだ)、ただにたにた笑ってまったく抵抗しなかった。へらへら笑いやがって、気持ちの悪いガキだ、と吐き捨てるように云って、おまけのように腹を蹴飛ばしたものである。おふくろは立ち尽くしてそれを見ているだけだった。
こんなことを思い出すのは久し振り、というよりも記憶の奥底に沈んでいた。昔のことを思い出してもそこへ移動しないのは過去だからか、とふと思った。いや、おれにとっては最早すべてが過去なのだから、移動するにはそこへ行きたいという意思が多少なりとも働かなければならないのだろうか……、と考えごとに耽っていたら、
「君は何故、無抵抗で理不尽な父親の暴力に耐えていたのかね」とエミの親父さんが訊ねてきた。
「別に耐えていたとか、そんな大層なもんじゃなくてですね、なんか、どうでもいいというか、殴られても痛くも痒くもなくて、悔しいっていうような感情もすごく遠いところにあるみたいな感じで……。うーん、自分でもよく判らないですねえ。中学の二年になった時に、三年のまあ、所謂不良グループに……、グループって云っても四人くらいだったんですけど、因縁つけられてどつき廻され掛かって、さすがのおれもその時は必死で応戦したんですよ。でもやっぱり相手が殴ってこようが自分が殴り返そうが、痛くもないし実感も湧いてこないんですよ。たぶん自分が何をしているか、相手に何をされてるかなんてのはどうでもよかったんでしょうね。こう、煩わしいことが忘れられればなんでもよかったんじゃないんですかねえ」
おれの云うことをじっと聞いていた親父さんは、憐れむような、申し訳ないような、なんとも複雑な表情をしている。
「わたしは精神科医ではないのだが、少年時代の君は、一種の離人症だったようだな。だが、わたしの知っている君はそんな様子には見えなかったが、そんな状態から脱するきっかけなんだったのかね」と、一番触れられたくない部分に切り込んできた。
「あのー、エミには黙っていてもらえますか」それを聞いた親父さんは、顔を顰めて、「娘にはとても云えないようなことなのかね」と云った。「まあ、堂々と云える類いの話ではないですね」おれがそう答えると、親父さんは、宜しい、娘には黙っていよう、と確言した。
おれがエミの親父さんの云う「離人症」とやらから抜け出せたきっかけを語るには、どうしてもアキのことを避けて通る訳にはいかなかった。
自分で云うのもなんだが、中学生までのおれは見てくれと違って頭が良かった。高校も最高レベルの進学校に楽勝で入れた(そこにどうやって今井が入学出来たのかは未だに謎である)。だからといって嬉しくともなんともなかった。
高校生になっても周囲の反応は同じだった。おれの異様な容貌や仕草などから、寄って来る奴と来ない奴ははっきり分かれた。寄って来た奴は話してみると意外と普通なので去ってゆく者もあり、普通に喋れるからと友人らしき存在になった者もいた。どちらでもたいして変わりはない、とおれは思っていた。
別に不良を気取っていた訳じゃないが、十三、四の頃から煙草を喫っていた。何がきっかけだったかは忘れてしまった。憂さ晴らしのつもりだったのかも知れない。進学校だけあって喫煙する者など殆ど居なかったが、駐輪場の陰に時々吸い殻が落ちていた。受験の息抜きかと思い、こいつらが喫っているのなら此処は死角になっている訳か、ということに気づいた。
十五才でありながら既にニコチン中毒になりかかっていたおれは、そこで煙草を喫うようになった。そして或る日、いつものようにしゃがみ込んで煙草を喫っていると(膝を抱えていなかったらヤンキーと見分けがつかなかっただろう)、見知らぬ女生徒がやってきておれの隣に同じようにしゃがみ込んだ。肩くらいの髪を真ん中で分けた、切れ長の目をした女である。
「あんた、不気味君って呼ばれてんだって?」
その女は外見に似合わない、蓮っ葉な口調でおれに話しかけた。おれの名前を知らない上級生がそう呼んでいるのは知っていた。第一、クラスの連中や教師たちですら、水尾をミナオと読めず、ミズオと呼んでいたのだ。
おれは見ず知らずの女に気安く話しかけられたことに戸惑い、知らねえ、とぶっきらぼうに答えた。女はくすくす笑って、「不気味君じゃ機嫌も悪くなるよね。名前はなんてゆーの」と訊いてきた。仕方がないので、ミナオだと答えた。
「それ、苗字、名前?」と更に訊いてくるので、いいかげん鬱陶しくなって、どっちでも構わねえだろ、と苛々した声でおれは云った。
女はおれの目が隠れるくらい伸びた前髪をひとさし指で撥ね上げて、「あんた、面白いじゃん。気に入っちゃった。今日、あたしんちに来ない」と、実にあっけらかんとした口振りで云った。何考えてんだ、こいつ、と思ったが、崩壊というか瓦礫になってしまった家に帰らずに済むのは好都合だったので、おれはあっさりその女に承諾の意を伝えた。
「じゃあ、ガッコひけたら此処で待ってるね」と云い残し去って行った。喋り方は兎も角、外見は真面目そうだし、煙草を喫いに来た訳でもなかったので、彼女はただおれを探す為だけに此処へ来たようだった。変な女だな、と思いながらもう一本煙草に火を点けた。
授業がすべて終って駐輪場へ行くと、例の女が言葉通り待っていた。おれは自転車の籠に鞄を放り込んで、「あんた、自転車は」と訊ねた。すぐ近くに住んでるから、と彼女は答えた。おれの引き出した自転車を見て、「あ、荷台がある。すごい実用的なのに乗ってんのね」と云って、勝手に荷台に腰掛けた。
遠慮というものを知らんのか、こいつは、と思ったが、仕方がないのでそのまま漕ぎだした。腰に廻した彼女の腕の感触がくすぐったかったのを覚えている。
校門を出て、「どっち行きゃいいんだよ」と彼女に訊ねた。校庭の方廻って、など、彼女の指示通りに自転車を漕いで行くと、学校の近くのアパートが彼女の云う「うち」だった。頑張れば一世帯住めないこともなかろうが、どう見てもひとり暮らしか、せいぜい新婚家庭用のアパートだった。実際、死ぬ前におれが住んでいた夢の島ハイツと間取りはそう変わらない。2Kというのだろうか。彼女の部屋は五階にあり、此処にはちゃんとエレベーターがあった。
玄関口に突っ立っていたおれに、「遠慮しないで這入ってよ。あたし、ひとり暮らしだから親とか居ないよ」と彼女は云った。おれとしてはそこが這入りづらい要因なのだが、覚悟を決めて部屋に這入っていった。女の子らしい部屋の白い丸卓子を挟んで、暫く沈黙が続いた。ああ、と云って彼女が立ち上がった時は心の底からほっとした。
戻ってきた彼女は、「飲み物も出さないでごめんね」と云って、缶ビールを卓子に置いた。ごめんねって、明るいうちから酒勧める方がどうかしてんじゃねえのか、と思ったが、半ば自棄糞になってビールを飲み、「おれ、あんたの名前も学年も知らねえんだけど」と文句をつけるように云った。
「あー、そうだったね。あたしはアキ。亜空間の亜にジュラ紀の紀。三年だよ」
名前の説明に亜空間やらジュラ紀だとかを持ち出す女はそうそう居ないんじゃないだろうか。「三年生ってことは、十七?」おれがそう訊いたら、「うん。でも七月になったら十八になっちゃうんだけどね」と答えた。
「いっつもこうやって年下の男を連れ込んでんの」と訊ねたら、「違うよー、あたしは年上のひとしか興味ないもん。ミナオ君はなんとなく面白そうだったから声掛けただけ」と、実にあっけらかんと答えた。おれは、ああ、そう、と答えるしかなかった。
「ミナオは中学ん時からそんな髪形してんの」と、二本目のビールを手にアキは訊ねた。どうやら酒には弱いらしい。自分で切ってるからこんなんにしかなんねえんだよ、とおれは答えた。ふーん、と云ってアキはおれの方にすり寄ってきた。
「こんなにきっちりネクタイ絞めてないでリラックスしたら。ああ、膝は抱えてるのね、噂どーり」と云って仰向けに寝転がった。性質の悪い酔っぱらいだな、と思ったが、嫌悪感は覚えなかった。
八時頃にはすっかり出来上がってしまい、アキは眠りこけてしまった。どうしたものかとおれは考え込んだ。このまま放っておいて帰ると、鍵を開けっ放しにすることになるので不用心である。それにおれ自身、家には帰りたくない。
部屋にあるふたつのドアのうちひとつは、洗面所と風呂場だった。便所が洗面所から這入った処にあることは、既に使用したので判っている。もうひとつの扉を思い切って開けると、果たしてそこは寝室であった。
彼女を此処に移動させた方がいいのかどうか考えたが、自分の細腕で女ひとり抱えられるか自信がなかったので、布団を持ってきて掛けてやった。ビールが切れたのかウイスキーの瓶を持ち出してきてあったので、それをちびちび飲みながら、することもないので教科書を開いて勉強を始めた。あほみてえだな、と我ながら思った。
アキとの関係はどうなったかというと、その日は彼女が泥酔してこと無きを得たが、翌日あっさり童貞を奪われた。なんというか、はっきり云って強姦されたようなものである。
昔、シベリアに抑留された兵隊が女看守に強姦されたという話を何処かで読んだか聞いたかした記憶があった。女が男に対してそんな狼藉が働けるとは思いも依らなかったその男は不能になってしまったそうだが、まさに常識を覆される出来事である。おれが覚えているのはコンドームを嵌めるのに手間取ったことだけだ。ただひとつの救いは、アキが色情狂のように毎日おれを求めてこなかったことである。
所謂、筆おろしをされたおれは、その翌日、アキに此処に居候させて貰えないかと訊いてみた。彼女は吃驚していたが、すぐに嬉しそうな顔をして、「ほんとに? 一緒に住んでくれるの?」と云って、おれの首っ玉を引き寄せキスをした。
何故そんな決心をしたのかといえば、瓦解した家から逃げ出せるなら何処でも良かったのだ。同居の承諾を得たその日の放課後、自転車で家へ必要なものを取りに戻った。泥沼のような家庭に母親をひとり残して行くことに罪悪感を覚えたが、もうこんな家から解放されたいという気持ちが先立った。
荷物をボストンバッグに詰めて出て行くおれに、おふくろは何も云わなかった。ただ黙って、耄けたように手を振っていた。
そうしてままごとのような同棲生活がはじまった。アキは意外に家庭的で、料理も巧かった。若干変なところもあるが、それにもじきに慣れていった。高校に入ってすぐに女と暮らすのは感心しない、と今井は云っていたが、おれの家庭環境を熟知していたので無理に引き離そうとはしなかった。
そんな奇妙な生活をしていたおれに、更に奇妙な事態が起こった。或る朝、目を覚まして台所の隣にある方の部屋へ行くと、卓子の上に一枚の紙切れが置いてあった。そこには「ちょっと出掛けてきます」とだけ書かれている。朝っぱらから何処へ行ったんだろう、と思ったが、深く考えないで学校へ行った。
昼休みにアキからのメールが届いた。友達にミナオのこと頼んだから、ちゃんと留守番しててねという、ひとを舐めくさった内容である。なんのこっちゃ、と思って返信もせずに放っておいたら、部屋に戻って吃驚した。
アキと同じ年頃の髪の長い女が、勝手知ったるとばかりに、のうのうと煙草を吹かしビールを飲んでいたのだ。「あんた、誰」と訊ねたおれに、「ああ、あんたがミナオとかいう子ね。あたし、あんたのお守りを頼まれたの」その女はこともなげに答えた。
お守りって、おれは幼稚園児かよ、と怒りが込み上げてきた。他所の学校の制服を着た女は、まあまあ、という感じで立ち上がっておれの肩に手を廻し、「あの子と住んでんなら、このくらいで驚いてちゃやってけないわよ」と云って、おれを座らせた。いつもの癖で膝を抱えると、女は、あははと笑い出した。「ほんとにそういうカッコするんだ。冗談かと思ってた」面白そうにおれの方を見遣る。
「あんた、アレね。そうやって膝を抱えて丸くなるのは胎内回帰願望よ」と女は云った。なんだよ、それ、とおれがむっとして云ったら、「お母さんのお腹の裡に戻りたいのよ、ぼくちゃんは。温かくて、何も考えなくていい、安全で安心な場所に戻りたいって心の裡で思ってんの」と女は判ったようなことを云った。
でも、こういうのは不味いわねえ、と女は呟いた。なにが、と訊ねたら、「あんた馬鹿じゃないんだから、アキがフツーじゃないことくらい判るでしょ。心に瑕持った者同士が一緒に居ていい訳ないじゃない」と、えらくまともなことを云う。
あいつは何を抱え込んでるんだよ、とおれが訊ねたら、「アキに自傷癖があるのは知ってるよね」と女は云った。それはアキの手首にある疵跡でなんとなく判っていた。しかしそれは、自殺未遂の痕といった深い疵ではなく、尖った物で引っ掻いたような軽い疵だったので、敢えてそれには触れずにいた。
「あれはあの子の母親が自殺してからはじまったんだけど……」と女は説明しだした。
アキの両親は、彼女が中学を卒業するのを待つかのように離婚したのだという。そして、半年経ったくらいの夏休みに、母親は自殺サイトで知り合った男と、どこやらの山中で排気ガスをホースで車内に引き込んで死んでしまった。母親はアキを溺愛していて、とてもそんなことをするような人間には思えなかったらしい。
そして、アキは暫く父親の処に厄介になっていたのだが、女の出入りが激しくこのアパートに移り住むことになったのだそうだ。その後、彼女は父親の影を追うかのように道行くサラリーマンに声を掛けては、部屋に連れ込んでいたのである。
ある時は一晩限りだったり、そうかと思えば三ヶ月くらい続いた男も居たという。そして自分をそんな目に遭わせた父親を責めるように、月命日(月忌というらしいが)になると母親が死んだ山に連れ出すのだそうだ。
その話を聞いて、おれはとんでもない女と拘わりを持ってしまったもんだ、と思った。しかし、後悔の念などは不思議と湧いてこない。アキの友達の名はショーコといった。
何故だか当然のように彼女とベッドを共にする羽目になった。頼まれたっていうのはこういうことも含まれていたのか。頭のイッちゃってる奴の考えることってのは理解出来ねえな、とぼんやり思った。
エミの親父さんに云わせると、おれもこの当時は危ない状態にあったらしいのだが、人間というものは自分自身のことはなかなか客観的に把握出来ない。
翌朝、ショーコさんとおれは一緒にアパートを出て、それぞれの学校へ向かった。帰りに駐輪場へ行くと、アキがいつものようにおれを待っていた。おれは普段通りに彼女を荷台に乗せてアパートに帰った。彼女は何も云わなかったし、おれも何も訊かなかった。
アキは毎月二十四日から二十五日に掛けて家を空け、ショーコさんがおれの「お守り」にやって来た。もうどうでもいいや、好きにしてくれ、という心境である。
そんな訳の判らない生活を続け、冬休みに入った或る晩、夜中にふと目を覚ましたおれは、隣にアキが居ないことに気づいた。ベランダに出ているのかと思いカーテンを開けたが居ないので、台所の方の部屋へ行った。彼女は電灯の豆球だけ点けた薄暗がりに座り込んで居る。「なにしてんの」と声を掛けると、彼女は弾かれたようにおれの方へ振り向いた。
手にはカッターナイフが握られている。
おれはアキの隣にしゃがんで、左手首を見てみた。手首の内側が薄皮だけ疵つけられて、薄っすら血が滲んでいた。「こんなことして、なんかいいことあんのか」とおれは彼女に訊ねた。彼女は俯いて、疵がひりひりすると生きてるって実感出来るから……、と消え入りそうな声で云った。
おれは彼女の握ったカッターナイフを力づくで取り上げ、自分の腕にざっとその刃を滑らせた。内側だと血管が皮膚のすぐ下を通っているから表側を切ったのだが、思った以上に血が流れ出た。彼女はそれを見ると、悲鳴を上げて頭を掻き毟った。ぎゃーぎゃー喚いて暴れる彼女を羽交い締めにするように抱きかかえて、なんとか落ち着かせようとした。
まさかこんな激烈な反応をするとは思わなかったので、おれもパニック状態にあった。血がだらだら垂れている左腕でアキの体を抱え込んで、もがくようにばたつかせる両手を右手で摑んだ。彼女は暫く喚いていたが、だんだん落ち着いてきて、しゃくり上げだした。そしておれの胸に顔を埋めておいおい泣きはじめた。
お母さん、お母さん、と繰り返していたが、そのうちお父さんという言葉も混ざってきた。窓の外が白みはじめる頃には泣き疲れて、アキはおれの腕の中で眠ってしまった。おれが自分の左腕につけた疵の血も既に止まって固まりかけていた。
「で、彼女が目を覚ましたら腕の疵の手当をしてくれたんですけど、薬用アルコールで血を拭き取った時に滲みたんですよ。疵口がひりひりして、その時やっと痛いという感覚がどういうものだか実感出来たんです」
エミの親父さんはおれの長々とした話を目を閉じて黙って聞いていたのだが、うう、という唸り声を出して、「それは君が高校一年生の……、一年生だと幾つだ」と訊いてきた。十五です、とおれが云うと、「十五才の時に経験したことなのかね」と絞り出すように訊ねた。
「はあ、そうです」
「十五でそんな経験をするというのは、異常な事態だと思わなかったのかね」と云われて考えてみたが、渦中にある当時は流されるようにその状況の中で生きていて、それが過ぎ去った後は思い出しもしなかった。ので、「特に思わなかったですねえ」と答えたら、しかし十五才で……、と親父さんは十五という年齢に拘った。
十五、十五とうるせえおっさんだな、と思いはじめたところで、「それで、そのアキという娘さんはその後どうなったのだね」と、やっと十五から解放してくれた。
「ああ、彼女は自分の目の前で他人が自傷行為をするのを見たことにショックを受けたのかなんだか判りませんが、取り敢えず自分の体を傷つけたりはしなくなりましたね。父親を母親の自殺現場に連れて行くのもやめました」
それを聞いた親父さんは腕組みをしてううむ、と考え込んで、「つまり十五才の少年だった君が、結果的にアキさんとやらを病的な状態から救い出したという訳なんだね」と、また十五に戻ってしまった。やれやれ、と思いつつ、「病的かどうかは判りませんが、傍から見てあきらかにおかしい行動はとらなくなりましたね。ただ……」
と云いかけたところで、言葉尻を摑むように「ただ、なんだね」と詰め寄るような口調で訊いてきた。不味いな、ここから先を云うのはいくらなんでもいかんだろう、と思って、「いや、なんでもないです」と誤魔化した。
「で、彼女はショーコさんとやらに君の守りをさせるのもやめたのかね」
親父さんはおれが誤魔化した核心に触れてきた。勘のいいおっさんだな、と思いながら、「ええ、そういうこともやめました」と、おれはすっとぼけた。やめるどころかアキは父親の代理を捜すのに熱心になってしまい、お守りを増やしたとは口が裂けても云えない。というか、思い出したくもない。
「彼女の異常な行動について君はどう思っていたんだね」と親父さんが話を逸らしてくれた時には感謝すらした。
「まあ、ぼくなりに考えたんですけど、アキが母親に対して異常なほどの執着心を持っていたのは誰から見ても判るんですが、どうもそれだけじゃないように思えたんですよ。で、わんわん泣いた時にお父さんと云っていたことや、サラリーマンと関係を持ちたがったことからから考えて、ひょっとしたら彼女は壊れてしまった家族を再生させたかったんじゃないかと思ったんです」
再生とはどういうことかね、という問いかけに、「未熟な頭で考えたことだから見当外れかも知れませんが、アキの両親は必要以上に互いを愛していて、ふたりだけで充足した状態だったんじゃないかと思ったんですよ。そこへアキが生まれて、母親の方は愛する男の分身を溺愛した。ところが父親の方は子供に自分の女の愛情を奪われてしまったと感じて、どんどん気持ちがすれ違って離婚に至ってしまったと。これは親の方の事情で、アキは兎に角、バラバラになってしまった家族をそっくりそのまま自分の手で作り出そうとしていたんじゃなかな、と思ったんです。彼女に母親の写真を見せてもらったんですが、薄気味悪いくらい似てるんですよ。だから自分が母親になり、父親に似た男を捜し、子供を、それも自分と同じ女の子を産めばいいと考えた。でも、男女の産み分けなんか自然な性交渉じゃ出来ないですよね。男が産まれちゃ彼女としては計算が狂う訳で、だから避妊せざるを得なかった——発想自体が既におかしいんですが、彼女としては子供を産みたいのに産めないというジレンマに陥っていたんじゃないかと当時のぼくは推測したんです」と云い終えたおれをまじまじと見つめて、「君はたった十五才で、それだけの分析をしたのかね」と親父さんは訊ねてきた。
また十五に戻ってしまったことにうんざりして、いい加減にしろよ、この糞ジジイ、と云いそうになったが、やはり怒りの感情は泡沫のように消えてしまう。怒りたいのに怒れないというこの状況はストレスが溜まるんじゃないかと思ったが、幽霊にストレスが溜まるなんてのもおかしな話だからまあいいか、と自分を納得させた。
時計を見るともう夜中の一時を廻っている。おっさん眠くなんねえのかなあ、と考えていたら、思いが通じたのかやっとソファーから腰を上げてくれた。
「しかし、なんだな。君はその娘さんとはエミと交際をはじめるまでつき合い続けていたのだろう。普通ならもっとまともな女性とやり直そうとしそうなもんだが、けったいな性格をしているんだな」
親父さんはそう云い残して部屋を出ていった。
余計なお世話だ、あほんだら、と云ってやろうかと思ったが、なんとか思い留まった。散々思い出したくもない過去をほじくり返されて忌々しい気分だったが、それもやはり長続きしない。厭な気分がすっと消えてなくなることがこんなにもどかしいものとは思わなかった。
思い出したついでにアキのことを考えてみた。
——あいつはいったい何を考えて、三年以上もおれに執着していたのだろう。自分の裡のもやもやしたものを取り払ってくれた恩人だとでも思っていたのだろうか。その割にはおれに対する待遇が非常識極まりなかった。何処の世界に恩人だと思っている男を、自分の友人知人へ盥廻しにする女が居るだろうか。
みんなでやろうか、なんつって乱交パーティーみたいなことにならなくて本当に良かった。
しかし、おれとふたりで居る時は多少おかしいところがあったものの、縁結びの神社の鈴を買って寄越すような可愛らしい一面も見せていた。そうでなかったら、いくら生きることに投げ遣りになっていたおれでも逃げ出していただろう。それに彼女の暗闇の部分を覗いてしまった以上、放り出すことも出来なかった。こんなおれでもそこまで無責任な人間ではない。
考えを巡らせているうちに、なんだかどうでもよくなってきた。元来、おれは物事に拘らない性質なのだ。手に入らないものを慾しがったことなどないし、 他人を羨んだりしたこともない。そこまで考えたら、この性格は逆に考えると、向上心のない、ただのぼんくらということになるんじゃないのかと思い至った。
死ぬまで気づかなかったが、おれはただのだらけきったぼんくらだったのか、と思ったら暗澹たる気持ちになってきた。
難有いことに、そのマイナスの感情もするっと何処かへいってしまった。
幽霊は眠らない。したがって夜が長く感じられる。閑を潰そうにも、何もすることがないときている。仕方がないので住んでいた居たアパートに行ってみた。
おれの部屋は午後に誰かが来たらしく、荷物はすべて梱包されていた。記憶にある部屋と違って、実に寒々しい光景だった。自分の遺体を見た時よりも、この殺風景な部屋の方が死を実感させる。此処で暮らした三年半の、大学生だったおれの存在が、ポスターでも剥がすようにひっぺがされた気分だった。
碌でもねえな、と思わず呟いた。マイナスの感情がすぐに消え去っても、後から後から暗い気持ちが湧きあがってきて、どうにも遣りきれなくなってくる。
クルの様子でも見てこようかと思って行ってみたら、寝室には誰も居なかった。彼女のとこにでも行ってるのかな、と思ったら寒さに身を縮こまらせて布団の中に潜り込んでいることが判った。猫みてえな奴だな、と思ったら少し気が晴れてきた。オバさんの部屋は女性だから遠慮して、ケルマの様子を見てみた。部屋の様子を見て、一瞬たじろいだ。
部屋中の段ボール箱を城塞のように巡らせ、その中で体を折り曲げて彼は眠って居たのである。こんなんで大丈夫かな、と心配になったが、普段から何を考えているのか計り知れない奴だったから、これがケルマなりの喪失感への対処法なんだろうと思うことにした。
夏にオバさんの誕生祝いに花火をした駐車場へ行ってみた。蝉の声が聞こえる訳でもなく、皆のはしゃいでいる姿も見えない。そんなことは当たり前なのだが、それが無性に淋しかった。裸足の皮膚にアスファルトの感触は伝わってくるのだが、生きているものと同じように、冷たさは感じられなかった。
誰の物とも判らぬ車のシートに座ってみた。おれは車を運転したことがない。車の免許を取っている余裕などなかったからだ。シートには座れるのに、ハンドルもシフトレバーもすり抜けてしまう。これらの境界線は何処にあるのだろうか、と考えたがさっぱり判らなかった。物に対する認識の違いだろうか。
いつまでこの状況が続くのだろうとシートの上で膝を抱えて考えてみた。永遠というものがあるとして、先も見えない、考えも及ばないくらい存在し続け、通り過ぎてゆく事物を傍観し、 気がふれてしまうこともなく、誰にも顧みられず、思い出されることもなく、それを嘆くことも出来ない……。これは拷問に近い状態じゃないのか、と思い至った。
そんなひでえ目に遭うようなことをおれがしたのか? 自分を大切にしなかったからか? おふくろを見捨てたからか? 何処の誰とも判んねえ女をコマしたからか?
「そんなこと、好きこのんでやった訳じゃねえよ」
と、おれは叫んだ。叫んだつもりだったが、出てきたのは普通の声である。遣りきれない思いが、躰の中で渦巻いていた。かといって、どうすることも出来ない。街灯の照らす薄暗がりの中で、誰に向けていいか判らない怒りが湧いては消えてゆくことに苛立ちながら車のシートの上でいつまでも膝を抱えていた。
やがて朝日が射し込み、太陽の難有さをしみじみ実感した。その暖かさを感じることは出来なかったのだが、暫く朝日を浴びていた。浴びている気分になっているだけで、光が自分を通過していることくらい判っていた。いつまでも此処に居たってどうしようもならないので、エミの家に戻ることにした。
居間に戻ったおれは、同じひとけがない部屋でもアパートの殺伐とした雰囲気とはまったく違うことに驚いた。ひとが住んでいる状態でたまたま部屋が空いてるのと、ひとが完全に居ない部屋との温度というか、感触の違いの大きさがこれほどだとは思わなかった。
深夜のビルを掃除していても、ひとりきりでやっていた訳ではないし、警備員も居ればさっきまでそこで働いていたひとたちの気配も残っていた。ふと、気配と幽霊の違いはなんだろうと思ったが、また堂々巡りで混乱しては適わないので考えを中止した。
ドアが開いて、エミのおふくろさんが這入ってきた。
「あら、ケンジさん、ずっとそこにいらしたんですか」と訊いてきたので、眠ることが出来ないので、アパートの方に行ったりしていました、と答えた。眠れないんてお気の毒に、と云うので、そのうち慣れるんじゃないですかとおれは答えた。
実際、慣れてもらわなくては困る。それにしても、おれがあれだけ苦悩していたのに幽霊どもはまったく声を掛けてこなかった。同胞が苦しんでんだから、ちったあ助けようとか思わねえのか。それとも『例外』の存在に、もう飽きてしまったのだろうか。
「ケンジ君、おはよう」とエミが声を掛けてきた。彼女の声を聞いたらなんだか気が抜けた。おれの隣に腰掛けて、「ゆうべお父さんと随分遅くまで話していたみたいだけど、なに話してたの」と訊ねてきた。「んー、親父さんの病院であった出来事を色々聞かせてもらったよ」と、おれはでたらめを云った。
どんなこと? と、エミが興味津々に訊いてくるので、「あー、霊安室にな、その日の夕方に死んだ妊婦が寝かしてあったんだけどさ、その前を通りかかった夜勤の男が、 こう、なんとも云えない粘着質のものがぐつぐつ煮えるような音が裡から聞こえてくるのに気づいたんだよ。で、恐るおそるドアを開けたら、数時間前に死んだ筈の妊婦が腐乱死体に変わっちまって、膨れた腹が気味悪く蠢いているのに気づいたんだ。恐いもの見たさで近づいた男の顔に、女の腹から飛び出したゴケミドロが……」そこまで云うと、彼女は実にしらけた顔をして、「話したくないなら素直にそう云えばいいじゃん。ケンジ君、死んだら馬鹿になっちゃったの?」 と、食卓の方へ行ってしまった。
ちょっと悪のりしすぎたか。だからといって馬鹿はねえだろ。
飯も喰えねえのに食卓につくのも虚しいので、ソファーの上でじっとしていた。そこへエミの親父さんがやって来て、昨日のように向かい側に腰掛けた。来やがったな、この糞ジジイ、と構えたが、「いや、ケンジ君、ゆうべは済まなかったね。君も云いづらいことを訊ねられて辛かっただろう。わたしもちょっと動転していたものでな。そうやってエミに見えるうちは娘の傍に居てやってくれ。君は知らんだろうが、救急車から出て来たあの子の取り乱しようといったら、見ている此方が辛くなってしまうほどでな。恐らくわたしが死んでもあんな風には嘆かないだろう」と穏やかに云うので、ああ、そうですか、と答えるしかなかった。
おれは怒りを爆発させることに餓えているのかも知れない。怒るという感情は生きている時は良くないものだと思っていたが、精神のバランスをとる為には必要なものだったのだ。
朝飯を喰い終わったのか、エミが戻って来ておれの横にまた座った。こいつはなんでいつもおれの左側に居るのだろう、と改めて疑問に思った。癖なのだろうか。膝を抱えようとしたので、「スカート穿いてる時にそういう座り方すんなって、なんべん云や判んだよ」と云うと、淋しそうな笑みを浮かべ、「死んでもおんなじこと云うんだ」と彼女は呟いた。
「おまえ、それがおれみたいに癖になっちまったら、彼氏が出来た時困るぞ。レストランとかでやったら摘み出されるだろ」
彼氏なんか作らないもん、とエミは俯いてしまった。
「オバさんみたいに一生ひとりでいるつもりか?」彼女の顔を覗き込んでそう云うと、肩を震わせて泣き出してしまった。間の悪いことに、そこへおふくろさんがお茶の盆を持って現れた。
「まあ、エミちゃん、泣いたりしてどうしたの。ケンジさんが困ってらっしゃるじゃないの」
ああ、緊張感がなくていいなあ、このおっかさんは。
「お茶を飲んで落ち着きなさいな。ごめんなさいね、ケンジさん」と、おれに向かって済まなそうに首を傾げるように軽くお辞儀した。すると、エミは母親に向かって、「だって、ケンジ君が他に彼氏作れって……」と涙声で云った。
あほか、こいつは。十八にもなって親に何をぬかしとるんだ。呆気にとられていたら、「まあ……」とおふくろさんは向かいのソファーに腰掛け、考え込んでしまった。そんなことをいちいち相手にするなよ、腰を落ち着けるな。
「でもね、エミちゃん。こうしてわたしたちには見えるけれど、ケンジさんはもう亡くなってしまったのよ。忘れてしまいなさいと云っているのではなくてね、生きている以上は前に進んでいかなくちゃならないの。ケンジさんもそういう意味で仰ったんじゃないかしら」おふくろさんはおれの方を見た。
「ええ、勿論そうです。今すぐ誰か探して来いと云ったんではなくて、一生ひとりで居る訳にはいかないだろうと……」
頷きながらおれの言葉を受けて、「エミちゃん、ケンジさんの仰る通りよ。当たり前のことを云われて泣くなんて恥ずかしいでしょう」穏やかな声でおふくろさんは云った。ごめんなさい、とエミは呟いた。
母よ、あなたは偉かった。それにしても疲れる母娘だ。
「ケンジ君、何もすることがなくて閑でしょ。あたしの部屋に行こうよ」とエミが云った。いいけど、と答えて思い出した。おれはこの家に来ても午飯を喰って暫くしたら引きあげていたので、彼女の部屋に這入った例しがない。先輩幽霊が云うには、生前行った処にしか行けないという話だった。
「おれ、おまえの部屋に這入ったことねえから、無理だと思うよ」おれがそう云ったら、なんで? とエミは訊き返してきた。
「幽霊は生きてた時に行ったとこにしか行けねえんだってさ」
それを聞くと、彼女はそんなの嘘だよ、と云って立ち上がってほらほら、というように手招きした。おれは犬か。
仕方なく後をついて階段の下近くまで行った。エミは階段を三段上がった処に立っておれを待っていた。試しに手すりを摑もうとした。手すりの前で何か、抵抗するものにぶつかった。もう片方の手も差し出してみたが、やはり同じ位置で何かにぶつかった。階段の下の少し此方側に見えない障壁のようなものがあって、そこから向こうへは行けないようである。
——まるで巧く出来た書き割りの前に居るようだ。
「駄目みたいだな……。諦めな」おれはエミに云った。
「そう思ってるから来れないんだよ。頑張ってよ」と彼女は半べそ顔になってしまった。
「無理だって。だいたいおまえの部屋に行って、なんか面白いもんでもあるのか」
彼女は階段を下りてきて、「あるよ、シーモンキーとかケサランパサランとかツチノコの拓本とか」と云った。こいつ、だいぶ映研の奴らに感化されてるけど、大丈夫かな、と心配になってきた。ほら、と云っておれの手を握って階段を上がろうとする。
無茶すんなあ、と思ったが、 驚いたことに彼女がおれの手を引いて階段を上がって行くと、先刻、結界が張られたように進んで行けなかった処を難なく通り過ぎてしまった。これはいったいどういう現象なのだろう。こんなに例外だらけになってしまって、果たしていいものだろうか。後でどかんと纏めてとんでもないことが起こるのではないだろうか。
階段の上まで行くと、来れるじゃんとエミが云った。
「いや、先刻は本当に階段の前になんか障害物みたいなのがあって、それより先には指先を出すことすら出来なかったんだよ」
「なんだろうね。ケンジ君が見えるひとが触ってれば、行けない処にも行けるようになるのかな」彼女は不思議そうに云った。
「判んねえなあ。もう、自分では理解出来ねえことばっかで草臥れたよ」おれは溜め息をついた。彼女は悲しげな顔をして、「なんか幽霊も大変みたいだね」と呟き、 おれの肩をさすった。たぶん頭でも撫でて慰めたかったのだろうが、てっぺんまでは届かないので肩を撫でたのだろう。エミの背が必要以上に低いことに感謝した。こんな時に年下の女から頭を撫でられたりしたら、自分が情けなくて堪らなくなるに違いない。
エミの家は病院の院長をしているような大物の家だけあって立派なのだが、恥ずかしながらおれの実家も阿呆みたいに立派だったから特に圧倒されたりしなかった。
彼女の部屋は、実にシンプルというか、女の子にしては実用一点張りという感じである。外見からして、気持ち悪いくらいメルヘンな装飾が施された部屋で、ポエムでも読んでいるのかと思っていた。よく考えてみたら、女の子らしい恰好はしていたが、フリルでひらひらだったりレースの服を着たりはしていない。
しかし、二年半ほどつき合っていたが、こんなミニマル主義の人間だとは思わなかった。机なんか事務用机だ。男だってこんな机を使っている奴はそう居ないだろう。机の前の椅子を見て、もしやこの机一式は病院の物ではないだろうか、と思って彼女に訊ねてみたら、果たしてそうであった。
「おまえはこれで良かった訳?」
「実用的に作られてるから便利だよ。椅子も丈夫だし、長時間座ってても疲れないように出来てるから」
なるほど、と思い至った。 こいつは見た目をあまり気にしないのだ。だからおれなんかに懐いてきた訳か。電車で遭った痴漢ならぬ、親切なひとという、その一点だけで。
エミが部屋のドアを閉めようとしたので、「ああ、閉めるな。開けとけ」と云ったら、なんで? と訊き返してきた。
「おっかさんが部屋に籠ってなにやってんだろうって心配するかも知んねえだろ」
それを聞いて、「ケンジ君って本当に真面目だね」と彼女はくすくす笑いながら云った。
はあ? と思っておれはエミの顔を視つめた。自慢じゃないが、おれは生まれてこの方、生意気だと云われたことはあっても真面目だと云われたことなどない。
「おまえ、おちょくってんのか」
「だってあたし、ケンジ君くらい真面目なひと、見たことないもん」と、エミはおれをじっと視た。
「じゃあ、おまえは出会った人間がよっぽど巫山戯た奴ばっかだったんだよ」思わず目を逸らして、おれは答えた。彼女はそうかもね、と云って、またくすくす笑い出した。幽霊だと思って舐めとんのか、このガキは。
「で、そのツチノコの拓本とやらは何処にあるんだよ」居たたまれないような、恥ずかしいような、奇妙な感情に囚われて、おれは話題を変えた。
「ああ、そっか。見せたげる」
本当に出してきたらどう反応したらいいもんだろう、などと考えていたら、何処にでも売っているようなポケットアルバムを抽き出しから取り出し、ベッドに腰掛けた。余程シンプルな物が好きらしく、藁半紙のような色の表紙には経線が二本引かれているだけである。右手でベッドの上をぽんぽんと叩くので、仕方なく腰を降ろした。階段を上れたように、ベッドの上にもちゃんと座れた。
アルバムを広げると、いつ誰が撮ったのか判らないが、おれとエミの写真がこれでもか、とファイルされている。生きている時は自分の姿を見るのが厭で、写真を撮られるどころか、鏡すらまともに見たことがなかった。しかし、死んでしまうとそういう自分を嫌悪する感情も消えてしまうのか、平静な気持ちでそれらの写真を眺めることが出来た。
「ひとつ訊くけどさ、これ、誰が撮ったんだよ。おれ、撮られた記憶ねえんだけど」と彼女に訊ねた。アルバムには彼女が大学に入る前の写真まで数枚あったのだ。
「ああ、この最初の方のはナオキさんがくれたの」
クルか、盲点だった……。あいつはカメラの性能で携帯電話を選ぶような奴だからな。はっきり云って隠し撮りじゃねえか。あいつ、いつか捕まるんじゃねえのか、とおれは思った。
エミが大学に入った後の写真も、サークルの誰かが写したのだろう、部員を勧誘している様子やら、飲み会の座敷やら、部室で馬鹿話に花を咲かせている様子がくっきり残されていた。オバさんの処に居る時のはまたクルが携帯電話でこっそり撮ったのだろう。
こうして見てみると、皆が頻りに仲がいいと云うのも頷けた。おれは常にエミの横に居て、寄り添うように、或いは肩を抱いて、まるで何かから彼女を守るようにしている。自分が笑っている写真が多いのも、実に奇妙な感じがした。何かを楽しんだという記憶が殆どなかったからだ。おれはこんなふうに何かを楽しんで笑っていたのだ。
「あたし、この写真が一番好き」
エミが指さしたのは、だいたい伸びた前髪で片目くらいしか写っていない中で、珍しく髪をかきあげてエミとふたりで誰かの携帯電話を覗き込んでいるものである。髪の毛をかきあげるのは自分では意識していなかったものの、おれの癖らしいので他にもありそうなものだったが、彼女が指した写真だけだった。
俯き加減で手元の携帯電話を見ているので伏し目になっているのだが、自分がこんな穏やかな表情が出来る人間だとは夢にも思わなかった。おれは自分のことを寓話に出てくるのヤマアラシのように、丸くなって棘を突き出し、他人の暖かさが慾しくてもその棘で誰に近づくことも出来ずに顫えている愚か者だと思っていたのだ。
彼女が、どう? と訊いてきた。「いや、自分の写真なんてまともに見たことなかったから面白かったよ。ツチノコの拓本には負けるけどな」そう云うと、彼女は満足そうに微笑んだ。
「ちゃんと見てくれると思わなかった。ケンジ君、写真撮られるの嫌いだから」彼女はアルバムを大事そうに持って、また抽き出しに仕舞いに行った。すると、不意に机の上の彼女の携帯電話が鳴った(まあ、電話は不意に鳴って当然なのだが)。
「あ、小山先輩、 なんですか? ……はい。……実験? ……はあ、そうですか。……判りました、失礼します」
小山からの電話だったようだが、実験という不穏当な言葉が気になった。
「小山、なんの用で掛けてきたんだ?」エミに訊ねたら、彼女は云いにくそうに、「ケンジ君をビデオに撮って、なにか写らないか実験したいって」と答えた。あの超常現象野郎、死んで初七日も済ませてねえ同輩使って遊ぶ気かよ。
集まるのは映研の部室だというので、電車でちんたら移動するのもうざったいから先に行ってる、と云ったがおれはそのままだった。エミがおれの手を握っている。この所為か、と思ったら少し恐ろしくなってきた。
こいつの執着心というか、磁力のようなものはいったいなんなのだ。彼女が手を引いて行ったら、上れる筈のない階段を昇ってしまった。そして、手を握られているおかげで、移動出来た筈の部室へ行けなかった。他にどんなことがこのちっこい娘の力で起きてしまうのだろうか。
万が一、小山の実験でおれの姿がビデオに写ってしまったら、もうどうしたらいいか判らなくなってしまうだろう。
どうせ誰にも見えねえんだからおまえひとりで行ってこい、と云うのに、約束したからと押し切られ、仕方なくふたりで学校へ向かう羽目になった。駅に向かう下り坂をエミの歩調に合わせて歩いていった。
ゆっくり歩くのにも慣れてしまっていた。はじめの頃はおれがすたすた歩いていってしまうので(猫背なのでだらだらゆっくり歩くように思われるが、歩くスピードは普通なのだ)、どんどん離れてしまう彼女が「ケンジ君、待って、待って」と大声で呼び掛けていた。
呼び掛けられるのが恥ずかしいか、手を繋ぐのが恥ずかしいか考えた結果、手を引いて歩く方を選んだ。迷子になられたら困る、というのもあったが。
改札をすり抜け、電車を待った。ふと気がついて、「おれに話し掛けたりじっと見たりするなよ。キチガイだと思われるから」と彼女に釘を刺した。判ってるよ、そんなこと、と不貞腐れたようにエミは答えた。電車に乗ると、その動きが生きている時と同じように感じられた。が、吊り革に摑まろうとしてもしてもすり抜けてしまう。仕方がないので彼女の肩に摑まった。
「そんなことしたら知らない振りなんて出来ないじゃん」笑いを堪えながら彼女は云った。
この、ものを感じたり感じなかったりするのを、どちらか一方だけにすることは出来ないものだろうか。エミに手を触れていても、横に居たり重なったりする人間は、おれを認知することはなかった。おれが思った通り、クルの説は間違っていた訳だ。
あいつは理数系の人間だから、物事をプラスかマイナスで考えがちだ。然し、人間というものはもっと複雑で微妙な世界に生きている。自分の感情を正確に認識出来なかったり、勘違いしてあさっての方向に行ってしまうことなどざらにある。テストじゃないんだから、マークシートを塗りつぶすようにはいかない。丸で囲った外の感情もあるのだ。
部室に行くと、新入部員も含めて映画研究会全員が揃っていた。芸人だったら大喜びするだろうが、生憎おれはそういう商売じゃないし、死んだ人間なので難有くもなんともない。今井まで来ていて、「ミナオ、よく来たな。小山の云うことなんかシカトするかと思ってたよ」と云った。じゃあ来んなよ。
「ミナオ、居んの? 葬式の時はぼんやり見えたんだけど、もうおれには見えないや……」小山が淋しげに云った。こいつのこんな表情は見たことがなかったので、お調子者だとばかり思っていたがまともな感情も備わってるんだな、と思った。他の奴らも、全員葬儀に列席していたらしいが、本当にミナオさん居るんですかとか、なんでエミちゃんと今井にだけ見えるんだよ、と口々に云っている。
デジタルムービー・カメラを三脚に設置して、皆が見えるようにコンピューターのモニターに繋ぎ、安手ながらも本格的な実験がはじまった。最初はおれだけが椅子に座ってとか、カーテン触ってとか云われて指示通り動いたが、彼らの満足する映像は撮れなかったようである。
小山が「じゃあエミちゃん、ミナオの横に行って」と云った。彼女はおれの顔を伺いながらそろそろと近寄ってきた。
「あいつら、馬鹿みてえだと思わないか」と訊いてみたら、「ちょっと思う」と答えた。ふたりして思わず笑うと、「エミちゃん、なんで笑ったの。ミナオがなんか云った?」小山がエミに訊ねた。馬鹿みたいと云ったとは伝えられなくて、「ケンジ君がくすぐったの」と答えていた。
「死んでもいちゃついてんのかよ」と、呆れたように井伊垣が云った。おれは思わず声を上げて笑ってしまった。彼女がそんなに笑わないでよ、と云った。なにやってんだよ、おまえら、と小山はこぼした。
「エミちゃん、ミナオの肩に手を置いてみて」
彼女は小山が云う通りおれの肩に手を置いた。皆でモニターを見て、うーん、身長的に位置は合ってるなとか、手のひらの形も何かに手を掛けてなきゃあんなふうになりませんよ、と云い合っている。なんだかあほらしくて、どうでもよくなってきた。
モニターから離れて、今度は「ミナオ、エミちゃんのどっか判りやすいとこに触ってみて」と、小山はエミの隣のあたり、おれが立っている場所に向かって云った。判り易いとこって何処だよ、と訊ねたら、彼女が「どうすればいいんですか」と通訳してくれた。うーんと考えて、「スカートめくるとか、目で見て判るようなことしてくれよ」と小山は云った。
考えた末に出てきたのがスカートめくりかよ、おまえは小学生か、と思ったが、兎に角、何か動かしゃいいんだろうと思い、エミの髪の毛を一束摘んで持ち上げてみせた。今井以外の全員が目の玉をひん剥いて、おお、と云った。
「おまえ、このサークルもうやめろよ。映画のことなんて誰も詳しくねえし、おまえだって特別映画が好きでも、こういう訳判んねえことが好きなんでもないだろ」その言葉に、彼女はおれの方に向いて、「でも、このひとたちと居ると面白いよ」と答えた。
「それは、はっきり云って馬鹿にしてるってことだぞ」彼女の髪をくしゃくしゃにして撫でた途端、わーっと云う声がした。モニターを見ていた連中が騒いだ声である。
小山の云う『実験』が終わって、録画された内容を見てみた。おれひとりの時は何事も起こらなかったが、エミが傍に来ると、彼女がおれの手を握った不自然な仕草や、小山に指示されて肩に手を置いた様子は、一流のパントマイマーのようだった。
だが、おれの姿はいっさい写っていない。おれが髪を動かした場面も、今時のコンピューター・グラフィックならいくらでも出来るだろう。それでも小山たちは興奮していた。第三者が撮った映像を見たのと違って、肉眼で見たからだ。小山は、「これでエクト・プラズマでも写ってりゃなあ」と云っていた。
勝手にやってろよと思い、今井に「おまえ、今日バイトあんの」と訊ねた。
「ああ、五時から十一時半まで。なんで?」
取り敢えず、ちょっと話があるから、とだけ云っておいた。エミはコンピュータのモニターを熱心に見ていて、今の会話には気づいていないようだった。
おれはエミにも彼女の母親にも黙って、今井のアパートへ移動した。
なんともいえない遣る瀬ない気持ちが募ってきたからだった。彼女が母親にすべてをゆだねて甘えている様子は、おれが知ることのなかったアキと母親の関係を思わせたからだ。アキの両親が彼女をこんなふうに愛していたなら、あんな歪んだ人格にはならなかっただろう。
然し、過ぎたことはどうしようもならない。それは自分自身で痛いほど感じていた。アキが自殺したりせずに生きていれば、そのうち自分か、誰かの手でもって軌道修正してしっかり地に足をつけた生活を送れるだろう。あいつは壊れた玩具のように脆そうに見えても強かな女だから、そこら辺をふらふらしながらでもしっかり生きているだろうと思った。
どれだけ頭に思い浮かべても、何故か彼女と暮らしたアパートには行けなかった。幽霊どもの云う、『例外』なのかなんなのかは判らないが、行けないのだから仕方がない。もしかするとおれ自身が無意識に、アキの記憶に障壁を作っているのかも知れない。そして、自分があの最低で自堕落で、混乱の極みにあった彼女が本当に好きだったことを、今更ながら思い知った。
エミの猛攻勢に負けて、アキに別れ話を切り出した時のことを思い出す。大学に受かり、彼女が留守をしている隙を狙って、逃げるように引っ越した。わざと彼女のアパートと正反対に位置する東三区のアパートに移り住み、それでも、月に二、三回は時間を空けて、彼女のアパートを訪れていた。
おれは、もうこんな関係はやめにしよう、というようなことを云った。彼女は、「あのしょっちゅう電話やらメールやら寄越してくる女の子の為?」となんでもないように云った。それもあるけど、もうこんな生活には疲れた、頼むから解放してくれ、とおれは云った。
「そうだね、子供のあんたにあたしは随分酷いことをしたよね」アキはうつ伏せに寝転んで、爪にヤスリをかけながら云った。そして彼女は、「あたしはミナオが好きだったけど、あんたにはとてもそうは思えない行動ばっかした。疲れて当然だよね」そう云って床に顔を伏せると、さっさと出てって、とおれを追い払うように手を振った。
おれはなす術もなく、腐ったようなスニーカーをつっかけ、彼女の部屋を後にした。
それっきりである。アキはおれを子供だと云ったが、彼女の方こそ疵だらけで泣きべそをかいている子供だったのだ。おれを弄び、振り廻すことで彼女の瑕が癒えるのなら、傍に居るべきだったのかも知れない。
然し、何もかもが遅過ぎた。おれは自分のことをあまりにも知らな過ぎたのだ。
今井の部屋は相変わらずごたごたと物が置かれて雑然としている。そこにぽつんと取り残されたように座っていると、自分がそこら辺のがらくたと変わらないような存在に思えてきた。
生物が存続する為の絶対数が決まっているように、死者にもそういう法則が当て嵌まるなら、たった五人にしか認識されないおれは絶滅種なのだ——かといって、今現在その五人が一斉に死んでも、おれが消えてなくなる保証は何処にもない。
感情があっさり消え去ってゆくように、自分の意識も消えてしまえばどんなに楽だろう。ホラー映画を作る人間たちは、皆一度、こういう体験をしてみるといい。恐怖というものは目に見える物事にではなく、見えないところにあるのだと気づくだろう。でも、見えないものは映像に出来ないか、と考えたら少し可笑しくなった。
実際、小山の『実験』で、カメラはおれを捉えることが出来なかった。サーモ・グラフィだったらどうかな、と考えたが、自分に体温があるかどうか判らない。熱を生じるにはエネルギーの消費活動が必要だから、死んだ人間に体温なんてある訳ないか、と思った。
日附けが変わる頃、今井が帰ってきた。
「なんだよ、ミナオ。エミちゃん放っておいていいのか」彼はマフラーを外しながら云った。
「いいよ、別に。おれなんかが構ってやらなくても、あそこにはちゃんと娘を溺愛している両親が居るんだからさ」そう答えたおれの向かいに胡座をかいて、「なんかその云い方、高校時代のおまえみたいで気に喰わねえな」 と彼は云った。
「じゃあ、なんて云えばいいの、カズミちゃん」
「カズミって呼ぶなよ」
今井はむっとして返した。彼のフルネームはイマイカズミという。漢字で書くと今井数見だ。和実や一巳なんかだったら判るが、数を見るとは、親はいったい何を考えて名づけたのだろう。会計士にでもなって慾しかったのだろうか。
「あー、こんなことになるって判ってたら、変な親切心起こさずに介抱ドロでもしときゃよかったな」おれがそう云ったら、エミちゃんのことか? と訊いてきた。
「他に介抱してやった奴なんか居ねえだろ」
「エミちゃんの財布盗んだところで、たいした金持ってなかったと思うぞ。家が金持ちでも、高校生に大金持たせるような親じゃなさそうだし」と彼は呆れたように云った。「たとえ四、五千円でも、あん時のおれにとっちゃ大金だよ」それを聞いて、「ああ、そうだな。おまえ、学費も生活費もみんな自分で稼いで払ってたからな……」と俯いて云った。
「高校ん時に親父が振り込んできた金に殆ど手えつけなかったし、入学金だけは振り込んでもらったからな。大学入ってからは女が時々、金振り込んできたし」
女って誰だよ、と今井は訊ねた。
「親父の愛人。五万とかそれくらいだったけど、あのひとなりに後ろめたい気持ちがあったんだろうな」それを聞いて、彼は深い溜め息をついた。
「で、話ってなんだよ」エアコンのスイッチを入れながら訊いてきた。寒いのか、と気温を感じないおれは思った。
「ああ、おまえさあ、一度エミとふたりで会う気ないか」と云ったおれの言葉に、彼は何云ってんだ、こいつという目つきでおれを見た。
「厭なら無理にとは云わねえけど、おれが見える若い男っていったら、おまえとクルしか居ねえんだよ。クルみてえな訳判んない奴に頼む訳にはいかねえから、おまえに頼んでんだけどさ」
「エミちゃんにはミナオが居るじゃねえか」そっぽを向いて、彼は怒ったように呟いた。
「おれは居ねえんだよ。小山の馬鹿げた実験、見ただろ。おれは存在しない、そこんとこをあいつは完全に飲み込めてねえんだよ。このままじゃ癲狂院行きだ」
彼はおれをじっと見つめて、「おまえって、とことん優しい奴だな」と云った。
優しい? 今日は意外なことが色々判明するな。エミには真面目だと云われるし、こいつはおれが優しいと云う。
「なんでおれが優しい訳よ」おれがそう訊ねたら、気づいてないってのも残酷なもんだな、と彼は項垂れた。「おまえは誰にだって優しかったんだよ。中学一年の時のこと、覚えてるか」と今井は云った。そんな昔のことなんか覚えちゃいねえよ、とおれは答えた。
「遠藤って奴が苛められてたんだよ。そいつは吃り……、吃音症っていうのか? そういう奴でさ、性質の悪い奴らがそれを真似てからかってたんだよ。からかっているうちは良かったんだけど、だんだんエスカレートしてって、教科書の入った机の中にペンキぶちまけられたり、女子便所の個室に無理矢理閉じ込められたり、靴に鳥の屍骸とか入れられたりって悪質になってきてさあ。そこへミナオが、それまで口も利いたことのなかった遠藤に話し掛けて、いっつも一緒に居るようになったんだよ。おれはなにしてんだろうなって思ったんだけど、遠藤に対する苛めがぴたっとやんだんだ。ミナオのことはみんな気味悪がってったっていうか、睨まれたら即死しそうな目つきしてたから、怖がられてただろ。遠藤もはじめのうちは、おまえのことも自分を苛めるつもりなんだって怖がってたんだけど、そんな気配はまったくないって判ったらしくて、だんだん打ち解けてって、その頃にはおれもミナオと遠藤の中に這入って喋るようになっててさ。ああ、おまえはたいして親しくもない遠藤を守る為にくっついてたんだな、って判ったんだよ。ゆっくり喋りな、おまえは頭の回転が速過ぎて口がついていかないだけなんだよって、こっちの耳に胼胝が出来るほど云って聞かせてやってたな。そのうち遠藤もコツを摑んできて、深呼吸して、頭の中で組み立てた文章を指でなぞるようにゆっくりゆっくり喋ればあんまり吃らないって判ったみたいでさ。あいつの吃りってのは……、そうだなあ、慌てて走り出して蹴っ躓くみたいなもんだったんだよ」
ひと通り聞いたが、まったく覚えていなかった。
「覚えてねえなあ。おれはそんな博愛精神なんか持ち合わせてなかったしよ」そう云うと、「だから気づいてねえのは残酷だって云ってんだよ」彼は悔しそうに呟いた。
「高校の時の清水って女の時もそうだったじゃねえか」
シミズ? 誰だそりゃ——と考えてみたら、それはアキの苗字だった。
「翻弄された挙げ句に腕まで切ってよー。あんな女の為に十一針も縫って、何処でやって貰ったのか訊いたら獣医だって答えた時には、おまえを殴りつけてでも実家に帰そうかと思ったよ」
そういえばそうだったな、と思い出した。
「いや、あの時は普通の病院に行ったら保険証出さなきゃなんねえだろ。年末だから緊急外来だし、未成年だし、そうすっと家に連絡が入るだろうし、保険証なしじゃものすげえ金ふんだくられるから、仕方なく近くにあった動物病院に行って、おれたちビンボーで医者に行けないんだけど、ガラスで手え切っちまって大変なんですって、嘘八百並べてさ。またそこの獣医が親切なおっさんで、ただで治療してくれたんだよ。大変な目に遭ったねえ、とか云ってさ。カルテに『ジョン、犬、雑種』って書かれてたの見た時は爆笑もんだったよ」
笑い事じゃねえよ、と今井はおれの眼を見据えて云った。
「ミナオは体張ってでも、ひとを守ろうとする奴なんだよ。自分じゃ全然判ってねえようだけどよ」
そう云って今井はおれのTシャツの左袖を捲り上げた。「あんなだらしねえ女の為に、こんな一生残る疵つける奴が何処に居んだよ」と泣き出してしまった。慥かに犬猫用の治療法で縫合した疵痕は、いつまで経っても消えなかった。
「雑種のジョンの為にそんな泣くなよ」とおれは云った。「馬鹿だよ、ミナオは。なんで大事なエミちゃんのことをおれなんかに任そうとするんだよ」泣きながら云う今井に、「おまえしか居ねえから頼んでんじゃねえか」と、おれはぼそっと答えた。
どうしようもならなかった。何もかもがおれの力では及ばない勢いで、それぞれの終着点へ向かっているように感じられた。ひとの運命を変えることは出来ないということがつくづく実感される。おれが死んだことも、こんな存在になってしまったことも、おれを認知出来る人間がごく限られたものだということも、すべてはあらかじめ決められていたのだと感じた。
今井は知らないことは残酷だと云った。それはおれだけではなく誰にでも当て嵌まる言葉だった。だが、その逆であるとも云える。これを買ったら、或るいはこの人間と拘ったら、この道を通ったら、いついつ何処で事故を起こして死ぬとか、ひどい怪我や病気に罹ったりすると判ったら、何をどうしていいものやら悩んで、仕舞いにはノイローゼになってしまうだろう。
どんな人間も自分の寿命を知らない。だから笑ったり泣いたり怒ったりして生きている。明日死ぬと判っていたら、人間なんて何をするか判ったものじゃない。銀行強盗をするかも知れないし、そこら中に火を点けて歩くかも知れないし、核爆弾のスイッチを押すかも知れない。
なにしろ自分は明日になったら死んでしまうのだ。世界がどうなろうと知ったこっちゃない。
善行を施している人間だって、世界平和を訴えている人間だって、一皮剥けば皆同じだ。自分が死ぬとなったら、真っ先にそれを逃れる方法に縋るだろう。だから、知らないことは残酷かも知れないが、幸福なことでもあるのだ。
おれは自分がいつまでこの状態でいるのかと考えることを、もうやめようと思った。答えのない問いにいつまでも取り組んでいたって意味のない話だ。宇宙の終焉まで意識が続くかも知れないし、死んだ時のように自分も気づかないまま消えてゆくかも知れない。
エミには、おれが消えてしまったら柳の木の下へ行けと云ってやろう、と思った。昔の絵双紙の幽霊は、たいてい柳の影から半身を覗かせている。
おれも消えたらそうやって柳の葉陰に居ると云ってやろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
