
act8 : Once upon a time
◀第1話 act1 : Sun. Dec. 17th から読む
──私は、自分の名前が嫌いでした。
最初にそう思ったのは、小学生の頃だったでしょうか。
「『りん』の名前って、むずかしい字をかくんだね」
長い休みのたびに、先生から返却される通知表。
そこに記されている私の名前……『凛』の字を見ては、クラスの人たちに口を揃えて言われたものです。
自分の名前に使われている字を、何気なく辞書で調べた時。
その意味を知って、重い気分になったことを覚えています。
『凛』──『態度などがひきしまっているさま。りりしいさま』
私には、こんな字は似合わない。
第一印象は、それでした。
引っ込み思案な私にとっては字面すらも恐れ多くて、文字通り「名前負け」していると思ったものです。
入退院を繰り返していた、ある日のことでした。
病院で定期検査を終えたところで、私と父は医師に呼ばれたのです。
そこで、私は自分の身体が病魔に侵されていることを知りました。
悪性の腫瘍が両手足に見つかったということ。
進行が早く、すでに末期の状態にあること。
そして、生きるためには、四肢を切断しなくてはいけないということ。
担当の医師から告げられた時、私はぼろぼろと泣いていました。
凛として。そうあろうとして、でもなれなくて。
ただ震え、怯えていることしか私はできなかったのです。
そんな私を横にして、父は言いました。
「千載一遇の機会だ」──と。
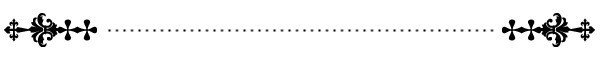
手術はつつがなく成功し、私は四肢を失いました。
そして同時に、新しい手足を授けられたのです。
病室の白い天井を眺めながら、私は右手を宙にかざしました。
私の、新しい右手。表面上は、いたって普通の小さな手でした。
握って開いて、握って開いて……。
私の思い描いたイメージとは裏腹に、指はわずかに折れ曲がっただけでした。
父は「すぐに動かせるようになる」と言っていたけれど──とてもそうは思えなかったのです。
私に与えられたのは、通常の義肢ではありませんでした。
父の手掛ける事業……エンジェルドールのパーツを初めて組み込まれた人間。
それが私でした。
なんでも、そのパーツは新しく開発されたものだということでした。
一般的な義肢よりも遥かに高性能だとして、装着を勧められたのです。
栄えある最初の事例になるのだと、父は興奮気味に話していました。
しかし、親戚の人たちからはすこぶる評判が悪いようでした。
自分の事業、ひいては名声のために、娘を体のいい実験台にしてるだけだ。
血も涙もあったものじゃない。
叔父さんや叔母さんは、陰でそんなふうに父を非難していました。
事情を知る人たちからは、同情と憐みの眼差しで見つめられました。
病気で四肢を失ったことに対して。
そして、その四肢をドールパーツで補われたことに対して。
病室を見舞う親戚たちは、みな一様に顔をしかめるのでした。
その表情は、言外に憐れみを匂わせていました。
「人形」の部品を接がれた私を、ひいては父のことを快くは思っていなかったのです。
それでも、私は精一杯の笑顔を浮かべて言うのでした。
「もっと小さい頃は、『お人形さんみたい』ってほめてくれてたじゃないですか。お父さんの役にもたてますし、だいじょうぶです、気にしてないんです──」
こんこん、と突然ノックの音がしました。
慌てて手を下ろしたところで、勢い余ってベッドの支え部分に手を強くぶつけてしまいました。
「……どうぞ」
ドアを開けて現れたのは、哲くんと鈴木くんでした。
「凛、久しぶり」「よう、凛」
面会謝絶が解けて以来、親族以外では初めてのお見舞いでした。
どこか沈みがちに、せわしなく視線をさまよわせる哲くん。
対して、以前と変わりなく朗らかな笑みを浮かべる鈴木くん。
まるで対照的な二人なのでした。
「凛、今日は中学校の入学式があったよ。
でさ、教科書とか色々配られたんだ。
凛のぶんも、ちゃんと持ってきたから」
そう言って、哲くんは手に提げた鞄から、私の分の教科書を出してくれました。
「ありがとう! ……ごめんね。重かったよね?」
本当なら、両親が持ってくるべきなのでしょうが……。
母は物ごころついた時には亡くなっていましたし、父は仕事の都合で入学式には出られないということでした。
たくさんの教科書を前に、申し訳ないような気持ちがふつふつと沸いてきます。
「平気だよ。ついでに言うと、このカバンまるごと凛のものだから」
「体操服と制服も持って来たぞ! 哲に持たせとくと危険だからな。
勢い余って匂いまでかぎそうだったから」
「張り倒すぞおまえ」
「……ふふっ」
いつものやり取りに、思わず口元が緩みます。
とても懐かしくて、嬉しくて、私はひとしきり笑っていました。
「クラス発表もあったんだ。俺も哲も、凛も3人そろって同じクラスなんだぜ。8クラスもあるのにびっくりだよ。これは運命だな!」
「運命かどうかはともかく、確かにラッキーだね。これからもよろしくな」
「……うん、ありがとう」
ひとしきり笑い合ったあとで、鈴木くんが口を開きました。
「……で、凛はいつごろから学校に来れるんだ?」
「あのね……たぶん、秋ぐらいになるの。リハビリに時間がかかるみたい」
「そっか……ちょうど運動会の季節だな」
二人の視線が、示し合わせたように私の手足に注がれます。
不意に、沈黙が訪れました。
二人とも、私が運動会が出られないことを分かっているのです。
哲くんが責めるような眼差しを鈴木くんに向け、鈴木くんは他の話題を探しあぐねているようでした。
「……しっかし、よくできた手足だよなぁ。とても作り物とは思えない」
視線を留めたまま、鈴木くんが感嘆のため息を漏らしました。
哲くんの顔がますます厳しくなっていくのも気にせず、鈴木くんは言葉を続けます。
「これ、ドールの部品なんだろ? すっげぇよな!
ロボットみたいで、かっけーじゃん!!」
たぶん鈴木くんは、単なる好意でそう言ったのだと思います。
当時はサイボーグもののアニメが流行っていて、多くの男の子はそれに夢中になっていました。
それを分かっていたから、私は傷ついたりはしませんでした。
ただ単に、寂しかったのです。
ああ、他の人から見れば、私という存在はそんなふうに見えるんだなあ、と。
やっぱり、私は人形なのだな──とも。
ぱん、と乾いた音が耳を打ったのは、それから数秒後のことでした。
鈴木くんがバランスをくずして、備え付けの棚に倒れこんで。
視界の端に、哲くんの振り抜かれた平手をとらえたところで。
ようやく、哲くんが鈴木くんを打ったことを理解しました。
「凛は人間なんだ! 機械なんかじゃない!」
病室内に、突き上げるような大声が響き渡りました。
「てめぇ……やりやがったな!?」
起き上がった鈴木くんが、間髪いれず、哲くんに飛びかかり──
瞬く間に取っ組み合いのケンカとなりました。
棚に置いてあった花瓶が床に落ちて割れ、
数個あった椅子が冗談のように宙を舞い……。
私は、とっさにナースコールを押していました。
駆け付けた看護婦さんは病室の惨状に悲鳴を上げ、怒り心頭といった様子で、二人をすぐに部屋の外へと連れ出していきました。
……そして、数十分後。
「……さっきは、ごめん」
哲くんは、しおらしい表情で深々と頭を下げていました。
頬の部分には絆創膏を貼りつけていて、私は思わず噴き出してしまいました。
「ちょっともう、病院に来てケガするなんて……」
「看護婦さんにめちゃくちゃ怒られたよ……」
さも痛そうに頬をさすり、苦笑するのでした。
「……鈴木くんは?」
「あいつも、もうすぐ来るよ。ごめんな、病室で暴れて……」
「大丈夫、気にしてないよ」
「……鈴木のやつは、あんなこと言ってたけどさ。俺はそうは思わないから」
暗かった彼の表情が、意を決したように引き締められました。
「おまえは人間なんだ、そうだろう?」

「……ロボットだなんて、誰にだって言わせやしない。
どんな姿になったって、凛は、凛なんだ」
その言葉には、力と温度がありました。
「……ありがとう」
嬉しくて、胸の芯が温められていくようでした。
けれども、私は思うのです。
さっき手を動かした時の、ぎこちない感触。
手の外見は人間のそれと同じく自然なのに、身体は違和感を訴えていました。
ただ、「何とか動かせる」という点で、手はまだましと言えました。
しかし、脚のほうは、ほとんど動かすことができなかったのです。
膝を折り曲げることもできず、かろうじて指先が動くぐらいでした。
「私ね、立てる気がしないの。身体が全然言うことを聞いてくれなくて……それが、すごくもどかしくて」
「そんな、かなしいこと言うなよ」
「俺、凛と一緒に歩いて行きたいんだ。
だから……俺が手にだって足にだってなるから。頑張ってみようよ」
そのとき、ドアを開けて鈴木くんが入ってきました。
手には袋を提げていて、どこかお買い物に行っていたようでした。
鈴木くんは、その袋を私に差し出してきました。
「……青汁パンとドリアンミルク、買ってきたぞ」
「お詫びの印、ということで」
哲くんと鈴木くんが、改まった調子で並び立ち……
二人の口から、「せーの」と小さい掛け声が上がりました。
「……さっきは本当に、すみませんでした」
二つの声が、柔らかに重なりました。
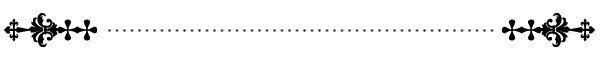
ほどなくして、リハビリの日々が始まりました。
手足を単純に動かせるようにする、というのが第一目標でした。
物をつかんだり、歩いてみたり。
以前までは難なくできた動作が、できなくなっているという現実。
打ちひしがれそうになりながら、私は来る日も来る日も訓練に明け暮れました。
初め、医師からは秋まで学校を休学してリハビリに専念するように言われていましたが、私はそれを受け入れませんでした。
哲くんと、鈴木くんと、一緒に卒業したい。
無理を通して、私は学校に通いながらリハビリを続けることにしました。
パーツが順応するまでは、車椅子で登校することにしたのです。
ヘルパーが常時そばにつき、何をするにしても助けを借りなければいけませんでした。
学校が終われば、すぐさま病院に行ってリハビリをしなければなりません。
哲くんは、学校帰りによく病院に来てくれました。
休憩の合い間に差し入れを持って来ては、色々なお話をしました。
学校にいる間はあいさつ程度の会話しかしない私にとって、哲くんとの会話はとても楽しいものでした。
けれど、いつもそうとは限りませんでした。
訓練がうまくいかない時。不安と苛立ちに押しつぶされそうになった時。
私は決まって、彼に辛く当たってしまうのでした。
一方的にまくし立て、時には自分のふがいなさに涙して。
そんな私に対して、彼は何も言わず、ただ黙って話を聞くのでした。
──春が過ぎ、夏も終わりにさしかかった頃。
私はようやく自力で食事をしたり、文字を書いたり、走れるようになっていました。当初の見込みより数ヶ月早く、私は車椅子が不要となったのでした。
「エンジェルドール」が世間で注目されるようになったのは、ちょうどその頃だったと記憶しています。
人間らしい挙動と感情表現を可能とする精巧なヒューマノイドの登場によって、人々の意識に変化が表れました。
単なる家事手伝いとして用いられる事が多かったヒューマノイドを、「恋人」として認識する層が現われたのです。
ドールの発売当初から、そういった目的で購入するユーザーは存在していましたが、それもごく小数でした。
何より、当時は世間の目が冷たかったのです。
「生身の人間と恋愛を避けて、ドールに逃避するなんて」という価値観が根底にあったのでしょう。
しかし、発売から五年以上が経ち、それまで触れられなかった「恋人」としての用途に光が当たり始めました。
メディアはこぞってこの風潮を取り上げ、瞬く間に大きな話題となりました。
老若男女、様々な人たちが「恋人」としてドールを購入したことを公にするようになったのです。
世間の反応は、賛否両論でした。
「恋人」としてのドール人気の高まりに伴い、製造メーカーである堂崎カンパニーに対する批判も大きくなっていったのです。
そこに追い討ちをかけるように、風俗産業への転用も進みました。
そんな一連の流れがあって、ドールを冷ややかに見る層は増えていったのでした。
ドールそのものを侮蔑の対象とする人が現れ出したのも、この頃だったと思います。
堂崎カンパニー社長の娘であり、ドールパーツを組み込まれた私は、そういった種類の人々にとっては格好の標的なのでした。
学校で、周囲から陰口を叩かれていたのは知っていました。
悲しくはありましたが、一方で仕方のないことだとも割りきっていました。
私が復学してから、日を追うごとに哲くんの生傷が増えていきました。
本人は頑なに何も話しませんでしたが、周囲から話は耳に入ってきます。
私の陰口を言っているグループの会話を聞きとがめて、喧嘩になったこと。
原因はいつも、私に対する中傷なのでした。
感謝しつつも、私は気が気でなかったのです。
私が悪く言われるのは構いませんでしたが、一緒にいる哲くんまでが中傷の対象になるのは避けたかったのです。
実際、彼は学校でも孤立しがちになっていました。
「もういいよ、哲くん。もういいんだよ」
私はもう慣れているのです。
耳をふさいで、目を閉じればいいだけのこと。
真っ向からぶつかっていく必要なんてないのです。
私なんかのために、彼までもが中傷を受けるいわれはないのです。
……私のために、という物言いが傲慢なものだとは分かっていました。
それでも、そう言わずにはいられなかったのです。
私がそう訴えた時、哲くんは言いました。
「分かってるよ。殴ったって、凛に対する悪口がなくならないってことは。
それでも、面と向かって言われれば、やっぱり悲しいし悔しいんだよ。
心の中で思ってるだけなら、それはどうしようもない。
でも、はっきりと形にされたなら……それが自分の目の前でやられたなら、俺は我慢できないんだ」
後ろ頭を掻いて、ばつの悪そうな表情を浮かべる哲くん。
眉をしかめたまま、彼はとつとつと言葉を継ぐのでした。
「正直に言えば……凛のためというよりは、俺の身勝手なんだよ。
だって、好きな子が悪く言われれるのは許せないから」
「好き」という単語が、心の隙間にすっと染み込んでいきました。
あまりにも自然に放たれた告白に、私は数秒の間ぼうっとしていました。
「……好き、っていうのは」
「そのまんまの意味だよ」と哲くんが返し、それから一拍の間を置いて続けました。
「……恋愛感情としての『好き』なんだ」
はっきりとした口調は、私の胸を震わせるのに充分な熱量をはらんでいて。
温かな塊がせり上がってくるのを感じると同時、視界がふいに滲みました。
「……凛?」
哲くんの驚いた声が耳に響き、私は慌てて涙をぬぐいました。
「……ありがとう」
絞り出した声は、どうしようもなく揺れていて。
深呼吸をひとつ差し挟んで、私は再び口を動かしました。
「私も、同じ」
自分が上手に笑えていたかどうかは、分かりません。
それでも、哲くんは気恥ずかしそうに微笑んでくれたのでした。
しばらくして涙が引いた後で、私は哲くんに言いました。
「私ね、脚を交換しようと思うの。ドールパーツじゃなくて、普通の義肢に」
換装しようかと悩んだことは、それまで幾度もありました。
それは、自分のためではなく、哲くんの身を考えてのことでした。
私への陰口に対して反発し、心身ともに傷を負う哲くん。
好きな人が無用な痛みを抱えるのは、とても辛いことでした。
それに、彼は口にこそ出さないものの、エンジェルドールの存在を好ましく思っていませんでした。
だから、私がドールパーツを身につけていることについても、良くは思っていないだろうと推測していたのです。けれど──
「その必要はないよ」
哲くんは、静かな口調で続けました。
「ドールは確かに好きじゃない。
でも、だからってドールパーツを身につけている凛を嫌いにはならない。
凛にとって、それは必要なものだろう。
俺が凛とこうして立っていられるのは、凛の努力と、そのドールパーツのおかげなんだろう?」
……たしかに、ドールパーツは高性能でした。
普通の義肢に比べれば強度も高く、動かしやすいという利点があったのです。
私が通常より早く復学できたのも、ひとえにドールパーツの人体への順応性の高さゆえでした。
「凛にまた一からリハビリをさせたくないしさ」
その言葉に、私は沈黙せざるを得ませんでした。
一般的な義肢とドールパーツでは機構が異なるのです。
ドールパーツから義肢に換えるならば、また一から諸々の訓練をやり直す必要がありますし、そのために再び休学することにもなるのでした。
「──だから、俺のことは気にしないでさ。凛は堂々としてればいいんだよ」
それ以降も、哲くんが自らの姿勢を変えることはありませんでした。
周囲との衝突は絶えませんでしたし、一部では恐れられるようにもなっていました。
しかし、それが功を奏したのも事実のようで……
学校での誹謗中傷は、段々と少なくなっていきました。
中学を卒業する頃には、少なくとも面と向かって罵声を浴びせられることはなくなっていたのです。
四月──入学式。
哲くんと鈴木くん、そして私は同じ学校の門をくぐりました。
県下有数の進学校と称される高校に、私たちは入学したのでした。
「また、同じ学校で過ごせるんだな」哲くんが感慨深げに言いました。
「ここから、俺の麗しき学園ライフが始まるわけだな……!」
鈴木くんは、何やら期待に打ち震えているようでした。
「鈴木……頼むからさ。入学式初日に女子に告白して玉砕、みたいな寒いイベントは起こさないでくれよ?」
「え、ダメなの?」
「本気だったのかよ。おまえさ、中学の時も入学式で告白して痛い目を見ただろうが」
「ふっ、あの時の俺は未熟だったんだ……。しかし、今なら行ける! 俺の魅力も、中学三年間で磨き上げられた……色々と成長したんだ。それに、中学の時は一人にしかアタックしなかったが、今回は違う。この前の入学説明会で、彼女候補として二〇人ほど目星をつけといたからな!」
「こいつ学習してねぇ……」
哲くんのつぶやきには、私も全面的に同意せざるをえませんでした。
「結果を見てから驚くんじゃねえぞ……。俺だってな、おまえらみたいなカップルになりたいんだよ! 悪いかチクショウ!」
「ちょっ、バカ、声でけぇよ!」
「なんだよ照れてんのか? 別にいいじゃん、じきに知られることなんだから。それにさ、今アナウンスしとけば、凛に男どもが言い寄ってくることもないだろ?」
「いいから。そんな気遣い要らないから!」
「みなさぁあん! ここにいるお二人はすでに恋人同士で──!」
なおも続けようとした言葉は、哲くんの拳に遮られました。
ぼぐっ、と鈍い音が響き、鈴木くんがその場で崩れ落ちました。
けれども、時すでに遅かったようで。
真新しい制服に身を包んだ面々が、好奇の眼差しでこちらを振り返っているのでした。
「あぁもう、初っ端から面倒くさい」
哲くんは参った様子で、しきりに首を振っていました。
「凛、行こう。鈴木に構ってるヒマなんてない」
哲くんの右手が、私の左手をつかみました。
おや、と思ったのも一瞬のことで……手をつないだまま、彼は昇降口へ向かってずんずんと歩き出していくのです。
その横顔が赤く染まっていることに気付き、ややあって私の顔も熱を帯び始めました。
「あいつ、言ったそばから期待に違わぬ行動力を……!」
今度ばかりは、鈴木くんの言葉に同意せざるをえませんでした。
どう考えても、さっきよりも数段恥ずかしい状況なのです。
哲くんは、心ここにあらずと言った様子で歩を進めるのでした。
それでも私は嬉しくて。歩調を合わせ、その腕に寄り添いました。
幸か不幸か、こうして、私たちのことは初日にして新入生の間に知れ渡ることとなったのでした。
……ちなみに。
鈴木くんの肝心の戦績はというと、二〇戦全敗とのことでした。
彼も、一日目にしてその蛮勇を轟かせることとなったのでした。
もっとも、その後の数ヶ月間は女子から避けられていたようですが。
何はともあれ、私たちは私たちのままでした。
ずっとこの先も、楽しい日々が続いていくと思っていたのです。
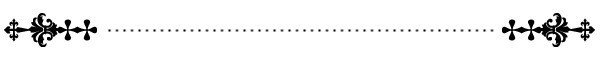
「ずいぶんと張り切っているみたいだね、凛」
家政婦と一緒にキッチンに立つ私を見て、父が微笑みました。
今日は私の一八歳の誕生日でした。
広いテーブルには、すでに家政婦が作ってくれた料理が幾つも並んでいました。
私の担当は料理ではなく、誕生日ケーキを作ることでした。
祝われる側の立場である私が、自分のためにケーキを作るというのも、他の人から見ればおかしな光景に映るのかもしれません。
それに、いつもならケーキはお店に予約していたのですから。
けれども、今年は特別なのです。
私の誕生日に、久しぶりに父がいるのです。
仕事で忙しい父は、いつも夜遅くに帰ってくるので、これまでの誕生日は一緒に過ごすことができませんでした。
それに、今日は佐藤さん……哲くんの家族も来るのです。
だから、いつもより特別な誕生日に備えて、私はケーキを作ることにしたのでした。
クッキーのようなちょっとしたお菓子はよく作っていましたが、本格的にケーキを生地から作るのは初めてのことでした。
レシピをそばにおいて、何度も何度も見直して。
家政婦たちからも、横から色々と教えてもらったりして。
その苦労の結晶が、ようやく出来上がったのでした。
「凛さん、上手く出来てますよ」
家政婦に褒められ、私はほっと胸をなでおろしました。
ふっくらと焼き上がったスポンジケーキ。
クリームのデコレーションも良い感じ。
フルーツの彩りも目に賑やかです。
自分で言うのも少し恥ずかしいのですが、かなりの力作なのでした。
「お父様も──それに哲くんも、絶対に喜びますよ」
家政婦に微笑み返しながら、私はケーキをテーブルへと運びました。
ぽっかりと空いた中心部に、誕生日の主役を据えて、私は席に着きました。
父も居間にやってきて、あとは佐藤さんを待つばかりとなりました。
自分の作ったケーキを、ぼんやりと眺めます。
お店で売っているような派手さはありませんが、それでも見劣りするようなものではないと自負していました。
数々の料理に囲まれて、ケーキは誇らしげにたたずんでいました。
おいしいって言ってくれるだろうか。大丈夫かな。
期待と少しの不安を胸に、そわそわと到着を待つのでした。
けれど──約束の時間を過ぎても、哲くんたちはやって来ませんでした。
連絡もつかず、そろそろ先に始めてしまおうか……と話していた頃。
父のもとに、一本の電話がありました。
佐藤さんからの連絡だろうか。
私は色めき立ち、会話に耳をそばだてていました。
「はい……そうですが……えっ?」
父の声が、不意に厳しさを帯びました。
そこには、何か不穏なものが透けて見えたのです。
「はい……わかりました、病院ですね」
ひとしきり話した後、父の表情は険しいものになっていました。
そして、おもむろに私の方へ視線を移し、重たそうに口を開いたのです。
「……佐藤さんの車が、事故に遭ったそうだ」
次の日、私たちは病院へと赴いていました。
佐藤さんに親戚との交流はなかったらしく、家族同然に親密だった私たちのもとへと連絡が来たということのようでした。
私たちは診察室に通され、そこで担当の先生から安否を聞かされました。
ご両親は即死、とのことでした。
そして、哲君は──
「頭を強く打っており、重体です。非常に厳しい状態ですね。もってあと一週間……仮に助かったとしても、おそらく脳に障害が残るでしょう。植物状態となってしまう可能性も十分に考えられます」
……帰り道、私の頭は真っ白でした。
何も考えられなくて、信じられなくて。
帰宅して部屋に戻るなり、両の目から思い出したように涙がこぼれました。
哲くんが死んでしまう。哲くんがいなくなる。
助かっても、もう、哲くんじゃなくなるかもしれない……。
私は、部屋の鍵を閉め、閉じこもっていました。家政婦さんたちの、食事ができたと呼ぶ声に応じることはなく。せめて水でも、と心配する声に対しても、頑なに拒否し続けました。
枕に顔をうずめ、喪失の予感にただ怯えていることしかできませんでした。
父が鍵を開けて入ってきたのは、事故から3日目のことでした。食事のことでもなく、私の体調を気遣うでもなく……父は、単刀直入に言ったのです。
「哲くんは、そろそろ危ないらしい」
無表情、かつ淡々とした話しぶりでした。
私は、父の顔を直視することができず、じっとうなだれていました。
「──哲くんを、助けたいかい?」
頭上から降ってきた声に、私は思わず顔を上げました。一瞬、耳を疑って、私は夢見心地に問い返しました。
──助けられるの? でも、どうやって?
医師の説明を聞く限りでは、生還はほとんど絶望的でした。さじを投げた、と言っても過言ではなかったのです。
それに、例え意識が戻ったとしても、哲くんはもう……。
「方法が、一つだけあるんだよ」
父の表情が、ゆらりと緩みました。
「わが社で進めているプロジェクトがあるんだが、それに彼を使いたい」
「どういうこと、なの……?」
「人間の自我と記憶を備えたドールを作る。記憶同期システムを利用し、哲くんの脳から記憶データを抽出する。それをドールに被せるわけだ」
「でも、それは」
頭の隅をよぎったのは、ヒューマノイド法でした。
ヒューマノイドの製造から運用に至るまでの大原則を定めた法律。そこには、ヒューマノイド自身とそのユーザーが守るべき義務が記されているのでした。
エンジェルドールは、いわば最先端のヒューマノイド。ゆえに、ドールとて例外ではありません。
一つ、ヒューマノイドは人間に危害を加えてはならない。
一つ、ヒューマノイドを軍事的な用途に用いてはならない。
一つ、ヒューマノイドには自身をヒューマノイドであると自覚させなくてはならない。
最後の条項について簡単に言うならば……ドールが素性を問われれば、正直にドールと答えなければならないということです。
とはいえ、それは心理プログラムに組み込まれた「本能」であり、嘘をつくことは不可能でした。
精巧なドールは人間との容姿の区別がつかないため、その点において政府は明確な線引きを課しているのでした。
ヒューマノイドが人間としての自我を持つということ。
それはすなわち、ヒューマノイドの自覚を持たないことと同義なのです。
ヒューマノイド法に抵触する恐れは十分にありました。
「政府から直々にまわってきたプロジェクトだ。もちろん部外秘だがね」
政府の依頼、とは素直に考えられませんでした。
政府はヒューマノイド法の遵守をことさらに強調していたからです。
しかし、それはパフォーマンスの一種であって、いわば建前なのかもしれません。……ともあれ、真偽のほどは定かではありませんでした。
「無理強いはしないよ。厳密に言えば、ドールに人間としての自我を植え付け、記憶をかぶせたからといって、それが人間になるというわけではない。あくまで複製……オリジナルに限りなく忠実な別人格といえるだろう」
静かな声音で、父は淡々と説明を加えていきました。
「哲くんの場合は脳を損傷しているからね、抽出できる記憶も通常に比べて不完全なものになるかもしれない。それを『哲くん』かどうか判断するのは、接する人間の心持ちしだいだ」
そこで言葉を切って、父は私の目を見据えましす。
「肝心なのは、凛がその存在を受け入れられるかどうかだ。さぁ、どうする? 脳が活動を停止してしまえば、その時点で記憶の抽出は不可能となる。提案しておいて心苦しいが、残された時間は少ないのだよ」
決断を迫るには、あまりにも短すぎる猶予でした。
熟考するだけの時間が与えられていたならば、私はもっと適切な判断を下すことができていたと思うのです。
父の提案とは別に、第三の選択肢を提示することも可能だったかもしれません。
今になって考えてみれば、父は初めから猶予を与える気などなかったのでしょう。
結果として。私は父の提案を呑んだのでした。
「お願い、します……哲くんを、助けて……」
助けて、と懇願しつつも、頭の片隅では彼の死を悟っていました。
ドールに記憶をかぶせたところで……「オリジナル」の哲くんが助かるわけではありません。
父の言うように、彼の記憶を乗せたドールが誕生するというだけの話なのです。
しかし、当時の私はそれでもいいと思ったのです。
「哲くん」がそばに居てくれるのなら。たとえそれが人形であったとしても、一向に構わないと考えていたのです。
──つまりは、私の身勝手に他なりませんでした。
その日の夜。
哲くんは記憶同期システムを使用され、記憶を複製されたのでした。
父は迅速に手続きを済ませていきました。
哲くんは、すぐに別の病院に移されました。
そこは、堂崎カンパニーと繋がりのある病院でした。
より高度な医療を施すため、という名目でしたが、実際のところ、哲くんが治療らしい治療を受けることはありませんでした。
施されたのは、生命を維持するためだけの簡素な処置。
言いかえれば、彼は死を待つだけの身となったのです。
父の関心は、前例なきドールの誕生にのみ向けられているようでした。
「なぁ、凛。哲はいつになったら回復するんだ?」
学校で鈴木くんから尋ねられるたびに、私は「まだ意識が戻っていないから」と曖昧に言い訳することしかできませんでした。
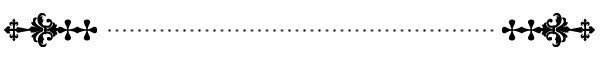
それから二週間も経った頃でしょうか。
私は、父に連れられて病院へと赴きました。
哲くんの記憶を乗せたドールが、おおよそ完成したということでした。
隔離された病棟で、「彼」は椅子に座っていました。その姿を目にした瞬間、私は呼吸を忘れるほどに見入っていました。
何本ものチューブを身体に繋がれていながらも──その外見は、生身の人間と遜色ない出来でした。
まさしく、そこには「哲くん」がいたのです。
「どうだ、精巧なものだろう?」
傍らの父が、子どものように得意げな笑みを浮かべました。
「外見だけじゃない。内部の機構さえも、人間のつくりに準拠しているからね」
なんでも、人体の器官までも模して造られたということでした。
人工の肺で呼吸を行うことも可能ならば、疑似的な消化系統のおかげで排泄行為さえも行うらしいのです。
「ただ、当然ながら機械の身体は成長しないから、髪や爪は伸びない。そこは、メンテナンス時に『髪と爪を切った』という記憶プログラムを一緒に組み込んでやる必要がある」
こればかりはどうしようもない、と父はさも残念そうに言うのでした。
「しかし、もっと残念なのは……」
そして、父は「最大の問題」と前置きしたうえで話を始めました。
「脳の損傷が激しかったため、所どころデータを抽出できない箇所もあった」
……懸念していたことではありましたが、記憶を完全には複製できなかったのです。
「今日ここに凛を連れてきたのはほかでもない。哲くんの記憶がどれほど残っているか、確かめて欲しいのだよ」
確かめる、という言葉に違和感を覚え、父に目を向けました。
いったい、私に何ができるというのでしょう。
「おまえは、哲くんと小さい頃から過ごしていただろう? 彼との思い出も多いはずだ。そのなかで凛の印象に残っている出来事があれば、彼も憶えている可能性が高い。それを尋ねていってほしい。……そうして、哲くんの記憶がどこで断絶しているのかを確かめてくれ」
非常に地道な作業だがね、と苦笑する父。
今の「哲くん」には、心理プログラムは組み込まれていないとのことでした。
現段階では、乗せられたのは記憶だけであり、感情表現はできないらしいのです。
また、自発的には活動できないこと。
こちらから質問を投げかけても複雑な回答はまだ望めず、基本的に「はい」か「いいえ」のシンプルなやり取りしかできないこと。
通り一遍の事情を簡単に説明すると、父は病室から出ていきました。
残された私は、じっと「哲くん」を凝視していました。
その時、彼の目がすっと開きました。
赤ん坊のような、無垢な瞳が私を見つめていました。
「哲くん……私の名前、わかる?」
「──はい」
おぼろげで掴みどころのない口調。
それでも、久しぶりに聞いた声は違和感なく私の耳にしみていきました。
残された記憶とこぼれ落ちた記憶の境界を探るべく、私は近い出来事から順に問いかけていきました。
「高校の名前、覚えてる?」
「──はい」
「中学の時に、学校で喧嘩ばっかりしてたこと、覚えてる?」
「──はい」
「中学に入って、病院で鈴木くんと喧嘩したことは覚えてる?」
「──いいえ」
「私の手足がドールパーツであることは、覚えてる?」
「──いいえ」
「……どうして中学校で喧嘩していたのか、その理由は覚えてる?」
「──いいえ」
彼は、私の入院やリハビリに関する記憶を失っていたようでした。
時期にして、中学一年から二年までの間です。
家族のことや鈴木くんのこと……そういった人間関係については覚えているものの、その間に起こった出来事に関してはひどく曖昧だったのでした。
そして──私の四肢がドールパーツで補われていることについては、完全に忘却していました。
そのことを父に伝えると、彼は満足した様子で頷きました。
「ご苦労さま。欠けている部分が分かれば、対処のしようもある。そこは、別にパッチを作成して充てることにしよう」
「あの……お父さん、お願いがあります」
「なんだね」
「私の手足が義肢──ドールパーツだということは隠しておいてください。それに、私がよく通院していたことも。『堂崎凛は昔から健康だった』ことにしてほしいんです。……『哲くん』に心配をかけたくないから」
私が手足をドールパーツで補われてから、哲くんは嫌な思いをたくさんしたと思うのです。
リハビリを始めてからは、辛くあたったこともありました。
いつも、心配ばかりかけていました。
学校では、私をかばって、私の代わりとばかりに立ち向かって……。
中学生の頃の記憶は、そのまま後悔となって私の内に刻まれていました。
私がドールパーツを身につけていなければ、辛い思いをさせることもなかったのでは?
それに彼は、ドールそのものを嫌っていたのですから。
──「あの頃」の記憶は必要ない。
彼にとっては、忌まわしいものに違いない。
私は、そう思うようになっていたのでした。
「それは構わないが……」
父は、試すように私を正面から見据えました。
「凛の周りには、凛がパーツを着けていることを知っている友達も多いのではないかな? 例えばそう、鈴木くんといったか。『哲くん』が社会に出た後、彼らの口から何かの拍子にふっと漏れるかもしれない。それも度々ね。露呈しやすい事実を隠し通すことは根気がいるよ」
「……大丈夫、です」
高校に入ってから、私は自分の手足がドールパーツであることを隠していました。
同じ中学からこの高校に入ったのは私と哲くん、鈴木くんの三人だけ。
その鈴木くんも、今となってはことさらに私の手足に言及することはありません。それは、哲くんがその話題を嫌ったからでした。
それに、私はもう歩けるのですから。
激しい運動もできますし、水泳の授業だって参加できるのです。
一見しただけでは、ドールパーツか生身かは判別できないのです。
五体満足の私として、彼の目に映りたい。
大丈夫、十分に隠し通せる。
もし知られた時は、記憶同期システムで記憶を書き換えればいい……。
私は、そんなふうに本気で考えていたのです。
「そこまで言うのなら、分かった」
父は、私の願いを承諾してくれました。
──かくして、補完プログラムは私の要望を反映させて作られ、彼の記憶に組み込まれる運びとなりました。
そして、一週間後。
「哲くん」は、模造された記憶と心理プログラムを搭載され、眠りから目覚めました。
奇しくも、彼の本来の身体が生命活動を停止したのは……それから数時間後のことでした。
延命措置を受けていたとはいえ──当初は一週間が限界とされていたところを、一カ月も生きながらえたのです。
その様は、まるで自らの命を人形に託したかのようにも思われました。
こうして「哲くん」は「一命を取り留めた」のでした。
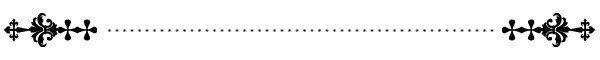
およそ三カ月の入院期間を経て、「哲くん」は我が家に迎え入れられることとなりました。
身寄りのなくなった「彼」を、父が後見するために。同時に、ドールである彼を管理するために。
ほどなくして、彼は再び学校に通い出しました。
──「哲くん」がドールであることが気付かれはしないだろうか?
最初は、気が気ではありませんでした。
しかし、その心配もまったくの杞憂でした。
クラスメイトは温かく迎えてくれましたし、鈴木くんも違和感なく接しているようでした。
「哲くん」は、拍子抜けするほど簡単に、かつての日常へ溶け込んでいきました。
鈴木くんたちと談笑する彼を目にするたび、私はほっとしたものです。
私の判断は間違っていなかったはずだ。
事あるごとに、私はそう自分に言い聞かせるのでした。
心配するような問題もなく、月日は淡々と過ぎていきました。
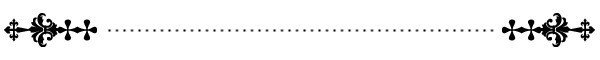
やがて私たちは高校を卒業し、大学に入学しました。
「哲くん」と鈴木くんは推薦で同じ大学に、そして私は受験して地元の国立大学へ進学したのです。
進学先は違っても、二つの大学は互いに近い距離にあったため、疎遠になることはありませんでした。
私が入学した学部は、工学部でした。
かつては父も在籍していた、ヒューマノイド研究の名門なのです。
受験に際して、私はカンパニーを継ぐ意思を父に伝えていました。
その時の父の喜びようといったら、狂気乱舞といっても差し支えないほどでした。
父のために、会社のために。
でも、一番の理由は「哲くん」のために。
ドール研究に携わり、社のトップにのぼりつめること。
それが、彼を守るための最良の選択に思えたのでした。
私が大学に入ってからというもの、父はなるべく家族との時間を持とうとしていました。
暇を見つけては何かしらのイベントを企画し、私と「哲くん」を連れ出していたのです。
イベントと言っても簡単なもので、お花見や海水浴といった日帰りのものが常でした。
カメラ好きの父は、そのたびにカメラを持ち出し、写真に収めていました。
父はそれらの写真をアルバムにまとめ、大事に保管したものです。
思うに、父がそういった家族の時間を増やしたのは、ドールとの関係構築のためだったのではないでしょうか。
「哲くん」の運用は、父にとっては実験的な試みでした。
ドールに本来搭載されるべきプログラムを意図的に載せなかったことは、その最たる事例と言えました。
それはつまり、「哲くん」がヒューマノイド法に基づいて定められた大原則に縛られないということを意味していました。
人間に危害を加えることができるということ。
人間を特別な存在として認識しないということ。
人間との直接的な喧嘩はもちろんのこと、殺人すらも可能なのです。
ヒューマノイドの思考アルゴリズムにおける最大の制約から逃れた「佐藤哲」は、自由な人間として自らの意志を遂行できるのでした。
その特性ゆえに「哲くん」は、あくまで人間として、私たち堂崎家の面々に接しているということでした。
彼の境遇としては「身寄りを失い、他人の家に居候している身」なのです。
私たち堂崎家の人間に引け目を感じていることは、想像にかたくありませんでした。
記憶同期システムによって「堂崎家と良好な関係を築いていた」という過去の記憶を持ってはいたものの、父はそれだけでは不十分と考えていたのでしょう。
それに、「哲くん」との関係構築に失敗すれば、将来的に寝首をかかれるという可能性もないとは言い切れないのです。
父の家族サービスは、そういった幾つもの懸念が重なった結果ということのようでした。
純粋に家族を思って、というよりは、プロジェクトの一環として私たちと接していたように思います。
しかし、父の意図がどうあれ、私にとっては喜ばしいことでした。
「哲くん」が傍にいるというだけで、私の心は満たされていたのです。
ドールであることに対する違和感はとうに失せ、私は彼をそのまま人間として見ていました。
休養に行こうという話が持ち上がったのは、その年の秋のことでした。
父は、近くの山林に別荘を持っていました。
そこで一泊してゆっくりしようということになったのです。
泊まりがけの休養は、我が家にとっては本当に久しぶりのことで……「哲くん」が私たちと暮らすようになってからは初めてのことでした。
旅行の前日、私は深夜に父の書斎へと呼ばれました。
珍しい、と思いました。
というのも、父は私たちに書斎への立ち入りを固く禁じていたからです。
幼い頃は何度か入れてもらったこともありますが、それも片手で数えられるくらいのもの。
中学生になって以降、一度も足を踏み入れたことはありませんでした。
書斎に入ると、父は椅子に座るよう促しました。
「カンパニーを継ぐ意思に変わりはないかね」
机を挟んで向き合う格好になったところで、父は私に問いかけました。
私は、強く頷きました。
「……いかなる事があっても、カンパニーを守ると約束してくれるか?」
再度、首を縦に振る私。
父の厳かな表情が、わずかに緩んだように見えました。
「ならば、話しておくことがある。『哲くん』のこととも大いに関係があることだからね」
そう言うなり、書類の束を手渡されました。
「旅行の『しおり』だよ」
言葉の軽さとは反対に、父の顔に笑みはありませんでした。
あまりにもアンバランスな振る舞いに、私は「しおり」へと目を滑らせました。
……それは、旅行の行程表のような楽しげなものではありませんでした。
まず目に飛び込んできたのは、冊子の表題──「新型ドールの概要と開発過程」。
この資料が、今回の旅行とどう関連しているというのでしょうか。
父がいったい何を意図して、この資料を私に見せているのかが分かりませんでした。
「知らなくていいことで、世の中は溢れている。それでもなお、一定の地位にあるならば知っておかなければいけないことだ」
私は反射的に紙面から目を離し、父を見つめました。
しかし、父は無表情で私を見つめ返すだけでした。
「先に読み進めろ」という意思表示のようでした。
──旅行用に特化したドールでも造るつもりなのかしら。
私は資料に視線を戻し、ページを順に手繰っていきました。そして、そこに記されている内容は、およそ予想からかけ離れたものでした。
「『兵器運用を想定した汎用型ヒューマノイド』……?」
目を引いた一節が、そのまま自然と口の端からこぼれていました。
紙面には「戦闘」や「諜報」、それに「暗殺」といった物騒な単語が散りばめられていました。
「どうして、こんな……」
ヒューマノイドの軍事転用は堅く禁じられているのです。
冊子の内容は、明らかにヒューマノイド法に違反するものでした。
「もともとは、国が発案したことなのだよ。もう二十年も前のことだ」
「……エンジェルドール開発以前の話なのですか?」
「そうだ。当初は、この『兵器』の開発が求められていた。……紆余曲折を経て、結局は頓挫したがね。その過程で得たノウハウを転用したのが、エンジェルドールというわけだ」
どこか誇らしげな笑みを浮かべながら、父は言いました。
「例えば、カスタマイズ機能。今でこそファッション的なものとして認知されているが……本来の目的は違う。敵地での地理条件や作戦に合わせて臨機応変にパーツを換装するためだ。その特性は、諜報員としての運用にも適していた。外見は生身の人間と変わらないし、パーツさえ付け替えれば自由自在に人相を変えられるからな。……そう、当時は様々な運用方法が立案されたものだ」
父は旧知の友人を前にしたように、遠い眼差しをしていました。
「……一〇ページ目を見て欲しい」
言われるままに、私は該当するページを開きました。
『プランD──セクサロイドとしての運用』
『セクサロイドの体内にウイルスを仕込み、性行為を介して対象を感染させる』
『ウイルスは伝染性の強いものが望ましい。現段階では、娼館に紛れさせるといった手法が効果的であろう。敵国民に流行病を蔓延させるには効率の良い方法と言える』
『発病までの期間はおよそ数ヶ月程度を見込むこと。治療困難かつ致死性のあるものが求められる』
「それが、現在手掛けている新型ドールの概要だ」
「手掛けている、って……なぜ今さら……!?」
先ほど、父は言ったはずです。「頓挫した」と。
「──脱税スキャンダルを、ある組織に掴まれたからだ」
額に汗が滲んでいくのが、自分でもはっきりと分かりました。
脱税、という言葉が鼓膜をすり抜け、頭の内側を殴っていきました。
父が口にした金額は、数十億単位の莫大なものでした。
私は、ほとんど放心していました。
金額の大きさもさることながら……カンパニーが脱税を行っていたという事実こそが、信じられませんでした。
「奴らは、スキャンダルの隠匿と引き換えに新型ドール……セクサロイドの製造を持ちかけてきた。──私は、それに応じたのだよ」
「そんなもの……すぐに破棄すべきです! ヒューマノイド法に違反するばかりか、犯罪組織に手を貸すなんて!」
「破棄、か。簡単に言うね。しかし、そうなれば悲しむのは……凛、おまえなのだよ」
私が? 悲しむ?
言葉の真意をつかみかねて、私は口をつぐみました。
数秒の思考を要した後で……一つの推測に行き当たります。
はっとすると同時、悪寒が全身に走りました。
「……まさか!」
叫びにも似た私の声に、父はゆっくりと頷きました。
「そうだ。『哲くん』だ。彼こそが、新型ドールのプロトタイプなのだよ」
手元の資料が、くしゃり、と音を立てて歪みます。
無意識のうちに、私は紙を握り締めていました。
血液が沸騰したかと思うほどに、全身が熱くなっていくのを感じながら──私は震える声で問いかけました。
「彼に『人間』としての自我を植え付けたのも……最初からそれが目的で? 政府からの依頼というのは嘘だったのですか」
「そうだな、嘘だ」
平然と言い放たれた言葉。
呆然としているところに、再び父の声がかぶさりました。
「ただし、それは組織の依頼ではない。私の個人的な実験だ。自我を備えたヒューマノイドの開発は、私にとって長年の夢だったからね。……技術的にも実現可能であると目処がたったところに、運悪く組織からの脅迫。そこに佐藤一家の事故が重なり──哲くんを活用したというわけだ」
「佐藤哲」の死は二重の意味で好機だった、と父は語りました。
「……『哲くん』は、私の最高傑作だよ。これまで様々なドールを手掛けてきたが、彼は特別だ。もっとも、私は彼に嫌われてしまっているがね」
ふぅ、と小さく溜息をつきながら、父は言葉を続けます。
「自身が人形であるにも関わらず、人形を嫌っている。そして、その作り手である私をも嫌っている。まったく皮肉なものだよ」
言葉とは反対に、その表情は喜ばしげなものでした。
「ああ、まったく同じだ。『生前の』哲くんの人格を忠実に再現できている」
その物言いが、私の背筋をひやりと撫でました。
父にとって、もう哲くんは「死者」でしかないのです。
しかし、それは正しいことでした。
間違っているのは、おそらく私のほうなのです。
人間の記憶と自我をかぶせられた人形を、佐藤哲そのものとして……生きたものとして扱っていること。
それが異端であることを、残酷なまでに思い知らされたのでした。
「とても嫌そうだね、凛。おまえは物静かだが、すぐに顔に出る」
「…………」
「さて、本題に入ろうか」
細められていた父の目が開かれ、私をがっちりと正面から捉えました。
その視線に射抜かれるような心地さえ覚えつつも、負けじと目をかち合わせます。
せめてもの意地でした。
けれども、それもわずかな間のことで。
父の口から放たれた言葉に、私はいとも容易く突き崩されたのでした。
「別荘の寝室は、哲くんと一緒の部屋を用意する。明日の晩は、彼と寝なさい。……いいね?」
父の意図は、分かりやすいまでに露骨なものでした。
男女の意味においての「寝る」ということ。
父は、私に「兵器」の実験台としての役割を担わせようとしているのでした。
「データを採取したいのだよ。セクサロイドと交わった人間の身体に、どんな影響が出るのか。そもそも、きちんと感染するのかどうか。……大丈夫だ、ワクチンは用意してある。何も心配はいらないのだよ」
ほくそ笑む父。何度となく見た、父の笑顔。
私が四肢をドールパーツで補うように提案された時も。
哲くんの記憶をドールに被せるかどうか選択を迫った時も。
父は、笑っていました。
その表情の意味を、私はようやく悟ります。
そこに在るのは、慈愛でもなければ慰めでもなく。
父親という仮面をかぶった研究者の、利己心の表れでしかないのでした。
「肝心の実験データが揃わなければ、組織は動く。スキャンダルを告発され、私は社長の座を追われるだろう。さらに、警察から捜査の手も入る。……そうなれば『哲くん』のこともいずれは隠し通せなくなる。警察に回収された違法ドールの末期は知っているだろう?」
知っています。痛いほどに、理解しています。
精密検査でデータやスペックを分析され、用済みとなれば廃棄処分。
ドールメーカーの関係者でなくとも知っている、ごく常識的な知識でした。
「……分かり、ました」
絞り出すように、そう言うのがやっとでした。
そして、それきり何も言えませんでした。
私こそが、人形なのかもしれません。父の掌の上で躍らされるだけのマリオネット。自分が空っぽになったような虚無感に浸りながら、ぼんやりとそんなことを思うのでした。

「うぉおやべえ! 別荘、やべぇ!」
「落ちつけよ鈴木」
「ははっ、鈴木くんは相変わらず元気がいいねぇ」
家から程遠く離れた山の、山頂付近。
そこに、我が家の別荘はありました。
古びた洋館を改修したもので、古風な外見はそのままに、内装は現代風に整えられていました。
防犯設備も最新式のものを導入していて、セキュリティも万全というのが父の自慢なのでした。
「さて、哲くんと鈴くんは先に中に入りなさい。しばらく、二人でくつろいでいるといい」
「あれ? 堂崎さんと凛はどこか行くんですか?」
「夕方にやるバーベキューの機材を、うっかり家に忘れてきてしまってね。凛もちょっと取りに帰りたいものがあるみたいだから、一緒に戻るよ」
「なにか手伝えることがありましたら、ご一緒しますけども……」
「ああ、大丈夫だよ。哲くんはゆっくりしてるといい。よかったらでいいんだが、テーブルなんかの家具を軽く拭いてもらえないか。久しぶりに来たから、ほこりも少し積もってるだろうしね」
「……分かりました」
「哲、素直に言えよぉ、凛と一緒にいたいんだろー?」
「そ、そういうことじゃないっての!」
「まぁまぁ、時間はいっぱいあるからね。今日の夜あたり、凛とゆっくり過ごすといいさ」
「ちょっと堂崎さんまで!」
笑い声が、紅葉した木々の合い間に響き渡ります。
山あいの涼やかな風が、さわさわと鳴っていました。
私と父が乗った車は林道を駆け、山の中腹に差し掛かったあたりで止まりました。
私たちは、もとから家に戻るつもりなどありませんでした。
バーベキューの機材はトランクの中に積んでありましたし、私だって家に忘れ物をしたわけではありません。
父の言葉は、単なる建前でした。
「凛に見せておく場所がある」
昨晩の話が終わった後で、父は厳かに言ったのです。
いわく、それは研究所ということでした。
ただし、都市部に位置するカンパニーのメイン研究所ではなく、父が個人的に所有するものらしいのです。
「ここからは、歩きだ」
車を降り、父は道路の脇を指し示しました。
そこに目を凝らすと、おぼろげに「道」が見えました。
父は、なんのてらいもなく山道へと入って行きました。
慌てて、私もその後に続きます。
……一〇分も経った頃でしょうか。
悪路を抜け、私たちは研究所に到着しました。
古びた外観の建物は、研究所というにはみずぼらしく、想像とはかけ離れていました。
都市部の整った施設とは違い、廃屋のような印象を受けたものです。
「祖父の代から受け継いでいる施設だからね。もともと義肢の研究は、ここで行われていた。今となっては、カンパニーの人間でこの施設を知る者はいない」
独自に研究をするには大変都合がいい、と父は言いました。
そして、「哲くん」に関する研究も、ここで行っていると説明したのです。
私は、そこで施設の概要を教えられました。
施設の成り立ちから設備の説明、そしてその用途に至るまで。
さながら社会見学に来た小学生のような心持ちでした。
父が言うには、この施設こそが唯一の新型ドール研究の拠点ということでした。
そして、「佐藤哲」に関するデータの宝庫である、とも。
「言うまでもなく、蓄えられているデータの一つ一つは重要かつ部外秘。今夜の結果も研究を進めるうえで重要な一歩となる。凛、頼んだよ」
肩に乗せられた父の手を、重く感じながら。私は無言で承諾したのでした。
その夜。
別荘の寝室で、父はわたしと「哲くん」の写真を撮りました。
「ほら、もっと寄って寄って!」
楽しげな様子の父に急かされ、私たちは肩を寄せ合ってベッドに座りました。
正直、気が気ではありませんでした。
思考を占めるのは、恥ずかしさというよりは、強烈な不安。
この後に控えている「イベント」を意識すると、いてもたってもいられませんでした。
そして、「哲くん」からも、その雰囲気を感じるのです。
横にいれば、空気はひしひしと伝わるのです。
やはり、意識をしているようでした。
「ははっ、まるで新婚旅行の夫婦みたいじゃないか」
それとなく焚きつける父。
その言葉に反応しながらも、努めて押し隠そうとする「哲くん」。
父の目論見は上手くいっているようでした。
そして実際、その通りに事は運んだのです。
父が部屋から去った後、「哲くん」は言いました。
「……いいのか?」
何に対して許可を求められているのか。
そんなこと、問うまでもありませんでした。
彼から求められていること。それは、父も求めていること。
当の私だって、漠然と想像していたことでした。
期待したことがなかった、と言えば嘘になります。
……私は、小さく頷きました。
彼の顔が近づき、乾いた唇どうしがそっと触れ合いました。
途端に、抑えつけていた恐怖が胸にせり上がってきます。
父のために。カンパニーのために。そして何よりも彼のために。
これが、最善の道。
もとより、選択肢なんてありませんでした。
ちゃんと、分かっているつもりでした。
──なのに。どうして、こんなに怖いのでしょう。
……犯罪に加担しているという罪の意識からでょうか。
……「兵器」と交わることへの根源的な拒否でしょうか。
おそらくは、両方でした。
彼の手が、私の服へと伸びました。
なされるがままに剥がれていく自分。
自覚すればするほどに、ひび割れていく決意。
閉じ込めていたはずの怖気が、胸の奥から溢れだしていきました。
それはすぐに、「震え」となって明らかな形で表れました。
静まれ、と必死に己に言い聞かせます。
けれど、理性の奥の本能をとどめることは叶いませんでした。
彼は、私の異変に気付いたようで、一瞬のためらいを見せました。
しかし、それでも──意を決したように、自身の身体を私に寄せてきたのです。
──彼が、押し入ってくる。
──感染してしまう。
視界が彼の身体で覆われたその刹那。
虚勢の壁が、音を立てて決壊しました。
「……っ!」
手のひらに、固い手応えを感じました。
──私は、彼の胸を押し止めていました。
眼前には、呆然とした様子の彼。
直視することができず、私はとっさに目をつむりました。
「……こわい、ごめんなさい、怖い!」
無意識に口を突いて出たのは、偽りのない本心。
それは同時に、拒絶の意思表示でした。
「…………ごめん」
頭上から降ってきた声に、私は恐る恐る目を開きました。
視界はおぼろげに滲んでいて、自分が涙を流していたのだと気付きます。
数秒後に晴れた私の目には、彼の居たたまれない表情がありました。
「そうだよな、なんていうか……まだ早いよな、こういうの」
そう言って「哲くん」は、そっと身体を離しました。
そのまま、くるりと背を向け、手早く衣服を身につけていきます。
「大丈夫だから。……無理やりに、とかしないから」
薄明かりに照らされた横顔は、言いようもなく寂しげで。
私は、ごめんなさい、とつぶやくことしかできませんでした。
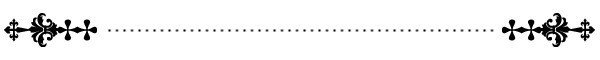
「なぜ、交わらなかった?」
別荘から帰宅したその日。
私は、行為に及ばなかったことを父に打ち明けました。
当然ながら、父の反応は冷たいものでした。
「計画の重要性については、さんざん話したつもりだったが? それが達成できなければ、私たちや『哲くん』がどんな未来を辿ることになるか。十分に分かっていたはずだろう? なぜ止めた?」
重く低い声は、まるで氷を思わせました。
問い詰められるだけで、情けないことに身が竦んでしまうのでした。
それでも……今にも折れそうな心を奮い立たせ、私は抗いの言葉を絞り出しました。
「間違ってます、こんなの」
「間違い?」
父の眉がつり上がり、額に幾筋ものしわが寄りました。
「正しい選択なんて、もとから用意されていない。新型ドールを完成させること、ひいては組織に協力すること。それこそが唯一にして最善の選択なのだから」
「……技術供与をすればそれで終わり、というわけではないでしょう? むしろ、『共犯』となったぶん、こちらの弱みが増えるだけです。研究を盾にして、新たな要求を突きつけてくるのは目に見えています。そうやって、ずるずると関係を続けて……罪を重ね続けて……それが表ざたになれば……その時こそカンパニーは……」
「潰れる、と? しかし、それは組織の条件に従わなかったとしても同じだ」
「ならばもう、いっそのこと潰すべきです」
「……本気で、言っているのか?」
怒りを通り越して、呆れたような顔つきでした。
「『哲くん』が、どうなってもいいと?」
「……どのみち、組織に引き渡すのでしょう?」
今度こそ、はっきりと父の顔がひきつりました。
父の怯んだ気配に乗じて、私は一心にまくし立てていました。
「重ねて言いますが、技術だけを供与するわけではないのでしょう? 組織からすれば、せっかくの『完成品』があるのなら、それを活用しない手はないですよね。お父さんは明確には言いませんでしたけれど……組織の要求にはそこまで含まれているのではないですか?」
問いつめる私を前にして、父は苦々しげに口元を歪めていました。
「社員を路頭に迷わせるわけには行かないのだよ」
答えになっていない答え。しかし、自分の見立ての正しさを確信するには十分でした。
……父にとっての家族は、会社であって、私じゃない。
前々から分かっていたことではありました。
「哲くん」にいたっては、はなから人間として認識していないのでしょう。
けれども、私は違います。
私にとっての家族は、父であり、そして「哲くん」なのですから。
「……私は、自分の家族に、罪を負わせたくないんです。もちろん、社員の方々だって大事に思っています」
「ならば、どうするつもりかね」
「……密告はしません。でも、私は協力はできません。何か……何か方法があるはずです。私は、それを探します」
次善の策なんて、ありませんでした。
問題を先送りしてなお、傍観者となるということ。
私は、卑怯な手をとったのです。
「……そうか」
父の声に、先ほどまでの覇気はもうありませんでした。
落胆とも諦めともつかない色を顔に浮かべて──私に退室するよう命じたのでした。

それから数ヶ月が経った、冬の頃。
父は、私と「哲くん」に引っ越しを命じました。
何の前触れもない指示に、「哲くん」はもとより、私も耳を疑ったものです。
「……どういうことですか?」
例のごとく、私は書斎で父と話していました。
ただ、今回は私の方から、自らの意思で赴いたのです。
秋に父からの指示を拒んで以来、私はドールについての話題を出さなくなっていましたし、努めて避けるように意識していました。
しかし、この日ばかりは別でした。
「……組織ですか?」
私がまっすぐに問うと、父は仰々しく頷きました。
「『哲くん』を引き渡さなかったからな。何らかの形で、回収しに来るかもしれない」
「引っ越し」の意図はこうでした。
この屋敷は都市部から離れているために、仮に組織から襲撃されても警察の迅速な対応は期待できない。
屋敷の警護に人員を割くにも限界がある、と。
新たに契約したマンションは、都市部に近く、セキュリティ設備も最新鋭のものを備えているという話でした。
要するに、私と「哲くん」を避難させようということらしいのです。
「組織は、哲くんのことを知っているのですか?」
「いいや、知られてはいないはずだ。新型ドールの制作を請け負ってはいるものの、その詳細については秘匿している。そしてこれからも、明かす気はない」
その視線には、決然とした意志が見て取れました。
「研究所の処分についても、準備が整った。近いうちに、隠滅するつもりだ。もし私に何かあったら──その時は頼んだよ」
そうして、最後に父はこうも付け加えたのでした。
「『哲くん』は、おまえが守れ」
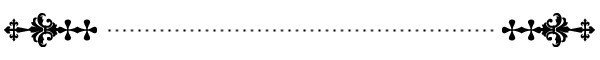
準備は整い、後は荷物を移動させるだけとなりました。
「哲くん」のためにとベッド型に模して作られた充電装置を前にして、私はこれからの日々に思いを馳せていました。
明日から、私は彼を守らなくてはならないのです。
その責任の重さを噛み締めながら、じっと窓の向こうを見つめます。
夜の闇に煌々と照り映えるマンションの群れ。遠目にも、無数の光が輝いているのが分かります。
彼が入居している部屋も、そのうちの一つなのでしょう。
今頃は何をしているのだろうか、とぼんやり考えずにはいられないのでした。
そんな時でした。暗がりに異質な光が閃いたのは。
窓越しに見えたそれは、街の灯りのように、自ら光を放ったのではありませんでした。
目に飛び込んできたのは、黒い光。
室内灯を反射して光った「それ」の正体を認識するには、あまりにも短すぎる時間でした。
瞬間──耳をつんざく轟音とともに、ガラスが飛沫となって飛び散りました。
室内の空気がそのまま衝撃となって、私の身体を押し飛ばしていました。
したたかに背中を壁に打ち付け、激痛に目の前がくらみます。
突然の事態に、何が起きたかも分かりませんでした。
徐々に晴れていく視界のなかで、最初に認識したのは、目の前の充電装置が黒煙を吹いているということでした。
部屋を、一面の炎がなめ尽くしていました。
そのなかで、蠢く人影。黒装束の、見知らぬ人々。
ただし、「知らない」のはこちらだけだったようで。
「──堂崎社長の娘だな?」
厳かな声が、耳を刺しました。
知っている? 私を?
瞬時にして、父と交わした会話と目の前の光景が、一本の線で繋がりました。
新型ドールの受け渡し拒否。組織。襲撃。
──逃げなくちゃ。
脳が下した指令そのままに、私は床を蹴っていました。
叫ぶことすら、忘れたままで。ただ襲撃者から遠ざかりたい一念で、半開きだったドアを押しました。
けれど、精巧なはずの脚パーツは、この時ばかりは動いてくれませんでした。まとわりつく恐怖の前に、両脚は単なる二本の棒と化し、もつれるばかりで。
ドアを押し開いたところで、私は床に倒れ伏していました。
ぴちゃ、と水音が耳元で鳴りました。
左腕の辺りから聞こえたその音に、反射的に目を向けると。
そこには、紅い水たまりが広がっていました。
水源は、すぐに見つかりました。
目と鼻の先で、自分と同じように倒れているもう一つの身体。
あまりにも見慣れた顔が、そこにありました。
「──おとう、さん?」
瞳孔の開ききった瞳に、すでに光はなく。
そこには、父の亡骸が……血の海に沈んで横たわっていました。
「あっ──ぁ、ぁあああ!」
意味をなさない呻きは、わずか数秒で遮られました。
背後から伸びてきた手が、私の口元を覆っていたのです。
そこには何か布のようなものが握られていて、息を吸った瞬間に、ほのかな薬臭が鼻腔に刺さりました。
その拍子に、視界がぐにゃりと歪み、頭がぼうっと霞みます。
どこか遠くで響く銃声と悲鳴のなか、私は暗闇の底へと真っ逆さまに落ちていきました。

`( ´8`)´<頂いたサポートはラムネ菓子となり僕の脳に100%還元されます。なお、押してくださった♡はモチベとなり僕の心に1000%濃縮還元されます。
