
act7 : Sat. Dec. 23th
◀第1話 act1 : Sun. Dec. 17th から読む

目覚めると、目の前にリンの顔があった。
どうやら、そのまま寝込んでしまったらしい。
音を立てないように、そっと身を起こす。
ソファーにもたれる格好で、すやすやと寝息を立てるリン。
そのままの体勢で寝ていれば、首や肩を痛めてしまうだろう。
俺はリンの背中を、ゆっくりと後ろに倒した。
背中に右手を当て、左手を膝の下に差し入れてそっと持ち上げて、ソファーの上に横たえる。
リンは目覚める気配もなく、幸せそうな寝顔をさらしている。
無理に起こす必要もないと思い、そのままにしておいた。
キッチンでコーヒーを淹れ、口に含んでみる。やはり、味は感じなかった。
今となってはもはや、楽しみを感じない朝の日課。
おそらく、もう自分は長くないのだろう。
焦げ茶色の湯を飲み下しながら、そう思った。
コーヒーを飲み終えて一息ついたところで、出し抜けにアラーム音が鳴った。
音源は、テーブル上のノートパソコン……それも、通話の着信だった。
無線機器の調子が回復したのだろうか?
訝しく思いつつも、椅子に座ってパソコンを立ち上げる。
途端に、スピーカーからわしゃわしゃと音の洪水が流れてきた。
通常ならば表示されるはずの映像も、映らないままだ。
今度はPC本体の故障か、と思いかけたところで、
意味をなさない雑音が徐々に「声」となって聞こえ始めた。
「──かな? ……聞こえるかな、佐藤 哲くん」
ノイズが収束し、はっきりとした言葉となる。
頭の中心から揺さぶるように聞こえだした声は、およそ常人のそれではなかった。
幾重にもフィルターをかけられたように音声加工が施されていて、耳にまとわりつくような不快感があった。
その不審げな声が、自分の名前を呼んでいるという事実。面喰らった、というのが率直な感想だった。
「……誰だ?」
思わず、つぶやきを漏らしていた。
パソコン通話のアドレスを教えている友人はそう多くない。
それも、実際のやり取りをするのは鈴木ぐらいのものだった。
しかし、この相手は明らかに鈴木ではない。
こんな悪戯めいた通話をするとは到底考えられなかった。
異常な通信を切ることもできず、俺は呆気にとられていた。
「『傀儡』と言えば、分かってくれるかな?」
真正直というか、律義というべきか……声の主は、自らを名乗る。
分からないはずがない。ドールを用いる悪名高い組織。それを、開けっぴろげに自称している。
数秒の思考停止を経て、俺は投げやりに言ってみせた。
「……手の込んだイタズラですか? 止めてくれませんか、そういうの」
無言電話よりはいくぶんマシだったが、それでも性質の悪い冗談だ。
——そんなふうに、思うことにした。
信じたくないという拒絶と、信じられないという不審。
先立つものは、後者だった。防衛本能と言ってもいい。
まかり間違っても、世間を騒がせている犯罪集団が馬鹿正直に名乗るわけがないのだから……。
「——『堂崎凛』が、そこにいるだろう?」
その一言に、心臓を鷲掴みにされるような心地がした。
「まずはお礼を言っておこうか。彼女を預かってくれてありがとう、とね」
さも愉快そうに、だみ声が跳ねる。俺は何も言葉を返せずにいた。
相手は、ここにリンがいることを知っている。
どう返せばいい?
思考は空転する。あくまで白を切るべきか、このまま通話を切るべきか——
「おとといの『誕生会』は楽しそうだったね。
人と人形の交流が、かくも和やかなものかと認識させてもらったよ」
「…………っ!」
今度こそ、俺は相手を——「傀儡」を認めざるを得なかった。向こうは、おとといの出来事を把握している。そして何よりも……リンがドールであることを分かっている。
「ちなみに、こちらの声は彼女には聞こえない。
人間とドールでは音の可聴領域に違いがあってね。
人間だけに聞こえる音、そして逆に
ドールだけに聞こえる音というものも存在する。
この通信は、いわばラジオのようなものであって、
周波数の合う君だけに聞こえるのさ」
こちらの沈黙を肯定と受け取ったのか、相手は嬉々とした調子で説明を続けた。
「つまり、君が声を荒げない限りは、彼女もそうそう起きないだろう。
冷静に話し合おうじゃないか」
「……おまえらが、堂崎家を襲撃したのか?」
「ああ、そうだよ」
あまりにも重い事実を、ごく軽い調子で肯定する『傀儡』。
「君の素性を調べたよ。非常に興味深かった。
堂崎凛の恋人だったそうだね。
……さしずめ、姫を守る王子様というところか?
今になってもそんな役割を続けているとは、律義なものだ」
「黙れ! 警察に……」
「通報する、かい? 無駄だよ。
通報したところで、私たちの足跡は追えまい」
相手の声に動揺は微塵もなかった。
軽々しい口調は変わらず、どこか楽しんでいるようにさえ感じられる。
「むしろ、それはこちらの台詞だよ。
こちらの指示に従わなければ、君たちを警察に通報する」
「冗談も大概にしろよ、いったい何の罪があって——」
「殺人兵器——アクマの所持、という名目で。
そうすれば君たちも、めでたく我々の一員だと認識されることだろうね」
「なっ……!?」
「君たちは、今や社会的に『追われる』側であることをわきまえた方がいい」
「…………」
「自分の立場を認識してくれたかい?
それならさっさと本題に移ろうか」
「……何が、目的なんだ」
「単純なことだよ。私たちは、きみたちを『保護』したいのさ」
ものは言いよう、ということか。
狙いはおそらく、アクマであるリンの回収。
そして、事情を知る俺の口封じ。
良くて軟禁、といったところだろうか。
いずれにせよ、その内実は決して真っ当なものではないように思えた。
「最近では、警察も捜査網を広げてきている。
君たちが拘束されるのも時間の問題だ。
——明日、お宅へお邪魔するよ。
逃げ出そうなんて思わないことだ、分かったね」
「……ああ」
表面上は承諾しておいたが、内心は違う。
結末の見え透いた要求を呑むことなど、できなかった。
——絶対に逃げてみせる。リンを渡すわけにはいかない。
考えるまでもないことだった。すでに、腹は決まっていた。
再び、機械じみた音声が室内に響く。
「最後に一つ。……恋人なら、身だしなみには気をつけたほうがいい」
「……余計な世話だよ」
「そうかそうか。じゃあ、明日。楽しみに待つといい」
不気味な笑い声を残し、通話は途絶えた。
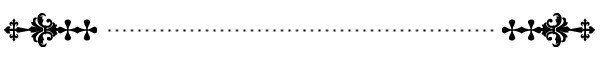
まどろみから覚めたとき、私はソファーの上に寝かされていました。
壁掛け時計を見れば時刻はもう昼に近く、ガラス窓からさんさんと陽の光が降り注いでいます。
昨晩の記憶を辿るうちに、はっと気付いたことがありました。
彼が眠っていたはずのソファーに、私がいるという状況。
「テツくん?」
部屋を見回しても、彼の姿はありませんでした。安穏とした休日の静けさが、どことなく心細く感じられてなりませんでした。
上体を起こし、小さく伸びをしたところで、ドアの向こうから足音がしました。
ほどなくして扉が開き、彼が部屋に入ってきました。
ほっと安心したのも束の間、その面持ちが険しいことに気付きます。
彼の右手には、小さなホワイトボードとペンが握られていました。
「……おはよう」
心持ち硬い笑みを浮かべながらの挨拶。
次いで、彼は空いている左の掌をこちらに突き出しました。
そうした後に、今度は人差し指を立てて唇に当てるのです。
(……『待て』『静かに』?)
ジェスチャーの意図をくみ取り、私は無言で頷いてみせました。
彼は机に向かうと、ホワイトボードにペンを走らせ始めました。
ほどなくして彼が掲げたボードには、短い文章が書き連ねられていて。
そこにいわく、
『室内の会話が盗聴されているみたいだ。筆談で会話しよう』
思わず、声を上げるところでした。
せりあがってきた息を唇でどうにか押しとどめ、私は彼を見つめました。
ソファーから立ちあがり、彼のもとへ歩み寄ります。
ペンを受け取り、私は板の余白へと質問を記しました。
『何か、あったの?』
ペンがさらさらと動き、一連の出来事が板の上に再現されていきました。
私が眠っている間に、「傀儡」からPC通話を用いた接触があったこと。
彼らは、私がこの部屋に身を寄せていると知っていたこと。
のみならず、私がそのとき眠っていたという状況さえも把握していたこと。
そして——傀儡が私たちを「迎え」にくるという予告。
彼は、私に問いかけます。
『リンは、そもそも傀儡のもとへ戻るつもりだったのか?』
——ううん、そんなつもりは欠片もなかった。
『じゃあ、他に行くあてがあったのか?』
——うん、そう。行かなくちゃ行けない場所があるの。
彼は思案げに私を見据えました。
その目は雄弁に「どこへ行くのか」と問いかけていました。
しかし、それも少しの間の事で、彼は追及を思い留まったように目を伏せました。
『どうやってそこに行くつもりなんだ』
——できることなら、車を使いたい。
目的地は、徒歩で行くには遠すぎて、鉄道路線からは離れすぎていました。
彼の顔が曇ります。
私の記憶が確かならば、彼は運転免許を持っていないはずでした。
『リンは運転できるのか』
——ごめん、できない。
身勝手な要望であることは重々承知しています。
それでもやはり、目的地を目指すための交通機関としては、車が最善でした。
『少し、考える時間をくれるかな』
そう書き置いて、彼は居間を後にしたのでした。
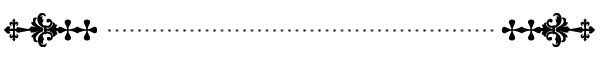
彼女とともに、どうやって逃げるか。
そのことだけが、頭の中を占有していた。
あえて、リンに行き先は訊かなかった。
どこに監視の目が光っているかが分からないからだ。
それを聞くのは、外に出てからでも遅くはないと思った。
得た情報は、「目的地」は徒歩で行くには遠いということ。
そして鉄道路線からは離れているということ。
リンは車を希望しているということ。
(距離は遠くて、付近に鉄道が通ってなくて、道路でしか行けない場所……)
それだけでは、皆目見当もつかなかった。
俺としては、人混みでの「発作」を避けたいという思いもあって、車を使うことには賛成だった。
問題は車をどうやって手に入れるか、そして手に入れたとしても誰が運転するのかということだ。
俺に運転経験はない。リンも出来ない。
ならば、タクシーを使うぐらいしか手はない。
行先はリンが指示してくれるだろう。ただ、どこまで行くかは分からない。
資金は手持ちの分だけで足りるだろうか……。
不安は尽きず、思考を巡らせれば巡らせるほどに気落ちしてしまいそうになる。
——その時、唐突に携帯が鳴った。
「傀儡」からのPC通話が脳裏をよぎり、一瞬にして身が竦んだ。
着信を恐る恐る確認する。そこに表示されていたのは「アルミ」だった。
「やー、元気ですか?」
能天気な声が響いて、思わず脱力してしまう。
気を取り直して、俺は画面越しにアルミを見つめた。
「なんだ、どうした……?」
「いや、せっかく電話番号教えてもらったのに、
全然かけてなかったなーと思って」
「用件が済んだなら切っていいかな」
「ちょっと! 素っ気なさすぎ!
……もちろん、ちゃんとした用があるから連絡したんだよ?」
一拍の間を置いて、アルミの声が耳元で響いた。
「——たっくんが心配してたよ? 昨日もいきなりパニクったんでしょ?」
「……大丈夫だよ、心配ないから」
ふーん、と適当に相槌を打つアルミ。
はなから信じていない様子だった。
「……そっか、自分で言うなら大丈夫なんだろうね。
じゃあ明日は一緒にデート行けるんでしょ? ね?」
「——はっ?」
「あ、たっくん来た。はいはい代わるねー♪」
「おいアルミ、ちょっ……」
「おい哲、レンタカー借りてやったぜ!!」
受話口からいきなり野太い声があがり、耳元の空気を大きく震わせた。
「おまえ、本当に借りたのかよ……行かないって言っただろ?」
「俺とアルミが『凛』に会いたいの!
PC通話だけじゃ物足りないんだよ……
しかもさ、明日には返却するんだろ?」
「……別に今日じゃなくたって、」
また会えるだろう——そう言いかけて、思う。
いったん逃げ出してしまえば、もうリンはここに戻らない。
そして、俺も戻るつもりはなかった。いや、おそらくは「戻れない」のだ。
急激に悪化する体調と、ここ数日に起きた身体の異変を思い返せば——
俺はもう、長くない。
すでに、俺は感染してしまっているのだろう。
それは予感というより、ほとんど確信に近かった。
だからと言って、病院に行く気もない。検査とやらを受ける気もない。
自分の命よりも、彼女が傍から居なくなることのほうが惜しかった。
「兵器」として摘発されれば、リンは捜査のために処分されてしまうに違いない。
そんなことは、絶対に許せなかった。
リンとともに逃げるということ。
それはすなわち、俺にとっては死出の旅路を意味していた。
そして、鈴木とアルミにもう会うことはない──
「何と言おうと迎えに行くからな。『凛』も絶対に連れて来るんだぞ!」
やめろ、と制しかけたところで——
鈴木の言葉に、ふと「案」が浮かんだ。
「……鈴木、一度切るぞ。あとの連絡はメールでするから」
通話を切り、数分の迷いと葛藤の末に……俺は鈴木へとメールを打っていた。
『リンは行きたい場所があるらしい。そこに連れて行ってくれないか?』
——鈴木のレンタカーに乗って、リンの言う「目的地」まで運んでもらう。
それは、心苦しい選択だった。
彼らを利用する形になる。
加えて、鈴木とアルミを厄介事に巻き込むことにもつながる。
無関係な彼らを危険に晒してしまうかもしれない。
だが——逃げ出すなら、即座に行動するべきではないのか。
『傀儡』との通話から、まだ三〇分と経っていない。時刻は昼時。
人気の多いこの時間帯なら、うかつに手を出せないのでは?
そんな希望的観測が、のそりと芽吹いた。
間を置かず、携帯が振動する。
鈴木からの返信は『OK』だった。
『今からマンションに迎えに来てくれないか。なるべく早く頼む』
今度の返信は、ものの数秒だった。
『おうよ任せとけ!』
「ごめんな……鈴木」
今頃は、喜び勇んで車に飛び乗っているかもしれない。
二人の楽しげな様子が目に浮かぶようで、いたたまれなかった。
その後、鈴木と短いメールのやり取りをした。
『以後の連絡はメールで頼む』
『車の外見を教えてくれ。可能なら車種も』
『車はマンションの玄関口に停めてくれ』
『到着の五分前ぐらいには連絡を』
矢継ぎ早に送受信を繰り返し、俺は居間へと向かった。
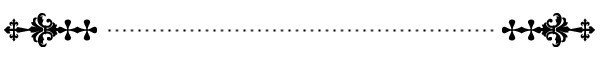
『鈴木とアルミが車で迎えに来るから、準備して』
ホワイトボードに手早く書き込んで見せると、リンは驚いたような素振りを見せた。
『赤いミニバンで来るらしい。車種は……』
鈴木から送られてきたメールを見せつつ、計画の要点をかいつまんでボードに記していく。
ひと通りの説明が終わると、リンは仕方なしと寂しそうに微笑んだ。
準備を整えるようにと伝えはしたものの、持つ荷物は特になかった。
リンの手荷物はポーチ一つ。俺にいたっては、ほとんど手ぶらと言っていい。
財布に携帯……いつもの携行品。
ただ一つ違うのは、ポケットに忍ばせた一振りの果物ナイフ。
折り畳み式の小さいものだ。
護身用には少し心もとないが、何も持っていないよりはマシだと思った。
他にできることと言えば、マフラーやキャップで顔の輪郭を隠すことぐらいだった。
土間に二人して腰掛け、その時を待った。
やがて、携帯が鳴る。鈴木からのメールだった。
……あと五分で、彼らが到着する。
——行こう。
リンの手を引き、俺は玄関のドアを押し開いた。
エレベーターに乗り込み、1階ボタンを押す。
幾度となく繰り返してきた何気ない行動にも、今はひどく緊張してしまう。
自分の手が小刻みに震えていることに気付き、胸の内で叱咤した。
40……39……38……
降下していくスピードが、やけに遅く感じられる。
30……29……28……
刻々と減っていく数字に目を凝らす。
20……19……18……
繋いだ手が、強く握られる。
10……9……8……
応えるように、強く握り返した。
——扉が開く。
広々とした正面玄関が眼前に表れ、俺たちは一歩を踏み出した。
同時に、ガラス製の自動ドアの端から、車の影が滑り込んできた。
赤のミニバン——とは似ても似つかない、シャープな車体。
ボディを彩るのは、白と黒のツートンカラー。
そして、頭頂部には赤のランプ。
「……パトカー?」
瞬間、思考が凍りついた。反面、足は弾かれるように動いていた。
馬鹿な。何故こんな早くに!
突如として湧きあがる疑問、驚愕。
諸々を振り切って、逃げることだけを考える。
ドアを抜け、建物づたいに裏口に回ろうとしたところで——息を呑んだ。
そこには、大柄な二人の警官が壁となって立ちふさがっていた。
「……佐藤 哲さんですね?」
手帳を開きながら、片方の警官が尋ねてくる。
「少し、お話を伺いたいのですがよろしいですね?」
返答を待たず、もう片方が畳み掛けるように口を開いた。
反射的に凛を背中にまわし、かばうようにして後ずさる。
俺の挙動に、警官の視線がリンへと注がれる。
「そちらの女性は『ドール』ですね」
「……違う!」
「センサーは反応を示しているんですよ。なぜ嘘をつくのですか?」
警官の手には、棒状の細長い装置が握られていた。
ヒューマノイド・センサー。
ヒューマノイドの発する微弱な電波を感知する、検査機器。
そのランプが赤く光り、ドールの存在を明示していた。
「身長、髪型、服装。
どれも、通報にあった『女性型』の特徴とも合致しています」
もう一人の警官が、こちらを見据えながら言葉を重ねた。
「……少し前に、あなたが違法ドールを所持していると通報がありましてね」
背中をひやっとしたものが滑り落ちた。
傀儡の仕業だということは明らかだった。
「そう怖い顔をなさらずに。
『検査機』を持参しておりますので、ここで済ませてしまいましょう」
そう言って、警官は懐からリモコン状の機器を取り出した。
「これを当てるだけで、正常な『エンジェルドール』かどうかは分かります。
反応がなければよいのですが……万一、反応があった場合は署までご同行願います。よろしいですね?」
有無を言わせない口調で、検査機を持った警官がこちらに歩み寄る。
「やめろッ!」
無意識のうちに叫んでいた。
考えるより先に身体が動き、警官の前に立ちふさがっていた。
相手の顔に、疑念の色がはっきりと浮かびあがった。
「いや……っ!」
不意に、背後で短い叫びが上がった。
振り返ると、リンが別の二人組の警官に捕まっていた。
「——リン!」
とっさに、俺は駆け出していた。
リンを囲む警官の目が、見開かれる。怯んだ様子が見て取れる。
やるしか、ない。
思考するより先に、ポケットに忍ばせていたナイフを取り出そうとした。
——瞬間、横腹に鈍い衝撃が走った。
視界の端に、警官の拳を捉えながら……俺はその場に崩れ落ちていた。
「少し、静かにしていて下さいね」
そのまま地面に押さえつけられ、身動きが取れなくなる。
体に力が入らない。
身をよじり、リンを視界にとらえるだけで精一杯だった。
「いや! 離してっ、離してよ!」
リンは二人の警官に羽交い絞めにされていた。
もう一方の警官の手には、検査機が握られている。
なおも身体をよじらせて抗うリン。
髪を振り乱し、声にならない声を上げる。
かろうじて動く脚を振り回し、警官を遠ざけようともがいていた。
しかし、必死の抵抗も、長くは続かなかった。
リンはその場に組み伏せられ、完全に固められる格好になる。
その上から、検査機が迫っていた。
「やめろ……やめてくれよ……!」
何もできなかった。ただ、目の前の光景に叫ぶことしかできなかった。
そして、検査機がリンの首筋に押し当てられ──
「やめろ————————!!」
——静寂が、訪れた。
永遠のようにも思われた数秒の後に……警官たちの表情が一変した。
その挙動には、焦りが色濃く表れていた。
やがて、リンを組み伏せていた警官が呆然としたように口を開いた。
「反応が……ありません……!」
——反応が、ない?
「……その女性型は『兵器』ではない、と?」
「はい。ですが……」
検査機を携えた警官が、うろたえた様子で言い淀む。
「ですが……それだけではなく……ドール反応さえも無いのです」
殴りつけられたような衝撃が、頭を打った。
交わされる言葉に理解がまるで追いつかず、頭が真っ白になる。
——リンが、ドールですらない、だって?
一体、何を言っているのだろう?
「これは、いや、この女性は……『人間』です」
先ほどの抵抗が嘘のように、リンは沈黙していた。
周りを取り巻く警官たちは、事態の不可思議さに戸惑っているようだった。
「どういうことだ?」
俺の傍に立っていた、リーダー格らしき年配の警官が口を開いた。
その問いは俺に対してではなく、リンへと向けられていた。
「あんたが人間なら……どうして検査を拒んだ?」
リンは答えない。顔を伏せたまま、動じない。
年配の警官は、手元の計器を覗きこみ、うっすらと顔を曇らせた。
「センサーはまだ反応を示している……ということは、だ」
・・・・・・・・・・
迫る足音が、地を伝って耳に響く。
首をひねると、頭上に警官が立っているのが見えた。
腰を屈め、突き出した手には検査機が握られていた。
間を置かず、首筋に固いものが押し当てられる感触があった。
ピ————————————
無機質な電子音が、天高く鳴り響いた。
いま聞こえる音の意味。
いましがた聞いた言葉の意味。
……あれ?
何がなんだか分からない。分かりたくない。
夢、幻聴、どれでもない。
分かってしまう。分かってしまった。
リンは人間で——
そして、俺は——
——ぱァん、と。
瞬間、鋭く乾いた音が断続的に爆ぜた。
後を追うように、苦しげなうめき声が上がる。
反射的に顔を上げると、リンを取り囲んでいた警官が、地面でのた打っていた。
立ち上がるリンの手元で、黒い物体がきらめく。
こちらに向けられた「それ」は拳銃だった。
再び、数回の発砲音。
身体がふっと軽くなり、どさりと音を立て、横に警官が崩れ落ちた。
抑えた肩から、赤いものが染み出していた。
「────逃げて!!」
怒鳴るような叫びに、俺は打たれたように駆け出す。
リンも、俺に続いて並び走った。
背後から、苦悶の唸り声と怒声が追いすがる。
しかし、足音はない。辺りを横目で確認するが、他に人はいない。
駐車場が途切れ、道路に面した出口が見えた。
このまま突っ切れば、逃げられるか?
そう思った時だった。
数発の銃声が背後から上がり——下半身に衝撃があった。
脚がもつれ、走る勢いそのままに、出口付近へと倒れ込んでしまう。
「テツくん!」 リンが叫んだ。
太もものあたりに痛みを感じる。
けれど、それほど辛くない。大丈夫だ、まだ動ける。
よろめきながらも立ち上がり、歩道へと飛び込んだ。
「うお——い、哲!」
名前を呼ぶ、遠くからの声に視線を向ける。
こちらに向かって疾走する赤のミニバン。
窓から顔を出して手を振っているのは——アルミだ。
急停車し、後部ドアが開け放たれる。
リンが先に乗り込み、手を差し伸べてくる。
俺はそれを掴み、死力を振り絞って身体を投げ出した。
「鈴木、すぐに出してくれ!」
「あいよっ!」
威勢のいい声とともに、車体がぐんと加速した。
住宅街の一本道は閑散としていて、行く手を遮るものは何もない。
瞬く間に遠ざかっていく高層マンションを見やりつつ、大きく息を吐いた。
横を向くと、アルミも肩で息をしていた。
「悪い悪い、渋滞に捕まってな。一〇分も遅れちまった」
「てか、二人とも……何でそんなにぐったりしてんの?」
何か喋ろうとしたものの、歯の根が合わなくて言葉が出なかった。
いまだに膝が笑っている。
安堵の気持ちは皆無だった。
俺たちは、今度こそ完全に追われる立場になったのだから。
一度に様々なことが起きたばかりに、思考が整理できずにいた。
左の太ももが小さく疼く。
そっと触れてみると、ジーンズには「穴」が空いていた。
駐車場を駆けた時に聞こえた銃声と、その時の衝撃が生々しく思い出された。
恐る恐る、傷の奥へと指を這わせてみる。
ささくれだった皮膚。
しかし、湿り気はなく、手が赤く染まることもなかった。
——血が、出ていない。
不吉な予感が、背筋を這い上がる。
前の座席からは見えないように、そっと傷を覗き込む。
穿たれた穴のさらに奥で——金属骨格が、薄日を反射して光っていた。
「なぁ哲、おまえってば無視してんのか?」
「……えっ?」
斜め前方から唐突に飛んできた声に、慌てて顔を上げる。
「ほらほら、見て気付かないか?」
そう言って、運転席の鈴木が振り向いた。
そこでようやく、「変化」に気付く。
鈴木の頭が丸刈りになっていたのだった。
「あ……髪、切ったのか。しかも、また大胆に」
朝のセットがダルいんだよな、とぼやいていたくらいにとんがった髪は、もう見る影もない。
以前とのギャップが大きいぶん、インパクトも抜群だった。
「デートに備えて変えてみたんだが、どうよ?」
見るからに寒そうだよ、と苦笑しかけたところで、助手席のアルミが遮るように身を乗り出した。
「似合ってるよ、たっくん! 高校球児みたいで爽やか!」
「……ああ、イメチェンとしては悪くないんじゃないかな」
「あたしもね、ネイルしてみたー! どう、似合う?」
手の甲をこちらに向け、ひらひらと振って見せる。
ピンクに彩られた爪はラメやビーズで飾りつけられていて、ハートなんかの模様も見える。
「ああ、似合ってると思うよ」
「でしょでしょ! 自分でも気に入ってるの」
満足げにアルミが笑い、俺の頭へと視線を移した。
「哲は、髪型変えないの?」
「俺はいいよ。別に髪なんて——」
自分の言葉に、喉が詰まる。
そう言えば、髪を最後に切ったのは、いつだった?
それだけじゃない。爪を切ったのは、いつだった?
まるで思い出せなかった。
髪を切ったことはある。爪を切ったこともある。当然のことだ。
でも、どちらも最後の記憶は……確か、堂崎家が襲撃された数日前のことで。俺は、この一年、髪も爪も切っていないじゃないか。
なぜ、切らなかった?
だって「伸びなかった」から。
傀儡との通話が、ふっと頭をかすめた。
あの時、相手が最後に付け足した言葉。
『身だしなみには気をつけろ』と。
確かに、俺は身だしなみとやらを怠っていた。
なぜなら、その必要がなかったからだ。
髪も爪も伸びない身体——
そう、つまりは俺がドールだったからで。
「……別に、今の髪型のままでいいと思ってるからさ」
「なにそれ、つまんないの」
俺の無味乾燥な返事に、アルミが不満そうに口をとがらせた。
やれやれと肩をすくめ、それから、隣の凛のほうへ身を乗り出した。
「凛ちゃん、改めまして初めまして!」
アルミがリンに笑顔を向ける。リンも、つつましげに笑い返した。
「わぁ……間近で見て改めて思ったんだけど、凛ちゃんかわいいね!」
「だろう?」 運転席から、鈴木の声が飛ぶ。
「中学や高校でも密かに評判だったんだぜ?
狙ってる男も多かったんだ。
もっとも、凛には哲がいたから、そいつらは悔しそうにしてたけどな」
どこか誇らしげな鈴木の説明に、アルミは納得した様子で目を輝かせていた。
「だよねー。お化粧してなくてもきれいだもの。
それに、お肌の質感もドールとは思えないくらい——あいたっ」
鈴木が、空いている左手で、アルミの頭を軽く小突く。
アルミは自分の「ミス」に気付いたようで、えへへと慌てたように愛想笑いを浮かべた。
……『リンを、人間の『凛』として扱ってほしい』
かつて俺が、PC通話で鈴木とアルミに頼んだことだった。
さっきのアルミの発言は、リンがドールであることを前提としたものだった。だから鈴木は、それをたしなめるために、アルミを軽く小突いたのだろう。
ドールであるリンを、表面上は人間の『凛』として扱う。
それが暗黙の了解だった。
今にして思えば、それは結果として「正しかった」。
リンは、ドールではなく……本当に、人間の凛だったのだから。
「なぁ『凛』、どこ行きたい?
遊園地か? 水族館か? それとも買い物か?」
うきうきとした調子で、鈴木が凛に尋ねる。
話題を切り替える意味合いもあったのだろう。
俺としても、その質問はありがたかった。
どこに行くかもわからないまま、道をさまよっていてはまずい。
鈴木とアルミは知る由もないが、俺たちはもう「犯罪者」なのだ。
警察内では連絡が行き渡っているだろうし、すぐに検問も敷かれるだろう。
捕まる前に、一刻も早く目的地に到着して、鈴木たちと別れなければいけない。
不意に、凛が静かに口を開いた。
「大通りを離れて、山道に乗ってほしいの」
「山道? どうしてまたそんな?」
「昔みたいに、みんなで別荘に行きたいの。鈴木くん、場所は覚えてる?」
「ああ、覚えてるぜ! 別荘か……懐かしいねぇ」
「うん。昔みたいに、ゆっくりしたいなと思って。
——でね、もう一つお願いがあるんだけど、
途中でそれとは別の別荘に寄りたいの。
そこに色々と荷物が置いてあったから。……ね、テツくん」
「ああ、そうだな」
同意を求められ、反射的にうなずく。
しかし、俺は凛の言う「別の別荘」の存在を知らなかった。
「はいよ、了解。じゃあ、そっちの別荘の道案内は任せた」
整備された街路から離れ、車は林道へと滑りこんでいった。
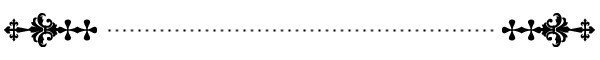
……それからしばらくは、穏やかな談笑の時間が続いた。
アルミと凛は、すぐに打ち解けた様子で、色々と話をしていた。
といっても、喋っているのはもっぱらアルミで、凛はそれに相槌を打つ程度だった。
それでも、傍目から見れば楽しげなやり取りに映るのだった。
「鈴木くん、あの標識のところで停めてくれる?」
三〇分ほどの時間が経った頃だった。
凛の指示に従い、鈴木が道路脇に停車する。
「……ここでいいんか?」
鈴木は車窓から辺りを見回し、リンに訝しげに尋ねた。
山の中腹。周囲のどこを見渡しても、一本道の道路以外には道などない。
ただ、雑木林が延々と広がっているだけで、「別荘」はどこにも見当たらない。
鈴木の問いも当然のことだった。
「うん。この道から、少し歩かなきゃいけないの」
凛が指差した先に目を凝らすと、草葉に隠れてうっすらと「道」が見えた。
褐色の地肌が少し覗いている程度で、言われなければ「道」とは認識できないような一本の筋が、斜面に沿って薄く伸びていた。
道幅は狭く、とてもじゃないが車は入れそうにない。
「なんつーかあれだな、ケモノミチだな」
鈴木が頭をかきながら、そんな感想をぽつりと漏らす。
「鈴木くんとアルミちゃんは、知ってる方の別荘に先に行ってて」
「えっ? 俺たちも付いていったほうがいいんじゃないのか」
「ありがとう。でもね、大丈夫。
その別荘までは距離があるけど、そこには車もあるし、
運転手用のドールも備え付けられてるの。
荷物を準備したら、別のルートで鈴木くんたちのいる別荘に行くから」
「……そうか?」
「うん。それにね、実を言うと……テツくんと二人で話したいこともあるんだ」
「たっくん空気読もうよ!」
底抜けに明るい声でアルミが悪戯っぽく言うと、鈴木は渋々ながらも了承したようだった。
「……ごめんね」
「ああいや、いいんだ。『凛』がそう言うなら。
いやまあ俺もそこまで無粋な男じゃないし!
男女の機微には人一倍ビンカンですからね、ええ!」
冗談めかして笑う鈴木だったが、やはり無理をしているように見える。
ドールと思い込んでいるとはいえ……凛と長く居たいと思う気持ちはあるのだろう。
胸の内を察しつつ、後ろ髪を引かれるような思いにとらわれそうになる。
凛がドアを開け、歩き出そうとする……が、
「あっ」
数歩進んだところで、小さな叫びと同時に華奢な背中がよろめく。
そして、そのまま地面にへたりこんでしまった。
「……凛!?」
突然の異変に、車を降りて凛に駆け寄る。
鈴木も同じく、横から飛び出していた。そして、驚いたような声を上げた。
「おい、おまえその脚……」
見れば、凛の履いていたハイソックスは破れ、その裂け目から傷が見え隠れしていた。
両脚に点々と空いた穴が、事態の深刻さを物語っている。
おそらくは、マンションの駐車場で警官に撃たれたものだ。
もともと、家に来た時から傷だらけだった脚。
加えて銃弾を浴びたとなれば、さしものドールパーツであっても無事ではないだろう。
「違うの、転んで引っかけただけだから……大丈夫だから……!」
落ち着きなく、苦しそうに弁解する凛。
必死に立ち上がろうとするが、腰を宙に浮かせたところで再びバランスを失い、地面に倒れてしまう。
「ちょっと凛ちゃん、その脚じゃ無理だよ!」
「無理じゃ、ない……」
みたび、身体を起こそうとする凛だったが、やはり結果は同じだった。
「たっくん、あたしの『パーツ』って車に乗せてたよね?
それ出してあげて!」
ああ、と鈴木が応じ、車のトランクを開ける。
その中から——『脚』を腕に抱え、戻ってきた。
呆然としている俺に向かって、アルミがにこやかに告げる。
「私が前に着けてた『脚』だよ。
この前、一緒にドールストアに行った時に交換したやつ」
アルミは鈴木から『脚』を受け取ると、座り込んでいる凛のそばに屈みこんだ。
「たぶん大丈夫……型番も、替えがきくタイプみたいだし。
ちょっとごめんね」
凛の脚を横たえ、アルミが靴とソックスを脱がせる。
数々の傷跡と、足裏の円いエンブレムが露わになった。
アルミが、両足に刻まれたエンブレムの中心部を押した。
その光景は、まるで整体師が足のつぼを押しているかのようにも見えた。
瞬間、かちり、と鍵を解錠するような音が鳴る。
アルミはそれを確認すると、やにわに凛の太ももと足首を掴み、ネジを緩めるかのように手を回した。
「じゃあ、失礼しますね」
すると、滑らかに脚が回転し、膝から下の部分が取り外された。
金属骨格と、その周りを取り巻く透明な疑似筋肉が表出する。
アルミは、かつての自身の『足』を手に取り、断面へと接いだ。
そうして、再び両足裏のエンブレムを同時に押し込んだ。
再度、かちり、と音が鳴り——アルミが表情を緩ませた。
「——うん、これでどうにか大丈夫かな。
念のためにあと五分ぐらい待てば、ちゃんとくっついてると思う!」
流れるような一連の動作に、俺はただ魅入っていた。
アルミがこちらを振り返り、申し訳なさそうな表情を見せた。
「出しゃばってごめんね? ……こうするしかないと思って」
「あ——いや、ありがとう。助かったよ」
ドールパーツの着脱を目の当たりにするのは、二回目のことだった。
けれど一回目は、ドールストアでちらりと垣間見た程度。
実際のところ、ここまで詳細に着脱の手順を見たのは初めてだった。
アルミは凛に視線を戻し、色々と話しかけている。
大丈夫かな、おかしくないかな、と聞こえてくるあたり、「癒着」の状態を気にかけているらしかった。
「おい、哲」
振り向きざま、鈴木が俺の肩を引き寄せた。
強い力でもって、そのまま車の影まで連れて行かれる。
凛とアルミから死角となっている場所で立ち止まり、低い声で耳打ちされた。
「……何が、あった?」
……俺は、答えられなかった。じっと真正面から見据えてくる鈴木。
直視できず、俺は逃げるように顔を背けてしまう。
「あの傷、どう考えても不自然だろ。
『転んだ』とか『ひっかけた』程度のもんじゃない、
ぶっとい釘を打ったような穴があったじゃんか」
「…………」
「明らかに、誰かに傷つけられた跡だ。しかも手ひどくな。
おまえも知ってるだろうが、ドールパーツってのは
少しぐらいの傷じゃびくともしないんだよ。
それが『歩けない』ほどに傷つくなんてのは相当だ。
……でもな、おまえが『凛』にそういう事をするとは思えないんだよな」
大きく息を吐き、鈴木は強い口調で言った。
「質問を変えるよ。誰から、何を、された?」
眉間に皺をよせる鈴木。
薄々、感づいているのだろう。身を案じてくれているのだろう。
けれど、事情を教えるわけにはいかなかった。
鈴木を、アルミを、巻き込むわけにはいかなかった。だから。
「……今は、言えない」
そう口を動かすのが、精一杯だった。
「俺たちと別れたら、別荘に閉じこもっててくれ。
あそこは、セキュリティも整ってるはずだから。
……もしくは、そのまま逃げてくれ。
正直に言えば、きょう俺たちと関わったことを忘れて欲しいくらいだ。
警察に何か訊かれたら、
俺たちのことを悪者に仕立て上げてくれて構わない。
脅されたとか適当にでっちあげてくれていい」
俺が話している間、鈴木は無言だった。
車体に背を預け、しばらく虚空を見つめていたが——
やがて、深々とため息をついた。
「……ぶっちゃけ、何が何だか分かんねえよ。すっげーモヤモヤする。
でも、これ以上訊いたところで、おまえはだんまりを決め込むんだろう?
肝心なことは何ひとつ話さないとか反則だろうよ」
まったくもってその通りだ。責められても、何も文句は言えやしない。
それでも、俺は黙するしかなかった。
鈴木はなおも厳しい視線を俺に注いでいたが、やがて根負けしたように首を振った。
「分かったよ、何も訊かんよ。——その代わり、約束しろ」
鈴木が、こちらにゆっくりと向き直る。
「『凛』に着けたドールパーツ。
あれ、おまえにやったわけじゃないからな……
『貸した』だけなんだからな?」
それから、一息の間を置いて、続けた。
「——だから、絶対、戻ってこいよ?」
「……ああ」
肯定だけを、短く伝える。単なる、その場しのぎの言葉だった。
おそらくは破られることになるであろう、あまりにも脆い「約束」。
後々、きっと鈴木は俺を責めることになる。
そう遠くない将来の光景が目に浮かび、自己嫌悪に胸が痛んだ。
「てーつー! もうリンちゃん大丈夫だよー!」
アルミの呼び声が林に木霊する。
それを合図に、俺たちはゆっくりと動き出した。
凛が、アルミと並んで立っていた。姿勢に不安定さはない。
どうやら、パーツはきちんと合致しいていたようだった。
「大丈夫か?」と念のために尋ねてみると、
「うん、平気」と明るい返答があった。
「ありがとな、アルミ」
「いえいえー。しばらく着けておくといいよ!」
アルミの好意が、どうしようもなく痛かった。
口をつぐむ俺の隣で、凛が鈴木に向かって口を開いた。
「そうだ、二人には別荘のロック番号を教えておくね。
指紋認証のデータは残ってると思うから、
番号さえ打ち込めば中に入れるはず」
凛がロック番号を告げ、鈴木が携帯にメモしていく。
それも終わると、もうここに留まる理由はなくなった。
「……行こうか」
凛はうなずくと、草道に分け入る。後に続いて、俺も足を踏み入れた。
「ふたりとも、また後でねー!」
弾むような声の後には、木々の葉が揺れる音だけが残る。
振り返らないまま、俺は片手を軽く上げた。
背後でドアの閉まる音がした。
ほどなくして上がったエンジン音は、すぐさま走行音にとって代わる。
唸るような、くぐもった音が遠ざかり、やがて消えた。
——俺と凛は、前を見据えて歩き出した。
細長い道を、ひたすら歩いていく。
足取りは重く、思うように動かない。
両脚はさながら鉛のようで、身体の節々に至っては動かす度に悲鳴を上げた。
覆い隠すように生い茂っていた草木は途切れたものの、依然として悪路が続いていた。
一歩踏みしめるごとに、足裏で雪がさくりと鳴った。
厚く積もった雪に足を取られそうになりながらも、俺たちは無言で「別荘」を目指す。
「……さっきは、迷惑かけてごめんね」
白い息とともに、かすかな声が耳を撫でた。
「仕方ないさ。でも、鈴木が……アルミがいてくれて本当に良かった」
彼らがいなければ、この道を凛と歩くことはできなかった。
感謝してもしきれないくらいだ。
今頃は、別荘に行っているのだろうか。
それとも、警察に行っているのだろうか。
いずれにせよ、無事であればいいと思った。
「……鈴木は『傷』の意味に気付いたみたいだったよ」
「……鈴木くんには、説明したの? 車の陰で話していたみたいだったけど」
「いや……何も説明しないまま、結局『逃げろ』としか言わなかった」
「……そう」
「説明しようにもできなかった、というのが本音かな。
正直なところ、自分でも状況をよく飲み込めていないんだ。
……だからさ、リン。聞きたいことがあるんだ。
もう、いいよな?」
「……うん」
「おまえは人間で……本物の堂崎凛なんだろう?」
「うん」
「そして俺は……『兵器』なんだろう?」
「うん」
「……そうか」
質問というより、確認だった。
俺がドールで、彼女が人間。
ひとまずは、その事実だけを確かなものとして認識したかった。
もちろん、問いたいことは山のようにある。
でも、だからこそ、聞けなかった。
多すぎて、溢れすぎて、まとまらなかった。
「……聞きたいこと、いっぱいあると思うけど、
今はそれぐらいしか答えられない。
でも、もう隠すつもりはないから。これから、すべてを見せるから」
胸の内を見透かしたかのように、凛が口を開いた。
その声音には、決然とした意思がこもっていた。
——ふいに、視界が開ける。
鬱蒼とした林をくり抜いたように、一帯には整備された敷地が広がっていた。
そこに佇むのは、見るからに古びた外見の建物だった。
黒ずんだ壁には、ツタの葉が這っている。
よく見れば建物の所々は崩落しかけていて、陰鬱な雰囲気を醸し出していた。
朽ち果てたコンクリートの箱、とでも言うべきだろうか。
「ここが、『別荘』——もとい、研究所」
凛が、静かに言った。
指紋認証とロック番号を解除し、扉が開かれる。
建物の中は、古びた外見に反して、整っていた。
リノリウムの床を、ひたひたと歩いていく。
電気系統は生きているらしく、進みゆくにつれ、照明灯が自動点灯した。
途中、何度も扉に行き当たったが、凛は建物に入った時と同じように指紋認証とロック番号を打ち込み、次々と解錠していった。
複数の区画をまたぎ、階段を降り——建物の地下へと踏み入っていく。
いくつか下の階層に辿りついたところで、またも扉が現れた。
凛が慣れた手つきで解錠する。
ドアを開いた先には、広々とした空間が広がっていた。
部屋には、所狭しと様々な計器が並んでいる。
最も奥まった場所には、機械に囲まれた二つの椅子があった。
「……あれは?」
「──『記憶同期システム』。あなたに、私の記憶を見せたいの」
凛は椅子の傍にある機材に歩み寄ると、それらを次々に起動させていった。
「……椅子に座って」
促されるままに、腰を下ろす。
それから、凛は上部にあった半円型の機械を俺の頭に取り付けていった。
「システムを使って、今から私の記憶をあなたに移すからね。
……大丈夫、『上書き』はしない。
あなたは自分の記憶を保ちつつ、私の記憶を抱えることになる」
淡々と説明する凛。
しかし、その声音には、どこか不安げな響きもあった。
「ただ、記憶データというものは、とても容量が大きいから……
あなたのキャパシティを越えて、エラーを起こしてしまうかもしれない。
もし辛くなったら、その時は言って」
「……ああ、わかったよ」
凛が隣の椅子に着き、同じように機械を頭部にかぶせた。
「……じゃあ、始めるね」
かちり、とスイッチを入れる音。
同時に、思考の糸が別のものと繋がる感触があった。
そして、頭の内側に水を注がれるかのような感覚が襲ってくる。
流れ込んでくる「記憶」は勢いを増し、やがて奔流と化していく。
「脳」に押し寄せる激しい圧迫感に、歯を食いしばりながら。
俺は、意識を深みへと沈ませていった。
`( ´8`)´<頂いたサポートはラムネ菓子となり僕の脳に100%還元されます。なお、押してくださった♡はモチベとなり僕の心に1000%濃縮還元されます。

