
act5 : Thu. Dec. 21th
◀第1話 act1 : Sun. Dec. 17th から読む
俺は、ほの暗い闇の中を走っていた。
前方には凛の背中があった。
こっちだよ、と笑い声が弾む。
二つの足音が重なりあい、遠く響いている。
どうやら、鬼ごっこらしい。
ずっとずっと前から、追いかけていたような気がする。
そろそろ交代させてやらなければ。
俺は力を振り絞り、ぐんと加速する。
じわじわと、凛との距離が縮まっていく。
……もう少しで、彼女に届く。
揺れる髪が目前に迫り、息遣いさえ聞き取れるくらいになったとき、
俺は彼女へと手を伸ばした。
瞬間、閃光が迸った。
──炎が、周囲を取り囲んでいた。
凛が、足元でうつ伏せに倒れている。
だらりと四肢を投げ出し、壊れたように動かない。
俺はとっさに屈みこみ、凛の肩を狂ったように揺すった。
血は出ていない……そう理解しかけたところで、異変に気付く。
ぱっくりと割れた皮膚。
目を凝らせば、体の節々には明らかな傷を負っていて。
その中身が、燃え盛る紅を反射してきらめいた。
ああ、そうだ、これは金属骨格で──
「……見られちゃったね、ごめんなさい」
喉元に伸びた手を視界に捉えた時には、もう遅かった。
瞬時にしてその場に押し倒され、ぎりぎりと首を絞めあげられる。
「ごめんなさい、
ごめんなさい、
ごめんなさい──」
謝罪の言葉を繰り返すたび、指先に込められた力が強くなっていく。
燃え盛る炎に照らされて、凛の髪が宙に躍る。
その合間に覗いたのは、皮膚が破れ、露わになった銀の骨。
人体模型のような様相に変わり果てた凛を見て、俺は──
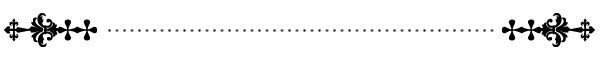
「う……あぁああああああああああああ!」
闇雲に伸ばした手が、空を切った。
そこに、先ほどまであった恐ろしげなモノはなかった。
跳ね起きて辺りを見回してみるが、火の海はない。
そこにはただ、さんざん見慣れた自分の部屋が広がっているばかりだった。
……呼吸が苦しい。全身に、軋むような痛みがまとわり付いている。
覚えず、シーツを握りしめていた。
掌に伝わるなめらかさ、手の甲にかかった毛布の柔らかさが、
ここは平穏な場所だと証明してくれる。
数度の深呼吸の後、俺はベッドから這いずるようにして離れた。
カーテンを開くと、待ち構えていたように光が部屋を照らし出した。
快晴だ。しかし、陽がずいぶんと高い位置にあった。
まさかと思い、やにわに時計へと目を移す。
PM 2:51
「……またか」
ゆうべは早めに寝たはずだった。
これまでにないくらいの疲労感を覚えて帰宅し、
シャワーも浴びずにベッドに倒れこんだ。
おそらく、夜の八時くらいにはもう眠っていたはず。
にもかかわらず、昼に起きたということは……
確実に半日以上は寝てしまったということだ。
今日は、リンとの約束の日だった。
早く就寝したのも、充分に睡眠をとって朝から活動するためだ。
なのに、性懲りもなく惰眠をむさぼるなんて……。
自己嫌悪にくすぶる頭を抱えつつ、居間へと向かった。
リンはいつも通り、テーブルに着いてホットミルクを飲んでいた。
俺が部屋に入ってきたことに気づき、向き直って微笑む。
「おはよう、テツくん」
「リン、ごめん。こんな時間まで眠ってて……本当に、ごめん」
開口一番に、謝った。
挨拶を返すより先に、そうしなければならないと思った。
「……ううん、いいの。テツくん、とても疲れてたみたいだから。
起こすのは悪いと思って。
体調は大丈夫?」
「ああ、もうばっちりだよ」
カラ元気をひねり出し、出来る限り明るい声を意識する。
でも、おそらく今の俺はひどい顔をしているのだろうと思う。
間近でリンと顔を合わせれば、瞬時に見透かされそうな気がして、
俺はそそくさとキッチンに足を向けた。
いつものように、眠気覚ましのコーヒーを淹れる。
インスタントパックの封を切り、バッグをカップに設置して、
湯を注ぐこと数回。もうっと白い蒸気が立ち昇り、
心地よい温もりが顔にかかる。
コーヒーを入れる時間で、最も好きな瞬間だ。
封を切った時の新鮮な香りもいいけれど……
個人的には、淹れるその瞬間、
湯気とともに広がる香りこそが至高だと思う──
……。
…………うん?
香りが、しない。
すんすんと鼻を鳴らしてみるが、それでも何も感じなかった。
風邪でもひいてしまったのだろうか、と思う。
鼻が詰まっているふうでもなかったが、
昨日からの身体の異変に照らし合わせれば、
やはり体調は悪いのだろう。
カップを手に、リンの向い席に腰を降ろした。
漂う湯気を吹き冷まし、コーヒーを口に含んだ。
(…………!?)
味が、しなかった。
薄いというのではない。まるで苦みが感じられなかった。
あたかも、白湯をそのまま飲んでいるかのような心地。
湯量を多くしたわけじゃない。きっかり適量のはずなのに。
「ねぇ、テツくん」
飛んできたリンの声に、慌てて顔を上げる。
「……どうしたの?」
「あのね、今日のことなんだけど……私、ケーキを作りたいの。
だから、良かったら材料を買ってきて欲しいなって……」
「え、手作りなのか」
「あっ、ごめん。お店で買った方がいいのならそうするけど……」
リンの声がしぼみかけて、俺は大慌てで遮った。
「いや違うって、責めてるわけじゃなくて。
わざわざ作ってくれるとは思ってなかったからさ」
ああ、確かに凛はお菓子を作るのが好きだった。
クッキーなんかを作っては、よく食べさせてもらった憶えがある。
甘党の彼女が作る菓子類は、大体において砂糖が多めに加えられていて、
甘いものが苦手な俺としては色々と複雑だったのだけれど。
「買いものね、いいよ。何を買ってきたらいい?」
「必要なもの、これにまとめておいたの」
そう言ってリンが手渡してきたのは、材料のメモだった。
ざっと目を通しただけでも、
必要なものはそれなりに多そうなことが分かる。
「調理器具で、足りない物とかなかったか?」
「キッチンの棚を見てみたけど、ひと通り揃ってたから大丈夫」
「そうか、じゃあ着替えたらすぐに買い出しに行ってくるよ」
そう言って居間を出ようとしたところで、ふと思い出したことがあった。
「──そうだ、忘れてた。
買った服さ、もう見てみた?」
俺の言葉に、リンは小さくかぶりを振った。
彼女が見つめた先……部屋の隅には、買い物袋の山が積み上がっている。
俺が昨日の晩に、居間に無造作に置いていたのを
ひとまとめにしてくれていたらしい。
しかし、そのどれもに包装を開けた跡はなかった。
「開けていい、って言われなかったから……」
どこか遠慮がちにリンが答える。
勝手に開けていたとしても、まったく気にしなかったのに。
というより、リンのために買ったものなのだから、
そもそも俺の許可なんて待つ必要もないのだ。
それをしなかったのは、「凛」の律義な性格ゆえか。
何だか無性におかしくて、思わず口元が緩んでしまう。
「そっか、じゃあ折角だから着てみてくれないかな?
いつまでもジャージじゃあんまりだし」
「え? うん。……じゃあ、ちょっと待っててね」
一瞬きょとんとした素振りを見せたものの、
リンはすぐに顔をほころばせて、買い物袋の山へと駆け寄る。
そして、それらを一気に引き摺りながら居間を出ていった。
「……持ち運ぶの、手伝ってあげればよかったかな」
そこはかとなく後悔しつつ、一〇分ほど待ったところで。
「……えっと、お待たせしました」
居間のドアが、ゆっくりと開かれた。
「…………」
「……あの、テツくん」
呼びかけられて、はっと我にかえった。
「……黙ったままじっと見られると、その、
けっこう恥ずかしいかな……なんて」
どことなく顔を赤らめながら、そわそわと目を伏せるリン。
そう言われて初めて、自分が無言で彼女を見つめていた事に気付かされる。
何か言葉を発しなければと思う反面、
口はぱくぱくと開閉を繰り返しただけで、上手く喋れずにいた。
陸に上がった魚のようだ、と頭の片隅でちらりと自嘲する。
そんな形容は思いつくくせに、肝心な言葉は探し出せなかった。
「……おかしかった、かな?」
無言の俺を前にして、リンの声が自信なさげに沈みかける。
「違う、そうじゃなくて!」
俺は焦って否定する。
色々と褒めたくて、でもそれを上手く言い表せなくて。
もどかしくて仕方がなかった。
「可愛いし……綺麗だし、似合ってたから……」
それは本当だけど、そういう事が言いたいんじゃなくて。
「見惚れてたというか……正確に言えば惚れ直したわけで」
自分で言った瞬間、顔の中心部が燃えるように熱くなった。
表情に音があるのなら、間違いなく「ぼっ」と盛大に鳴っていただろう。
リンの顔が、ふっと上がる。
まっすぐに向けられた瞳には、光が宿っていた。
「……ありがとう」
緊張で固くなっていたリンの表情が緩み、笑顔が弾けた。
……今度は、俺がうつむく番だった。
「えっと……ところでさ、靴下は履かないの?」
目についたのは、露わになった脚の部分。
そこに巻きつけられた包帯が、服装と相まってその歪さを際立たせていた。
「靴下? うーん……袋の中、ぜんぶ見てみたけど入ってなかったの」
「本当に? 確かに買ったはずなんだけどな」
辺りを見回してみたものの、居間に買い物袋は残っていない。
なぜならリンがすべて持ち運んでいったのだから。
そして、当のリンも見落としていないと言う。
……もしかして昨日、帰り際に落としてしまったのか?
昨晩のことを思い出す。
マンションの入口ホールに入った時点で、
念のためにと購入した品物を確認した記憶がある。
そのなかには確かに靴下もあったはずで──
だとすれば、落としたのはその「後」だ。
マンションの廊下か、エレベーターか。
そう予想していたのだけれど、
結果から言えば、そんな心配はまったく無用なものだった。
慌てて玄関へと向かったところで、「それ」は見つかった。
土間の隅っこに、見覚えのある小さな買い物袋がひとつ、
所在なさげに落ちていた。
おそらくは、昨日の晩に帰宅した際に
靴下の入った袋だけを落としてしまっていたのだろう。
「靴下、あったよ」
密かに安堵しつつ、足早に居間へと戻る。
俺はリンの傍まで歩み寄り、屈みこんで──
右脚の包帯に、ゆっくりと手をかけた。
「えっ? ……えっ、テツくん?」
頭上で戸惑いの声が漏れる。あえて気にせず、そのまま包帯をほどいていく。
「もう、傷も治ったはずさ」
するりと瞬く間に包帯が解け、「それ」が露わになる。
目の前には、相も変わらず痛々しい傷が存在していた。
「──うん、もう大丈夫そうだな。
あれから『出血』はないだろう?」
見上げると、リンがこくりとうなずいた。
その反応を見て、律儀なものだと今更のように思う。
俺──「佐藤哲」が本来のユーザーではないにせよ、
彼女はこちらの定めたルールをきちんと守ってくれている。
だから、せめてものお返しとして。
俺は俺で、より彼女を「凛」らしく──
いや、「人間」らしく、接してあげたかった。
「……包帯なんてさ、もう必要ないんだよ」
立ち上がり、リンの袖をまくる。
ガラス細工を思わせる華奢な腕。
そこに巻かれた包帯を、先ほどと同じようにほどいていく。
白の布地が、はらりと床に落ちていった。
俺は袋の中からニーハイソックスを取り出すと、
包装を取り去ってリンに差し出した。
「履いてみなよ。きっと、似合うと思うんだ」
俺が包帯と包装をゴミ箱に捨てている間に、彼女がソックスを履き終える。
「うん、すごく可愛い」
「……本当に?」
「自分でも見てみなよ」
いぶかしげに
部屋の奥からスタンドミラーを引っ張り出し、その前に立たせてみる。

「わぁ……」
恥じらい混じりに、リンの口から感嘆の声が漏れた。
「……なんというか、けっこう大胆だね。
こういう服、今まで着たことなかったから……
ちょっと落ち着かないかも」
そう言って、困ったように笑った。
「八割がたアルミのチョイスだしな」
俺も、つられて苦笑した。
昔は、お嬢様然とした大人しめの服装が多かったから、
慣れないのも無理はないと思う。
でも、とても似合っていた。
今までになかった「凛」の新しい一面を、垣間見た気がした。
それはひとえに、リンのおかげなのだ。
俺とリンで作った、新しい「凛」の思い出なのだ。
俺にはそれが、とても嬉しかったんだ。
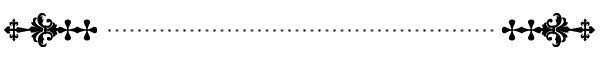
マンションを出たところで、
入口の傍らに設置してあるベンチに腰を降ろした。
改めて、リンから渡されたメモを見返してみる。
そこには、卵や果物といった材料がずらりと書き連ねられていた。
街のスーパーに行けば、大した苦労もなく揃えられるだろう。
「……街に行かなきゃいけないのか」
いつもなら、何も迷う必要はない。
街まで歩いて、さっさと用事を済ませるだけだ。
けれど、今はそんな簡単なことさえ躊躇してしまう。
脳裏をよぎるのは、昨日のファッションビルでの出来事だ。
「……あれは、なんだったんだ」
周囲にあふれる人々を目にした時、俺の内に生まれた声。
「壊せ」と。
確かに俺は思ったはずだ。
あのとき俺を突き動かした、凶悪な破壊衝動。
思い出すだけで身震いがする。我ながら反吐が出そうだった。
しかし、事実として、俺はあの衝動に支配されそうになっていた。
すんでのところで回避できたものの、
あの場に留まっていれば犯罪を起こしていたかもしれない。
今ごろ自分が留置場にいたとしても、なんら不思議ではなかった。
街に足を運ぶことが、人の波に揉まれることが怖くて仕方なかった。
暮れなずむ夕日の眩しさに、目を細める。
この時間帯ともなれば、街の人通りはさらに増していく一方だ。
俺は重い腰を上げ、街とは反対の方向へと歩き出した。
街と反対の方向には、寂れた商店街がある。
街の再開発によって大型ショッピングモールが参入してきた影響で、
商店街の店舗の多くはすでに潰れていたが、
食材などを扱う個人商店はいまだに健在だった。
ケーキの材料ぐらいならば、ひと通り調達できるだろう。
……そう、見越していたのだが。
「えっ、売り切れですか?」
「ちょうど切らしててねぇ……すまんな、兄ちゃん」
老店主は、すまなそうに頭をぽりぽりと掻いている。
いくつかの商店を巡り歩き、
メモに書かれていた品を順当に揃えていくことができたのだが──
ただ一つだけ、見つからないものがあった。
「ベーキングパウダーかぁ、お菓子でも作るのかい?」
「あ、はい」
最後の最後に、ベーキングパウダーが見つからなかった。
ここにきて、品切れという運の悪さだった。
訪れたのは、商店街で最も大きいとされる商店。
といっても、街のコンビニよりいくらか大きい程度だ。
商店街の人の話では、粉の類はこの店にしか置いてないとの
話だったので、そのぶん落胆も大きかった。
──結局、街まで出るしかないのか。
ため息をついて店を出ようとしたところで、店主に後ろから呼び止められた。
「兄ちゃん、重曹ならあるけどダメか?」
「ジュウソウ? それでもケーキとか作れるんですか?」
「作れるともさ。ベーキングパウダーってのはな、
お菓子を作りやすいように重曹に色々と加えたものなんだ。
なんだ、そんなことも知らなかったのかい?」
知らなかった。菓子作りの常識であっても、
残念ながら俺はそういった趣味がないもので。
でも、それで代用できるならわざわざ街に行く必要もない。
「……じゃあ、それください」
「おう、まいどっ!」
どうにかすべての材料を揃えて、俺は家路についたのだった。

「……はい、ミックスピザとベネチア風特製ピザのMサイズをひとつずつ。
以上です。……時間は九時ぐらいで。はい、お願いします」
携帯で宅配ピザの注文を終え、開いていたカタログを片付けた。
食事は何にしようかと迷った末に、宅配ものにしたのだった。
リンは家から出たがらないだろうし、俺としてもその気にはなれなかった。
リンはキッチンでせこせこと準備に取り掛かっていた。
棚の上には、さっき買ってきたケーキの材料が所狭しと置かれている。
買い物から帰ってきた時、
俺はまずベーキングパウダーが手に入らなかったことを謝った。
その代わりに重曹を買ってきた旨を伝えたが、
リンは別段気にしたふうでもなかった。
ただ、お菓子づくりで重曹そのものを扱うのは初めてらしく、
「上手に出来るかな」と少しだけ困ったように笑っていた。
「リン、なにかできることない?」
「手伝ってくれるの? ちょっと待ってね…… じゃあ、とりあえずテーブルを拭いてくれる?
準備ができたら呼ぶね」
「ああ、分かったよ」
ひとまずテーブルの上からカップやテレビリモコンを退かして、
布巾で丁寧に拭いていく。
五分もすれば一連の作業は終わり、リンの指示を待つばかりとなる。
特にすることもなくなったので、何気なくパソコンを開いた。
予習としてケーキの作り方でも調べるかと思い立ち、
いつものようにブラウザを立ち上げてみる。
──「インターネットの接続を確立できません」
ディスプレイに表示されたエラー画面を眺めつつ、はて、と思う。
接続機器の故障だろうか。
設定をいじっても改善の兆しは見られなかった。
ネット接続を諦めて、手持ち無沙汰を紛らわせるために
テレビリモコンに手を伸ばした。
スイッチを押してみるが、テレビ画面は黒々としたままだ。
本体の電源を押しても、うんともすんとも言わない。
ふと、電源ランプがついていないことに気付いた。
しかし、コンセントはきちんと挿してある。
テレビから伸びた電源コードを目で追っていくと、
中ほどの辺りから金属線が覗いていた。
「……マジかよ」
いつの間に、こんなに消耗していたのか。
配線をいじったこともなければ、上に重いものを乗せていたわけでもない。
足を引っ掛けたことなんて皆無だ。
それに、三日前はリンがニュースを見ていたはずで……。
「テツくん、こっちに来てくれる?」
リンの声で、思考は中断される。
どうにも違和感を拭い去れないまま、俺はキッチンへと向かった。
「……さて、何をしたらいいのかな?」
「えっとね、クリームを作ってほしいの」
そう言って、リンが生クリームの入ったボウルを手渡してきた。
「このボウルの底をね、
氷水の入ったもう一つのボウルに当てながら、泡立てて……」
リンの説明に聞き入りつつ、ふんふんと頷く。
課せられた使命は生クリーム作りらしい。
ひと通りの手順を把握すると、
俺は泡立て器を手にさっそく取り掛かることにした。
しゃこしゃこと小気味良い音がキッチンに広がる。
リズミカルな単純作業も、慣れるに従って面白くなってくる。
その隣で、リンは果物を切っていた。
とんとんとん、と一定の調子で響く音が耳に心地よい。
二人して黙々と作業に没頭する時間が、無性に楽しかった。
あの事件が起きなければ。凛が巻き込まれさえしなければ、
こんな時間を過ごすこともあったのだろうか。
そんなことを、ふと思った。
凛のいなかった空虚な一年間が、走馬灯のように脳裏を駆け巡った。
事件が起きて最初のうちはただ呆然として、
何か悪い夢を見ているのではないかとさえ思った。
警察の聴取、それに記者からの取材攻勢を受けるに至っても、
現実感がまるでなくて。
けれど、日が経つにつれ、
堂崎の家を失ったという実感は固いものになっていった。
心の傷は時の流れが癒してくれる、というのはよく言われることだ。
しかし、俺の場合は逆だった。
過ぎゆく時間に比例して、喪失感は段々とその重みを増していった。
針で刺したような、小さな穴。
事件直後に生まれた虚無感は、それぐらい小さなものだった。
けれど──それは徐々に綻び破れて、その大きさを広げていき……
気付いた時には、すでにぽっかりと風穴が空いていた。
なぜ、自分だけ難を逃れてしまうのだろう。
どうして、周りは自分を置いていくのだろう。
父さんも母さんも、堂崎の家も、そして凛も──。
大事な人たちは、呆気なく、ある日突然に消えてしまう。
ねえ、もういいんじゃないかな。
彼らの後を追いかけてもいいんじゃないかな。
穴に吹き荒れる風が、そう囁くようになっていた。
その誘惑に応じようとさえ考えていたことを、今更のように思い出す。
悶々とした閉塞感を忘れていた理由なんて、考えるまでもなく明らかだった。その穴を塞いでくれた存在が、いま隣にいる。
でも、彼女もあと数日で去っていく。
リンが、いなくなってしまう。
その「先」の風景を、俺はどう歩いていけば良いのだろう。
何を拠り所に、生きていけばいいのだろう──
ふいに、肩をぽんと叩かれ、我に返った。
隣を向くと、リンの顔が近くにあった。
何やら、ぱくぱくと口を動かしていた。
ひとしきり身ぶり手ぶりを交えつつ、笑う。
……伝言ゲームのようなお遊びなのだろうか?
いかにも何かを話しているようで、そのくせ何も聞こえない。
まるで、世界から音が消えたようで──はっとした。
俺が生クリームをかき混ぜる音、泡立て器とボウルがこすれ合う音。
リンが果物を刻む音、包丁がまな板を叩く音。
手は休めていないはずなのに、その一切が聞こえてこない。
さっきまで周囲を取り巻いていた音が、消えていた。
「ごめん、なにか言った?」と、尋ねてみた。
そう声に出したはずだったのに。
喉を震わせ、口を動かしているにも関わらず、
自分でその声が聞こえなかった。
馬鹿な、そんなことが──
瞬間、ずきりと頭が軋んだ。
続けざまに、金属を掻き鳴らすような断続音が内側で響く。
立ちくらみを覚え、思わず流し台の端に手をついた。
ふと、肩に手を置かれる感触があって──
横目に見やると、リンの顔が近くに迫っていた。
何か早口にまくし立てているようだった。
「だ…じょ…ぶ…
ど……たの…
きぶ…わ…くな…たの」
ノイズ混じりの断片的な音声が「聞こえる」。
ああ、聞こえる。
胸の片隅に、かすかな安堵が生まれる。
耳鳴りが次第に小さくなっていくにつれ、
聴覚がようやく明瞭さを取り戻していった。
「──くん、ねぇテツくん? どうしたの!?」
リンの声も。
エアコンが風を送りだす音も。
そして、自分の荒い息遣いさえも。
ちゃんと、聞こえるようになっていた。
「……ごめん、もう平気だから。
さっき、なんて言ったんだっけ?」
「えっと……クリーム、泡立てすぎると
ぼろぼろになっちゃうから気をつけてね、って」
「なるほどね、気をつけるよ」
一息ついて、俺はクリームをもう一度混ぜ始める。
なおもリンは何か言いたそうにしていたが、
やがて彼女も果物を淡々と切り始める。
再び、キッチンを音が満たした。
しかし、その手に今までのようなテンポの良さはなく、
どこか重たい響きをはらんで耳に届くのだった。
「テツくん、ありがとう。
後は私がやるから、居間の方で休んでて」
生クリームを混ぜ終えると、リンはそう言った。
明らかに俺を気遣ってのものだった。
強情を張って手伝い続けることも考えたけれど、
それではただの邪魔になりかねないと思い直す。
結局、俺は生クリームを固めただけで
お役御免となってしまったのだった。
やれやれとソファーに腰を降ろすと、ずしりと身体の重さを感じた。
このまま目を閉じれば寝てしまえるぐらいかと思うほどに。
けれど、そればかりは避けなくてはならない。
誕生日祝い……それが前倒しの仮祝いであっても、
祝ってもらう当人が爆睡していては興ざめだろう。
──と、いきなりポケットの携帯が震えた。
着信は、鈴木からだった。
「よう、いま大丈夫か? もしかしてお取り込み中?」
「いや、いいよ。むしろちょうど良かった」
話していればそのうち眠気も醒めるだろう。
暇をつぶせることが何よりの救いだった。
「そっか、良かった。なぁ、明日は大学来るんだろ?」
「……なるべくなら、休もうかとも思ってる」
「マジで言ってんの?
いや、『凛』と過ごしたい気持ちは分かるんだけどさ。
明日はさすがに行かないとヤバいだろ」
「ヤバいって言っても、
別に受けなかったからって留年するわけじゃないし……」
そう言ったところで、はたと気づいた。
そうだ。明日の試験を受けなければ、俺は留年してしまうのだ。
受話口の向こうで、ため息混じりに声が響いた。
「必修試験を受けなかったら一発アウトだぞ、分かってんだろ?」
俺の大学は、学年ごとに「必修試験」なるものを課している。
国の学力調査の一環として、大学生の基礎学力の確認を行うという名目だ。
試験の内容自体は高校レベルの平易なものだが、
これを受験することが進級の条件となっているのだった。
そして、俺の学年……二年生の試験は明日の昼なのだ。
無断欠席なら留年は避けられないし、
別日程での受験手続きはとっくに締め切られている。
「……わかった、明日は行くよ」
「了解、帰りは一緒に帰ろうなー」
「それなんだけど、明日は正門じゃなくて裏門のほうで待ち合わせないか?」
「……別にいいけど、なんでまた裏門なんだ?」
「人混みを避けてさっさと帰りたくてさ」
明日は、二年生対象の試験日。
それはつまり、大学に在籍している二年生全員が登校するということなのだ。
マンモス校として名を馳せている大学とあって、
学年あたりの在籍人数はおよそ1万人を越える。
試験会場はいくつかのキャンパスに分散されるにしても、混雑は必至だった。試験が終われば、教室棟に近い正門付近は人波でごった返すに違いない。
それに比べて、裏門は教室棟から遠いために人通りも少ないのだ。
──とにかく、人だかりを避けたかった。
おとといのファッションビルでの出来事をいまだに引きずっている、
そんな自分に嫌気は差すものの、
軽く無視できるほど悠長に構えてもいられなかった。
「ふーん? まぁ分かったよ。試験会場、同じ教室になればいいな」
「……そうだな」
必修試験に受験票の類は必要ない。
座席は、会場の先着順に空き教室へと割り振られるからだ。
そして、俺は大学に一番乗りする気でいた。
ともすれば、始発の電車に乗るぐらいの勢いで。
それは単純に通学・出社ラッシュの時間帯を避けるためだ。
それだけ早く登校すれば、必然、受験番号もかなり早くなるだろう。
もしかしたら一桁の番号かもしれない。
鈴木が普通に試験開始時間にあわせて
登校したとすれば、到着は昼過ぎになるわけで。
とてもじゃないが、朝一番に登校するつもりの俺と
同室になるとは考えられなかった。
そのとき、インターホンが鳴った。
反射的に時計を見やると、午後九時ちょうど。
宅配ピザの届く時間だった。
「じゃあ、とりあえずそんな感じで」
「はいはい、明日な」
軽い調子で通話を打ち切り、俺は玄関口へと向かった。
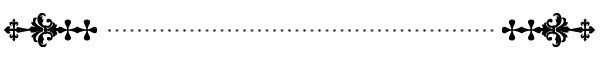
届いたピザをテーブルに置き、グラスを並べていく。
その隣に置いたのは、酒屋で買った安価なシャンパン。
テーブルの中心部分を空けるようにして、それぞれを配置していく。
真中のスペースは、言うなれば主役の座だ。
そこに納まるべきモノは、間もなくやってくる。
「お待たせしました」
持ち運ばれてきたのは、純白のデコレーションケーキ。
所々に彩られた果物が、目に鮮やかだ。
その隙間を縫うように、二〇本のロウソクが立てられている。
テーブルの真ん中に鎮座したケーキは、
華やかながらも重厚な威圧感を放っていて、なかなかに壮観な眺めだった。
ボリュームがある……というか、
クリームたっぷりのいかにも甘そうなケーキだ。
「では、火を点けさせていただきます」
リンは恭しい口ぶりで、着火器でロウソクに火を灯していく。
部屋の照明を消すと、暗がりに二〇個の灯りがぼうっと浮かび上がった。
「Happy birthday to you—……」
リンの歌声が闇に躍る。
穏やかな笑みが、優しい灯りに照らし出されている。
「Happy birthday Dear……」
胸に染み渡るような声は、一瞬だけ途切れて。
「で、でぃあ、テツくん……」
恥じらいに染まった、か細い調子で締めくくられた。
「──ありがとう」
俺は深く息を溜め──万感の想いをこめて、すべてのロウソクを吹き消した。
「……おめでとう!」
照明が点くと同時に、ぱちぱちと拍手が鳴った。
リンがケーキからロウソクを抜き取り、ナイフで六等分に切り分けていく。
その間に、俺はシャンパンの栓を空けておくことにする。
布巾を手に栓を捻ると、しゅぽんと軽快な音が上がった。
琥珀色の液体が、音を弾けさせながらグラスを満たしていく。
「二十歳に、乾杯だね」
グラスを重ねると、きん、と澄んだ音が室内に響いた。
リンがケーキを取り分け、俺に皿を差し出してくる。
「……はい、どうぞ」
俺がフォークを口に運ぶさまを、リンはじっと見つめていた。
その表情には、薄く緊張が張り詰めている。
自分もフォークを持っているのに、
そのまま固まっているところがおかしかった。
察するに、俺の評価を仰いでから食べるということらしい。
まずい、なんて言うつもりもないし、実際よく出来ているに違いない。
凛がお菓子作りを失敗したことなんて、
少なくとも俺の知る限りでは一度もなかった。
控えめな彼女が何かを表に出す時は、
それなりに自信がある証でもあったのだから。
リンの視線を受け止めつつ、素知らぬふりをして口に入れた。
生クリームの柔らかな感触と、スポンジケーキの歯触り。
焼き加減は上々。申し分のない食感だった。
なのに、どうして──
(……味が、しないんだ?)
まったくの、無味無臭。
飾り付けられたフルーツを食べても、舌も鼻も動じない。
甘みもなければ酸味もなく……
ただ、ケーキの食感だけが異様に生々しく感じられた。
「……どう、おいしいかな?」
「──ああ、おいしいよ。上手に出来てる。
個人的にはちょっと甘みが強い気もするかな」
リンの顔に、安堵が浮かぶ。
……俺がとっさに吐いた嘘に、胸を撫で下ろしていた。
罪悪感で、ずきりと腹の底が痛んだ。
それを押し込めるように、俺はケーキを一息に頬張る。
おいしくないわけがない。そうだろう?
味について何も言えないならば、行動で示すしかない。
一つめのケーキを食べ終え、即座に二つめへと手を伸ばす。
満足そうに微笑みながら、リンがようやく自分のぶんのケーキを取った。
五層構造からなるケーキの断面から、リンゴや黄桃が覗いている。
そこには今にも溢れそうなほどに、生クリームが詰められていて……
はたと、頭に引っかかるものを感じた。
何か大事なことを忘れているような気がした。
それがどんなものだったかを思い出そうとした、その時だった。
「けほっ、ごほ……!」
リンが背中を折り、激しくせきこんでいた。
皿の上に、横倒しになったケーキの残骸と、フォークが散らばっている。
彼女がケーキを口にして、ほんの数秒後の出来事だった。
尋常ならざる光景を目の当たりにして、閃光のように記憶が浮かぶ。
そうだ──あの時、鈴木の誕生日に用意されていたケーキ。
ホットケーキ然としていて、
生クリームでデコレーションされていなくて。
なぜそんなに簡素なのかと尋ねた時に、鈴木はなんと答えたか。
──『ドールにとっての生クリームは、
人間にとっての餅のようなものでさ』
「リン! 大丈夫か!?」
跳ねるように席を立ち、慌ててリンのもとへ駆け寄った。
けほんけほんと、彼女は苦しそうに断続的なせきをしている。
上下する背中に手を添えて軽くさすった後、大急ぎでコップに水を注ぐ。
「……水、飲めるか?」
リンは小さく首を縦に振り、コップに口をつけた。
水をたどたどしく飲み干すと、ようやく顔に回復の色が戻った。
──うっかりしていた。
引いていく不安の代わりに、湧きあがるのは自責の念。
ややもすれば、致命的なエラーをも引き起こしかねない愚行だったのだ。
『凛』として人間扱いしているうちに、そんなことも忘れてしまっていた。
リンがドールであるという事実が、今更のように頭を打った。
「無理するな、あとは俺が食べるから」
俺は彼女を椅子に座らせると、
残りのケーキを一心に口へと詰め込んでいった。
依然として味を感じることはなかったけれど、気にしない。
黙々とケーキを減らしていく様子を、リンはぼんやりと見つめていた。
「……おいしい?」
「ああ、おいしいよ」
リンはピザを片手に、ようやく笑う。
俺も、そっと微笑み返しておいた。
「リン」
「うん」
「……明日は大学に行くよ。落とせない試験が残っててさ。
だから、明日は早めに起こしてくれるかな」
「……うん。なるべく早く帰ってきてね」
どこか心配げな表情で、リンは言ったのだった。
`( ´8`)´<頂いたサポートはラムネ菓子となり僕の脳に100%還元されます。なお、押してくださった♡はモチベとなり僕の心に1000%濃縮還元されます。

