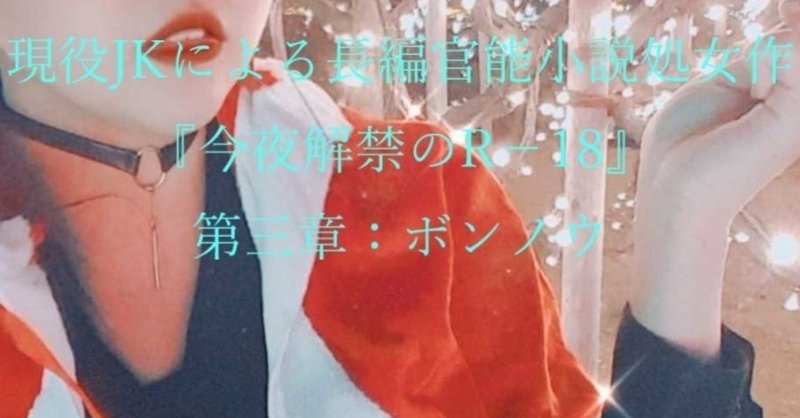
第三章:ボンノウ
「はぁ…」
杉谷[すぎや]公孝[きみたか]はいつもに増して疲れた表情で家のドアを開けた。それもそのはず、同時に二人の女を失ったのだ。本命には絶望され、浮気相手には失望された。「私、他人のモノじゃなくなったアナタになんて興味ないわ」本当にそう思う女がこの世にいるなんて。
電気をつけ、清潔で広々とした部屋が照らされた。その広さが今は、自分の寂しいという感情をあおる…はずだった。
「ん?」
公孝の視界に異様な光景が飛び込んできた。
目の前に女のサンタが倒れているのだ。
2034年のクリスマスは『ルナ』という会社のバイトサンタが枕元までプレゼントを届けてくれるのだ。
※第一章参照
「!。もしもし、大丈夫ですか?!?!?!」
まず意識の確認を図った。その時に触れた赤いローブに包まれた身体はとても華奢だった。髪の毛は…
「ん…っ」
幼くかわいらしい声と共に、二重の大きな目をもつ、くっきりとした顔立ちのロシア系美少女がこちらを向いた。
「あ、気がつきました??よかった」
公孝の心には安心以上に驚きと照れがあったが、ここは紳士にならねばと、状況を伝えた。
「今は25日の夜8時半で、ここは僕の…あ、杉谷家です」
さすが医者だ。目の前の病人がなにを求めているかを冷静に判断し、言動に移している。
「もっもしかして、私24日からずっと倒れてました?!?」
「あいにく僕は昨日の朝からここには戻っていないのでわかりませんが、見た感じそのようですね」
公孝はつい数時間前に元カノになった菜緒とはラブホテルでいつも事を行っている。なぜなら近所迷惑になるほど菜緒の喘ぎ声は大きいのだ。たまにその性癖をいじめて自宅で行うこともあるのだが、クリスマスは一縷の縛りなく互いの体を満たし合いたかったので、ラブホテルに24日の仕事が終わった後から一泊泊まることにした。
「どうしよう…。プレゼント、まだ配り終わってない…」
「僕も手伝いましょうか?」
「えっ?」
彼女の戸惑いに満ちた目を見て、気が付いた。あぁ、軽くナンパか。これ。
だが、本当にその目を見てから気が付いたのだ。別に、そのあとの何かを期待する思いはなかった。あるとすれば自己満足と承認欲求くらいだろうか。
「あ、嫌、かな…?」
「いえっとんでもないですっ。そちらこそ迷惑なんじゃ」
「迷惑ならこんなこと言い出さないですよ」
「では…お願いしますっ」
二人は急いで表に止めてあった車に乗り込み、14~15件の家をまわった。許してくれる人もいたが、カンカンに怒っている人や、不在の家もあった。たくさんの人に頭を下げて、公孝は億劫な気持ちが募っていったが、彼女にその雰囲気はなかった。どの家にも、ペコペコと頭だけでなく、小柄な全身を使い反省の意を伝えていた。その姿があまりに清らかでかわいらしかった。人のいない家には手紙を置いていた。
「本当にありがとうございました」
「いえいえ、でもあの…君って肺ガンだよね?大丈夫なの?」
彼女の笑顔から一瞬、熱が奪われた。
頭に髪の毛がないこと、身体つき、せき込むことが多かったことから医者じゃなくても想像はつく。
「(笑)気づいちゃいました?もう、末期で助からないんです。だから、やりたいこと、ぜんぶしてから、お空にいきたいなって。その一つが夢を配るサンタさんでした。」
「聞こうか迷ったけど、一応僕、医者だから。見て見ぬふりはできなくて。」
「そうなんですね…」「ん…。あのっ」
「ん?」
「よかったら、私と付き合ってください!」
「え?」
公孝の優秀な頭脳も、この出来事には対応できなかったらしい。なにが起きているのか理解できず、バグった。
「え…?ついさっき知り合ったばかりだよ?」
「最後に、恋がしてみたくて」
「そっか。でもそんな大切な恋。僕よりも適任がいるよ」
「あなたが…あなたでいいんです。」
「誰でもいいってこと?」
「もう時間もないですし。あ、もしかして彼女いらっしゃいます?」
公孝は答えに困ったが、良い妥協点を見つけたようで。
「いないよ。ん~。本当に僕でいいなら、『担当医』兼『彼氏(仮)』になろうか?」
「…お願いしますっ///」
こうして、公孝は寂しさを感じる暇もないまま藤原絵美[えみ]との交際(仮)が始まった。
絵美の両親にも「それが絵美の望みなら」とすぐに了承も得られ、公孝の家は広かったため、すぐに同居を始めることができた。
もちろんタバコはやめた。
観光地やグルメスポットに行ったり、家でまったり映画を観たり。
仕事以外の時間すべてを絵美に費やした。その時間は、公孝の一生のうちでは100のうちの1にもならないが、絵美にとってはその何倍もの割合を占める時間なのだから。
体も交し合った。
肺ガンのせいで、絵美の口内は淡の量が多かった。しかしそれが逆に功を奏し、今までに味わったことがないほど最高のフェラだった。公孝の性器にそのネバネバがそっとまとわりつく。
そんな名器ならぬ名口の持ち主の体を公孝は、優しく愛撫した。絵美のガンの進行は医者である公孝からみても早かった。日に日に衰弱する儚い身体を、寝台に寝かせ、丁寧に服を剥く。公孝の3本のゴッドハンドでいたわるように、優しく、優しく治療を施す。せき込んでしまったら、そっと背中をさする。その行動でさえ快感をおぼえた。絵美とのSEXは受けも攻めも初めての体験だった。今まではただ性欲や、愛情を満たされるためだけの行為であった。しかし、求めていたものは違った。
だが、
12月31日、午後7時14分。
絵美の様態が急変した。息が荒くなり、体力が奪われ、体を起こすことができなった。次第にずっと発作を起こし続けている状態に陥った。
病院に行くことを提案した公孝だったが、絵美はかたくなに断った。
午後9時46分。
「…私…幸せだったよ。短い時間だったけど、ありが…とう…っ」
「頼む、そんなこと言わないでくれ」
「…〈笑み〉」
「仮に、仮にだ…も、もし、死んでも…僕はっ!絵美の担当医として、絵美の彼氏(仮)として、絵美を愛し続ける」
「…!……
(公ちゃん…。やっぱりあなたにしてよかった。あの晩、あなたの家で倒れたふりをして待っていてよかった。なぜだか、この家の主に期待してしまったの。運命に操られるかのように、そうすることしかできなかった。そうすることしか頭になかった。今でも不思議だけど、この謎も、この嘘も、『あなたがいい』とあの時言いかけた言葉も全部、向こうの世界へもっていこう)」
「っつああぁっ。苦しい…っ!!」
「絵美っ!」 (…)
「公ちゃん…。きみちゃぁっんっ。助けて…いやぁぁあっ!!」
「絵美、大丈夫。大丈夫」 (あぁ…)
「死にたくないっ…。私、やっぱり…まだっ…死にたくないっ…!!!」
「絵美っ。それ以上は話すな。落ち着けっ!」 (すばらしい…)
「公っ…ちゃん…」
「絵美っ!」 (なんて、美しい)
「絵美っ…おい!絵美!」
「…」
「絵美…。」 (最高だ)
「…」
贅沢な材質のクイーンベットの上で、美貌をゆがませ、ボロボロな四肢であがきながら絵美の魂は天国へと旅立っていった。
小ぶりの唇にキスをした。
(絵美…。約束どおり、愛シてあげるね)
公孝は目の前の死体の服を丁寧に脱がせ始めた。露になったソレを、公孝は隅々まで舐めまわす。所々、白い肌に赤紫の死斑が徐々に出始めている。
(あぁっ。絵美。美しいよ。君の人体[カラダ])
なぜこんなにもこの女性に惹かれるのか。今までその問いの答えは、儚さがもたらす美しさだと思っていた。だが、その答えは生温かった。公孝は一つの生命体が最期を迎えるという事象の過程に、異常なまでに興味を持ち、興奮を覚えていたのだ。医者なので、「死」というものは反吐が出るほど見てきたが、こんなにも長く間近で、こんなにも美しい被写体の「死」を見ることはなかった。
別れが短期間に重なり、壊れた心が生み出した感性なのだろうか。あまりに危険なその趣向は理性で器用に隠されていた。だが、今そのパンドラの箱が開く。命にかかわる者としての何かが目覚め、人としての何かが失われた瞬間だった。
この世に生を授かり、子孫を残し、そして死を迎える。
その非情な自然界の定を舌先から感じ取る。
(なんて甘美で味わい深いんだ。たまらない。あぁ、たまらない。こんなに心が奮えたのは生まれて初めてだ。たまらない。もっと。もっと。もっと)
公孝は勃起したその陰茎を目の前のメスに挿れた。
もう、その禁断の行為は止める事ができなかった。完全に好奇心に支配されている。
やはり、シマりは悪く、温度も低い。
だが、これは孕むことの不可能な母体に、自分の生殖器を挿れ、交尾をしている。その完全に生物学に反した行動をしているということに価値があった。
「絵美ぃ?幸せかい?…っ…ああぁっイクよ?イクっあああぁぁっ!!」
2034年、最後の日。
東京の街には除夜の鐘が鳴り響き、シロい雪が降る。
~相関図~
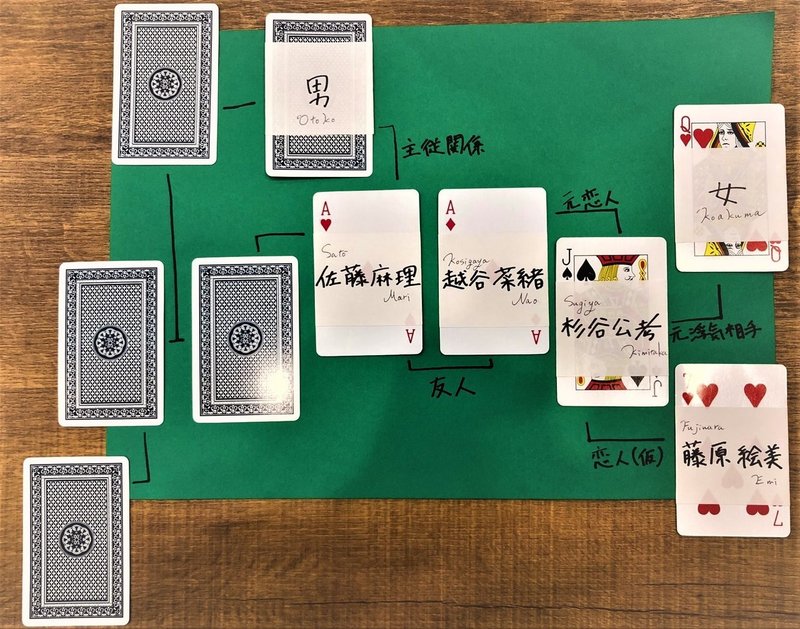

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
