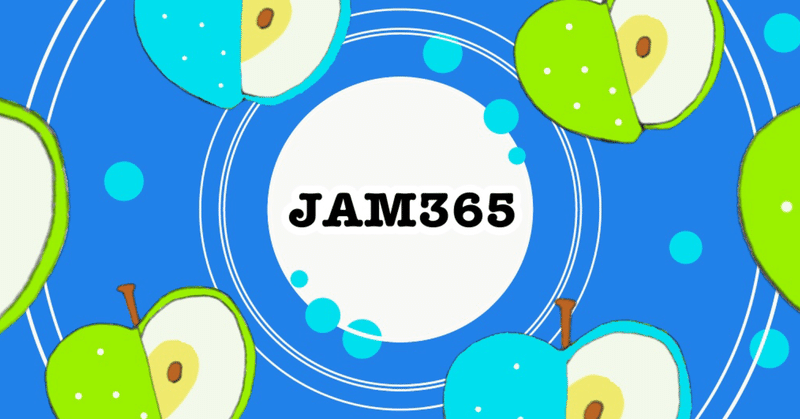
7・10 納豆の日
一は食事について、別に誰がどんな食べ方をしようと気にしない質だった。
味覚など違うのが当然であるし、そうでなければこの世に嫌いな食べ物などという概念は存在しないはずである。
これだけの物が世の中にはあるのだ。
好きな物を選んで食べればよい。
嫌いな物も、きっと誰かの好きな物なのだから、それはそちらに任せれば良く、逆もまた然りである。
障子のはられた格子戸の向こうから射す陽は、今にも消えそうな行灯の火よりも暗い気がする。
一はその障子の向こうは今日も曇天かと、眉根を寄せながら黄色い沢庵をかじった。
もう二十日もまともな陽を浴びていないので、肌から髪の根本から脳味噌までが黴びてしまいそうだ。
日に日に鬱々とした気持ちに拍車がかかり、今では原型も分からないほどに肥大した気持ちはさながら鬱達磨であった。
そうでもなければ、この日、温厚な一がこんな些細なことで雷を落とすことは無かっただろう。
「いい加減にしろ、ニチカ、三郎、止めないと飯を取り上げるぞ」
年の離れた兄に怒鳴られた年子の兄弟は、それでも言い争いをやめない。
「だって兄貴、ニチカが納豆にのりの佃煮をかけたんだ。信じられる?僕の分を取る前に全部にだよ?」
三郎はニチカの長い前髪を掴んで引っ張っている。
「だって兄さん、三郎ったら、納豆をデザートにしようとしてるんだぜ。頭おかしいよ、こいつと兄弟とか本当に嫌なんだけど」
ニチカは足のつま先を三郎のみぞおちに食い込ませて応戦している。
「おまえ達、もう高校生なんだからやめなさい。毎日毎日理由をつけては喧嘩して。本当は…」
仲がいいんじゃないのか、と言おうとして一は慌てて口を噤んだ。
前回この言葉を出した時、弟達は仲の悪さを兄に証明しようと流血沙汰の喧嘩をした。
小学生の頃と変わらない勢いで喧嘩をするには、高校の柔道部と剣道部でそれぞれに鍛えた兄弟の体は大きすぎることにまだ気づいていないのか。
「いいから手と足を離しなさい。三郎は諦めて、今日はチョコソースだけで我慢してくれるか」
三郎は、小さな頃から甘党であった。
納豆は苦いから嫌いだと床にぶちまけた幼少期の三郎に切れた母が、近くにあったパンに塗る用のチョコレートソースを入れたのが始まりで、それ以来三郎は納豆にチョコレートソースをかけて食べる習慣がついた。
ニチカが顔を歪ませる。
「納豆にチョコレートとかあり得ないから。共通点茶色だけだから」
「うるさいな。食べてみたこともない奴が言うなよ。大体岩のりの佃煮なんて白飯にかけて食ってればいいだろうが」
だんだんとまた二人の声量が増して、一は耳が痛くなってきた。
そろそろ二度目の雷を落としそうだったが、朝から怒鳴ってばかりいると一日のペースが乱れそうだったので、苛々しながらもなんとか冷静さを保とうとする。
「まあ、カカオ豆も一応豆だしな。納豆に砂糖をかけて食べる人の話も聞くだろう?三郎はそれが好きなんだからそれでいいんだ。海鮮と沢庵と納豆と卵で爆弾丼というのもあるくらいだから、海鮮系と納豆も合うんだよ、三郎。それぞれ好きに食べればいい。明日からは器にあけずにパックごと出すから、それでいいだろう」
二人とも納得してはいない様子だったが、兄に譲歩案を出されては従わずにはいられない。
ニチカと三郎は互いに背を向けて再度箸と茶碗を取った。
「そういう兄さんは、納豆何派なんだっけ」
一は心底どうでもいいと思いながら「普通に付属のたれと辛子だよ」と答えた。
「「それは個性が無さ過ぎる!」」
薄暗い和室に二人のハーモニーが響いた。
仲が悪いはずのニチカと三郎が顔を見合わせて笑い転げたので、苛々の頂点に達した一は今度こそ二度目の雷を落とすことになったのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
