
欅坂の最高のパフォーマンス=苦しみの果てだと映画を見てわかって苦しい
それから頭の中がずーっと行ったり来たり。
映画公開後に、インタビューや対談などで語られる真実もあった。
何が正しいのかわからない。
わからないから答えを出せない。
答えを出せないから何も言えない。
何も言えないから何も書けない。
でも、心の中でぐるぐるし続ける何かを吐き出したい。
映画以外の話も含まれますが、吐き出させてください。

とにかく「苦しむ姿」が目に焼き付いて離れない。
もちろん、命を削ってパフォーマンスをするのが欅坂46だというのは知っていた。パフォーマンスを見るたびに、「ここまで持ってくるの大変だよな、すごいな」と想像していた。しかしメンバーが直接苦しみを語りつつ楽曲や欅坂46と向き合う姿は、想像をより鮮明なものにした。
映画で見たのはほんの一部を切り取ったに過ぎない。その一部を垣間見ただけでも物凄く苦しかったのに、最高のパフォーマンスに到達するためにはどれだけ苦しかったのだろうか。苦しみの果てを鑑賞中に想像してしまい、とても怖くなった。
しかし映画は止まらない。ボロボロになりながら楽曲と向き合う彼女たちから目を背けたくなる。だが、圧倒的なパフォーマンスに心が奪われる。
苦しみの果てに生まれる最高のパフォーマンス。見たくないけど、見たい。そんな自分に気がつくと、心臓がドキドキしてくる。涙が溢れてくる。これはなんの感情なのだろうか。
苦しむ姿とともに考え続けてしまっていることが3つある。

1.秋元康はてち(平手)を救ったのか?
自身が納得できる表現を追求し、メンバーも理解できない領域に達していくてち。自身の才能と向き合う姿は、孤独そのものだった。
そんな彼女に手を差し出したのが秋元康。映画では語られていないが、秋元康とてちは直接やり取りをする間柄だったとインタビュー等で明かされている。才能をいち早く見抜いた秋元康が、彼女の思ったことを言語化させて話させようとしたらしい。
彼に天才を育てる術があったかはわからないが、数多くの天才を見てきてその苦しみや乗り越え方も見ているだろう。秋元康からの言葉だけでなく、知り合いを通じた助言もあったかもしれない。
こうして、てちは苦しみと引き換えに才能をぐんぐん伸ばしていき、秋元康は彼女の良き理解者となっていった。事実、てちは秋元康をとても信頼している様子がうかがえる。こう見ると、秋元康は彼女を孤独や悩みから救ったと言える。
しかし、彼女が悩む対象は秋元康が作った歌やグループだ。こんなにも悩み苦しむようなものを作ったせいで、心も体もボロボロになっていったんじゃないのか。てちとのやり取りの中で生まれたものを「僕」として背負わせる必要があったのだろうか。そんなの、救ったと言えるわけがない。
一方で、「自身が納得できるかどうか、感情を持っていけるかどうか」が根っこにあるてちは、そんじょそこらの歌では満足いくパフォーマンスができない。なので、彼女が表現者として追求し納得できるほどの「濃い」楽曲を用意してあげるべきだろう。「薄い」ものばかりを与えて表現者としての欲を削いでしまうことも一種の不幸だ。たとえ苦しもうともどれだけ傷付こうとも、全力でぶつかれる「濃い」楽曲を与えることで、アイドルの枠に収まらない彼女の表現欲を満たし続けてきたとも言えるのではないか。そう見ると、てちはある意味秋元康に救われたのかもしれない。画家にとってのキャンパスを与えてもらったみたいな感じ。
秋元康は苦しむてちを見てどう思っていたんだろう。
可哀想に、と思って手を差し伸べたのか。それとも、底知れぬ才能に心が躍ったのか。追い込めば追い込むほど人を魅了するものが出てくるとわかってて追い込んでいったのか。苦しみの果てに生まれるものを期待してたのか。その過程は楽しかったのか、辛かったのか。追い込まれることをてちが望んだのだろうか。互いに幸せな関係なら外野が騒ぐことでは無いのかもしれない。
こうやってぐるぐる考えてしまって結局よくわからない。ただ言えるのは、てちに幸せになってほしいってだけ。鑑賞中に、彼女を助けてあげて、と何度も何度も思った。彼女に表現欲がある以上、これからもずっと何かと向き合い苦しむんだろうし、本当に満足の笑顔が見れる日がいつになるかもわからない。けれどもこれからも「取り組んでみたい」の気持ちをずっと大事にしていってほしいなと思った。
そういえば、「平手」と呼ばず「てち」と相性で呼び続けている理由がある。これは、少しでも助けになれたらと思っているから。映画の感想を読んでると、「天才」「平手という才能」「平手友梨奈の存在」「呪縛」そんな言葉が目に入る。それを見ると、一人の女の子の「てち」がどんどん記号化されていくような気がして苦しくなる。何だか一人の人間じゃないような感覚になってくる。
映画の中のてちもそう。無邪気に笑う一人の女の子らしい姿がどんどん見えなくなっていった。本当はメンバーとの楽しい時間もあったのは分かっているけど、どこか遠くに行ってそのまま消えてしまいそうで苦しかった。だから僕は、実におこがましい話だが、一人の人間として見ているよというメッセージのつもりで、親しみを込めて「てち」と呼んでいる。そうやって、人として見てもらえなくなる寂しさから自分が救っているような気になりたいだけだ。そう呼んだからといって、感想をあれこれ語る対象にしている時点で自分もてちの記号化に加担しているんだろうけど。

2.応援するのは正しいことか?
ステージに立つたびに身を削り疲弊するメンバー。手を握り合って崖に立っているようだと石森虹花は言う。特にてちはそのまま人格が消えるんじゃないか?最悪フッと死んでしまうんじゃないか?そう思えるほど入り込む姿が映っている。
それでも欅坂は楽曲と向き合う。
ハードなダンスで肉体的に、重たい歌詞への感情移入で精神的に追い込まれていく。それらに潰されないために振りも心情も自身に刷り込ませ、頭で考える時間すら失くしていく。そうして体も心も限界に達し理性も無くした苦しみの果てに到達した時、人を惹き込む最高のパフォーマンスが生まれる。それがメンバーもきっと分かっているからこそ身を放り出していく。
ステージで踊る欅坂が我々を熱狂の渦に巻き込んでいく。無心でサイリウムを振る大勢のファン。期待の高さを表す地鳴りのような歓声。
ゾッとした。
支える姿に見えなかった。応援の声に聞こえなかった。これは応援ではない。苦しみの果てへと引きずり出す姿。地獄からの呼び声。そうにしか見えない。そして何より、自分もその一部だと気付いた時、吐きそうになった。
最高のパフォーマンスを期待し熱狂する我々は、彼女たちを苦しみへと追い詰めているのではないか。ステージから見える景色も聞こえる声も、本当に彼女たちが待ちわびたものなのか。応援されて彼女たちは幸せなのか。不協和音中にヘッドセットから漏れる言葉にならない声を聞いて心奪われ感動する我々は、悪人ではないのか。そう思うともう応援できなくなっていく。
しかし、当然ファンがいなければ欅坂は活動できないので応援を辞めるとメンバーを悲しませてしまう。ならばそれだけの想いを持って踊り続ける彼女たちの覚悟を受け止め、こちらも目一杯応援し期待し続ければいいのだろうか。きっとまた最高のパフォーマンスをしてくれると楽しみにしていいのだろうか。いっそのこと何も考えず、ただメンバーが発信するものや楽曲をまるっと受け入れ、賞賛し労わり感謝し続ける受動的な態度こそが正しい応援のスタイルか。
秋元康を含めた欅坂に関わる大人たちやスタッフは、苦しむ彼女たちを間近で見てきているはずだ。それでも彼女たちをステージへ、最高の楽曲へと送り出す。どんな気持ちなのだろう。心痛め涙をこらえ震えているのだろうか。素晴らしい作品が生まれる期待に震えているのだろうか。頑張ってこい!の気持ちはポジティブかネガティブか。相反する気持ちが共存しているのかもしれない。だからTAKAHIRO先生は「大人の責任は見守り続けること」と答えたのかもしれない。
楽曲に力を入れて最高のパフォーマンスのために苦しみの果てへ向かっていく欅坂。その過程でファンは彼女たちの力になっているのだろうか。わからない。ずっと堂々巡り。サイリウムと歓声が目と耳にこびりついて離れない。

3.映画として論評できない
欅坂はこう戦っていた、こう生きていた、とは言える。が、構成がどうとか、あの話をもっと入れてほしいとか、映画としてどうだったとか、映像作品としての評価をしたくない自分がいる。
いい映画だとかよくできているとか、映像作品としての論評をよく目にする。その度に違和感を感じていた。僕が見たのは間違いなくメンバーの生き様だ。苦しむ姿も悩みを吐露する姿も迷いも涙も、全て作られたものでは無い。それを作品として評価することは、生きた姿を「殺す」ような感覚になるのだ。それは、彼女たちに苦しい思いをさせながら欅坂46を作品として手を加えてきた大人と同様ではないのか。
彼女たちの生きる姿を一つの作品とみなすことは僕にはできない。ドキュメンタリー映画の見方を知らないだけかもしれないけど。
しかし、こうも考える。
メンバーたちも欅坂46をよりよい「作品」にするためにパフォーマンスをしているのならば、この映画も「欅坂46から生まれた作品」と呼び評価することも彼女達の望むことなのかもしれない、と。ここまでくると考えすぎてよくわからない。
監督は、欅坂46という子たちの魅力を知ってもらいたいと思ったのだろうか。それとも、欅坂46という作品をさらに魅力的に映像作品として昇華したかったのだろうか。真実はわからないし、どっちの思いもあるかも知れないが、欅のファンでもない映画関係者に事前に声が掛かっていたのを見ると、色々勘繰ってしまうのが本音だ。メンバーを見てもらいたいのではなく、一つのエンタメ作品として鑑賞してもらうためだったんじゃないか、と。欅坂を生きた人間として扱っていない気がしてくる。まあそれがドキュメンタリー映画だろと言われてしまうかも知れないけど。
もしかすると自分は、「周りの大人は欅坂46としてもがくメンバーを商品として利用している」と批判したいだけなのかもしれない。24時間テレビへの批判と似たようなものを感じる。しかし、より良い欅坂46を魅せることはメンバー共通の想いでもある。それならば、欅坂46が作品として一番魅力的に映る形はメンバーが望むものであり、欅坂46が最高の作品として映る時こそ、メンバーの魅力が最大限に発揮されてる時かもしれない。これが僕たちの嘘と真実=フィクションとノンフィクションかもと思った。
そもそも、こうやって映画を見た感想を語ったり、偉そうに映画の作られ方についてあれこれ言及してる時点で、自分自身も欅坂46をエンタメ作品として消費してる側なのだろう。感想を書くことは生き様を殺してしまわないか、それでいいのかと葛藤とともにここまで心の内を吐き出した。
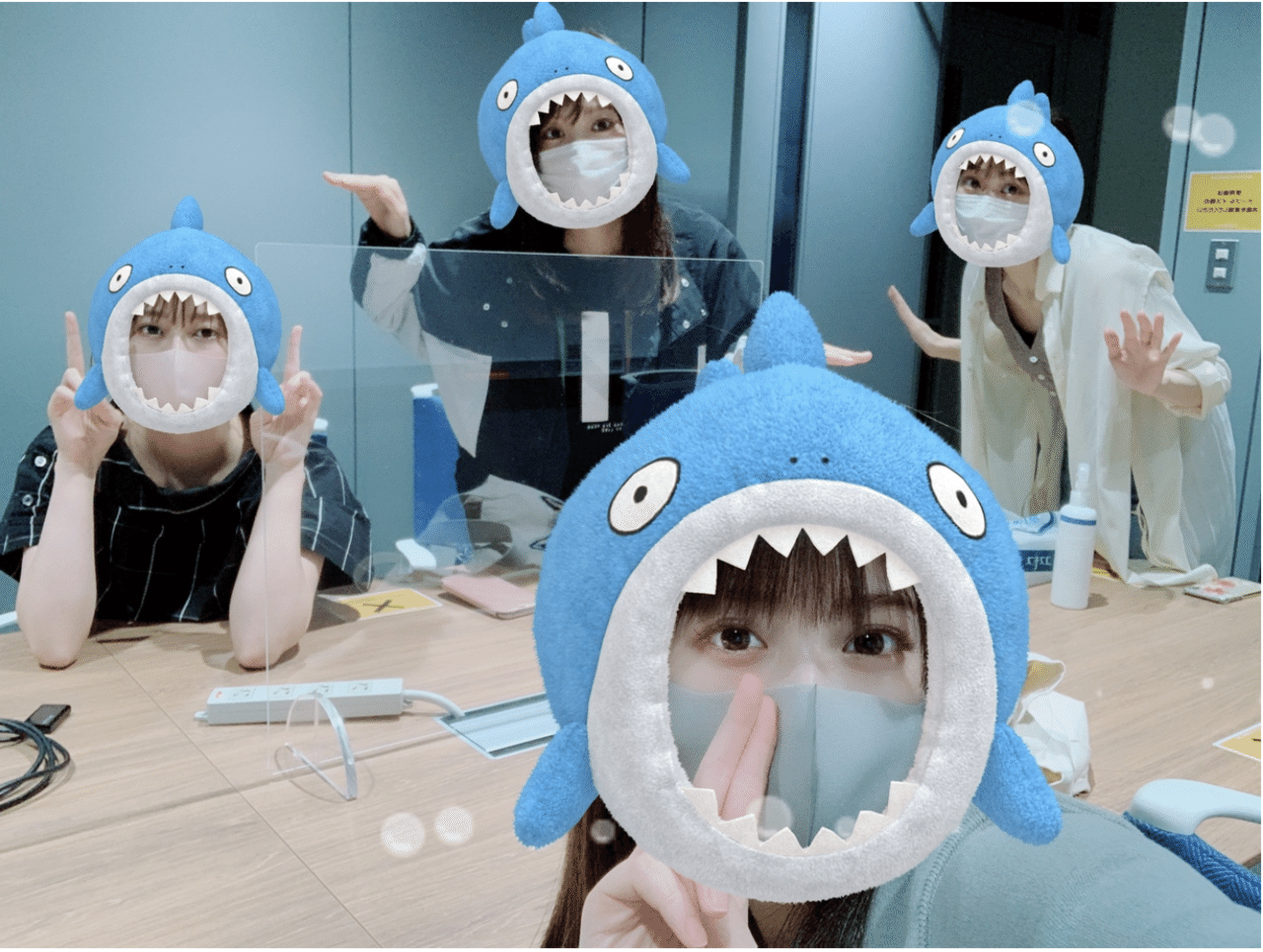
結局
伝えたいことも言いたいこともわからない。
感想が書きたかったのかもわからない。
こんなにまとまりのない文を読んで「結局何が言いたいのかわからない」と思う方も多いだろう。申し訳ないが、自分でも何が言いたいかわからないのだ。それでも心の内を吐き出さずにはいられなかった。
#僕たちの嘘と真実 見た。
— に し (@24maalhinata) September 10, 2020
残った感覚は、映画「怒り」を見たときと似てる。
感想を言葉にするには必ず「立場」が伴う。
僕はどの立場から言葉を発せばいいのかわからない。
欅坂とどの角度で対面しても、全ての自分が否定されてしまう。
そしてこの言葉もきっと欅坂を悲しませるからやはり違う。
鑑賞後、心に残るこの感じは映画「怒り」を見たときと似ていた。何が正解かわからず、自分が正解の側に生きているのかもわからず、悪者もいないのに誰かにぶつけたい心の取っ掛かりがいつまでも離れないこの感じ。
だが「怒り」と違って、メンバーが活動し続ける。
欅坂46は改名後もおそらく楽曲の表現に力を入れていくだろうし、てちもいろんな形で表現し続けていくだろう。そして披露されるパフォーマンスを見てきっと心を奪われるし、同時に苦しさも心に浮かぶんだと思う。そのモヤモヤはしばらく続きそうだけども、彼女たちに幸せな瞬間が訪れるたびに晴れていきそうな気がする。
みんながたくさん幸せになれますように願っています。

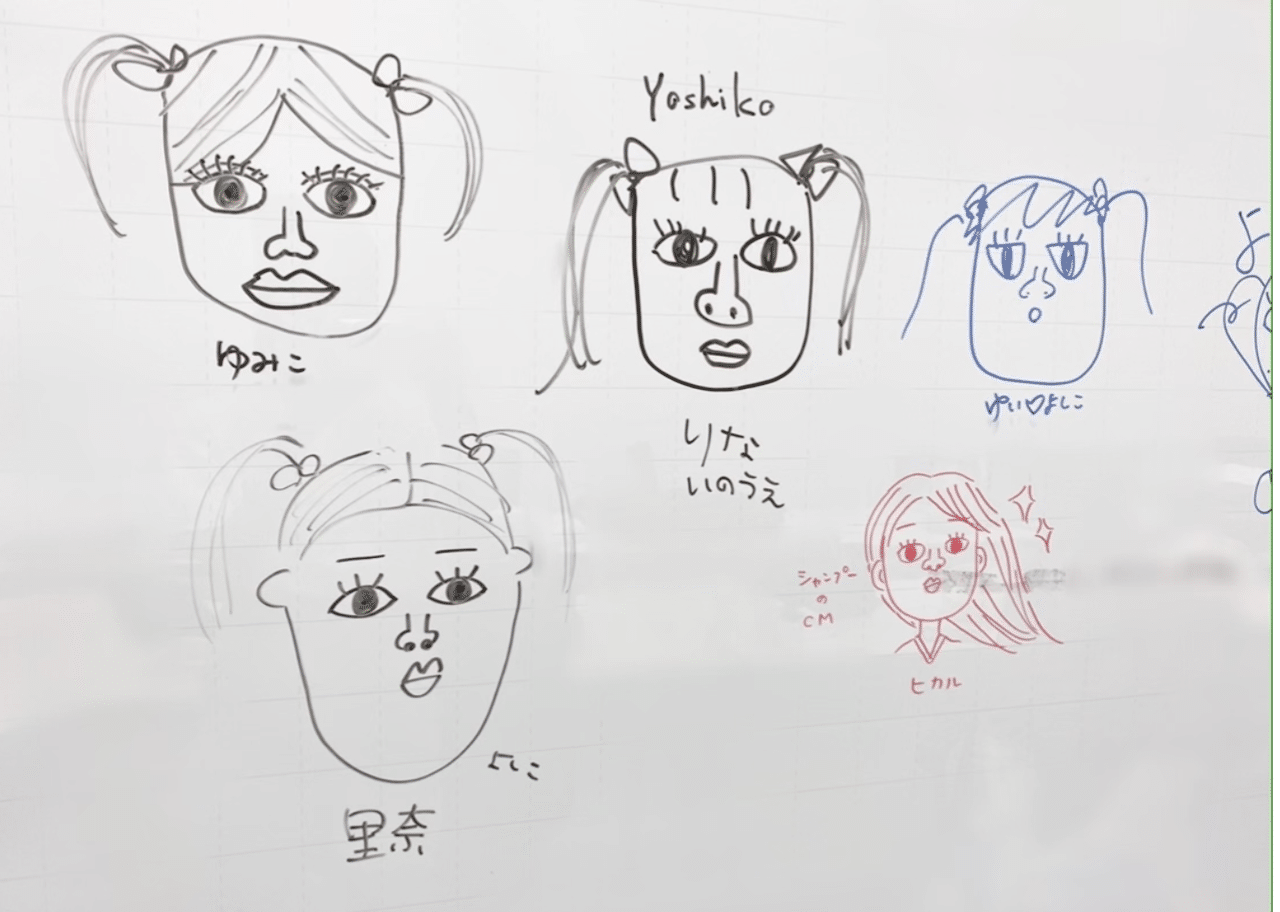

サポートくださいましたら執筆時の喫茶店のアイスコーヒーをカフェラテにさせていただきます!
