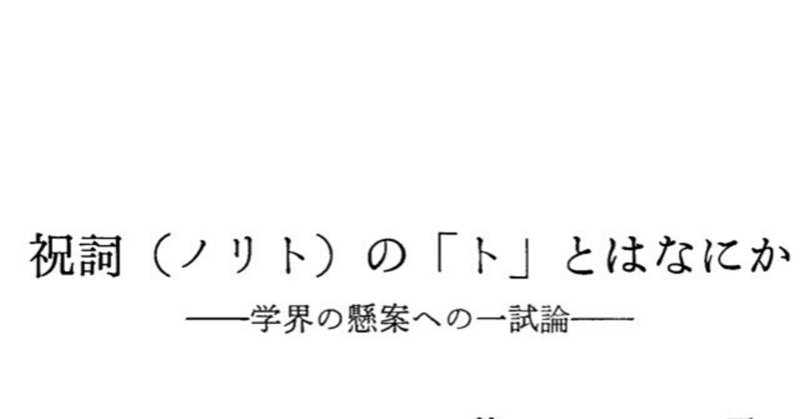
祝詞(のりと)のトとはなにか?:拾いpdfコピペと少し考察
こちらは、調べ物の途中でふと見つけました。
ノリトの言葉についての解説。
ヤマト(ヤマタイ)という言葉の起源にも触れられています。ヤマトとはどこから来たか?の補足に一部になるかもしれません。
あと、ドラヴィダ語も。
http://repo.kyoto-wu.ac.jp/dspace/bitstream/11173/780/1/0040_052_001.pdf
祝詞〈ノリト〉の「ト」とはなにか 一一学界の懸案への一試論一一 芝悉
はじめに
本稿は筆者の著書『日本語の起源・系統 その総方向的検証』ー祝詞「大祓い」の場合一(近刊〉の序説の一部である。前々から祝詞,とくに「大放へ」を資料として検証したし、と考えていたが,
いざ祝詞を扱おうとしてみると,祝詞そのものの意味が神道学界で未確定の懸案とされており,また確かに国語学 の内部のみでは解決が困難と思われ,日本列島近隣の言語を探すうち,いちお う見当がついたので,昨2002年12月 日本語語源研究会 に報告し,今年 3月『 語 源 研 究 」41号 に 掲 載 さ れ た 。
本 稿 は そ の 論 考 に い く ら か 加 筆 修 正 し た も の である。
祝詞〈ノリト〉の意味については,宣長ら以来種々論議されてきたが,問題 の核心はノリ・トのトが甲類のト(万華仮名の戸・斗〉であり, したがって 言・事の意味ではないという点である。
これはノリト(能理戸〉の漢語訳が〔祝詞〕となっていて, (詞)の字に惹かれて〔言〕と見がちなことにある。今日 までのところ, 要するに, (ノリトゴト〕の〔ノリ〕については,従来の諸 説によってほとんど遺憾なきまでに研究されているが, (ト〕については,な お今後の研究をまたねばならぬ。(次回潤「祝詞新講」192,p.1)と述べ
られ,また武田祐吉氏も「トについては,諸説があって明解を得ていないが, 云々 (「日本古典文学大系」「古事記・祝詞」194,p.368) とある。
(以下、甲乙が出てくるのですが、このpdf内には記述されておらず、そしてまだ探せていない…
ですが、とりあえず、そのまま読み進めていきます)
いったい〔ノリト]が〔祝詞]という漢語に当てられたのは何時の時点であろうか。
いわゆる醍醐帝時の「延喜式」(905.-927)の「神祇令」において は,平安朝になって 10年以上も経ているのであるから当然であるが,それど ころか平城遷都直前の大宝令(文武 4年, 701年〉には明確に見え, これらに ついては多くの優れた研究があるが,中でも梅田義彦氏の力作『神祇制度史の 基礎的研究」に助けられる。 r大宝神祇令には,年中諸祭の中に,仲春祈年祭 以下を規定し,その後に其ノ祈年月次祭ニハ,百官神祇官ニ集ヒ,中匡祝詞ヲ 宣リ,忌部幣吊ヲ班ツ J (93頁〉とあり,
さらに早く, 近江令が制定せられて 3年目,即位 3年 3月壬午の条に, 山ノ御井ノ傍ニ諸神ノ座ヲ敷キテ, 幣 吊ヲ班チ,中巨ノ金ノ連祝詞ヲ宣ル(88頁), これは書紀27天智帝の条であり,このように意外と早い時期にまで遡るのである。
さて,たとえば宣長は「大放詞後釈」中「天津祝詞乃太祝詞事」の条で「ノリトゴトく能理斗碁登〉は宣説言(ノリトキゴト〉なり」と言って, トを〔説 き〕と解したわけだが,自身が 2種類区別に着眼した最初の当人であるから,その矛盾に 気づいてもよかったのではないかと思われる。
(本居宣長が、祝詞の意味を変えて解説した、と言っているのでは?)
トコフ;トホフ
そこで,これまでの説の中では,小山龍之輔氏がこのトについてトコフ〔呪誼〕のトに言及されたがく『日本文学聯講」), 氏は, 例の「天津祝詞ノ太祝詞 事ヲ宣レ」の「ノリトゴト」を「ノリ」と「トゴト」に分かち, トゴトは〔ト 言ツ J,そのトはトコフく〔ト乞フ〕の意とされ〉のトと同じもので,強意、とさ れた。
しかし, 「天津祝詞乃太祝詞事」とし、文脈で,事〈言〉をトゴトとするのは無理のように思われる。祝詞は重ねられたもので,事(言)は前・後双方にかかると見るべきであろう。 なお,菟田俊彦氏は,祝詞の読み方の紹介のところで「その他,ノリト〔宣呪〕の義とみる説が行われているが(「'大日本百科事典」小学館, 1970, p.353)とあるが,私はむしろこれに注意したい。
さて,わたくしは上の「トコブ」そのものを,ノリ・トの〔ト]とみてはど うかと考える。つまり「ノリ」と「トコフ」が並置されているとみたい。 また , こ の 「 ト コ フ 」 は 「 ト ホ フ 」 と も 言 う (「神 功 紀 」)こ と に 注 意 し て ,
古 代日本語の周辺を探ると,固有モンゴル語に*Toxoxがある。小沢重男氏によれ
ば,現代語にも中世モンゴル語にも存在する(W'現代モンゴル語辞典J1983,p.380;W'古代日本語と中世モンゴル語J1968,p.249)0 /x/は喉音であるから, /k/に近く発音されたり, /h/に近く発音されたりするから,日本語では トコフとも, トホフともなっていることがよく理解される。この語の意味は単語家族の関連からも〔鞍を掛ける;鞍に鞍祷をかける;人に罪をかぶせる〕と いうようであり, また韓鮮語では、ねph;} [覆う;罪や責任などを他人に被せる〕である。
なお,トコフは「時代別・国語大辞典』上代編では「神に霊威を請うて,自己や他人を誼う」とあるが, ノリはもともと〔告り, 宜り, 呪い]であるか ら, [ノリ〕と〔ト〕の両者は重なるところがあるから,並置されたとみる こ とは自然なことと思われる。
なお, トコフの音韻上のことであるが,このトは上記の辞書では甲・乙いず れとも明記していないが,記・紀では「止古比」としていて,止ならば乙類で はある。しかし,上述のようにアルタイ諸語として新しく入ってきたものであ れば,固有の南島語にとっては,いわば外来語的な音韻は明確には判別できにくかったと考えられる。
(※筆者の説で推測できるのは、南島語が日本列島の固有の言語で、ノリトの使い手はアルタイ語を使用していたということである…🤫)
しかも, toxox とあるように, /0/であって, /δ/で ないのも,このことに合致していると言いえよう。
トフ〔問〕
上記のトコフ;トホフは,時代が降るとあまり多くは用いられないようであったが,実は日本語の中で非常に重要な語彙に先行した同族語であったと考え たい。その語彙とは,実はトフ〔問ふ〕である。トフ(斗敷) [問い尋ねる; 占い問う場合にもいう J(上記, W'時代別J)とある。これは音韻からも,その トは甲類であり, しかも前記のノリ・トのトと同様に, 記・紀では甲類であ り,万葉では乙類であるというように全く一致しているのである。上述のモンゴル語の*toxIox[toxJ日本上代語 *tofuへの移行が理解されるであろう。
この「問」は,大祓いにおいて「荒ぶる神等をば神聞はしに問はしたまひ,神掃ひに掃ひたまひ」とか「語問ひし磐根樹立,草の片葉をも語止めて」とあ るが,神々の前の「問はし 」,人々の「問ひ 」,草木にいたるまでの「語問ひ 」, さらには「天つ罪・国つ罪, 許多の罪」に対する自己自らへの「問ひ」, まさに「問ふこと」こそは大放への精神ということができる。
(※草木にまで問い詰められる?そのうち責め苦の幻聴が聞こえてきそう、、と私は思ったんですがどうでしょう、誰を問うか?がはっきりとは述べられていない…)
さらに言えば,ノリ・トのトは「問ひ」であり, I能理斗碁登は宣り説き言なり」と言った宣長の言華に擬えれば, 「告り問ひ言なり」ということにな る。
祝詞は一方,神々の御稜威を讃仰し,
(讃仰=《「論語」子罕しかんの「これを仰げば弥いよいよ高く、これを鑽きれば弥いよいよ堅し」から》聖人や偉人の徳を仰ぎ尊ぶこと。さんごう。https://kotobank.jp/word/%E9%91%BD%E4%BB%B0-513152)
神意、の「宣告」を奉じ,時に際し事に当たって「報告」・「祈念」するとともに,他方,神々の「問わし」人々の, 万象の「問い」自己自らへの「問い」ということができる。 ここにこそ「祓ヘ」の真の精神が在るのではないであろうか。
(キリスト教にそっくりなのではないですか…)
付説(1)
日本語トフ〔問〕の同義語タヅヌ〔尋〕について タヅヌ(多豆妓) (尋〕の起源・系統はどうであろうか。
まず,その意味で あるが,万葉集や仏足跡歌など例があるが, (道を尋ね求める〕とか,道理な どを〔推し求める〕などであり,人を訪問するというような用法の「確実な例」は上代には見られない、 (「時代別」)といわれる。
(上代の南島語を話す人々は、トフ(問う)"ことはなかったのでは?)
さて,このようなタヅヌ〔尋〕の系譜は南島諸語に求められるように思う。
インドネシア語には tanja(問し、;対話, 問答〕がある(O.Karow,u.a.)。 これは O. デンプヴォルフが *t~n)dn (正しくあること〕をあげているのに繋が ると考えられる。インドネシア語派のタガロゲ語ではネtil)in, トバ・バタク語*tol)on, ジャワ語 tel)enなどをあげ, また *tdl)ah(中,半分〕でンガージ ュ・ダヤク語, またトバ・バタク語キtOl)a, ジャワ語, マレイシア語では *t句 ah, ポリネシア系でも本tOl)aがある。 これらから見ると, 日本上代語 *tadunu と,意味の上からも合致し,音韻上も *tal)a(*tadunu) の移行関係は自然なものと考えられる。
付設(2)
乙類のト,とくにヤマト邪馬登(大和〉・ヤマタイ邪馬台について いわゆる」「魏志倭人伝」すなわち「三国志」、「魏書」倭人の条には,邪馬台国の名が記されているが,記紀,万葉などには夜摩苔,耶馬騰,耶馬登,耶摩 等などとなっていて,すべて乙類の toである。
例の「邪馬台国の所在は九州 か近畿か」の問題で,古代日本語の仮名遣し、から,大森志郎氏は近畿のヤマト(大和〉のトがすべて乙類であるのに,九州のヤマト〈山門〉のトは甲類ということで,後者への批判をされた (魏志倭人伝の研究J195)。また原田大六 氏は「上代語のヤマトはヤマタイから変化したのではなかろうか」と推理された(「邪馬苔国論争」1969,378頁〉が実はその仮説は正しかったということが できる。
そこで問題は,何故ヤマタイ yamatai であるのか。まず yamac(yamatc)は古代トルコ語で「山の片側, 斜面, スロープのこと J (M・レーセネン, s・184)である。ーtaiはモンゴル語のコミタチフ「共同格, 〜ともに」で ある。つまり「山とともに」「山タイ国」は山とともにある国,すなわち「山国」であり。弥生の初め大陸や朝鮮半島や日本列島に上陸した人たちは, いきなり鼻を突くような山国に驚いてこのようになづけたので、あろうと思われ る。
(古代トルコ語と古代モンゴル語を合わせた言葉、「ヤマタイ」……なぜ、違う言語が混ざるか?どちらの言葉も「ヤマト」を名付けた者は操っていたということか…も、知れない。
古代モンゴル語や古代トルコ語についてもう少し深掘りしたい、少しだけ調べると、メソポタミアやアッカド語と近い関係であることはすぐに出てきたけど確信には至らず🤫🤫)
なお台タイ tai→登ト toは自然の移行である。いったい名前は他者によって付けられる。その昔, インダス河畔に列達したアーリアンが shindhu! Shindhu!(海! 海 !) と狂気したように。それがインド, ヒンドウの地名 になった〈本田義央博士,インド哲学講義〉ごとくである。
付説(3)
上代日本語仮名遣いにおける甲類・乙類の区別はなぜ、消失したか。
上代日本語においては 8母音が存在した。すなわち,イ列音,ェ列音,ォ列 音に甲・乙 2種,キヒミケヘメコソトノモヨロ ギピゲベゴゾドの20音節であ る。原始日本語では,これ以上であったかもしれないが,少なくともこれが認 められている。その起源や系統については,南島諸語にもアノレタイ諸語にもある。例えば,前者では *kui[ki(木), *apuiJpi(火), *mui[mi(実), pi+ tauJpito(人〉など,後者では今日の韓国・朝鮮語に母音が 8個であるごとく。
さて,この甲・乙 2種の区別は何故消失したのか。筆者は1973年に「ドラヴィダ語と日本語」という論文を公けにして,両言語の親縁関係を学界に提起し たが(京都女子大学・人文論叢,次いでマドラス大学・プラマイ学会,第10回 国際ドラヴィダ言語学会年次会議報告, 1980), ドラヴィダ語族はアルタイ系 言語に属するが,すでに b.c.3000年頃西北インドに南下し,かの壮大なイン ダス文明を建立したが,その最盛期をやや過ぎた頃、かのアーリアンが侵入し, 闘争を繰り返しながら次第に南部へ,またマレーシアやインドネシアへも移動 したが,両民族は血縁的にも文化的にも多くは融合し,今日のインドを形成し ていて,その人口も今日 1億5000万人以上である。
さてその言語も世界で最も美しいものと称せられているが,サンスクリット もそれによる,例の五十音組織はドラヴィダの創始であって,その 5母音組織 の影響こそが,日本上代語の甲・乙類の区別を解消させたものと考えられる 。
ドラヴィダ語はアルタイ系言語であるが,数千年前にインドに南下し,先住の ムンダ一人(南アジアの海岸地帯の現在のモン・クメールやミャンマーなどと 同語族)を征服・同化したので,アルタイ語的要素とともに南アジア語的要素で古代日本語への影響も少なくないと考えられる。
主な参考文献・資料
祝詞定本・資料
以上
6
祝詞 武田祐吉校注 目本古典文学全集(1) 岩波書庖 1958 祝詞・寿調 千田憲編 岩波書庖 1940 祝詞新講 次回潤著 明治書院 1927
大野晋編本居宣長全集(7) 筑摩書房 1971
大蔵詞後釈 神祇制度史の基礎的研究 時代別・国語大辞典・上代編 岩波・古語辞典 漢字語源辞典
1.南島諸語関係
アイヌ語辞典
アイヌ語辞典 萱野茂著 二省堂 196
梅田義彦著
沢潟久孝編集代表
大野・佐竹・前田共編
藤堂明保著
吉川弘文館 1964 二省堂 1967 岩波書庖 1974 学灯社 1965
磯部精一著
東京実業社 1981
