
も み じ 饅 頭
もみじまんじゅうのことばっかりかんがえている。冷たく冷やした、もみじまんじゅう。
今日は病院ばっか行って、区役所にも行って、病院に予約の連絡してたけど手違いでスムーズに行かなくて、そんな些細なことでなんか自己嫌悪して、もみじまんじゅうのことばっかりかんがえちゃうわ。
広島に気をとばしたくないし、日常のめんどくさいことを一気に進めて、気を、わたしの体に集中させたいのに、どうしても自分を光らすことができなくて、帰りに指輪買ったわ。
左手の薬指にはめて、ビスケットアイスクリーム食べて、せっかく甘くなったのにたばこを吸って煙をはいたら、またもみじまんじゅうのことばっかりかんがえちゃったわ。
他人が、誰かが特別に自分を愛してくれなくたって、わたしがわたしを愛しているなら、それでやっていけるんじゃないかと安っぽいこと思って、安物の指輪を薬指にはめたって、どうしても、もみじまんじゅうのことばっかりかんがえちゃうわ。
他人のことを気にするなかれ。わたしはわたしの心配をしてろ。どうあがいても動かしようがない気持ちのことをかんがえるな、もみじまんじゅうのことをかんがえるな。
でも今日はなみだでるから、お酒飲んで、もう寝るし、寂しいことはもう受け入れるしかない。
わたしは寂しい。わたしはつらい。それを受け入れて、そばにいる。
今日はなんにもはかどらなかった自分を受け入れて眠る。悲しいからなみだでるけど、仕方ないから、眠る。気持ちを離して、もみじまんじゅうを考えない、ために。
*
東堂が広島に行くというだけで、あづ紗は嫌な妄想が掻き立てられる。手土産に買って帰ってきてくれたもみじまんじゅうは、もみじの形をしているものの、白い小麦の薄皮を被ったきんつばタイプのものだった。これは果たしてもみじまんじゅうなのだろうか。お土産はノーマルなもみじまんじゅうだろうが、普通は。普通、という言葉を一番嫌悪しているであろう東堂らしい手土産ではあるが、わざわざ買ってきてくれた土産に文句を言うのもなんだが、とにかく、あづ紗の想像と違った。普通、「もみじまんじゅう買ってきて」と言われて選ばないであろう、白い、薄力粉の薄皮を被ったきんつばタイプのもみじまんじゅうを手土産に帰り、東堂はそれを冷蔵庫に入れて今あづ紗の横で眠っている。
わざとだ。たとえ土産物一つにしても、あづ紗が希望することを東堂は叶えてはくれない。地味に面倒くさい、そういうことをやる男だ。
東堂は痕跡を隠そうとすることが無いため、例えば、わかりやすく女性の使う基礎化粧品やローズの香りの入浴剤がバスルームにあったり、歯ブラシが2本並んであったり、急いで剥がしたであろう丸められたシーツがベッドの横にあったりする。コンドームの箱の中身が1週間前に来た時よりも半分減っていて、精力剤の瓶がシンクに転がっていたりする。だから、きっと聞けば答えるだろう。
広島で誰に会ったのですか?
*
同棲を解消してからも、しばらく友枝はその部屋にいた。代わりに東堂が部屋を出て行き、運営しているギャラリーで寝泊まりをしていた。家が見つかるまではいていい、ということだったが、東京で一人でやっていけるほどの収入もなく、結局広島の実家に戻った。三十を過ぎて戻ってきた友枝に、家族も親戚も近所の人も、田舎特有の押し付けがましさで結婚の話を持ち出してくる。早くここを抜け出さないと、とは思うものの、今は疲れ切った心身を回復させることで精一杯だった。心身は磨耗していた。言霊が宿るからいい言葉を言い続けなさい、と祖母に言われてからは、 ありがとうございますありがとうございますありがとうございます、まるでありがとうございますの機械になったかのように、友枝は中空に向かって(もしくは壁に)ありがとうございますと言い続けていた。
東堂と別れて半年、東京の部屋を出て三ヶ月が経った頃、広島に出張で来ると東堂から連絡があった。連絡を取ったのは実家に到着した時以来だった。何を考えているのかわからなかった。復縁したいのだろうか。そもそも、お互い嫌いになったわけでもなく、うまくいかなくなったわけでもなく、ただ将来を見ている方向性が違い、友枝が結婚をせがんだことが別れの原因だった。
別れたのは、交際を始めて五年、同棲を始めて半年が経った頃だった。
*
友枝が出て行った次の日にあず紗は初めて東堂の部屋に泊まった。その時まだ、玄関のドアにも、ポストにも「東堂•友枝」とマジックで名前が書かれたマスキングテープが貼られていた。変わった苗字だったので、何となく記憶してしまい、その後東堂の制作した海外でのプロジェクトをまとめた一冊の本をペラペラとめくっていた時、最後のページに、「現地取材の記録やすべての取材音源の文字起こしをした友枝氏に感謝申し上げる」と謝辞が記されているのを見て、ああこの人かとあづ紗は思った。
海外でのプロジェクトを一冊の本にまとめた後、東堂は冴子と共にギャラリーの運営を始めた。半年後には友枝は東堂の元を去ったのだが、友枝が去った理由が、直接会った事もないがあづ紗には理解できると思った。
*
冴子はいつもダボダボしたTシャツに汚れたジーンズを履いて、髪は毛先が肩上で跳ね上がっている(つまり、ボサボサだ)。愛想がいい印象を持たれるように心がけているその表情は、いつも笑みが張り付いている。大学で教える東堂のアシスタントをしていて、指示にはいつも「はい!」と元気な返事を返すよう心がけ、はつらつとした印象を与えたいと冴子は思っている。脚立にのぼり、指示通りにレールライトのセッティングをし、均等な間隔になるようにレーザーライトを当て、寸分狂わずビスを打つ、というようなことを簡単な指示でこなせるよう、細心の注意を払っている。
冴子は東堂に必要とされた時にだけ会うことができる。
それは、そう言われたのだから間違いない。一人でなんでも完璧にこなしてしまう東堂が冴子を必要とする時、それは例えば、納期が差し迫っている業務がある時、人工を出せる依頼が入った時、額装が必要な時(冴子は額装士としても仕事をしている)、もしくは、共同で運営しているギャラリーのインストール及び搬出業務の時、すぐにセックスがしたい時、だ。
冴子は東堂から連絡が来ればすぐに駆けつけることができる。職場は同じだし、大体のスケジュールも把握している。家も、共同運営のギャラリーも自転車で十分程の距離である。
「必要な時にだけ連絡します」
三年前、出会ったばかりの頃にその言葉を言われてから、事あるごとに思い出す。スマホ病と自負するくらい冴子はいつもスマホを手にS N Sをチェックし、些細なことでも友達にラインする。恋人と別れてからはマッチングアプリで平均3〜4人と常に連絡が取れるようにしている。必要な時を待ってはいけない。待つことは苦痛である。
連絡があれば、嬉しい。今この瞬間だけは、必要とされている。
*
「優先順位は若さと近さ」だと、東堂はあづ紗にはっきりとそう断言した。あづ紗より十若く、東堂より七つ若い、助手の冴子も「質感の違う好きな人」なのだということも告げていた。
あづ紗と共に仕事もしたことがあり、友人でもある冴子との関係を、東堂が始めからあづ紗に話していたわけではない。
ある時「答えてくれないんなら本人に聞きます」とあづ紗は東堂に詰め寄り、やっと話したのだった。
三年前くらいから時々セックスをしています。冴子は誰とでもする人だし、でもそんなに頻繁じゃないですよ、月に一回くらい、と聞いて、あづ紗は「信じられない、わたしとの関係が始まってからも五回はしているということか」と苦手な計算をしてしまった。
「最初に、どうして言ってくれなかったんですか」と言うと東堂は黙ってしまった。それから「もう人のことを詮索するのはもうやめたらどうですか」と言った。
あづ紗はポリアモリーやオープン・リレーションシップに関する記事を読み漁ったが、そのどれにも当てはまらない、つまり、複数人が「質感の違う好きな人」であり、相手同士が関係することはなく、一人一人との関係性を築くタイプの東堂は、確かに、既存の名前のある状態ではないという理解に留まった。それが世の中でいう「浮気」と何が違うかというと、聞けば隠すことなく答え、離れていけばそれまでということだろうか。
*
東堂は明け方目を開けた時、カーテンの隙間から差した陽光が目を差し、眩しさにすぐにまた瞼を閉じた。奇妙な夢を見ていた。夢の中で東堂は左手を切断していた。作業中に丸鋸の操作を誤ったのか、どういう経緯で手を切ってしまったのかは夢の中では語られていなかったが、綺麗に左手首からその先を失った東堂は、再生する外科手術を受けにロサンゼルスの名医を訪ねに行くところだった。同じ夜(もしくは明け方だったのだろうか)に見た夢は、どこかの田舎で急流滑りに乗っていた。滑降するボートのその下は海で、そこには一頭のシャチが口を開いて待ち受けていた。ああ、喰われるのだろうかとぼんやりと思っている間に、横から別の生物がボートを追い抜き、滑り降りていく。その生き物は白イルカとアシカを掛け合わせたような出立ちをしていて、頭部は丸い白イルカそのもので、下半身は黒く、アシカの姿をしている。なんと呼ぶべきものなのか、東堂には見当も付かない。
<了>
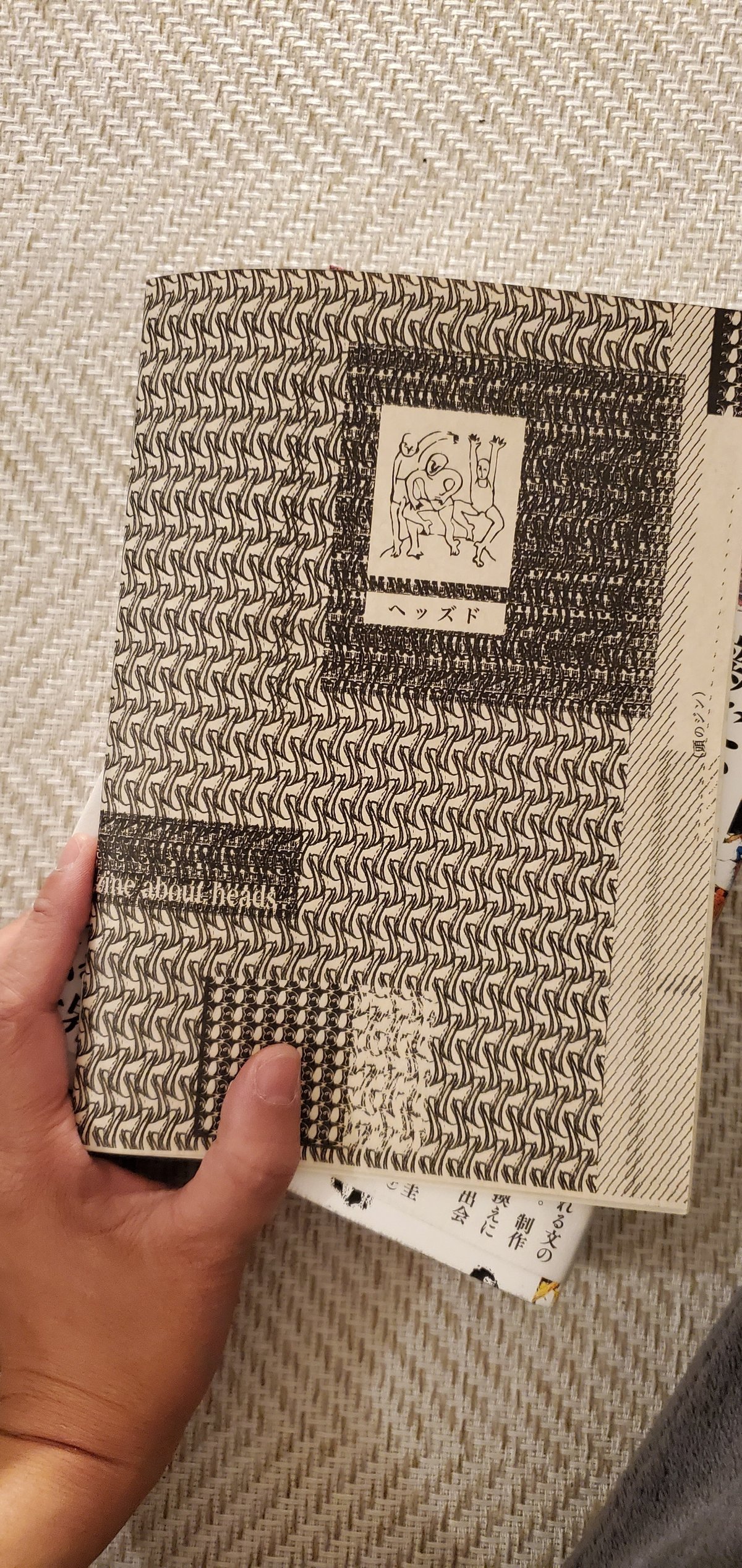
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
