
作家・池澤夏樹が考える「日本語と編集」〈後編〉
「千夜千冊」にまつわる人々をインタビューし、千夜について、本について、読書について語ってもらう「Senya PEOPLE」。今回は、現在、『日本文学全集』(河出書房新社)の個人編集をつとめる作家の池澤夏樹さんにインタビューをしました。後半は「古典と現代語訳の話」から「文学全集」制作の経緯をお話いただきました。東日本大震災以降、『日本文学全集』制作に掛ける思いとは。そして池澤さんにとって「編集」とは何なのか、を語っていただきました。
▽池澤夏樹(いけざわ・なつき)
1945年、北海道生まれ。埼玉大学理工学部物理学科中退。1988年『スティル・ライフ』で芥川賞を、1992年『母なる自然のおっぱい』で読売文学賞を、1993年『マシアス・ギリの失脚』で谷崎賞を、2000年『花を運ぶ妹』で毎日出版文化賞を、2010年「池澤夏樹=個人編集 世界文学全集」で再び毎日出版文化賞を受賞するなど受賞多数。その他の作品に『静かな大地』『きみのためのバラ』『カデナ』『双頭の船』など。2014年から『池澤夏樹=個人編集 日本文学全集』を河出書房新社より刊行中。3.11の被災地のルポルタージュ『春を恨んだりはしない―震災をめぐって考えたこと』が千夜千冊1465夜に掲載。2017年3月には『キトラ・ボックス』(KADOKAWA)を出版。
( 前編 / 後編 )

池澤夏樹=個人編集 日本文学全集
『日本語のために』(河出書房新社)
「古文」ではなく「古典」を読んでほしい
――『日本語のために』にはハムレットの翻訳がいくつも並べられていましたね。同じ訳なのに、文体の違いでここまで印象がかわるのかと驚きました。
池澤|『ハムレット』では文体の変遷がたどれるように時代順に有名な独白の訳をいくつか入れました。一番古い坪内逍遥の訳を読んでみると、なんとなく歌舞伎らしさがのこっていることが分かって面白いですよね。従来のものに加えて、新訳を劇作家の岡田利規さんにお願いしました。岡田さんには『日本文学全集』の「能・狂言」の訳も担当してもらっていて、今っぽい訳になっている分、若い人には読みやすいのではないかと思います。
原文さえあれば、作家ごとのモチーフで何度でも現代語訳ができるんです。翻訳も一つの創作なんですよ。昔は原文しかないから学者が片手間で翻訳をしていましたが、ここ何十年かで日本の翻訳スキルがグンとあがりました。現代語にしていく過程でどうしても抜け落ちていく部分はあるけれど、そのぶん変わるところもある。翻訳という再創作を通じて、一つの作品が次の段階に進むんです。
――わたしは逆に岡田さんの訳から読んでしまいました。時代を遡るのも面白い体験ですね。『日本文学全集』で訳を担当されている方々はまさしく日本現代文学を担う一流の作家さんばかりですよね。どのような意図があったのでしょうか。
池澤|翻訳で重要なのは文体です。文体あっての文学ですからね。だから今回は文体のプロである作家さんたちに頼もうと思いました。多少の訳の間違いはこちらでなおすことができる。それよりも、作家それぞれが苦労して磨いてきた文体の匂いを読者に感じてほしかったんです。
だから作家さんたちには何も注文をつけていません。翻案でなく翻訳であれば、ご自由に判断してもらって構わないということにしています。
僕の場合、日本文学全集の中で『古事記』を新訳しましたが、その際には本文の下に脚注をいれました。一見学術的ですが、余計な説明がないので本文が速く読める。『古事記』は元々速い文体なんです。どんどんストーリーを追っていって、気になったら下を見てもらえばいいとした。
ただこれは『古事記』だからこそ、この方法をつかっただけであって、作家さんたちにはそれぞれの作品にあった翻訳を工夫してもらっています。
――古典で読むとなると原文で読まないといけないという脅迫観念がありましたが、「日本文学全集」には現代語訳だからこその醍醐味が色濃く表れていますね。特に高橋源一郎さん訳の『方丈記』は驚きました。
池澤|そうですね。高橋源一郎さんは『方丈記』(42夜)を『モバイル・ハウス・ダイアリーズ』に改題して、訳も現代風に大胆にアレンジしています。あれはふざけているようだけれど、ものすごい工夫で、「ハルマゲドン」という章では、東日本大震災と重ねて読むことができる。『方丈記』で書かれた内容が、今の時代と響きあって、読者は惹きつけられるんです。間口を広く、敷居を低くして「古典」の世界によび込んでしまえば、あとは面白いことが起きる。それで原典も読んでみようと思ってくれる読者がでてくれば、それに越したことはないですよね。
原典のままなら他にいくらでもある。でもそれだと今は誰も買ってくれません。『日本文学全集』の現代語訳は「古典」であって学校で習う「古文」ではないんです。お勉強をしてほしいわけではない。それよりも『日本文学全集』はある種、啓蒙の仕事ですから、たくさんの人に「古典」を広めたいんです。現代語訳によって「古典」を今の文脈で解釈することが大事なんです。

文学全集は日本人の教養だった
――ラインアップが先に出されて、本が少しずつでてくるのを心待ちにするといった「文学全集」の文化は今の世代には馴染みがない分、新鮮に感じられますね。
池澤|「文学全集」は昭和のはじめごろから一気に流行して、戦争で一時途絶えたけれども、また現れ始めた。多分こういう現象は日本だけですよ。他に唯一知っているのは台湾と韓国。どちらも旧日本語文化圏ですね。巻数と内容を決めてラインアップを発表して、毎月の予約購読を集う。
あのころは、個人経営の書店が駅前に必ず一軒あって、頼んでおくと雑誌数点と文学全集1冊を自転車で配達してくれた。それが当時の教養でした。
1980年ぐらいにはそれが鎮静化して、本を教養材じゃなくて消費材にしてしまおう、読んだら捨てて次にいこうという流れになっていきました。教養主義の衰退ですね。そこで文学全集の文化は下火になっていったんです。
――では、なぜあえて今「文学全集」を手がけることになったのでしょうか。
池澤|2005年頃、ぼくと同世代の河出書房の編集者が『世界文学全集』の企画をもちかけてきたのが最初でした。ただ、そのときはいまさらという感じがして、その編集者のノスタルジアにしか思えなかったのでお断りしたんです。
だけどまたしばらく経って若い編集者が説得しにやってきた。話を聞いているうちに、独断で全集を編集できるならそれはそれで悪くないかなと少しその気になったんです。基本的に非妥協、協調性のない人間なんでね(笑)。

そのあとホテルに戻って白い紙とペンを持って昔の文学全集をなぞりながら考えていました。『オデュッセイアー』(999夜)は入れるけど『イーリアス』は入れないのか、シェイクスピア(600夜)はどの作品にしようとか。だけどわざわざそれらの作品を本に仕立てて売れるとは到底思えなかった。だったらいままで全集に入っていない作品を入れようと思ったけど、それだとただの落穂拾いになる。
いろいろ考えたあげく、ふとひらめいたんです。20世紀だけにしようってね。それも戦後にしようと。それなら従来の全集にないものというだけでなく、もっと積極的な意味を持たせられると思った。
第二次世界大戦が終わり、世界の様相はガラリと変化しました。植民地がなくなり、女性の立場が変わり、世界中で人々が国境を越えて動くようになった。また冷戦が終わり、そして9.11が起きてしまった。
そんなことを横目に見ながら、変わっていく時代を文学はどう表現してきたのか。そういう視点で世界文学全集を編集するなら意味があると思ったんです。
おそるおそる始めてみたらこれが結構好評だった。単発で翻訳を出すよりはだいぶ売れました。しかも半分以上はベトナムとかチェコとかポーランドの普通の人が聞いたこともない作家です。それでもなんとか全30巻を順調に出すことができた。
そうして最後の巻が刊行されたのが、2011年3月10日。奇しくも東日本大震災の前日だったんです。

日本人のルーツを知るための日本文学全集
——「文学全集」の日本版がスタートしたのはやはり東日本大震災が契機だったのでしょうか。
池澤|あの震災以降、「日本そのもの」についていろいろと考えるようになりました。日本はいったいどういう国なのか、日本人はなにを考えてそれまで生きてきたのか。
そもそも日本は独立性が高い国です。海に囲まれた島国であり、運よく1945年まで異民族支配を知らなかった。他の国は入り乱れているのに比べて、この国に住んでいるのはほとんどが日本人ならびに、準日本人としての蝦夷、アイヌ、琉球人。これはめったにないケースです。
そうやっていろいろ考えていたときに河出書房新社会長の若森繁男さんに「日本文学全集もやろう」と声をかけられたんです。実は「世界文学全集」が三分の二ぐらいまでいったときにも頼まれていたんですが、その場で即座に断ったという経緯がありました。ぼくは翻訳モノに関してはここ30年ぐらいずっと書評を書いてきたので、だいたい目を通しているし頭に入っている。しかし日本文学についてはあまり明るくなかった。それなのに『世界文学全集』が上手くいったから日本版もやるというのは、あまりにも安直だと思ったんです。
だけど若森さんも勘がいいのか、震災後うろうろしている僕にもういっぺん頼んできた。「池澤さん、やっぱりやらないか」と。それで一晩考えて、やることに決めました。
これはよっぽど勉強しなきゃいけないぞと思いましたけど、想像以上でした。『古事記』を訳している間はこれまでの人生で一番勉強しましたよ。まさしく60の手習い。そのときはすでに65でしたけどね(笑)。いまでもそうです。すべての全集作品に解説を書かなきゃいけないから、読まないといけないですし、参考書や資料にも一通り目を通す。
苦労も多いし、翻訳を受けた作家さんたちも大変な思いをしているようですが、今回の企画はなかなか上手くいったと思いますね。自分の人生のなかでめずらしく自負してますよ(笑)。

「編集」の文化を残したい
――以前インタビューで「『日本文学全集』では編集の妙を見せたい」とおっしゃっていましたよね。池澤さんにとって「編集」とはどういうものなのでしょうか。
池澤|今は編集というと、作家の手伝いをするか、雑誌を一号分まとめるとかだと思われていますよね。企画を立てて、書き手はだれにして、イラストをどうするかといった組み立てをする職業だと。
しかし『古事記』を訳していて気付きましたが、もともとは様々なところにあるテキストを集めて、一定の方針のもとに配列することが、本来「編集」なんです。
『古事記』は稗田阿礼が喋った内容を、太安万侶が全部書き起こしたということになっているけれども、各地の地方の豪族ならびに天皇家に残っていたそれぞれの歴史資料を集めて、そこから組み立てて成立したものです。
『古事記』以降、ある時期までは日本の主要な文学作品はほとんど「編集」によって作られてきました。『万葉集』も、『伊勢物語』もそうです。日本各地にある歌物語を集めて、ユニットにしてストーリーをつくっている。つまりどこかにオリジンがある。『今昔物語』も『宇治拾遺物語』も同じですね。
またそういう「編集」の現場には、何人もの人が関わってきた。たとえば松尾芭蕉(991夜)の場合、奥の細道は一人の作品ですが、俳諧はグループワークです。芭蕉は行く先々でコミュニティをつくり、そこでの仲間たちとコミュニケーションをとりながら共同の作品をつくる。そのために俳諧には多くのルールがあるんです。ある種、お祭りのような面もあったと思いますね。
『日本文学全集』も、訳者のラインアップの選定は河出書房の編集者の力が大きかった。ああでもないこうでもないと相談しながら、合意のもとで一人ひとり慎重に選んでいったんです。
古来、日本人がやってきた「編集」の文化を、『日本文学全集』の制作を通じて受け継いでいるんだと思いますね。(完)
( 前編 / 後編 )
¶ 関連する千夜千冊
0600夜『リア王』ウィリアム・シェイクスピア
0042夜『方丈記』鴨長明
0999夜『オデュッセイアー』ホメーロス
0991夜『おくのほそ道』松尾芭蕉
---

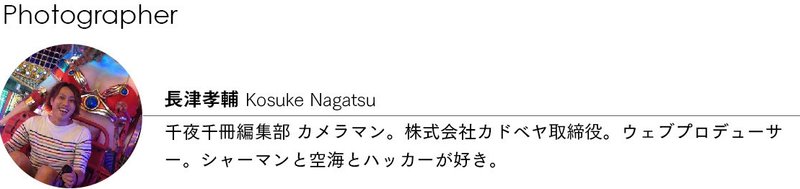
---
インタビュー・文:寺平賢司
撮影:長津孝輔
---
■カテゴリー:インタビュー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
